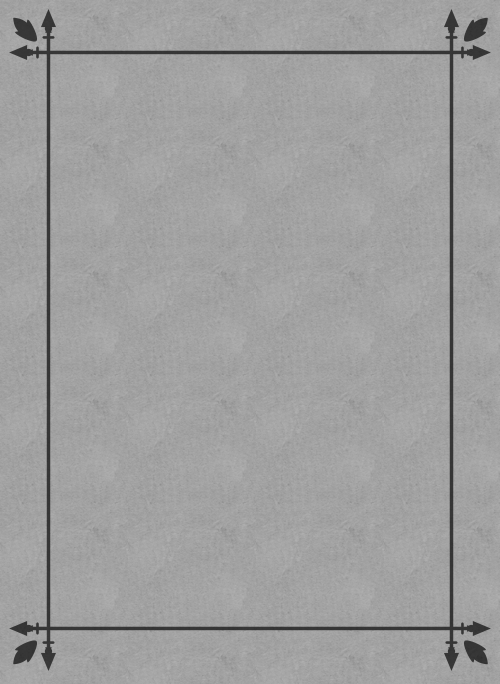翌日の六限が終わって、教室が「帰る人」と「残る人」に分かれていく時間。
僕――和真の頭の中は、ずっと白だった。
(寄贈棚。背表紙、白。抜け)
白い背表紙なんて、図書室には山ほどある。
むしろ、白が多い。
白は正義みたいな顔して、棚で増殖している。
「和真」
教室の入り口で呼ばれて顔を上げると、凛がいた。
いつも通り背筋がまっすぐで、いつも通り無駄がない。
「行く?」
凛は短く言った。
「……行く」
僕も短く返す。
「桃は?」
僕が聞くと、凛は首を振った。
「今日は委員会。後で合流するって」
凛は一拍置いて付け足す。
「その方がいいかも。図書室で変なことする人数は少ない方がいい」
「変なことって言うなよ」
「変なことだよ」
凛は淡々と断言した。
「寄贈棚の本を抜けって指示、正常じゃない」
(正常じゃないのに、僕はちょっとワクワクしてる)
この自分の性格が、いちばん信用ならない。
図書室に入ると、ひんやりした紙の匂いが鼻をくすぐった。
静かで、誰も怒鳴らなくて、誰も僕に「結果」とか「解散」とか言わない。
この空間はそれだけで心地良い。
「寄贈棚、奥」
凛が小声で言って、僕はついていく。
寄贈棚は、図書室のいちばん奥。
古い本が多くて、背表紙の色も、タイトルの文字も、全体的に疲れている。
ここだけ時間が止まっているみたいだ。
凛が棚の前で立ち止まり、腕を組んだ。
「……白、多くない?」
凛が珍しく、ちょっと困った声を出した。
「でしょ」
僕は思わず即答した。
「白、多い。想像の三倍くらい白い」
「背表紙、白。抜け、って……ガチャじゃん」
凛がガチャなんて言うの、意外すぎて笑いそうになった。
危ない。ここで笑ったら、昨日の笑うなの余韻が殴ってくる。
「背表紙が白いだけじゃなくて、たぶん白すぎるんじゃない?」
僕は真面目な顔で言ってみる。
凛が「白すぎるとは」と眉を寄せる。
でも、否定はしない。
二人で棚を端から見ていく。
白い背表紙。薄い白。黄ばんだ白。汚れた白。
白にもグラデーションがあるって、図書室で学ぶとは思わなかった。
「……これ、違う」
凛が一冊の背表紙を指で弾いた。
「ここに白って書いてある。文字の白じゃない」
「それは紛らわしい」
僕は小声でツッコむ。
「ここ、ほら」
凛が別の本を抜きかけて止めた。
「白いけど、タイトルがある。普通」
「普通じゃない白を探す」
僕が言うと、凛が小さく頷く。
「普通じゃない白、嫌いじゃない言い方」
(嫌いじゃない、って褒めてるのか?)
そのとき、棚の中ほどに――妙にまっさらな背表紙が見えた。
タイトルなし。
文字なし。
ただ、白。
潔癖みたいに白い。
「……あれ」
僕が指差すと、凛も視線を向けて、短く息を吸った。
「それっぽい」
僕はそっと手を伸ばした。
指先が背表紙に触れた瞬間、紙なのに冷たく感じた。
(なんで)
自分でも分からない。
「抜くよ」
僕が言うと、凛は周囲を確認してから頷いた。
「どうぞ。丁寧に」
丁寧に、ゆっくり、本を抜く。
――ぱさ。
何かが落ちた。
僕と凛は同時に固まった。
床に落ちたのは、黒い、小さな四角。
「……SDカード?」
僕が言うと、凛が一瞬で拾い上げた。
拾う動きが速い。さすが図書委員。落下物対応がプロ。
凛がカードを指先で挟んだまま、僕を見る。
目が言っている。
(何これ)
僕も目で返す。
(僕も知らない)
「図書室でSDカードが出てくるの、治安が悪いね」
凛がぽつりと言った。
「言い方」
僕は苦笑しかけて、慌てて飲み込んだ。
(やばい、笑うところだった)
白い背表紙の本を開くと、内側に小さな紙のポケットが貼られていた。
その中に、SDカードが入っていたらしい。
「……これ、完全に隠してただろ」
僕は喉の奥で呟く。
凛が淡々と頷く。
「寄贈棚の本にSDカード隠す人、まあまあ信用できない」
「信用できないのに、僕らは追ってる」
「だから変なことだって言った」
凛はカードを僕に渡そうとして、途中で止めた。
「……確認したいけど」
「ここで見る?」
僕が言うと、凛は首を振った。
「図書室で上映会はアウト」
凛は即答した。
「それに、カードリーダーある?」
「……ない」
僕は正直に言う。
「じゃあ映画部」
凛は本を閉じ、しっかり抱えた。
「この本は貸出中。正規ルート。安心して持ち出せる」
「その安心、妙にありがたい」
僕が言うと、凛は少しだけ口元を緩めた。
「安心は大事。暴走しないために」
(僕のことだな、それ)
映画部の部室。
編集用PCにSDカードを差し込む瞬間、なぜか手汗がひどかった。
(落ち着け。これはただのデータだ)
データ。映像。ファイル。
僕の得意分野のはずなのに、怖い。
フォルダを開く。
入っているのは、一本だけ。
ファイル名は短い英数字。
意味があるのかないのか、分からない。
僕はクリックして再生した。
画面いっぱいに、芝生が広がった。
広い。
とにかく広い。
どこまでも平たい緑が続いて、その向こうに低いフェンス。
さらに向こうに、建物の屋根が見える。
人影はない。
顔もない。
手もない。
ただ、芝生。
「……え、これだけ?」
僕が思わず言うと、凛がすぐ横で画面を見たまま答えた。
「……これだけっぽい」
音は――ほとんどない。
風の気配はあるのに、音としては薄い。
音は拾うなが、ここでも守られているみたいだった。
僕は動画を一時停止して、画面の隅を凝視した。
フェンスの向こうに、白い看板みたいなものがちらっと見える。
画質が荒い。拡大するとノイズが増える。
でも、文字の形だけは――
「……公民館?」
僕の口から漏れた。
凛が、画面に顔を近づけた。
「……読めるね。たぶん公民館」
僕の記憶が、ぶわっと広がる。
(公民館の裏、芝生あった)
小さいころ、地域の夏祭りがそこでやっていた。
ヨーヨー釣りの水の冷たさ。
焼きとうもろこしの匂い。
舞台のスピーカーのハウリング。
「これ、公民館の裏手の芝生じゃない?」
僕が言うと、凛が短く頷いた。
「可能性高い。地形が似てる」
「でも……あそこ、今――」
言いかけたところで、部室のドアが開いた。
桃が、委員会帰りの顔で飛び込んできた。
「ごめん遅れた!で、例の白い本――」
桃は、僕らの顔と画面を見て、言葉を止めた。
画面の芝生を見て、眉を寄せる。
「……それ、公民館の裏?」
桃が言った。
僕と凛が同時に桃を見る。
「知ってるの?」
「知ってるよ」
桃は頷く。頷き方が、いつもより重い。
「てか、あそこ……半年前くらいから閉鎖されてるじゃん。立入禁止のやつ。知らない?」
胸の奥が、嫌な形で繋がった。
半年前。
紗季先輩が学校に来られなくなった時期。
映画部の映像が切り抜かれて拡散したらしい時期。
(偶然じゃない)
「……閉鎖、いつから?」
僕が聞くと、桃は少し考えてから言う。
「春くらい?急にフェンス増えて、張り紙いっぱいになってた」
桃は声を落とした。
「なんか……事故があったって聞いた」
事故。
その言葉の中身を、桃は言わない。
言えないというより、知らない顔だった。
凛が僕を見て言う。
「閉鎖されてる場所を指示してるってことは――」
「行けってことだ」
僕は、ほとんど反射で言った。
言ってから、背筋が寒くなる。
(行けってことだ、って……僕は誰に従ってる?)
でも、心はもう決めていた。
怖いのに、決めていた。
凛が、淡々と釘を刺す。
「勝手に入るのはダメ。閉鎖は閉鎖」
「分かってる」
僕は頷く。
「中に入らない。外から見るだけでもいい」
桃が不安そうに言う。
「外からでも、あそこ、雰囲気ちょっと……嫌だよ?」
「嫌だから行く」
僕は自分でも驚くくらい、まっすぐに言った。
「嫌なものを、噂のままにしたくない」
凛が一拍置いて、静かに言う。
「……今の、たぶん正しい」
「たぶんって言った」
僕が言うと、凛は小さく肩をすくめた。
「今日は特別」
桃が、僕の手元のカメラを見た。
「撮るの?」
僕は少し迷ってから答えた。
「……撮る。手だけか、芝生だけかは分からないけど」
凛が言う。
「音は拾わない?」
僕は頷いた。
「拾わない。声も、噂も、必要以上には」
見せない優しさを覚えろ。
あの言葉が、今はただの綺麗事じゃなく、具体的なルールとして胸に残っている。
画面の芝生は、相変わらず無人で、ただ広い。
その無人さが、逆に怖い。
でも、怖いからこそ――そこに何かが隠れている気がした。
僕はSDカードをそっと抜き、指先で挟んだ。
薄いプラスチック一枚が、急に現実の重さを持つ。
「……行ってみよう」
僕が言うと、桃が小さく息を吸って、凛が静かに頷いた。
僕――和真の頭の中は、ずっと白だった。
(寄贈棚。背表紙、白。抜け)
白い背表紙なんて、図書室には山ほどある。
むしろ、白が多い。
白は正義みたいな顔して、棚で増殖している。
「和真」
教室の入り口で呼ばれて顔を上げると、凛がいた。
いつも通り背筋がまっすぐで、いつも通り無駄がない。
「行く?」
凛は短く言った。
「……行く」
僕も短く返す。
「桃は?」
僕が聞くと、凛は首を振った。
「今日は委員会。後で合流するって」
凛は一拍置いて付け足す。
「その方がいいかも。図書室で変なことする人数は少ない方がいい」
「変なことって言うなよ」
「変なことだよ」
凛は淡々と断言した。
「寄贈棚の本を抜けって指示、正常じゃない」
(正常じゃないのに、僕はちょっとワクワクしてる)
この自分の性格が、いちばん信用ならない。
図書室に入ると、ひんやりした紙の匂いが鼻をくすぐった。
静かで、誰も怒鳴らなくて、誰も僕に「結果」とか「解散」とか言わない。
この空間はそれだけで心地良い。
「寄贈棚、奥」
凛が小声で言って、僕はついていく。
寄贈棚は、図書室のいちばん奥。
古い本が多くて、背表紙の色も、タイトルの文字も、全体的に疲れている。
ここだけ時間が止まっているみたいだ。
凛が棚の前で立ち止まり、腕を組んだ。
「……白、多くない?」
凛が珍しく、ちょっと困った声を出した。
「でしょ」
僕は思わず即答した。
「白、多い。想像の三倍くらい白い」
「背表紙、白。抜け、って……ガチャじゃん」
凛がガチャなんて言うの、意外すぎて笑いそうになった。
危ない。ここで笑ったら、昨日の笑うなの余韻が殴ってくる。
「背表紙が白いだけじゃなくて、たぶん白すぎるんじゃない?」
僕は真面目な顔で言ってみる。
凛が「白すぎるとは」と眉を寄せる。
でも、否定はしない。
二人で棚を端から見ていく。
白い背表紙。薄い白。黄ばんだ白。汚れた白。
白にもグラデーションがあるって、図書室で学ぶとは思わなかった。
「……これ、違う」
凛が一冊の背表紙を指で弾いた。
「ここに白って書いてある。文字の白じゃない」
「それは紛らわしい」
僕は小声でツッコむ。
「ここ、ほら」
凛が別の本を抜きかけて止めた。
「白いけど、タイトルがある。普通」
「普通じゃない白を探す」
僕が言うと、凛が小さく頷く。
「普通じゃない白、嫌いじゃない言い方」
(嫌いじゃない、って褒めてるのか?)
そのとき、棚の中ほどに――妙にまっさらな背表紙が見えた。
タイトルなし。
文字なし。
ただ、白。
潔癖みたいに白い。
「……あれ」
僕が指差すと、凛も視線を向けて、短く息を吸った。
「それっぽい」
僕はそっと手を伸ばした。
指先が背表紙に触れた瞬間、紙なのに冷たく感じた。
(なんで)
自分でも分からない。
「抜くよ」
僕が言うと、凛は周囲を確認してから頷いた。
「どうぞ。丁寧に」
丁寧に、ゆっくり、本を抜く。
――ぱさ。
何かが落ちた。
僕と凛は同時に固まった。
床に落ちたのは、黒い、小さな四角。
「……SDカード?」
僕が言うと、凛が一瞬で拾い上げた。
拾う動きが速い。さすが図書委員。落下物対応がプロ。
凛がカードを指先で挟んだまま、僕を見る。
目が言っている。
(何これ)
僕も目で返す。
(僕も知らない)
「図書室でSDカードが出てくるの、治安が悪いね」
凛がぽつりと言った。
「言い方」
僕は苦笑しかけて、慌てて飲み込んだ。
(やばい、笑うところだった)
白い背表紙の本を開くと、内側に小さな紙のポケットが貼られていた。
その中に、SDカードが入っていたらしい。
「……これ、完全に隠してただろ」
僕は喉の奥で呟く。
凛が淡々と頷く。
「寄贈棚の本にSDカード隠す人、まあまあ信用できない」
「信用できないのに、僕らは追ってる」
「だから変なことだって言った」
凛はカードを僕に渡そうとして、途中で止めた。
「……確認したいけど」
「ここで見る?」
僕が言うと、凛は首を振った。
「図書室で上映会はアウト」
凛は即答した。
「それに、カードリーダーある?」
「……ない」
僕は正直に言う。
「じゃあ映画部」
凛は本を閉じ、しっかり抱えた。
「この本は貸出中。正規ルート。安心して持ち出せる」
「その安心、妙にありがたい」
僕が言うと、凛は少しだけ口元を緩めた。
「安心は大事。暴走しないために」
(僕のことだな、それ)
映画部の部室。
編集用PCにSDカードを差し込む瞬間、なぜか手汗がひどかった。
(落ち着け。これはただのデータだ)
データ。映像。ファイル。
僕の得意分野のはずなのに、怖い。
フォルダを開く。
入っているのは、一本だけ。
ファイル名は短い英数字。
意味があるのかないのか、分からない。
僕はクリックして再生した。
画面いっぱいに、芝生が広がった。
広い。
とにかく広い。
どこまでも平たい緑が続いて、その向こうに低いフェンス。
さらに向こうに、建物の屋根が見える。
人影はない。
顔もない。
手もない。
ただ、芝生。
「……え、これだけ?」
僕が思わず言うと、凛がすぐ横で画面を見たまま答えた。
「……これだけっぽい」
音は――ほとんどない。
風の気配はあるのに、音としては薄い。
音は拾うなが、ここでも守られているみたいだった。
僕は動画を一時停止して、画面の隅を凝視した。
フェンスの向こうに、白い看板みたいなものがちらっと見える。
画質が荒い。拡大するとノイズが増える。
でも、文字の形だけは――
「……公民館?」
僕の口から漏れた。
凛が、画面に顔を近づけた。
「……読めるね。たぶん公民館」
僕の記憶が、ぶわっと広がる。
(公民館の裏、芝生あった)
小さいころ、地域の夏祭りがそこでやっていた。
ヨーヨー釣りの水の冷たさ。
焼きとうもろこしの匂い。
舞台のスピーカーのハウリング。
「これ、公民館の裏手の芝生じゃない?」
僕が言うと、凛が短く頷いた。
「可能性高い。地形が似てる」
「でも……あそこ、今――」
言いかけたところで、部室のドアが開いた。
桃が、委員会帰りの顔で飛び込んできた。
「ごめん遅れた!で、例の白い本――」
桃は、僕らの顔と画面を見て、言葉を止めた。
画面の芝生を見て、眉を寄せる。
「……それ、公民館の裏?」
桃が言った。
僕と凛が同時に桃を見る。
「知ってるの?」
「知ってるよ」
桃は頷く。頷き方が、いつもより重い。
「てか、あそこ……半年前くらいから閉鎖されてるじゃん。立入禁止のやつ。知らない?」
胸の奥が、嫌な形で繋がった。
半年前。
紗季先輩が学校に来られなくなった時期。
映画部の映像が切り抜かれて拡散したらしい時期。
(偶然じゃない)
「……閉鎖、いつから?」
僕が聞くと、桃は少し考えてから言う。
「春くらい?急にフェンス増えて、張り紙いっぱいになってた」
桃は声を落とした。
「なんか……事故があったって聞いた」
事故。
その言葉の中身を、桃は言わない。
言えないというより、知らない顔だった。
凛が僕を見て言う。
「閉鎖されてる場所を指示してるってことは――」
「行けってことだ」
僕は、ほとんど反射で言った。
言ってから、背筋が寒くなる。
(行けってことだ、って……僕は誰に従ってる?)
でも、心はもう決めていた。
怖いのに、決めていた。
凛が、淡々と釘を刺す。
「勝手に入るのはダメ。閉鎖は閉鎖」
「分かってる」
僕は頷く。
「中に入らない。外から見るだけでもいい」
桃が不安そうに言う。
「外からでも、あそこ、雰囲気ちょっと……嫌だよ?」
「嫌だから行く」
僕は自分でも驚くくらい、まっすぐに言った。
「嫌なものを、噂のままにしたくない」
凛が一拍置いて、静かに言う。
「……今の、たぶん正しい」
「たぶんって言った」
僕が言うと、凛は小さく肩をすくめた。
「今日は特別」
桃が、僕の手元のカメラを見た。
「撮るの?」
僕は少し迷ってから答えた。
「……撮る。手だけか、芝生だけかは分からないけど」
凛が言う。
「音は拾わない?」
僕は頷いた。
「拾わない。声も、噂も、必要以上には」
見せない優しさを覚えろ。
あの言葉が、今はただの綺麗事じゃなく、具体的なルールとして胸に残っている。
画面の芝生は、相変わらず無人で、ただ広い。
その無人さが、逆に怖い。
でも、怖いからこそ――そこに何かが隠れている気がした。
僕はSDカードをそっと抜き、指先で挟んだ。
薄いプラスチック一枚が、急に現実の重さを持つ。
「……行ってみよう」
僕が言うと、桃が小さく息を吸って、凛が静かに頷いた。