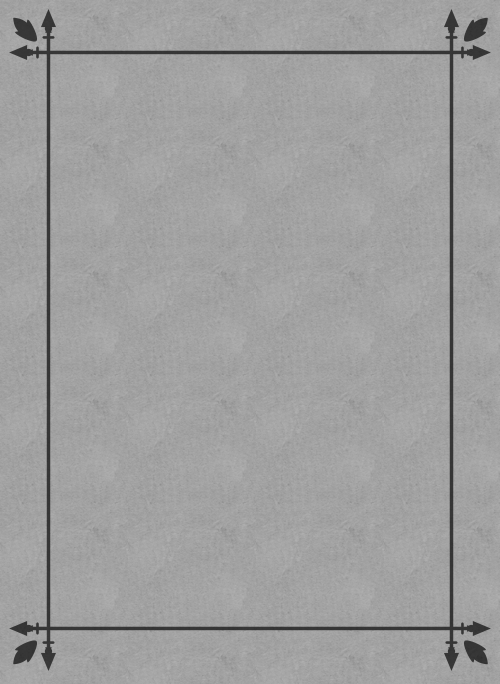商店街の入り口に立った瞬間、空気の温度が変わった気がした。
街灯が点き、シャッターの半分閉まった店先に、ネオンの光がじわじわ滲んでいく。
(ここで……笑うな、泣くな、息だけで)
ポケットの中の穴あきしおりが、紙の角で僕の指を軽く刺した。
「忘れるな」とでも言うみたいに。
「うわ、懐かしいこの感じ」
桃が商店街のアーケードを見上げて、声を弾ませた。
「放課後のデートスポットってやつ!」
「デートじゃない」
僕は反射で言ってしまい、すぐ後悔した。余計な反応は、余計な火種だ。
凛が、横から淡々と刺す。
「でも息だけでは、だいぶ恋愛映画っぽいね」
「……言い方」
「事実」
桃が「やば、二人とも今日刺し合ってる」と笑いかけて、ふっと口を押さえた。
「……あ、だめだ。笑うな、だもんね」
「そこ守れるの、えらい」
凛が褒めるような褒めないようなトーンで言う。
(僕も守れるのか?)
守る。見せない。拾わない。
そういうルールは、編集画面の中なら得意だ。
でも現実のルールは、目の前の人間の呼吸で崩れてしまう。
「……撮る前に確認」
僕はカメラを取り出し、みんなに向けた。
「撮影中、喋らない。声は入れない。息だけ」
桃が挙手する。
「質問。息って、音じゃないの?」
凛が即答する。
「言葉じゃない」
「なるほど!じゃあ、息はOK!」
桃は納得して、胸を張った。
「私、肺活量あるし」
「肺活量で勝負するな」
僕は言って、ほんの少しだけ笑いそうになった。
(危ない。笑うな)
凛が僕の手元を覗く。
「マイク、どうする?」
「内蔵は拾いすぎるから……」
僕は設定画面を開き、入力レベルを最低に落としてから、必要な帯域だけ拾うように調整した。
(……こんなこと、普段はやらない。でも今は、拾わないための技術が必要だ)
「技術者っぽい顔してる」
凛がぼそっと言う。
「編集担当です」
僕は小さく言い返す。
「今日は、編集担当の外仕事」
桃がスマホを取り出し、キラキラした目で言った。
「てかさ、ここ、映えるよ?アーケードのネオン、床に反射してるし。絶対――」
「どこにも上げない」
僕は言葉を被せた。自分でも驚くくらい早かった。
桃が目を丸くする。
「え、まだ撮ってもないのに?」
「まだだから」
僕は息を整えた。
「今は、作品のため。宣伝はあと」
凛が、僕を横目で見た。
「見せない優しさ、覚えてる」
「……うるさい」
でも、そのうるさいは少しだけ軽かった。
アーケードの中は、思ったより静かだった。
平日のこの時間は、買い物帰りの人がぽつぽつ。自転車がゆっくり通り過ぎ、店先のラジオが遠くで鳴っている。
(音、拾わない)
僕はカメラを構え、画角を落とした。
ネオンの看板は、直接撮らない。床に落ちた光だけを撮る。
水たまりがなくても、アスファルトが少し湿っていて、色が滲む。
「……手」
僕は小声で言いかけて、慌てて口を閉じた。
(音は拾わない、だろ)
凛がすぐに察して、紙を取り出した。
図書委員の癖なのか、いつも小さなメモ帳がある。
凛はペンで大きく書いた。
『手』
桃が「はいはい」と頷き、両手を胸の前でふわっと動かした。
まるで透明なガラスを撫でるみたいに。
ネオンの光が指先に乗って、指が色を持つ。
(……顔より、ずっといい)
僕はRECを押した。
赤いランプが点く。
みんなの呼吸が、少しだけ慎重になる。
桃が、息を吸って、ゆっくり吐いた。
白くはならない。まだそこまで寒くない。
でも、空気が揺れる。その存在だけが画面に残る。
凛が、穴あきしおりの二号機を折ってフレームにし、僕のレンズの前にそっとかざした。
穴越しに見るネオンは、丸い光の粒になる。
映画のボケ。レンズの魔法。
でもこれは紙の魔法だ。
(紙の勝ち……)
僕の頭の中で、凛の口癖が鳴る。
悔しいけど、今は同意しかできない。
「……カット」
僕は声に出さず、指で×を作った。
桃が、ぷっと吹きそうになって、肩を震わせる。
凛が桃の口元を指で指し、無言で笑うなと警告する。
桃は両頬を押さえ、必死に堪えた。
(ルールって、守ろうとすると面白くなるの、なんでだ?)
僕はカメラを少しだけ横に振った。
閉まった店のシャッター。そこに反射するネオン。
その前を、凛の手が横切る。指先がシャッターの冷たさをなぞる。
凛は僕に視線を投げた。
「……?」という顔。
僕は小さく頷いた。
(そう、そのまま)
凛が息を吐いた。
短く、静かに。
声はない。なのに、何か言っているみたいに見えた。
(言葉が下手でも、伝わることがある。それなら、僕にもできるかもしれない)
次の撮影場所を探して、少し歩いた。
古い喫茶店の前に、ネオンのOPENが点滅している。
その光が、ガラスに二重に映っていて、そこだけ別の世界みたいだ。
桃が、ふいに足を止めた。
「……あ」
僕も足を止める。
桃の視線の先、同年代の男子が二人、スマホを覗き込みながら笑っていた。
聞こえてくる単語が、いやに耳に刺さる。
「……それ、紗季のやつ?」
「うん、これ。ヤバくね?切り抜きだけどさ」
桃の指先が、ぎゅっと握られる。
肩が、わずかに震えた。
(やめろ)
(今は泣くなだ)
僕は反射で桃に声をかけそうになって、飲み込んだ。
凛が一歩前に出て、桃の隣に立った。
そして、何も言わずにメモ帳を開き、短く書いて桃に見せた。
『見ない』
桃は唇を噛んだ。
桃の目が、少しだけ潤む。
泣くな。泣くな。
その葛藤が、痛いほど分かった。
(泣きたいのを止めるのって、泣くより苦しい)
僕はカメラを下げ、代わりにRECを押した。
画角は足元。
ネオンの反射。
桃の靴先が、わずかに揺れる。
その隣で、凛の靴が動かない。
凛の手が、桃の手にそっと触れて、握る。
――息。
桃が、大きく息を吸って、ゆっくり吐いた。
声にならない息。
画面の中で、それだけが確かに鳴った気がした。
(これが、息だけで、か)
僕の胸が、痛いのに、変に落ち着く。
映像が、僕の代わりに言葉をやってくれている。
しばらくして、男子たちは飽きたみたいにスマホをしまい、どこかへ行った。
残ったのは、ネオンの点滅と、僕らの呼吸だけ。
桃が、小さく言った。
「……ごめん。撮影中なのに」
「撮影中だから、撮った」
僕は言った。自分でも意外なくらい、迷いなく。
「今のは……必要だった」
凛が、僕を見る。
「和真、今ちょっと監督だった」
「やめてくれ、照れる」
僕は言って、すぐに(照れるって何だよ)と自分にツッコんだ。
桃が鼻をすすりかけて、慌てて止める。
「……泣かない!泣かないって決めた!」
凛が淡々と返す。
「決めた顔が、もう泣いてる」
「言うな!」
桃が小声で抗議して、肩を震わせる。笑いそうになってる。
僕も危なかった。
笑うなが、今日いちばん難しい。
撮影がひと段落して、アーケードの端のベンチに座った。
ネオンの光が、僕らの膝の上に落ちる。
色が変わるたび、制服が別の制服みたいに見えた。
僕はカメラの映像を確認する。
踏切の白線。河川敷の夕焼け。商店街のネオン。
そして、手。手。手。
顔がなくても、ちゃんと人がいる。
(これ、つなげたら……映画になる)
不安は消えない。
でも、消えないままでも進めるくらいには、手応えがある。
「次の指示、探す?」
凛が言った。
僕はバッグから、例の文庫本を取り出す。
「持ってきてた」
「返却日はまだ先だからね」
凛はさらっと言う。
僕はページをめくり、不自然な文字列のページを探した。
指が覚えている。
来る。来る。――あった。
僕は穴あきしおりを重ねる。
ネオンの光で、穴がやけに黒く見える。
その黒の中に、言葉が並ぶ。
「図書室の寄贈棚。背表紙、白。抜け」
僕は声に出して読んだ。
凛がすぐに反応する。
「寄贈棚……図書室の奥の。古い本がまとめてあるところ」
桃が首を傾げる。
「背表紙『白』って、白い本ってこと?なんか呪いのアイテムみたい」
「呪いなら燃やして終わりだろ」
僕は言いながら、胸の奥が少しだけ熱くなる。
(図書室に、答えがある)
先輩たちが話してくれないなら、
顧問が「過去は過去だ」と言うなら、
僕は、紙の中の過去を辿る。
凛が本を閉じて、僕を見る。
「行くのは明日。図書室、もう閉まる」
「……うん」
僕は頷く。
「でも、明日行く」
桃が小さく笑って、でもすぐに口を押さえた。
「……あ、笑うなだった。もう終わった?」
「終わったことにしよう」
そう言って、僕はそっと、穴あきしおりを握り直した。
街灯が点き、シャッターの半分閉まった店先に、ネオンの光がじわじわ滲んでいく。
(ここで……笑うな、泣くな、息だけで)
ポケットの中の穴あきしおりが、紙の角で僕の指を軽く刺した。
「忘れるな」とでも言うみたいに。
「うわ、懐かしいこの感じ」
桃が商店街のアーケードを見上げて、声を弾ませた。
「放課後のデートスポットってやつ!」
「デートじゃない」
僕は反射で言ってしまい、すぐ後悔した。余計な反応は、余計な火種だ。
凛が、横から淡々と刺す。
「でも息だけでは、だいぶ恋愛映画っぽいね」
「……言い方」
「事実」
桃が「やば、二人とも今日刺し合ってる」と笑いかけて、ふっと口を押さえた。
「……あ、だめだ。笑うな、だもんね」
「そこ守れるの、えらい」
凛が褒めるような褒めないようなトーンで言う。
(僕も守れるのか?)
守る。見せない。拾わない。
そういうルールは、編集画面の中なら得意だ。
でも現実のルールは、目の前の人間の呼吸で崩れてしまう。
「……撮る前に確認」
僕はカメラを取り出し、みんなに向けた。
「撮影中、喋らない。声は入れない。息だけ」
桃が挙手する。
「質問。息って、音じゃないの?」
凛が即答する。
「言葉じゃない」
「なるほど!じゃあ、息はOK!」
桃は納得して、胸を張った。
「私、肺活量あるし」
「肺活量で勝負するな」
僕は言って、ほんの少しだけ笑いそうになった。
(危ない。笑うな)
凛が僕の手元を覗く。
「マイク、どうする?」
「内蔵は拾いすぎるから……」
僕は設定画面を開き、入力レベルを最低に落としてから、必要な帯域だけ拾うように調整した。
(……こんなこと、普段はやらない。でも今は、拾わないための技術が必要だ)
「技術者っぽい顔してる」
凛がぼそっと言う。
「編集担当です」
僕は小さく言い返す。
「今日は、編集担当の外仕事」
桃がスマホを取り出し、キラキラした目で言った。
「てかさ、ここ、映えるよ?アーケードのネオン、床に反射してるし。絶対――」
「どこにも上げない」
僕は言葉を被せた。自分でも驚くくらい早かった。
桃が目を丸くする。
「え、まだ撮ってもないのに?」
「まだだから」
僕は息を整えた。
「今は、作品のため。宣伝はあと」
凛が、僕を横目で見た。
「見せない優しさ、覚えてる」
「……うるさい」
でも、そのうるさいは少しだけ軽かった。
アーケードの中は、思ったより静かだった。
平日のこの時間は、買い物帰りの人がぽつぽつ。自転車がゆっくり通り過ぎ、店先のラジオが遠くで鳴っている。
(音、拾わない)
僕はカメラを構え、画角を落とした。
ネオンの看板は、直接撮らない。床に落ちた光だけを撮る。
水たまりがなくても、アスファルトが少し湿っていて、色が滲む。
「……手」
僕は小声で言いかけて、慌てて口を閉じた。
(音は拾わない、だろ)
凛がすぐに察して、紙を取り出した。
図書委員の癖なのか、いつも小さなメモ帳がある。
凛はペンで大きく書いた。
『手』
桃が「はいはい」と頷き、両手を胸の前でふわっと動かした。
まるで透明なガラスを撫でるみたいに。
ネオンの光が指先に乗って、指が色を持つ。
(……顔より、ずっといい)
僕はRECを押した。
赤いランプが点く。
みんなの呼吸が、少しだけ慎重になる。
桃が、息を吸って、ゆっくり吐いた。
白くはならない。まだそこまで寒くない。
でも、空気が揺れる。その存在だけが画面に残る。
凛が、穴あきしおりの二号機を折ってフレームにし、僕のレンズの前にそっとかざした。
穴越しに見るネオンは、丸い光の粒になる。
映画のボケ。レンズの魔法。
でもこれは紙の魔法だ。
(紙の勝ち……)
僕の頭の中で、凛の口癖が鳴る。
悔しいけど、今は同意しかできない。
「……カット」
僕は声に出さず、指で×を作った。
桃が、ぷっと吹きそうになって、肩を震わせる。
凛が桃の口元を指で指し、無言で笑うなと警告する。
桃は両頬を押さえ、必死に堪えた。
(ルールって、守ろうとすると面白くなるの、なんでだ?)
僕はカメラを少しだけ横に振った。
閉まった店のシャッター。そこに反射するネオン。
その前を、凛の手が横切る。指先がシャッターの冷たさをなぞる。
凛は僕に視線を投げた。
「……?」という顔。
僕は小さく頷いた。
(そう、そのまま)
凛が息を吐いた。
短く、静かに。
声はない。なのに、何か言っているみたいに見えた。
(言葉が下手でも、伝わることがある。それなら、僕にもできるかもしれない)
次の撮影場所を探して、少し歩いた。
古い喫茶店の前に、ネオンのOPENが点滅している。
その光が、ガラスに二重に映っていて、そこだけ別の世界みたいだ。
桃が、ふいに足を止めた。
「……あ」
僕も足を止める。
桃の視線の先、同年代の男子が二人、スマホを覗き込みながら笑っていた。
聞こえてくる単語が、いやに耳に刺さる。
「……それ、紗季のやつ?」
「うん、これ。ヤバくね?切り抜きだけどさ」
桃の指先が、ぎゅっと握られる。
肩が、わずかに震えた。
(やめろ)
(今は泣くなだ)
僕は反射で桃に声をかけそうになって、飲み込んだ。
凛が一歩前に出て、桃の隣に立った。
そして、何も言わずにメモ帳を開き、短く書いて桃に見せた。
『見ない』
桃は唇を噛んだ。
桃の目が、少しだけ潤む。
泣くな。泣くな。
その葛藤が、痛いほど分かった。
(泣きたいのを止めるのって、泣くより苦しい)
僕はカメラを下げ、代わりにRECを押した。
画角は足元。
ネオンの反射。
桃の靴先が、わずかに揺れる。
その隣で、凛の靴が動かない。
凛の手が、桃の手にそっと触れて、握る。
――息。
桃が、大きく息を吸って、ゆっくり吐いた。
声にならない息。
画面の中で、それだけが確かに鳴った気がした。
(これが、息だけで、か)
僕の胸が、痛いのに、変に落ち着く。
映像が、僕の代わりに言葉をやってくれている。
しばらくして、男子たちは飽きたみたいにスマホをしまい、どこかへ行った。
残ったのは、ネオンの点滅と、僕らの呼吸だけ。
桃が、小さく言った。
「……ごめん。撮影中なのに」
「撮影中だから、撮った」
僕は言った。自分でも意外なくらい、迷いなく。
「今のは……必要だった」
凛が、僕を見る。
「和真、今ちょっと監督だった」
「やめてくれ、照れる」
僕は言って、すぐに(照れるって何だよ)と自分にツッコんだ。
桃が鼻をすすりかけて、慌てて止める。
「……泣かない!泣かないって決めた!」
凛が淡々と返す。
「決めた顔が、もう泣いてる」
「言うな!」
桃が小声で抗議して、肩を震わせる。笑いそうになってる。
僕も危なかった。
笑うなが、今日いちばん難しい。
撮影がひと段落して、アーケードの端のベンチに座った。
ネオンの光が、僕らの膝の上に落ちる。
色が変わるたび、制服が別の制服みたいに見えた。
僕はカメラの映像を確認する。
踏切の白線。河川敷の夕焼け。商店街のネオン。
そして、手。手。手。
顔がなくても、ちゃんと人がいる。
(これ、つなげたら……映画になる)
不安は消えない。
でも、消えないままでも進めるくらいには、手応えがある。
「次の指示、探す?」
凛が言った。
僕はバッグから、例の文庫本を取り出す。
「持ってきてた」
「返却日はまだ先だからね」
凛はさらっと言う。
僕はページをめくり、不自然な文字列のページを探した。
指が覚えている。
来る。来る。――あった。
僕は穴あきしおりを重ねる。
ネオンの光で、穴がやけに黒く見える。
その黒の中に、言葉が並ぶ。
「図書室の寄贈棚。背表紙、白。抜け」
僕は声に出して読んだ。
凛がすぐに反応する。
「寄贈棚……図書室の奥の。古い本がまとめてあるところ」
桃が首を傾げる。
「背表紙『白』って、白い本ってこと?なんか呪いのアイテムみたい」
「呪いなら燃やして終わりだろ」
僕は言いながら、胸の奥が少しだけ熱くなる。
(図書室に、答えがある)
先輩たちが話してくれないなら、
顧問が「過去は過去だ」と言うなら、
僕は、紙の中の過去を辿る。
凛が本を閉じて、僕を見る。
「行くのは明日。図書室、もう閉まる」
「……うん」
僕は頷く。
「でも、明日行く」
桃が小さく笑って、でもすぐに口を押さえた。
「……あ、笑うなだった。もう終わった?」
「終わったことにしよう」
そう言って、僕はそっと、穴あきしおりを握り直した。