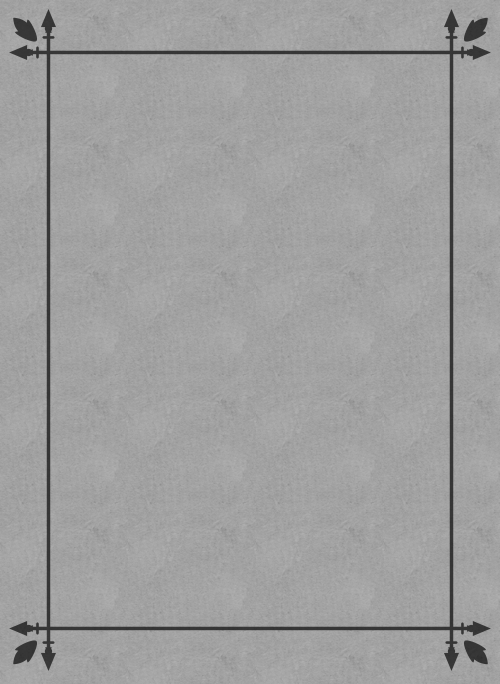その噂は、朝のホームルームより先に教室へ入ってきた。
廊下のざわめきが、いつもより少しだけ尖っている。
笑い声が、軽いのに、どこか湿っている。
「ねえ、知ってる?」
「え、何?」
「紗季先輩ってさ――炎上して消えたんだって」
その名前が聞こえた瞬間、僕――和真の背中に、冷たい線が走った。
(紗季先輩)
鉛筆の芯が折れたみたいな音が、頭の中で鳴る。
昨日、河川敷で読んだ言葉が、勝手に反芻される。
見せない優しさを覚えろ。
(それなのに、学校は見える方が好きだ)
僕は席に着くふりをして、耳だけをそちらに向けた。
盗み聞きは悪い。分かってる。
でも、名前を出されたら、勝手に心がそっちへ行く。
「映画部のさ、動画が回ったらしいよ」
「え、映画部?文化祭の?」
「違う違う、半年前のやつ。切り抜かれて拡散したんだって」
「切り抜かれている部分が、結構きわどいらしいよ」
「うわー、最悪。で、紗季先輩がそれで学校来れなくなってるとか」
「病んだってこと?」
「知らなーい。てか、炎上ってこわ」
炎上。
そのくせ実際に燃えるのは、画面の向こうの誰かの生活で、こっちは指先しか熱くならない。
(……半年前)
僕は去年の自分を思い出そうとする。
その頃は、コンクール用の映画を撮影していた。
でも、学年ごとのグループで作品を作っていて、先輩たちの作品がどんなものだったのかは教えてもらえていなかった。
理由はシンプルだ。
部活の後輩と言っても、コンクールに参加するライバルだったから。
だから、その映画に携わっていない。
という事実が、今日だけは腹立たしかった。
隣の席の桃が、机に伏せたまま、指先だけを動かしていた。
スマホ。画面の光が、彼女のまつ毛を青く照らす。
「……桃」
僕は小声で呼んだ。
桃は顔を上げないまま、唇だけ動かした。
「聞こえてる」
「……」
「やめてほしい、ああいうの」
桃の声は、いつもの明るさが削ぎ落ちていた。
「炎上して消えたって、言い方。人が消えたみたいに」
(消えた、か)
消えるのは簡単だ。
人は、存在を見ないことですぐ消せる。
見ない方が楽だから。関わらない方が安全だから。
ホームルームが始まり、担任が「はい席ついてー」と日常を押しつけてくる。
日常は、噂の上に平気で机を置く。
(これが見せない優しさなのか?違う。これは見ない怠けだ)
胸が痛い。
でも、その痛みの正体が分からない。
紗季先輩のため?映画部のため?それとも、自分のため?
(……自分のため、だろうな)
僕は、痛いのが嫌だ。
だから理由を知りたい。
理由が分かれば、編集みたいに整理できると思っている。
分からないものは、怖い。
休み時間。
教室の外に出ると、噂の粒がさらに濃くなって、空気に浮いていた。
「紗季先輩の動画、マジであるらしい」
「どこで見れんの?」
「知らん、誰か持ってんじゃね」
「うわ、最悪じゃん」
図書室へ向かう廊下で、凛に会った。
凛はいつも通り静かに歩いていて、周りのざわめきと別の温度で存在している。
「凛」
僕が呼ぶと、凛はすぐに僕を見た。
「顔、また死んでる」
第一声がそれだった。
「……今日はそういう日」
僕は言って、周りをちらっと見た。誰もこっちを聞いていない、たぶん。
凛は僕の視線の意味を察したらしく、声を落とす。
「噂、聞いた?」
「聞いた」
僕は喉が乾くのを感じた。
「紗季先輩のこと」
凛は一拍置いて、言葉を選んだ。
「炎上して消えたってやつ?」
「……うん」
凛は、呆れたように小さく息を吐いた。
「炎上って言葉、便利だよね。原因も責任も全部、火に投げられる」
「凛、たまに怖いこと言うよね」
「事実」
凛は淡々と返す。
「で、和真は何が知りたいの?」
その問いが、僕の胸の痛いところを正確に押した。
「……半年前のこと」
僕は言った。
「映画部の映像が切り抜かれて拡散したって」
凛は頷く。
「らしいね」
「先輩たち、何も言ってくれない」
凛が眉を少しだけ上げる。
「映画部の?」
「うん。顧問も。関わっていない作品だから、事情が分からない」
言いながら、腹の底が熱くなる。
「分からないまま、噂だけが回って、先輩の名前だけが燃えるのが……嫌だ」
凛は、しばらく僕を見ていた。
それから、静かに言った。
「知りたいのは、優しさ?」
「……」
「それとも、自分が安心したいだけ?」
刺さる。
刺さり方が、正確すぎる。
僕は一度、息を吸った。
「……両方だと思う」
凛は小さく頷いた。
「正直でよろしい」
(よろしい、ってなんだよ。先生か)
その日の放課後、映画部の部室はいつもより空気が重かった。
部室に入った瞬間、分かる。
何かが共有されていない感じ。
秋人先輩は机に手をついて、資料を見ている。
春斗は機材をいじっているふりをしている。
顧問の佐伯先生は、腕を組んだまま、僕らを観察している。
桃が先に口を開いた。
「……先輩。紗季先輩のこと、学校で噂になってます」
部室の空気が、一瞬だけ止まった。
秋人先輩の手が、紙の上で止まる。
春斗の指が、ケーブルから外れる。
佐伯先生は、目だけを動かした。
「噂って」
秋人先輩が、乾いた声で言う。
「何の」
桃が言いにくそうに、でも逃げないように言った。
「炎上して消えたって」
僕は、その言葉が部室の中に入った瞬間、吐き気みたいなものが喉に上がるのを感じた。
(この言い方、ほんとに最悪だ)
秋人先輩は、しばらく何も言わなかった。
言わないことが、否定でも肯定でもないまま、痛い。
ようやく先輩は言った。
「……今、それ話す?」
「話さないと」
桃が言う。
「何も知らないまま、みんな好き勝手言ってます」
「好き勝手言うやつは止められない」
佐伯先生が、低い声で割って入った。
「先生」
僕の声は、自分でも驚くほど荒かった。
「それ、逃げじゃないですか」
部室の全員が僕を見た。
心臓が、音を立てる。
佐伯先生は、少しだけ目を細めた。
「逃げ?」
「……だって」
僕は言葉を探しながら続けた。
「噂が広がってるのに、何も言わないのは、守ってるんじゃなくて……放置してるだけに見える」
言ってしまってから、後悔が波のように来た。
(僕が言えることじゃない。僕は当時関わってない。知らないのに)
でも、止まらなかった。
「教えてください」
僕は秋人先輩を見る。
「紗季先輩に何があったのか。何が切り抜かれたのか。どうして学校に来られなくなったのか」
秋人先輩は、唇を噛んだ。
「……和真」
名前を呼ばれると、急に怖くなる。
頼む、って言われた時とは別の怖さ。
「それを知って、どうする?」
秋人先輩が言った。
「正義の味方する?噂を止める?拡散元を探す?」
「……分かりません」
僕は正直に言った。
「でも、知らないまま、撮れない」
佐伯先生が、短く言う。
「撮れないのは、言い訳だ」
僕は反射で言い返しそうになって、飲み込んだ。
飲み込んだ代わりに、喉が痛い。
秋人先輩が、声を落とした。
「……紗季のことは、俺たちが勝手に話すべきじゃない」
「勝手に話すなって……」
桃が震える声で言う。
「もう勝手に話されてるよ、先輩」
その一言で、秋人先輩の顔が一瞬だけ崩れた。
苦しそうな顔。
罪悪感の顔。
(やっぱり、何かある)
でも、誰も口を開かない。
開けない。
見せない優しさなのかもしれない。
だけど、今の僕には、その優しさが誰に向いてるのか分からなかった。
佐伯先生が、机を軽く叩いた。
「過去は過去だ。今は文化祭に向けて結果を出せ。噂の火に薪をくべるな」
(薪をくべてるの、僕らじゃない)
そう言いたかった。
でも言ったら、たぶん僕は泣くか怒るか、どっちかになる。
部室の空気に耐えられず、僕は一歩下がった。
「……すみません。僕、少し外、行きます」
秋人先輩が何か言いかけたけど、僕は聞かないふりをして部室を出た。
廊下の窓から、夕方の光が差し込んでいる。
昨日の河川敷ほど強くない、薄いオレンジ。
それでも、光は光だ。
(映像に救われる感覚、って昨日言った。でも今日は、言葉に救われたい)
ポケットの中で、穴あきしおりが指に当たった。
紙の角が、妙に現実的だった。
(次の指示を見れば、少なくとも僕は前に進める)
僕は図書室へ向かった。
凛がいる。桃も、たぶん後で来る。
先輩たちが話してくれないなら、僕は僕の作品を作るしかない。
図書室の机に座って、あの文庫本を開く。
凛が貸出済みの手続きしてくれたやつだ。
妙に安心する。ちゃんとした手続きって、心を落ち着かせる効果がある。
ページをめくる。普通の文章。
そして――また、不自然なページ。
僕は穴あきしおりを重ねた。
指先が少し震えている。噂のせいか、怒りのせいか、怖さのせいか。
穴の中の文字が、すっと並ぶ。
「商店街のネオン。笑うな。泣くな。息だけで」
僕は声に出して読んでから、思わず苦く笑った。
笑って、すぐに自分で自分に突っ込む。
(……笑うなって言われてるだろ)
凛が向かいの席に座っていて、僕の顔を見た。
いつからいたのか分からない。図書委員は気配が薄い。良くも悪くも。
「次、出た?」
凛が小声で聞く。
僕は頷く。
「商店街のネオン。笑うな。泣くな。息だけで」
凛が目を細める。
「……息だけ」
「また、声を避けてる」
僕は呟いた。
凛は静かに頷く。
「うん。声は拾わない。顔も撮らない。……でも、息は撮る」
「息って、音じゃないの?」
僕が言うと、凛は少し考えてから答えた。
「音じゃなくて、存在かも」
凛は淡々と言う。
「ここにいるっていう証拠。声ほど危険じゃない形で」
その言葉が、胸の奥に落ちた。
危険じゃない形で、証拠を残す。
見せない優しさと、伝える意志の、ぎりぎりのところ。
(紗季先輩も、そこを歩いてたのかもしれない)
僕は文庫本を閉じて、しおりを握りしめた。
ネオン。夜。商店街。
そこで僕は、笑わず、泣かず、息だけを撮る。
(逃げるな。白線の外側で待ってた僕が、今度は白線の内側へ一歩近づく)
僕は撮る。
撮って、繋いで。
それしか今の僕にはできない。
廊下のざわめきが、いつもより少しだけ尖っている。
笑い声が、軽いのに、どこか湿っている。
「ねえ、知ってる?」
「え、何?」
「紗季先輩ってさ――炎上して消えたんだって」
その名前が聞こえた瞬間、僕――和真の背中に、冷たい線が走った。
(紗季先輩)
鉛筆の芯が折れたみたいな音が、頭の中で鳴る。
昨日、河川敷で読んだ言葉が、勝手に反芻される。
見せない優しさを覚えろ。
(それなのに、学校は見える方が好きだ)
僕は席に着くふりをして、耳だけをそちらに向けた。
盗み聞きは悪い。分かってる。
でも、名前を出されたら、勝手に心がそっちへ行く。
「映画部のさ、動画が回ったらしいよ」
「え、映画部?文化祭の?」
「違う違う、半年前のやつ。切り抜かれて拡散したんだって」
「切り抜かれている部分が、結構きわどいらしいよ」
「うわー、最悪。で、紗季先輩がそれで学校来れなくなってるとか」
「病んだってこと?」
「知らなーい。てか、炎上ってこわ」
炎上。
そのくせ実際に燃えるのは、画面の向こうの誰かの生活で、こっちは指先しか熱くならない。
(……半年前)
僕は去年の自分を思い出そうとする。
その頃は、コンクール用の映画を撮影していた。
でも、学年ごとのグループで作品を作っていて、先輩たちの作品がどんなものだったのかは教えてもらえていなかった。
理由はシンプルだ。
部活の後輩と言っても、コンクールに参加するライバルだったから。
だから、その映画に携わっていない。
という事実が、今日だけは腹立たしかった。
隣の席の桃が、机に伏せたまま、指先だけを動かしていた。
スマホ。画面の光が、彼女のまつ毛を青く照らす。
「……桃」
僕は小声で呼んだ。
桃は顔を上げないまま、唇だけ動かした。
「聞こえてる」
「……」
「やめてほしい、ああいうの」
桃の声は、いつもの明るさが削ぎ落ちていた。
「炎上して消えたって、言い方。人が消えたみたいに」
(消えた、か)
消えるのは簡単だ。
人は、存在を見ないことですぐ消せる。
見ない方が楽だから。関わらない方が安全だから。
ホームルームが始まり、担任が「はい席ついてー」と日常を押しつけてくる。
日常は、噂の上に平気で机を置く。
(これが見せない優しさなのか?違う。これは見ない怠けだ)
胸が痛い。
でも、その痛みの正体が分からない。
紗季先輩のため?映画部のため?それとも、自分のため?
(……自分のため、だろうな)
僕は、痛いのが嫌だ。
だから理由を知りたい。
理由が分かれば、編集みたいに整理できると思っている。
分からないものは、怖い。
休み時間。
教室の外に出ると、噂の粒がさらに濃くなって、空気に浮いていた。
「紗季先輩の動画、マジであるらしい」
「どこで見れんの?」
「知らん、誰か持ってんじゃね」
「うわ、最悪じゃん」
図書室へ向かう廊下で、凛に会った。
凛はいつも通り静かに歩いていて、周りのざわめきと別の温度で存在している。
「凛」
僕が呼ぶと、凛はすぐに僕を見た。
「顔、また死んでる」
第一声がそれだった。
「……今日はそういう日」
僕は言って、周りをちらっと見た。誰もこっちを聞いていない、たぶん。
凛は僕の視線の意味を察したらしく、声を落とす。
「噂、聞いた?」
「聞いた」
僕は喉が乾くのを感じた。
「紗季先輩のこと」
凛は一拍置いて、言葉を選んだ。
「炎上して消えたってやつ?」
「……うん」
凛は、呆れたように小さく息を吐いた。
「炎上って言葉、便利だよね。原因も責任も全部、火に投げられる」
「凛、たまに怖いこと言うよね」
「事実」
凛は淡々と返す。
「で、和真は何が知りたいの?」
その問いが、僕の胸の痛いところを正確に押した。
「……半年前のこと」
僕は言った。
「映画部の映像が切り抜かれて拡散したって」
凛は頷く。
「らしいね」
「先輩たち、何も言ってくれない」
凛が眉を少しだけ上げる。
「映画部の?」
「うん。顧問も。関わっていない作品だから、事情が分からない」
言いながら、腹の底が熱くなる。
「分からないまま、噂だけが回って、先輩の名前だけが燃えるのが……嫌だ」
凛は、しばらく僕を見ていた。
それから、静かに言った。
「知りたいのは、優しさ?」
「……」
「それとも、自分が安心したいだけ?」
刺さる。
刺さり方が、正確すぎる。
僕は一度、息を吸った。
「……両方だと思う」
凛は小さく頷いた。
「正直でよろしい」
(よろしい、ってなんだよ。先生か)
その日の放課後、映画部の部室はいつもより空気が重かった。
部室に入った瞬間、分かる。
何かが共有されていない感じ。
秋人先輩は机に手をついて、資料を見ている。
春斗は機材をいじっているふりをしている。
顧問の佐伯先生は、腕を組んだまま、僕らを観察している。
桃が先に口を開いた。
「……先輩。紗季先輩のこと、学校で噂になってます」
部室の空気が、一瞬だけ止まった。
秋人先輩の手が、紙の上で止まる。
春斗の指が、ケーブルから外れる。
佐伯先生は、目だけを動かした。
「噂って」
秋人先輩が、乾いた声で言う。
「何の」
桃が言いにくそうに、でも逃げないように言った。
「炎上して消えたって」
僕は、その言葉が部室の中に入った瞬間、吐き気みたいなものが喉に上がるのを感じた。
(この言い方、ほんとに最悪だ)
秋人先輩は、しばらく何も言わなかった。
言わないことが、否定でも肯定でもないまま、痛い。
ようやく先輩は言った。
「……今、それ話す?」
「話さないと」
桃が言う。
「何も知らないまま、みんな好き勝手言ってます」
「好き勝手言うやつは止められない」
佐伯先生が、低い声で割って入った。
「先生」
僕の声は、自分でも驚くほど荒かった。
「それ、逃げじゃないですか」
部室の全員が僕を見た。
心臓が、音を立てる。
佐伯先生は、少しだけ目を細めた。
「逃げ?」
「……だって」
僕は言葉を探しながら続けた。
「噂が広がってるのに、何も言わないのは、守ってるんじゃなくて……放置してるだけに見える」
言ってしまってから、後悔が波のように来た。
(僕が言えることじゃない。僕は当時関わってない。知らないのに)
でも、止まらなかった。
「教えてください」
僕は秋人先輩を見る。
「紗季先輩に何があったのか。何が切り抜かれたのか。どうして学校に来られなくなったのか」
秋人先輩は、唇を噛んだ。
「……和真」
名前を呼ばれると、急に怖くなる。
頼む、って言われた時とは別の怖さ。
「それを知って、どうする?」
秋人先輩が言った。
「正義の味方する?噂を止める?拡散元を探す?」
「……分かりません」
僕は正直に言った。
「でも、知らないまま、撮れない」
佐伯先生が、短く言う。
「撮れないのは、言い訳だ」
僕は反射で言い返しそうになって、飲み込んだ。
飲み込んだ代わりに、喉が痛い。
秋人先輩が、声を落とした。
「……紗季のことは、俺たちが勝手に話すべきじゃない」
「勝手に話すなって……」
桃が震える声で言う。
「もう勝手に話されてるよ、先輩」
その一言で、秋人先輩の顔が一瞬だけ崩れた。
苦しそうな顔。
罪悪感の顔。
(やっぱり、何かある)
でも、誰も口を開かない。
開けない。
見せない優しさなのかもしれない。
だけど、今の僕には、その優しさが誰に向いてるのか分からなかった。
佐伯先生が、机を軽く叩いた。
「過去は過去だ。今は文化祭に向けて結果を出せ。噂の火に薪をくべるな」
(薪をくべてるの、僕らじゃない)
そう言いたかった。
でも言ったら、たぶん僕は泣くか怒るか、どっちかになる。
部室の空気に耐えられず、僕は一歩下がった。
「……すみません。僕、少し外、行きます」
秋人先輩が何か言いかけたけど、僕は聞かないふりをして部室を出た。
廊下の窓から、夕方の光が差し込んでいる。
昨日の河川敷ほど強くない、薄いオレンジ。
それでも、光は光だ。
(映像に救われる感覚、って昨日言った。でも今日は、言葉に救われたい)
ポケットの中で、穴あきしおりが指に当たった。
紙の角が、妙に現実的だった。
(次の指示を見れば、少なくとも僕は前に進める)
僕は図書室へ向かった。
凛がいる。桃も、たぶん後で来る。
先輩たちが話してくれないなら、僕は僕の作品を作るしかない。
図書室の机に座って、あの文庫本を開く。
凛が貸出済みの手続きしてくれたやつだ。
妙に安心する。ちゃんとした手続きって、心を落ち着かせる効果がある。
ページをめくる。普通の文章。
そして――また、不自然なページ。
僕は穴あきしおりを重ねた。
指先が少し震えている。噂のせいか、怒りのせいか、怖さのせいか。
穴の中の文字が、すっと並ぶ。
「商店街のネオン。笑うな。泣くな。息だけで」
僕は声に出して読んでから、思わず苦く笑った。
笑って、すぐに自分で自分に突っ込む。
(……笑うなって言われてるだろ)
凛が向かいの席に座っていて、僕の顔を見た。
いつからいたのか分からない。図書委員は気配が薄い。良くも悪くも。
「次、出た?」
凛が小声で聞く。
僕は頷く。
「商店街のネオン。笑うな。泣くな。息だけで」
凛が目を細める。
「……息だけ」
「また、声を避けてる」
僕は呟いた。
凛は静かに頷く。
「うん。声は拾わない。顔も撮らない。……でも、息は撮る」
「息って、音じゃないの?」
僕が言うと、凛は少し考えてから答えた。
「音じゃなくて、存在かも」
凛は淡々と言う。
「ここにいるっていう証拠。声ほど危険じゃない形で」
その言葉が、胸の奥に落ちた。
危険じゃない形で、証拠を残す。
見せない優しさと、伝える意志の、ぎりぎりのところ。
(紗季先輩も、そこを歩いてたのかもしれない)
僕は文庫本を閉じて、しおりを握りしめた。
ネオン。夜。商店街。
そこで僕は、笑わず、泣かず、息だけを撮る。
(逃げるな。白線の外側で待ってた僕が、今度は白線の内側へ一歩近づく)
僕は撮る。
撮って、繋いで。
それしか今の僕にはできない。