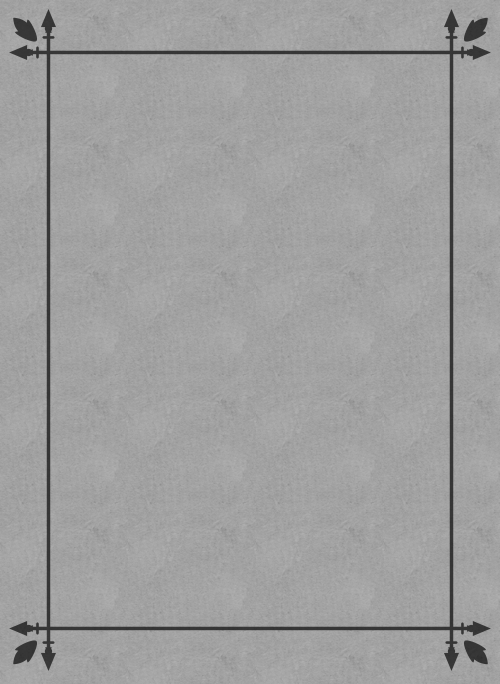河川敷に着いたとき、世界はもう、夕焼けの中に半分溶けていた。
堤防の斜面に伸びる影が長くて、草の先がオレンジ色に燃えている。
川面は、光を反射してちかちかと瞬いて――それが、まるで無数のフィルムの粒みたいに見えた。
(……強い)
僕――和真は、思わず口の中で呟いた。
強いというのは、絵として強い。映像として、黙っていても成立する強さがある。
「やっぱり夕焼け、ずるいよね」
凛が、制服の袖を引っ張りながら言った。
「ずるいって、褒めてる?」
僕はカメラの電源を入れつつ聞く。
「うん。人間が頑張らなくても、いい画になる」
凛は、堤防の上から川を見下ろして、淡々と続けた。
「つまり、和真向き」
「……それ、バカにしてる?」
「半分は」
「やっぱりか」
背後から、ぱたぱたと軽い足音がして、次に声が飛んだ。
「わーー!なにここ!エモい!」
桃だった。
夕陽に照らされて、髪の色がやたら綺麗に見える。本人のテンションも、夕陽みたいに高い。
「桃、来たの?」
僕が言うと、桃は胸を張った。
「来たよ。だって文化祭の映画作ろうとしてんでしょ?てか、夕焼け、正解すぎ!」
(正解すぎって……撮る前から褒めるの、やめてほしい)
嬉しいのに、胃がきゅっとなる。
褒められるのは好きだ。けど、期待されるのが怖い。
僕は、しおりのメッセージを頭の中で唱えた。
(次は河川敷。夕焼け。音は拾うな)
「……音は拾わない」
僕は独り言みたいに言って、カメラの設定画面を開いた。
内蔵マイクの入力レベルを下げる。というより、ほぼゼロにする。
念のため、外付けマイクも接続しない。
「音拾わないって、どういうこと?」
桃が不思議そうに首を傾げる。
「無音映画?チャップリン?」
「喋らないで、ってことじゃないの?」
凛が言う。
僕はカメラを構えたまま、夕焼けの空を見上げる。
オレンジから紫へ、境界が溶けるみたいに色が変わっていく。
「和真?」
凛が呼ぶ。
「……うん」
返事はしたのに、意識の一部が過去へ引っ張られていく。
紗季先輩。
映画部の一学年上で、去年まで中心にいた人。
編集も撮影もできて、言葉も強くて、でも、強いだけじゃなくて――誰かを守るみたいに笑う人だった。
(……紗季先輩、最近学校に来てない)
噂は、いくつもあった。
「体調が悪い」とか、「家庭の事情」とか。
でも、映画部の中では、もっと具体的な形でそれが語られていた。
ある動画のせいで。
誰かが撮った映像。
誰かが切り取った一瞬。
それが、勝手に広がって、勝手に意味を持って――取り返しのつかない形で誰かを傷つけた。
(僕は編集担当だ)
切り取る。繋ぐ。見せる。
その全部を、僕はやる。
つまり――僕は、人を救えるかもしれないし、壊せるかもしれない。
「……音は拾わない」
僕はもう一度言った。今度は、自分に言い聞かせるみたいに。
「声は、特に」
桃が少しだけ真面目な顔になる。
「和真、なんか……こわ」
「こわいよ」
僕は笑おうとして、失敗した。
「普通に」
凛が、僕の手元のカメラを覗き込む。
「じゃあ、撮ろ。夕焼けは待ってくれない」
「……うん」
僕はRECを押した。
赤いランプが点灯する。
手だけでいい。
僕は画角を落とす。
川面は入る。夕焼けも入る。だけど、人の顔は入れない。
堤防の草の先を揺らす風。影の長さ。白い石。
そして――手。
桃が、指先で小石を拾って落とした。
ぽちゃん、と音がしそうなのに、音は録らない。
水面の波紋だけが、静かに広がる。
凛が作った紙のフレーム――二号機のしおりを折ったものを、僕のレンズの前にかざした。
穴越しに見る夕陽が、丸いボケになって、画面の中に小さな星を作る。
「……これ、綺麗」
僕は思わず言った。
凛が目を細める。
「だから言った。紙の勝ち」
「またそれ」
「本当に勝ってるもん」
凛は淡々と、でも少しだけ楽しそうに言う。
「覗くって、映画っぽい」
(覗く)
覗くって、悪い言葉にもなる。
盗み見る。勝手に見る。
でも、今この覗くは、違う。見せすぎないための覗きだ。
僕は、凛の手元を追った。
紙のフレームを持つ指。折り目。爪の先。
そこに夕焼けが映り込み、指先が金色に光る。
(……綺麗だ)
自分の心の奥が、すっと軽くなる。
僕の中にあった解散という字幕が、遠のいていく。
代わりに、画面の中の夕焼けが、僕の呼吸を整える。
(映像に救われるって、こういう感じか)
誰かに救われるのは苦手だ。
借りを作るみたいで、怖い。
でも、映像なら借りじゃない。
僕が見つけた光で、僕が息をしているだけだ。
「……和真」
凛が小さく言う。
「今の、顔、いい」
「顔は撮らないって」
「撮らなくても分かる。変な顔してる」
凛は容赦なく言ってから、ふっと声を落とした。
「――でも、少し、生き返ってる」
僕はカメラを下ろして、喉の奥が熱くなるのを誤魔化した。
「……生き返ってない。たぶん」
「たぶん禁止」
桃が横から口を挟む。
「え、なにそれ。二人、ルール多くない?」
「文化祭までに結果が出ないなら解散だから」
僕は即答する。
桃は「うっ」と詰まって、すぐに明るく笑った。
「じゃあ結果出そ!ほら、手!手で演技するやつ!」
「手で演技って何」
僕が言うと、桃は真剣な顔で両手を差し出した。
「手で……悲しみとか、恋とか、表現できるでしょ?」
(恋)
その単語が出ただけで、心臓が余計なことをする。
音を拾わない設定にしておいて正解だ。僕の心臓は無断で主張しすぎる。
凛が桃の手を見て、少しだけ考える顔をした。
「……できる。むしろ、手の方が嘘つけない」
「でしょ!」
桃が得意げに言って、僕の方を見た。
「ね、和真、撮って!」
僕は、頷いた。
「……撮る」
たった二文字が、今日は少しだけ重くて、少しだけ嬉しい。
僕は再びRECを押し、桃の手を撮る。
桃は指先を絡めるように動かして、何かを掴む仕草をする。
凛はそれを見て、そっと自分の手を重ねた。
触れるか触れないかの距離。
夕焼けの光が、その隙間に落ちる。
(……これ)
これを繋げていけば、文化祭の映画になるかもしれない。
踏切。白線。境界。
河川敷。夕焼け。沈黙。
手だけで、ここまで語れるなら。
僕は、撮りながら思った。
(僕は、言葉が下手だ。だから映像に逃げてきた。でも、逃げじゃなくて――選べるかもしれない)
撮り終えて、僕らは堤防の斜面に座った。
制服の尻が草で汚れるけど、どうでもいい。
カメラの再生画面で、さっきのカットを確認する。
夕焼けの中で、手だけが動く。
音はない。なのに、うるさいくらい感情が見える。
「……怖いくらい、いい」
僕はぽつりと言った。
桃が「でしょ!」と胸を張る。
凛は頷きながら、僕の横顔を見た。
「音、入れてないのに、音が聞こえるみたいに見える」
凛が言う。
「想像させるって、強い」
「でも……」
僕は言葉を選ぶ。
「音は拾うなって、意味がよく分からない」
桃が指を折る。
「えーと、技術的に?風がうるさいからとか?」
「それもあるかも」
凛が言って、それから少し間を置いた。
「でも私は、別の意味だと思う。……声を映さない配慮かも」
「声を映さない?」
桃が眉を上げる。
「映すのは映像じゃん」
「映像に声が乗ると、誰かが何か別の意味を持たせる」
凛は淡々と答える。
「それが嫌だったんじゃない?」
その瞬間、僕の頭の中で、紗季先輩の笑い声が浮かんだ。
部室で、編集画面を覗き込んで、「ここ、切ると人が泣くよ」って冗談みたいに言った声。
そして次に、聞いたことのない冷たい噂が浮かぶ。
――紗季先輩は、ある動画のせいで学校に来られなくなっている。
僕は、息を吸ってから吐いた。
言うか迷う。
でも、言わないと、また僕は逃げる。
「……紗季先輩」
僕が言うと、凛の視線が動いた。桃の表情も少し固まる。
「去年の先輩」
僕は続ける。
「映画部の……」
桃が小さく頷く。
「うん。紗季先輩、最近見ない」
僕は唇を噛んでから、言った。
「……ある動画のせいで、学校に来られなくなってるって聞いた」
桃が目を逸らす。凛は黙ったまま、指先で草をちぎる。
沈黙が、夕焼けより重い。
「僕は、詳しく知らない」
僕は必死に言葉を繋いだ。
「でも……動画って、切り取られる。勝手に広がる。戻らない」
凛が小さく言った。
「だから、手だけでいいなのかもね」
「……うん」
桃が、いつもの軽さを捨てた声で言った。
「バズるって、いいことだけじゃないよね」
僕は頷いた。
「だから、音も……拾わない。声は、特に」
凛は、少しだけ遠くを見る顔をしてから、僕の方に向き直った。
「次の指示、知りたい?」
「……知りたい」
僕は即答した。
知りたい。怖い。でも、止まったら終わる。
「指示を見るには、あの本が必要だよね」
僕は言う。
「でも、僕……凜に返しちゃった」
凛は小さく息を吐いて、バッグの中から例の古い文庫本を取り出した。
「はい」
「え、いいの?」
「当然」
凛は得意げでもなく、ただ事務的に言った。
「きちんと貸出手続きしておいてあるから」
「……すごいね」
僕は正直に言った。
「ちゃんとしてる」
「当たり前」
凛はさらっと言う。
「当たり前をやらない人が多すぎるだけ」
桃が横で「刺さる〜」と小声で言い、僕はちょっとだけ救われた気がした。
(刺さるのは僕だけじゃない。よかった)
僕は本を受け取り、例の不自然なページを探す。
数ページめくると、また意味のない文字列のページが現れた。
(来た)
僕は穴あき栞を重ねる。
凛が作った二号機でも、元の栞でも、穴の位置は同じだ。
穴の中の文字だけが、すっと整列する。
「……見せない優しさを覚えろ」
僕は声に出して読んだ。
読んだ瞬間、胸の奥が、痛いような、温かいような。
(見せない優しさ)
見せるのが正義だと思っていた。
証拠。結果。作品。
でも、見せないことも、優しさになる。
紗季先輩のことが、また頭をよぎる。
もし先輩がこの言葉を残したのなら――。
夕焼けの最後の光が、川面に一本の道を作っている。
そこを渡っていけば、文化祭に間に合う――そんな気がした。
気がしただけかもしれない。でも、今はそれでいい。
堤防の斜面に伸びる影が長くて、草の先がオレンジ色に燃えている。
川面は、光を反射してちかちかと瞬いて――それが、まるで無数のフィルムの粒みたいに見えた。
(……強い)
僕――和真は、思わず口の中で呟いた。
強いというのは、絵として強い。映像として、黙っていても成立する強さがある。
「やっぱり夕焼け、ずるいよね」
凛が、制服の袖を引っ張りながら言った。
「ずるいって、褒めてる?」
僕はカメラの電源を入れつつ聞く。
「うん。人間が頑張らなくても、いい画になる」
凛は、堤防の上から川を見下ろして、淡々と続けた。
「つまり、和真向き」
「……それ、バカにしてる?」
「半分は」
「やっぱりか」
背後から、ぱたぱたと軽い足音がして、次に声が飛んだ。
「わーー!なにここ!エモい!」
桃だった。
夕陽に照らされて、髪の色がやたら綺麗に見える。本人のテンションも、夕陽みたいに高い。
「桃、来たの?」
僕が言うと、桃は胸を張った。
「来たよ。だって文化祭の映画作ろうとしてんでしょ?てか、夕焼け、正解すぎ!」
(正解すぎって……撮る前から褒めるの、やめてほしい)
嬉しいのに、胃がきゅっとなる。
褒められるのは好きだ。けど、期待されるのが怖い。
僕は、しおりのメッセージを頭の中で唱えた。
(次は河川敷。夕焼け。音は拾うな)
「……音は拾わない」
僕は独り言みたいに言って、カメラの設定画面を開いた。
内蔵マイクの入力レベルを下げる。というより、ほぼゼロにする。
念のため、外付けマイクも接続しない。
「音拾わないって、どういうこと?」
桃が不思議そうに首を傾げる。
「無音映画?チャップリン?」
「喋らないで、ってことじゃないの?」
凛が言う。
僕はカメラを構えたまま、夕焼けの空を見上げる。
オレンジから紫へ、境界が溶けるみたいに色が変わっていく。
「和真?」
凛が呼ぶ。
「……うん」
返事はしたのに、意識の一部が過去へ引っ張られていく。
紗季先輩。
映画部の一学年上で、去年まで中心にいた人。
編集も撮影もできて、言葉も強くて、でも、強いだけじゃなくて――誰かを守るみたいに笑う人だった。
(……紗季先輩、最近学校に来てない)
噂は、いくつもあった。
「体調が悪い」とか、「家庭の事情」とか。
でも、映画部の中では、もっと具体的な形でそれが語られていた。
ある動画のせいで。
誰かが撮った映像。
誰かが切り取った一瞬。
それが、勝手に広がって、勝手に意味を持って――取り返しのつかない形で誰かを傷つけた。
(僕は編集担当だ)
切り取る。繋ぐ。見せる。
その全部を、僕はやる。
つまり――僕は、人を救えるかもしれないし、壊せるかもしれない。
「……音は拾わない」
僕はもう一度言った。今度は、自分に言い聞かせるみたいに。
「声は、特に」
桃が少しだけ真面目な顔になる。
「和真、なんか……こわ」
「こわいよ」
僕は笑おうとして、失敗した。
「普通に」
凛が、僕の手元のカメラを覗き込む。
「じゃあ、撮ろ。夕焼けは待ってくれない」
「……うん」
僕はRECを押した。
赤いランプが点灯する。
手だけでいい。
僕は画角を落とす。
川面は入る。夕焼けも入る。だけど、人の顔は入れない。
堤防の草の先を揺らす風。影の長さ。白い石。
そして――手。
桃が、指先で小石を拾って落とした。
ぽちゃん、と音がしそうなのに、音は録らない。
水面の波紋だけが、静かに広がる。
凛が作った紙のフレーム――二号機のしおりを折ったものを、僕のレンズの前にかざした。
穴越しに見る夕陽が、丸いボケになって、画面の中に小さな星を作る。
「……これ、綺麗」
僕は思わず言った。
凛が目を細める。
「だから言った。紙の勝ち」
「またそれ」
「本当に勝ってるもん」
凛は淡々と、でも少しだけ楽しそうに言う。
「覗くって、映画っぽい」
(覗く)
覗くって、悪い言葉にもなる。
盗み見る。勝手に見る。
でも、今この覗くは、違う。見せすぎないための覗きだ。
僕は、凛の手元を追った。
紙のフレームを持つ指。折り目。爪の先。
そこに夕焼けが映り込み、指先が金色に光る。
(……綺麗だ)
自分の心の奥が、すっと軽くなる。
僕の中にあった解散という字幕が、遠のいていく。
代わりに、画面の中の夕焼けが、僕の呼吸を整える。
(映像に救われるって、こういう感じか)
誰かに救われるのは苦手だ。
借りを作るみたいで、怖い。
でも、映像なら借りじゃない。
僕が見つけた光で、僕が息をしているだけだ。
「……和真」
凛が小さく言う。
「今の、顔、いい」
「顔は撮らないって」
「撮らなくても分かる。変な顔してる」
凛は容赦なく言ってから、ふっと声を落とした。
「――でも、少し、生き返ってる」
僕はカメラを下ろして、喉の奥が熱くなるのを誤魔化した。
「……生き返ってない。たぶん」
「たぶん禁止」
桃が横から口を挟む。
「え、なにそれ。二人、ルール多くない?」
「文化祭までに結果が出ないなら解散だから」
僕は即答する。
桃は「うっ」と詰まって、すぐに明るく笑った。
「じゃあ結果出そ!ほら、手!手で演技するやつ!」
「手で演技って何」
僕が言うと、桃は真剣な顔で両手を差し出した。
「手で……悲しみとか、恋とか、表現できるでしょ?」
(恋)
その単語が出ただけで、心臓が余計なことをする。
音を拾わない設定にしておいて正解だ。僕の心臓は無断で主張しすぎる。
凛が桃の手を見て、少しだけ考える顔をした。
「……できる。むしろ、手の方が嘘つけない」
「でしょ!」
桃が得意げに言って、僕の方を見た。
「ね、和真、撮って!」
僕は、頷いた。
「……撮る」
たった二文字が、今日は少しだけ重くて、少しだけ嬉しい。
僕は再びRECを押し、桃の手を撮る。
桃は指先を絡めるように動かして、何かを掴む仕草をする。
凛はそれを見て、そっと自分の手を重ねた。
触れるか触れないかの距離。
夕焼けの光が、その隙間に落ちる。
(……これ)
これを繋げていけば、文化祭の映画になるかもしれない。
踏切。白線。境界。
河川敷。夕焼け。沈黙。
手だけで、ここまで語れるなら。
僕は、撮りながら思った。
(僕は、言葉が下手だ。だから映像に逃げてきた。でも、逃げじゃなくて――選べるかもしれない)
撮り終えて、僕らは堤防の斜面に座った。
制服の尻が草で汚れるけど、どうでもいい。
カメラの再生画面で、さっきのカットを確認する。
夕焼けの中で、手だけが動く。
音はない。なのに、うるさいくらい感情が見える。
「……怖いくらい、いい」
僕はぽつりと言った。
桃が「でしょ!」と胸を張る。
凛は頷きながら、僕の横顔を見た。
「音、入れてないのに、音が聞こえるみたいに見える」
凛が言う。
「想像させるって、強い」
「でも……」
僕は言葉を選ぶ。
「音は拾うなって、意味がよく分からない」
桃が指を折る。
「えーと、技術的に?風がうるさいからとか?」
「それもあるかも」
凛が言って、それから少し間を置いた。
「でも私は、別の意味だと思う。……声を映さない配慮かも」
「声を映さない?」
桃が眉を上げる。
「映すのは映像じゃん」
「映像に声が乗ると、誰かが何か別の意味を持たせる」
凛は淡々と答える。
「それが嫌だったんじゃない?」
その瞬間、僕の頭の中で、紗季先輩の笑い声が浮かんだ。
部室で、編集画面を覗き込んで、「ここ、切ると人が泣くよ」って冗談みたいに言った声。
そして次に、聞いたことのない冷たい噂が浮かぶ。
――紗季先輩は、ある動画のせいで学校に来られなくなっている。
僕は、息を吸ってから吐いた。
言うか迷う。
でも、言わないと、また僕は逃げる。
「……紗季先輩」
僕が言うと、凛の視線が動いた。桃の表情も少し固まる。
「去年の先輩」
僕は続ける。
「映画部の……」
桃が小さく頷く。
「うん。紗季先輩、最近見ない」
僕は唇を噛んでから、言った。
「……ある動画のせいで、学校に来られなくなってるって聞いた」
桃が目を逸らす。凛は黙ったまま、指先で草をちぎる。
沈黙が、夕焼けより重い。
「僕は、詳しく知らない」
僕は必死に言葉を繋いだ。
「でも……動画って、切り取られる。勝手に広がる。戻らない」
凛が小さく言った。
「だから、手だけでいいなのかもね」
「……うん」
桃が、いつもの軽さを捨てた声で言った。
「バズるって、いいことだけじゃないよね」
僕は頷いた。
「だから、音も……拾わない。声は、特に」
凛は、少しだけ遠くを見る顔をしてから、僕の方に向き直った。
「次の指示、知りたい?」
「……知りたい」
僕は即答した。
知りたい。怖い。でも、止まったら終わる。
「指示を見るには、あの本が必要だよね」
僕は言う。
「でも、僕……凜に返しちゃった」
凛は小さく息を吐いて、バッグの中から例の古い文庫本を取り出した。
「はい」
「え、いいの?」
「当然」
凛は得意げでもなく、ただ事務的に言った。
「きちんと貸出手続きしておいてあるから」
「……すごいね」
僕は正直に言った。
「ちゃんとしてる」
「当たり前」
凛はさらっと言う。
「当たり前をやらない人が多すぎるだけ」
桃が横で「刺さる〜」と小声で言い、僕はちょっとだけ救われた気がした。
(刺さるのは僕だけじゃない。よかった)
僕は本を受け取り、例の不自然なページを探す。
数ページめくると、また意味のない文字列のページが現れた。
(来た)
僕は穴あき栞を重ねる。
凛が作った二号機でも、元の栞でも、穴の位置は同じだ。
穴の中の文字だけが、すっと整列する。
「……見せない優しさを覚えろ」
僕は声に出して読んだ。
読んだ瞬間、胸の奥が、痛いような、温かいような。
(見せない優しさ)
見せるのが正義だと思っていた。
証拠。結果。作品。
でも、見せないことも、優しさになる。
紗季先輩のことが、また頭をよぎる。
もし先輩がこの言葉を残したのなら――。
夕焼けの最後の光が、川面に一本の道を作っている。
そこを渡っていけば、文化祭に間に合う――そんな気がした。
気がしただけかもしれない。でも、今はそれでいい。