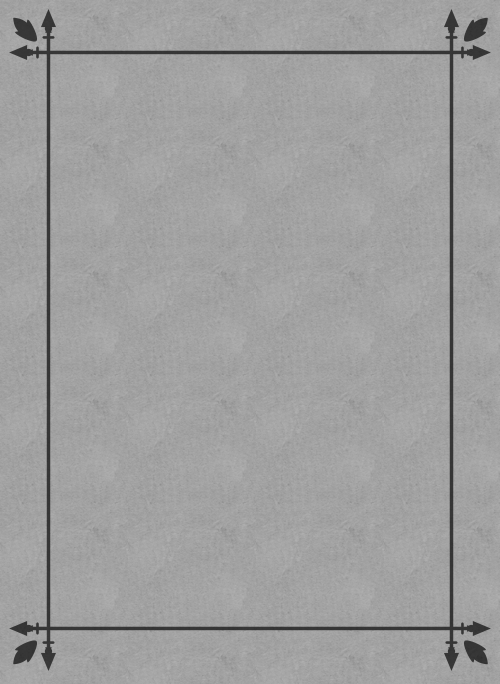家に帰っても、頭の中の踏切が鳴り止まなかった。
カン、カン、カン――
あの音が、耳の奥ではなく胸の奥で反復している。
(やめろ、録音してきたわけじゃないのに)
僕――和真は自室の机にカメラを置き、データをノートPCに取り込んだ。
編集ソフトを立ち上げる。タイムラインはいつものように空っぽで、空っぽだからこそ、吸い込まれそうで怖い。
(でも今日は、素材がある)
踏切。白線。遮断機。風。
そして――手。
再生ボタンを押す。
画面の中で、僕と凛の手が白線の内側へ伸びかけて、止められる。
ほんの一瞬のやり取りなのに、なぜか胸が締まった。
「……」
僕は、思わず無音で笑った。
(笑うな、って誰かに言われてる気がする)
顔を映していないだけで、映像が妙に強く見える。
表情がないぶん、見る側が勝手に感情を補ってしまう。
だから、目が離せない。
(これ……映画っぽくない?)
自分の頭の中でしか鳴っていなかった警報が、別の種類の音に変わる。
「やるしかないぞ」という、静かな拍手みたいな音。
僕はタイムラインにクリップを置いた。
踏切のカット。
次に、凛の手が入るカット。
その横に、白線のカット。
切り貼りして、ほんの十五秒に整える。
たった十五秒なのに、画面に物語が生まれた気がした。
(これを、積み重ねていけば……)
脳内で、部室の顧問の声が蘇る。
『文化祭までに結果が出ないなら、映画部は――解散だ』
(結果。結果ね……)
十五秒じゃ結果にならない。
でも、十五秒が積もるなら、結果になるかもしれない。
(踏切が一章なら、次は二章だ)
僕は、机の上の古い文庫本に手を伸ばした。
正直、読む気はない。読む余裕もない。
僕が欲しいのは、物語じゃなくて指示だ。
(……完全に指示待ち人間だな)
自嘲しながらページをめくる。普通の文章。普通の会話。
数ページ進んで、また――不自然なページにぶつかった。
意味のない文字列。
短い行。整いすぎた並び。
(来た)
ポケットから穴あきしおりを取り出し、ページに重ねる。
穴の中の文字だけが、するりと意味を持つ。
「次は河川敷。夕焼け。音は拾うな」
僕は小声で読み、背筋がぞわっとした。
(河川敷……夕焼け……)
映像のイメージが、勝手に立ち上がる。
水面に反射するオレンジ。堤防の影。風で揺れる草。
映画っぽい絵が、頭の中に並び始める。
(音は拾うな?)
問いが浮かんだが、答えは浮かばなかった。
分からない。けど、知りたい。
知りたいから、撮る。
僕はスマホを手に取り、凛にメッセージを送った。
『次の指示が分かった。河川敷。夕焼け。音は拾うな』
送った直後、(迷惑だったかな)と不安が湧いて、すぐにもう一文送った。
『もし時間あったら、一緒に……』
もしをつけると、逃げ道ができる。
僕の悪い癖だ。
送信。
画面が暗くなるのを見つめながら、僕は思った。
(逃げないでちゃんと最後まで映画を作ってみたい)
翌日、放課後。
図書室の前で凛と合流した。
凛は僕を見るなり、開口一番こう言った。
「まず返して」
「……はい」
僕は古い文庫本を差し出した。
凛はそれを受け取り、貸出カードを確認するでもなく、僕の顔を見た。
「盗難は良くない」
「わかってる」
「わかってるなら、やらない」
「……昨日は、頭が」
「知ってる。顔、死んでた」
淡々と言うくせに、ちゃんと見てるのがこの人だ。
凛は文庫本を抱えたまま、僕の手元を見下ろした。
「で、しおりは?」
僕は穴あきしおりを見せた。
凛が小さく頷く。
「それは……返さないの?」
「返したい。けど、これがないと読めない」
「必要なものなのに持ち出したのは、なお悪い」
「……ぐうの音も出ない」
凛は一瞬だけ口元を緩めた。
そして、バッグから厚紙と小さな穴あけパンチを取り出した。
「だから作る」
「……作る?」
「同じようなの。穴の位置、写せばいいでしょ」
(図書委員って、こんな工作キット持ち歩くの?)
「なんでそんなの持ってるの」
「しおり作りの会があるから」
「あるんだ……」
「うそ。今、作る」
凛は図書室の机に厚紙を置き、穴あきしおりをその上に重ねて、シャーペンで点を打ち始めた。
迷いがない。作業が速い。無駄がない。
(この人、編集向きだな……)
「和真、じっと見ないで。手伝って」
「ごめん。何すればいい」
「穴あけパンチ、押して」
「……押すだけなら得意」
凛が「そこ自慢するところじゃない」と小さく言って、僕の手をパンチに添えた。
指が触れて、心臓が余計なことをし始める。
(やめろ、音を拾うなって言われてるだろ。僕の心臓の音)
穴を開ける。カチン、カチン、と小さな音。
紙が少しずつ鍵になっていく。
凛が完成したしおりを掲げる。
「はい。二号機」
「二号機って言い方、メカっぽい」
「鍵はだいたいメカ」
凛はしおりをくるっと折った。
折り目をつけると、厚紙がフレームみたいな形になる。
「覗く構図、試す?」
「……覗く?」
「昨日の踏切、あれ面白かった。顔を隠してるのに、距離が見える」
凛はフレーム越しに僕を覗き込んだ。
僕の顔は映らないはずなのに、見られてる気がして落ち着かない。
「……やめて」
「何で?」
「心臓がうるさい」
凛が一拍置いてから言う。
「……音、拾わないでね」
(やっぱりこの人、意地悪だ)
凛はスマホを取り出して、フレーム越しに床の木目を撮った。
次に、窓から差し込む夕方の光。
その光が、穴の輪郭を丸く切り取って、紙の上に小さな月みたいな模様を落とす。
「見て」
凛が画面を見せてくる。
そこには、ただの窓際の光が写っているだけなのに、穴越しのボケが映画のレンズみたいに見えた。
「……それ、ズルい」
「ズルくない。紙の勝ち」
「紙の勝ちって何?」
凛が肩をすくめる。
「紙は、覗かせるのが上手い。見せすぎない」
僕はフレームを受け取り、試しに自分の手を撮った。
指先が、穴越しに切り取られて、変な主役感が出る。
(手だけでいい、ってこういうことか)
顔を映さない。
でも、見せたいものは見せる。
見せない優しさと、伝える意志が両立する感じがした。
「……これ、文化祭の映画にできるかもしれない」
僕はぼそっと言った。
凛が、少しだけ目を丸くする。
「え、今さら?聞いたよ、映画部が上手くいってなくて文化祭に参加できないかもって」
「うるさい。今さらでもいいだろ」
「いいよ。今さらでも、今からでも」
凛の返事が、妙にまっすぐで、僕は一瞬だけ言葉を失った。
そのときだった。
「なにそれ、かわいい!」
軽い声が飛んできて、僕は肩をびくっとさせた。
振り向くと、映画部の桃が廊下に立っていた。
いつも通り明るい。明るすぎて、今の僕には眩しい。
「桃……なんでここに」
「職員室帰り。で、何それ?」
桃は凛の手元のフレームと、スマホの写真を覗き込んだ。
そして目を輝かせる。
「うわ、フレーム越しの写真!なにこれ、めっちゃ映える!」
凛が一歩引く。
「覗かないで」
「覗くよ!だって覗くためのやつでしょ!」
桃は悪びれずに言って、僕のスマホも覗こうとする。
「和真のも見せて!」
「やだ」
僕は反射でスマホを引っ込めた。
桃が頬を膨らませる。
「えー、ケチ。……でもこれさ、SNSで絶対バズるって」
その一言が、僕の背中を冷たく撫でた。
バズる。
拡散。
切り抜き。
勝手に広がる。戻せない。
頭の中で、危険な音が鳴る。
どこかの誰かが笑う声。
そして誰かが黙る音。
「……やめとけ」
僕は思ったより低い声で言ってしまった。
「勝手に上げるのは」
桃がきょとんとする。
「え、上げないよ。今すぐは。てか、なんでそんな怖い顔?」
凛が、僕と桃の間に視線を落とした。
「和真、顔」
「……ごめん」
僕は呼吸を整える。
(落ち着け。まだ何も起きてない)
桃は首を傾げながらも、すぐにいつもの調子に戻った。
「でもさ、宣伝に使えるじゃん。文化祭の予告とか。顔出さないならなおさら安心だし」
(顔、出さない。手だけ)
その言葉が、今度は救いみたいに胸に落ちた。
手だけなら、守れる。
守りながら、伝えられる。
僕は、凛の作った二号機のしおりを見た。
穴の向こうに、夕方の廊下の光が見える。
(次は河川敷。夕焼け。音は拾うな)
逃げ道じゃない。
今度は、僕が選ぶ番だ。
カン、カン、カン――
あの音が、耳の奥ではなく胸の奥で反復している。
(やめろ、録音してきたわけじゃないのに)
僕――和真は自室の机にカメラを置き、データをノートPCに取り込んだ。
編集ソフトを立ち上げる。タイムラインはいつものように空っぽで、空っぽだからこそ、吸い込まれそうで怖い。
(でも今日は、素材がある)
踏切。白線。遮断機。風。
そして――手。
再生ボタンを押す。
画面の中で、僕と凛の手が白線の内側へ伸びかけて、止められる。
ほんの一瞬のやり取りなのに、なぜか胸が締まった。
「……」
僕は、思わず無音で笑った。
(笑うな、って誰かに言われてる気がする)
顔を映していないだけで、映像が妙に強く見える。
表情がないぶん、見る側が勝手に感情を補ってしまう。
だから、目が離せない。
(これ……映画っぽくない?)
自分の頭の中でしか鳴っていなかった警報が、別の種類の音に変わる。
「やるしかないぞ」という、静かな拍手みたいな音。
僕はタイムラインにクリップを置いた。
踏切のカット。
次に、凛の手が入るカット。
その横に、白線のカット。
切り貼りして、ほんの十五秒に整える。
たった十五秒なのに、画面に物語が生まれた気がした。
(これを、積み重ねていけば……)
脳内で、部室の顧問の声が蘇る。
『文化祭までに結果が出ないなら、映画部は――解散だ』
(結果。結果ね……)
十五秒じゃ結果にならない。
でも、十五秒が積もるなら、結果になるかもしれない。
(踏切が一章なら、次は二章だ)
僕は、机の上の古い文庫本に手を伸ばした。
正直、読む気はない。読む余裕もない。
僕が欲しいのは、物語じゃなくて指示だ。
(……完全に指示待ち人間だな)
自嘲しながらページをめくる。普通の文章。普通の会話。
数ページ進んで、また――不自然なページにぶつかった。
意味のない文字列。
短い行。整いすぎた並び。
(来た)
ポケットから穴あきしおりを取り出し、ページに重ねる。
穴の中の文字だけが、するりと意味を持つ。
「次は河川敷。夕焼け。音は拾うな」
僕は小声で読み、背筋がぞわっとした。
(河川敷……夕焼け……)
映像のイメージが、勝手に立ち上がる。
水面に反射するオレンジ。堤防の影。風で揺れる草。
映画っぽい絵が、頭の中に並び始める。
(音は拾うな?)
問いが浮かんだが、答えは浮かばなかった。
分からない。けど、知りたい。
知りたいから、撮る。
僕はスマホを手に取り、凛にメッセージを送った。
『次の指示が分かった。河川敷。夕焼け。音は拾うな』
送った直後、(迷惑だったかな)と不安が湧いて、すぐにもう一文送った。
『もし時間あったら、一緒に……』
もしをつけると、逃げ道ができる。
僕の悪い癖だ。
送信。
画面が暗くなるのを見つめながら、僕は思った。
(逃げないでちゃんと最後まで映画を作ってみたい)
翌日、放課後。
図書室の前で凛と合流した。
凛は僕を見るなり、開口一番こう言った。
「まず返して」
「……はい」
僕は古い文庫本を差し出した。
凛はそれを受け取り、貸出カードを確認するでもなく、僕の顔を見た。
「盗難は良くない」
「わかってる」
「わかってるなら、やらない」
「……昨日は、頭が」
「知ってる。顔、死んでた」
淡々と言うくせに、ちゃんと見てるのがこの人だ。
凛は文庫本を抱えたまま、僕の手元を見下ろした。
「で、しおりは?」
僕は穴あきしおりを見せた。
凛が小さく頷く。
「それは……返さないの?」
「返したい。けど、これがないと読めない」
「必要なものなのに持ち出したのは、なお悪い」
「……ぐうの音も出ない」
凛は一瞬だけ口元を緩めた。
そして、バッグから厚紙と小さな穴あけパンチを取り出した。
「だから作る」
「……作る?」
「同じようなの。穴の位置、写せばいいでしょ」
(図書委員って、こんな工作キット持ち歩くの?)
「なんでそんなの持ってるの」
「しおり作りの会があるから」
「あるんだ……」
「うそ。今、作る」
凛は図書室の机に厚紙を置き、穴あきしおりをその上に重ねて、シャーペンで点を打ち始めた。
迷いがない。作業が速い。無駄がない。
(この人、編集向きだな……)
「和真、じっと見ないで。手伝って」
「ごめん。何すればいい」
「穴あけパンチ、押して」
「……押すだけなら得意」
凛が「そこ自慢するところじゃない」と小さく言って、僕の手をパンチに添えた。
指が触れて、心臓が余計なことをし始める。
(やめろ、音を拾うなって言われてるだろ。僕の心臓の音)
穴を開ける。カチン、カチン、と小さな音。
紙が少しずつ鍵になっていく。
凛が完成したしおりを掲げる。
「はい。二号機」
「二号機って言い方、メカっぽい」
「鍵はだいたいメカ」
凛はしおりをくるっと折った。
折り目をつけると、厚紙がフレームみたいな形になる。
「覗く構図、試す?」
「……覗く?」
「昨日の踏切、あれ面白かった。顔を隠してるのに、距離が見える」
凛はフレーム越しに僕を覗き込んだ。
僕の顔は映らないはずなのに、見られてる気がして落ち着かない。
「……やめて」
「何で?」
「心臓がうるさい」
凛が一拍置いてから言う。
「……音、拾わないでね」
(やっぱりこの人、意地悪だ)
凛はスマホを取り出して、フレーム越しに床の木目を撮った。
次に、窓から差し込む夕方の光。
その光が、穴の輪郭を丸く切り取って、紙の上に小さな月みたいな模様を落とす。
「見て」
凛が画面を見せてくる。
そこには、ただの窓際の光が写っているだけなのに、穴越しのボケが映画のレンズみたいに見えた。
「……それ、ズルい」
「ズルくない。紙の勝ち」
「紙の勝ちって何?」
凛が肩をすくめる。
「紙は、覗かせるのが上手い。見せすぎない」
僕はフレームを受け取り、試しに自分の手を撮った。
指先が、穴越しに切り取られて、変な主役感が出る。
(手だけでいい、ってこういうことか)
顔を映さない。
でも、見せたいものは見せる。
見せない優しさと、伝える意志が両立する感じがした。
「……これ、文化祭の映画にできるかもしれない」
僕はぼそっと言った。
凛が、少しだけ目を丸くする。
「え、今さら?聞いたよ、映画部が上手くいってなくて文化祭に参加できないかもって」
「うるさい。今さらでもいいだろ」
「いいよ。今さらでも、今からでも」
凛の返事が、妙にまっすぐで、僕は一瞬だけ言葉を失った。
そのときだった。
「なにそれ、かわいい!」
軽い声が飛んできて、僕は肩をびくっとさせた。
振り向くと、映画部の桃が廊下に立っていた。
いつも通り明るい。明るすぎて、今の僕には眩しい。
「桃……なんでここに」
「職員室帰り。で、何それ?」
桃は凛の手元のフレームと、スマホの写真を覗き込んだ。
そして目を輝かせる。
「うわ、フレーム越しの写真!なにこれ、めっちゃ映える!」
凛が一歩引く。
「覗かないで」
「覗くよ!だって覗くためのやつでしょ!」
桃は悪びれずに言って、僕のスマホも覗こうとする。
「和真のも見せて!」
「やだ」
僕は反射でスマホを引っ込めた。
桃が頬を膨らませる。
「えー、ケチ。……でもこれさ、SNSで絶対バズるって」
その一言が、僕の背中を冷たく撫でた。
バズる。
拡散。
切り抜き。
勝手に広がる。戻せない。
頭の中で、危険な音が鳴る。
どこかの誰かが笑う声。
そして誰かが黙る音。
「……やめとけ」
僕は思ったより低い声で言ってしまった。
「勝手に上げるのは」
桃がきょとんとする。
「え、上げないよ。今すぐは。てか、なんでそんな怖い顔?」
凛が、僕と桃の間に視線を落とした。
「和真、顔」
「……ごめん」
僕は呼吸を整える。
(落ち着け。まだ何も起きてない)
桃は首を傾げながらも、すぐにいつもの調子に戻った。
「でもさ、宣伝に使えるじゃん。文化祭の予告とか。顔出さないならなおさら安心だし」
(顔、出さない。手だけ)
その言葉が、今度は救いみたいに胸に落ちた。
手だけなら、守れる。
守りながら、伝えられる。
僕は、凛の作った二号機のしおりを見た。
穴の向こうに、夕方の廊下の光が見える。
(次は河川敷。夕焼け。音は拾うな)
逃げ道じゃない。
今度は、僕が選ぶ番だ。