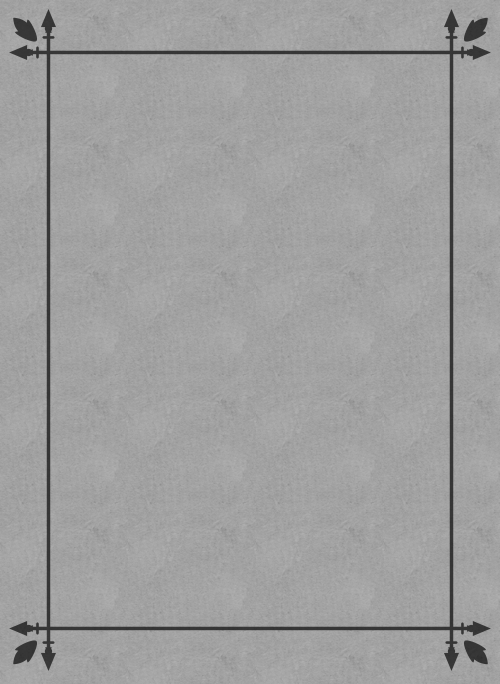踏切に向かう道は、放課後のにおいがした。
制服の袖に残るチョークの粉、部室の埃、教室の熱が冷めていく匂い。
(……僕、ほんとに何してるんだ)
ポケットの奥で、穴あきしおりをそっと触る。
図書室の古い文庫本も、なぜかバッグの中にある。
借りたわけでもないのに持ち出してしまった罪悪感が、胃のあたりで小さく跳ねた。
(これ、図書委員に見つかったら普通に怒られるやつだ)
怒られ慣れてないわけじゃない。
むしろ、怒られるのは慣れてる。
ただ、怒られたあとに何も残らないのが嫌だ。編集みたいに「次に活かす」ってことができない。
踏切は、学校から十分ほどのところにある。
古い住宅街の端っこで、線路だけがきれいにまっすぐで――だから余計に、境界線みたいに見える。
白線。
ここから先に出るなの線。
僕は、指示通りその白線の外側に立った。
踏切の警報機はまだ鳴っていない。遮断機も上がったまま。
車が二台、無関心に通り過ぎる。自転車のベルが遠くで鳴って、犬が一度だけ吠えた。
(待て、って……何を)
誰かが来るのか。
何かが起きるのか。
それとも――僕が、何かを始めるのか。
僕はなんとなく、バッグから小型のカメラを取り出した。
映画部の備品。編集担当の僕が家でデータ整理するために、時々持ち帰っている。
(踏切を……撮れってこと?)
カメラを構える。ファインダーの中に踏切が収まる。
でも、収まっただけだ。
何をどう撮ればいいのか、まるで見えない。
(ダメだ。脳内に絵コンテがない)
編集は「切る」仕事だ。
撮影は「選ぶ」仕事だ。
僕は、選べない。怖いから。選んだ瞬間に責任が発生する。
「……和真?」
背後から名前を呼ばれて、僕の肩が跳ねた。
振り向くと、見慣れた顔がそこにいた。
「……凛?」
凛は同じクラスの図書委員で、いつも背筋がまっすぐで、教科書みたいに無駄がない。
帰宅途中らしく、肩に通学バッグをかけたまま、僕とカメラを交互に見た。
「何してんの、こんなところで。踏切、好きなの?」
「好きじゃない」
即答してしまった。
好きじゃない、って言い切ると、なんだか人生まで否定してる気分になる。
凛は眉を少しだけ上げる。
「じゃあ……撮影?映画部の?」
「……うん。いや、違う。うん、合ってる。たぶん」
自分でも何を言ってるのかわからない。
凛は「たぶんって何」と言いたげな顔をした。
凛は一歩近づいてきて、僕の手元のカメラを覗き込んだ。
覗き込む距離が近い。僕は反射的に一歩引いて、ちょうど白線の外側を守る形になった。
凛が目を細める。
「……白線、意識してる?」
(バレた)
「……してない」
「してる人の否定の仕方だね、それ」
凛の視線が、僕のバッグの口に落ちた。
そこから、古い文庫本の角が覗いている。
「その本……図書室のだよね」
僕の喉が鳴った。
「……ちが、う。たぶん」
「たぶんが多い日だね。もしかして、貸出処理してないのに持ち出した?」
「……」
「図書委員としては、見逃せない」
凛は淡々と言う。淡々としてるのに、逃げ道を塞ぐのが上手い。
僕は観念して、バッグから本を出した。
「……ごめん。ちょっと、事情があって」
「事情、聞かせて。言い訳は要らないから、事実だけ」
(取り調べだ……)
「……本の中に、変なページがあって」
「変なページ?」
僕は本を開いて、あの不自然なページを見せた。意味のない文字列。
さらにポケットから穴あきしおりを取り出して、そっと重ねる。
凛の視線が止まった。
穴の中の文字だけが、言葉になる。
「放課後、踏切。白線の外側で待て」
凛は、瞬きもしないでそれを読んだ。
読んでから、僕を見た。
「……で。今、待ってたわけ?」
「……うん」
「素直だね。意外」
「馬鹿にしてる?」
「半分は。半分は、興味」
凛は腕を組んで、踏切を見た。
「誰が仕掛けたのかは知らないけど……それで、踏切を撮ってたところ?」
僕は言葉に詰まった。
「……うん、でも……どう撮ったら?」
凛が少しだけ呆れた顔をした。
「映画部なのに?」
「僕、撮影担当じゃないんだよ。編集担当」
「編集担当でも、何を撮るか分からないと編集できないでしょ」
「……それは、そう」
刺さる。
凛の言うことは、だいたい刺さる。
僕はカメラを構え直した。
踏切の風景をフレームに入れる。
――入れた。
それで終わり。
「……で?」と凛が言う。
その「で?」の圧が、踏切の遮断機より強い。
「……えっと」
僕は喉の奥から言葉を引っ張り出そうとした。
「……立って」
「誰が?」
「……凛が」
「何のために?」
「……踏切の、絵になるから」
凛は一拍置いて、口角をほんの少しだけ上げた。
「絵になるからって、雑すぎない?」
(雑だよ!わかってるよ!)
「いや、ちがう、そうじゃなくて――」
「じゃあ、どういうカットが欲しいの?」
凛は真面目な顔で聞いてくる。「引き?寄り?何を主役にする?踏切?人?音?」
「お、おと……?」
僕が言った瞬間、凛が小さく首を傾げた。
「踏切って、音が強いよね。ベルと遮断機と電車。音を主役にするなら、画は逆に静かな方がいい」
(この人、なんで急に撮影監督みたいなこと言うの)
「凛、映画詳しいの?」
「詳しくはない」
凛はさらっと言う。
「でも、図書委員だから。物語の見せ方は、少し考える」
僕はカメラを下ろして、息を吐いた。
(……僕より向いてるんじゃないか、映画部)
その瞬間、踏切のベルが鳴った。
カン、カン、カン――
あの規則正しい音が、空気の粒を揺らす。遮断機がゆっくり降り、道路の真ん中を塞ぐ。
凛が言った。
「今だね。撮るなら」
僕は慌ててRECボタンを押した。
赤いランプが点く。
(よし、撮ってる。撮ってるけど――)
「……えっと、」
僕は凛に声をかけようとして、言葉が詰まった。
踏切の前で、凛がどう立てばいい?
どこを見ればいい?
何をすればいい?
僕は、何を撮りたい?
頭の中が真っ白になり、口から出たのは、最悪の一言だった。
「……普通に、してて」
凛がこっちを見た。
「普通って、何」
「……自然体で」
「自然体って、何」
(助けて)
凛は一度だけ深く息を吸うと、諦めたように言った。
「分かった。じゃあ、私が勝手に動く。和真は撮るだけでいい」
「え」
凛は白線の外側にきちんと立ち、指先でスカートの裾を軽く押さえた。
その手が、妙に目に入る。
指先の動きが、踏切のベルより静かに、でも確かに意味を持っている気がした。
凛は遮断機を見たまま、ぼそっと言う。
「編集担当って、切るのは得意でも、始めるのが苦手なんだね」
「……うるさい」
「事実」
電車が通過する。
風が巻き起こる。
髪が少しだけ揺れて、凛の横顔が一瞬だけ――いや、僕は慌てて画角をずらした。
顔を撮るのが怖い。誰かの表情を記録するのが、怖い。
(……僕、何を恐れてるんだ)
RECを止めて、再生する。
画面には踏切。遮断機。道路。凛の肩がほんの少し映り込む。
映像としては、悪くない。けど――
「ただの記録だね」
凛が言った。容赦がない。
「映像じゃなくて、動画」
「……分かってる」
「分かってるなら、改善しよ」
凛は僕の手からカメラをひょいと取った。
「ちょ、勝手に――」
「貸して。今のは和真が悪い」
凛はファインダーを覗き、僕に言った。
「和真、白線の外側、ちゃんと守って」
「そこは守れてるよ!」
凛はカメラを構えたまま、小さく笑った。
「そこだけはね」
(くそ……)
凛は画角を下げた。
顔じゃない。足元。白線。遮断機の影。
境界だけを切り取る。
「……こういうのは?」
凛が小さく言う。
「越えちゃいけない線って、見てるだけで緊張するでしょ」
僕は思わず黙った。
確かに、画面の中の白線は、ただのペンキじゃない。
ルールの匂いがする。
凛がカメラを下ろした。
「で。次の指示は?踏切で待て、で終わり?」
僕ははっとして、本を開いた。
「……他にも、あるかもしれない」
ページをめくる。
次のページも、その次も、普通の文章。
けれど――数ページ先で、また「それ」が来た。
意味のない文字列。
短い行が並んだ、不自然なページ。
「またこれ」
僕の声が少しだけ上ずった。
凛が覗き込む。
「……同じ形式だね。しおり、重ねて」
僕は穴あきしおりを置いた。
手が、さっきより落ち着いている。
理由は分かってる。
(凛がいると、逃げられない)
穴の中の文字だけが浮かび上がる。
「撮るのは顔じゃない。手だけでいい」
凛が先に読んで、ふっと息を吐いた。
僕はその言葉を、何度も頭の中で反芻した。
顔じゃない。手。
それなら、僕にもできる気がした。
表情を撮るのは怖い。でも、手だけなら――。
その時、学校の噂が、脳裏をよぎる。
半年前のこと。
ある生徒が消えたって話。
その話は皆触れないようにしているのに、なぜか思い出して胸の奥が痛む。
凛が言った。
「試しに撮ってみる?」
凛は白線を指さした。「ほら。境界、あるし」
僕は少し迷ってから、カメラを構えた。
今度は、画角をぐっと下げる。
白線の外側。僕の手。
凛の手が、そこに入ってきても――顔は映らない。
「……じゃあ、えっと」
僕は喉を鳴らして、言葉を作った。「凛、手……出して」
凛が一瞬だけ目を丸くした。
「その言い方、雑」
「ごめん!監督の言い方知らない!」
凛は小さく笑って、指先をそっと画面の中に滑り込ませた。
僕の手が白線を越えようとする。
凛の手が、それを軽く止める。
――カン、カン、カン。
踏切のベルが、ちょうどいいタイミングで鳴った。
まるで、誰かが編集点を打ってくれたみたいに。
制服の袖に残るチョークの粉、部室の埃、教室の熱が冷めていく匂い。
(……僕、ほんとに何してるんだ)
ポケットの奥で、穴あきしおりをそっと触る。
図書室の古い文庫本も、なぜかバッグの中にある。
借りたわけでもないのに持ち出してしまった罪悪感が、胃のあたりで小さく跳ねた。
(これ、図書委員に見つかったら普通に怒られるやつだ)
怒られ慣れてないわけじゃない。
むしろ、怒られるのは慣れてる。
ただ、怒られたあとに何も残らないのが嫌だ。編集みたいに「次に活かす」ってことができない。
踏切は、学校から十分ほどのところにある。
古い住宅街の端っこで、線路だけがきれいにまっすぐで――だから余計に、境界線みたいに見える。
白線。
ここから先に出るなの線。
僕は、指示通りその白線の外側に立った。
踏切の警報機はまだ鳴っていない。遮断機も上がったまま。
車が二台、無関心に通り過ぎる。自転車のベルが遠くで鳴って、犬が一度だけ吠えた。
(待て、って……何を)
誰かが来るのか。
何かが起きるのか。
それとも――僕が、何かを始めるのか。
僕はなんとなく、バッグから小型のカメラを取り出した。
映画部の備品。編集担当の僕が家でデータ整理するために、時々持ち帰っている。
(踏切を……撮れってこと?)
カメラを構える。ファインダーの中に踏切が収まる。
でも、収まっただけだ。
何をどう撮ればいいのか、まるで見えない。
(ダメだ。脳内に絵コンテがない)
編集は「切る」仕事だ。
撮影は「選ぶ」仕事だ。
僕は、選べない。怖いから。選んだ瞬間に責任が発生する。
「……和真?」
背後から名前を呼ばれて、僕の肩が跳ねた。
振り向くと、見慣れた顔がそこにいた。
「……凛?」
凛は同じクラスの図書委員で、いつも背筋がまっすぐで、教科書みたいに無駄がない。
帰宅途中らしく、肩に通学バッグをかけたまま、僕とカメラを交互に見た。
「何してんの、こんなところで。踏切、好きなの?」
「好きじゃない」
即答してしまった。
好きじゃない、って言い切ると、なんだか人生まで否定してる気分になる。
凛は眉を少しだけ上げる。
「じゃあ……撮影?映画部の?」
「……うん。いや、違う。うん、合ってる。たぶん」
自分でも何を言ってるのかわからない。
凛は「たぶんって何」と言いたげな顔をした。
凛は一歩近づいてきて、僕の手元のカメラを覗き込んだ。
覗き込む距離が近い。僕は反射的に一歩引いて、ちょうど白線の外側を守る形になった。
凛が目を細める。
「……白線、意識してる?」
(バレた)
「……してない」
「してる人の否定の仕方だね、それ」
凛の視線が、僕のバッグの口に落ちた。
そこから、古い文庫本の角が覗いている。
「その本……図書室のだよね」
僕の喉が鳴った。
「……ちが、う。たぶん」
「たぶんが多い日だね。もしかして、貸出処理してないのに持ち出した?」
「……」
「図書委員としては、見逃せない」
凛は淡々と言う。淡々としてるのに、逃げ道を塞ぐのが上手い。
僕は観念して、バッグから本を出した。
「……ごめん。ちょっと、事情があって」
「事情、聞かせて。言い訳は要らないから、事実だけ」
(取り調べだ……)
「……本の中に、変なページがあって」
「変なページ?」
僕は本を開いて、あの不自然なページを見せた。意味のない文字列。
さらにポケットから穴あきしおりを取り出して、そっと重ねる。
凛の視線が止まった。
穴の中の文字だけが、言葉になる。
「放課後、踏切。白線の外側で待て」
凛は、瞬きもしないでそれを読んだ。
読んでから、僕を見た。
「……で。今、待ってたわけ?」
「……うん」
「素直だね。意外」
「馬鹿にしてる?」
「半分は。半分は、興味」
凛は腕を組んで、踏切を見た。
「誰が仕掛けたのかは知らないけど……それで、踏切を撮ってたところ?」
僕は言葉に詰まった。
「……うん、でも……どう撮ったら?」
凛が少しだけ呆れた顔をした。
「映画部なのに?」
「僕、撮影担当じゃないんだよ。編集担当」
「編集担当でも、何を撮るか分からないと編集できないでしょ」
「……それは、そう」
刺さる。
凛の言うことは、だいたい刺さる。
僕はカメラを構え直した。
踏切の風景をフレームに入れる。
――入れた。
それで終わり。
「……で?」と凛が言う。
その「で?」の圧が、踏切の遮断機より強い。
「……えっと」
僕は喉の奥から言葉を引っ張り出そうとした。
「……立って」
「誰が?」
「……凛が」
「何のために?」
「……踏切の、絵になるから」
凛は一拍置いて、口角をほんの少しだけ上げた。
「絵になるからって、雑すぎない?」
(雑だよ!わかってるよ!)
「いや、ちがう、そうじゃなくて――」
「じゃあ、どういうカットが欲しいの?」
凛は真面目な顔で聞いてくる。「引き?寄り?何を主役にする?踏切?人?音?」
「お、おと……?」
僕が言った瞬間、凛が小さく首を傾げた。
「踏切って、音が強いよね。ベルと遮断機と電車。音を主役にするなら、画は逆に静かな方がいい」
(この人、なんで急に撮影監督みたいなこと言うの)
「凛、映画詳しいの?」
「詳しくはない」
凛はさらっと言う。
「でも、図書委員だから。物語の見せ方は、少し考える」
僕はカメラを下ろして、息を吐いた。
(……僕より向いてるんじゃないか、映画部)
その瞬間、踏切のベルが鳴った。
カン、カン、カン――
あの規則正しい音が、空気の粒を揺らす。遮断機がゆっくり降り、道路の真ん中を塞ぐ。
凛が言った。
「今だね。撮るなら」
僕は慌ててRECボタンを押した。
赤いランプが点く。
(よし、撮ってる。撮ってるけど――)
「……えっと、」
僕は凛に声をかけようとして、言葉が詰まった。
踏切の前で、凛がどう立てばいい?
どこを見ればいい?
何をすればいい?
僕は、何を撮りたい?
頭の中が真っ白になり、口から出たのは、最悪の一言だった。
「……普通に、してて」
凛がこっちを見た。
「普通って、何」
「……自然体で」
「自然体って、何」
(助けて)
凛は一度だけ深く息を吸うと、諦めたように言った。
「分かった。じゃあ、私が勝手に動く。和真は撮るだけでいい」
「え」
凛は白線の外側にきちんと立ち、指先でスカートの裾を軽く押さえた。
その手が、妙に目に入る。
指先の動きが、踏切のベルより静かに、でも確かに意味を持っている気がした。
凛は遮断機を見たまま、ぼそっと言う。
「編集担当って、切るのは得意でも、始めるのが苦手なんだね」
「……うるさい」
「事実」
電車が通過する。
風が巻き起こる。
髪が少しだけ揺れて、凛の横顔が一瞬だけ――いや、僕は慌てて画角をずらした。
顔を撮るのが怖い。誰かの表情を記録するのが、怖い。
(……僕、何を恐れてるんだ)
RECを止めて、再生する。
画面には踏切。遮断機。道路。凛の肩がほんの少し映り込む。
映像としては、悪くない。けど――
「ただの記録だね」
凛が言った。容赦がない。
「映像じゃなくて、動画」
「……分かってる」
「分かってるなら、改善しよ」
凛は僕の手からカメラをひょいと取った。
「ちょ、勝手に――」
「貸して。今のは和真が悪い」
凛はファインダーを覗き、僕に言った。
「和真、白線の外側、ちゃんと守って」
「そこは守れてるよ!」
凛はカメラを構えたまま、小さく笑った。
「そこだけはね」
(くそ……)
凛は画角を下げた。
顔じゃない。足元。白線。遮断機の影。
境界だけを切り取る。
「……こういうのは?」
凛が小さく言う。
「越えちゃいけない線って、見てるだけで緊張するでしょ」
僕は思わず黙った。
確かに、画面の中の白線は、ただのペンキじゃない。
ルールの匂いがする。
凛がカメラを下ろした。
「で。次の指示は?踏切で待て、で終わり?」
僕ははっとして、本を開いた。
「……他にも、あるかもしれない」
ページをめくる。
次のページも、その次も、普通の文章。
けれど――数ページ先で、また「それ」が来た。
意味のない文字列。
短い行が並んだ、不自然なページ。
「またこれ」
僕の声が少しだけ上ずった。
凛が覗き込む。
「……同じ形式だね。しおり、重ねて」
僕は穴あきしおりを置いた。
手が、さっきより落ち着いている。
理由は分かってる。
(凛がいると、逃げられない)
穴の中の文字だけが浮かび上がる。
「撮るのは顔じゃない。手だけでいい」
凛が先に読んで、ふっと息を吐いた。
僕はその言葉を、何度も頭の中で反芻した。
顔じゃない。手。
それなら、僕にもできる気がした。
表情を撮るのは怖い。でも、手だけなら――。
その時、学校の噂が、脳裏をよぎる。
半年前のこと。
ある生徒が消えたって話。
その話は皆触れないようにしているのに、なぜか思い出して胸の奥が痛む。
凛が言った。
「試しに撮ってみる?」
凛は白線を指さした。「ほら。境界、あるし」
僕は少し迷ってから、カメラを構えた。
今度は、画角をぐっと下げる。
白線の外側。僕の手。
凛の手が、そこに入ってきても――顔は映らない。
「……じゃあ、えっと」
僕は喉を鳴らして、言葉を作った。「凛、手……出して」
凛が一瞬だけ目を丸くした。
「その言い方、雑」
「ごめん!監督の言い方知らない!」
凛は小さく笑って、指先をそっと画面の中に滑り込ませた。
僕の手が白線を越えようとする。
凛の手が、それを軽く止める。
――カン、カン、カン。
踏切のベルが、ちょうどいいタイミングで鳴った。
まるで、誰かが編集点を打ってくれたみたいに。