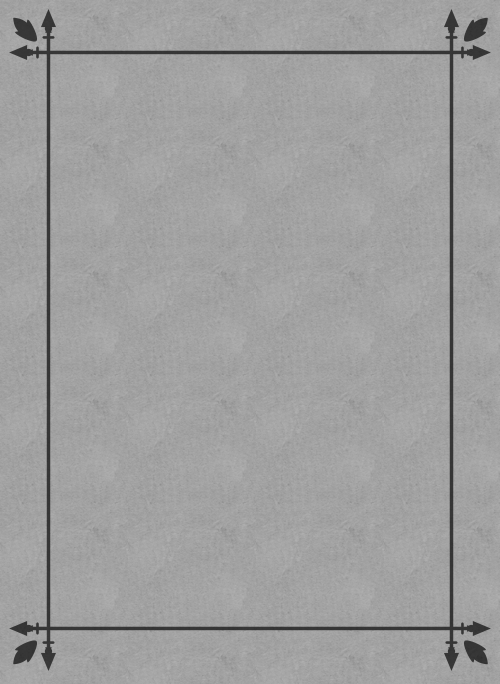「――上映枠、仮のままだってさ」
秋人先輩の声が、部室の空気をいっぺんに冷やした。
ここは視聴覚室の隅を「映画部の部室」と呼び張っている場所で、実態は古い編集用パソコンと三脚と埃の集合体だ。蛍光灯の片方が点滅していて、まるで「時間がないぞ」とモールス信号でも打っているみたいにチカチカしている。
「仮って……え、どういうこと?」
桃が眉を上げる。
秋人先輩は生徒会から回ってきた紙をひらひらさせた。
紙の上の文字は、見慣れた学校印刷のフォントなのに、やけに刺さる。
「提出物が揃ってないと、文化祭の上映枠は確定できない、だって。企画書と仮編集。今週中。出なけりゃ、枠は他の団体に回すってさ」
「今週中!?」
春斗が椅子の背にもたれたまま声を裏返した。「無理じゃね?俺たち、まだ撮影半分――」
「無理かどうか決めるのは生徒会じゃない」
顧問の佐伯先生が、机の角に指を置いて言った。声は低い。怒鳴っていないのに、怒鳴られるより怖いタイプのトーンだ。
先生はいつも淡々とを装う。装ってるだけで、内心はまあまあ怒ってる。
「君たちが出すか出さないか。それだけだ」
僕――和真は、編集用パソコンの前で固まっていた。
画面に映っているのは編集ソフトのタイムライン。素材の箱は空っぽじゃない。空っぽじゃない、はず。入っているのに、入っていないみたいに見える。
細切れの動画。途切れた音声。手ブレ。風の音。誰かの笑い声。
映像を繋げらない焦りがふつふつと湧き上がる。
「和真」
名前を呼ばれて、肩が跳ねた。秋人先輩が僕を見ている。みんなも。
視線って、映像より重い。編集してカットできないから。
「仮編集、どうなってる?」
秋人先輩は穏やかに聞いた。穏やかに聞いてるのが一番怖い。
「……いま、組んでます」
口が勝手に答えていた。
「組んでます」という言葉は便利だ。どの段階でも言える。言い訳の万能選手。タイムラインに何か並んでいるふりをしていれば、努力している人間に見える……たぶん。
桃が、ため息をついた。
「和真、ここ一週間ずっと『組んでます』って言ってない?さすがに……」
「素材が、足りないんだよ」
言い返してしまう。
言い返した瞬間、(あ、これ、嫌われるやつだ)と自分で思う。
「足りないって」春斗が手を振った。「撮影予定、ずっと和真の編集に合わせて空けてたじゃん。逆だろ。編集が遅いから撮影が止まってんの」
「止めてるのは和真じゃない」
秋人先輩が言う。
否定してくれたように見えて、その次の一言で僕の心臓は落ちた。
「でも、最後に形にするのは編集だ。和真、そこは頼む。頼むから――」
頼む。頼まれる。
頼まれるのは嫌いじゃない。むしろ、好きだ。
だけどそれは、できるときに限る。
できないときの「頼む」は、首にかけられるロープのようだ。
顧問の佐伯先生が、紙を机に置いた。
コツン、と音がして、全員の呼吸が揃った気がした。
「はっきり言う」
先生は僕らを見回し、最後に僕の目のあたりを通り過ぎた。真正面からは見ない。見られたら崩れるのが分かってるから。
「文化祭までに結果が出ないなら、映画部は――解散だ」
「……っ」
桃が息を吸い込む音。
春斗が「え、マジで?」と小さく言う音。
秋人先輩が歯を噛む音。
僕は、音が遠くなるのを感じた。
耳の奥に薄い膜が張って、世界が一段、ガラス越しになる。
解散という二文字が、画面の中央に字幕みたいに浮かぶ。白いゴシック体で、無慈悲に。
(ああ、これ、僕のせいだ)
そう思うのと同時に、(違う。僕だけのせいじゃない)とも思ってしまう。
自分を守る言い訳が先に立つ。逃げ癖は、こういうときに一番よく動く。
「……先生」秋人先輩が声を絞った。「最低でも、上映枠だけは――」
「枠を守りたいなら、結果を示せ」
佐伯先生は言い切った。
「情熱は提出物にならない。泣くのは上映が終わってからにしろ」
その言葉は正しい。正しすぎて、喉に刺さる。
僕は、椅子から立ち上がった。
立ち上がる理由は思いつく。いつだって思いつく。
人間は逃げる理由だけ、天才になれる。
「……トイレ」
それだけ言って、部室を出た。
返事が返ってくる前に、廊下に出た。
ドアが閉まる音が、背中に貼りついた。
(最悪だ)
廊下の窓から校庭が見える。夕方の光が、グラウンドの白線をやけに白く見せていた。
白線。境界。ここから外に出るな、って線。
僕は足早に階段を下り、職員室の前を通り過ぎ、正面玄関の方向へ……行かない。
帰ったら終わる。帰ったら、明日も同じだ。
だから、行く場所を変える。
いつもの逃げ道――図書室。
図書室のドアを押すと、冷えた空気が頬に触れた。
学校の中で、ここだけ時間の流れ方が違う。
紙の匂いと、インクの匂いと、静けさ。
人の声がないだけで、こんなに呼吸がしやすいのか、と情けなくなる。
カウンターの向こうに、図書委員の二年生が一人いた。
背筋を伸ばして、何かを書いている。顔は上げない。
僕が誰かなんて、興味もないのだろう。――羨ましい。
(編集は、いい。タイムラインの上では、誰も僕を責めない。ミスしても、Ctrl+Zで戻れる。現実にはないキーだ)
僕は棚の間を抜け、いちばん奥の席に座った。
机の木目に指を這わせる。ざらざらしている。
触れるものがあると、自分がここにいることが確かになる。
(どうすればいいんだ)
頭の中に、部室の空気が戻ってくる。
「解散」
「頼む」
「遅い」
「枠が消える」
映像は好きだ。
好きだから、怖い。
好きなものが壊れる瞬間を自分のせいで迎えるのは、耐えられない。
僕は適当に手に取った本を開いた。
古い文庫本だった。表紙は色褪せて、角が丸い。タイトルは薄くて読みづらい。
借りられた回数を示す貸出票が、何十人分も埋まっている。
ページをめくろうとしたとき、何かが指に当たった。
――しおり?
挟まっていたのは、紐のしおりじゃない。紙片だ。
厚紙を切って作ったみたいな、不格好な形。
そして、いくつもの穴が開いている。
(穴あき……?)
穴は、ただの丸じゃない。配置が妙に整っている。
星座みたいに点が散っていて、見ていると勝手に線で繋ぎたくなる。
僕は栞を抜き取り、光に透かした。
穴の向こうで蛍光灯がぼんやり滲む。
その瞬間、胸の奥が、ほんの少しだけざわついた。
(これ……誰のだ)
「誰の」なんて、考える必要はないはずだ。忘れ物のしおり。図書室にはよくある。
けれど、指先が離れなかった。
紙の端が微妙に毛羽立っていて、手作りの匂いがした。
作った人の時間が染み込んでいる感じがした。
ふと、挟んであった場所のページを見る。
そこには、文章じゃなかった。
短い行が四つ。
意味のある単語に見えない、ひらがなや漢字が混ざった文字列。
(なにこれ……)
僕は思わず周囲を見回した。図書室は静かで、誰も僕を見ていない。
カウンターの図書委員も、相変わらず顔を上げない。
(落書き?いや、印刷ミス……?)
文字列は、手書きじゃない。整っている。
まるで、最初から「こういうページ」として作られたみたいに。
僕は、さっきの穴あきしおりを、そのページの上に置いた。
ただの気まぐれだ。
意味なんてない。
……ない、はずだった。
穴の位置に、ページの文字がぴたりと収まる。
――放
――課
――後
――、
――踏
――切
――。
――白
――線
――の
――外
――側
――で
――待
――て
僕は息を止めた。
(……読めた)
穴の中に見える文字だけが、言葉になっていた。
紙の上の無意味が、穴によって意味になる。
僕の頭の中のごちゃごちゃが、一瞬だけ一本の線で繋がるみたいに。
「放課後、踏切。白線の外側で待て」
声に出して読んでしまい、慌てて口を押さえた。
静けさが、僕の声を吸い込んで、さらに静かになる。
踏切。
学校から十分のところに、古い踏切がある。
白線の外側――遮断機の前に引いてある、あの線。
越えたら危ない、って線。
(誰が、こんな……)
胸の奥で、さっきより大きくざわつく。
恐怖じゃない。興奮とも違う。
「呼ばれている」感覚に近い。
僕みたいな人間を、誰かが名指ししている気がした。
(なんだよ、これ)
笑い飛ばせばいい。
気味悪い。やめよう。忘れよう。
そう思うのに、指はしおりを離せなかった。
穴の向こうに、言葉がある。
穴の外には、いつもの現実がある。
僕はしおりを握りしめて、もう一度ページを見た。
文字列は、相変わらず意味不明のままそこに並んでいる。
穴を通して見ると、確かに言葉が見える。
まるで、僕にだけ読む許可が与えられたみたいに。
(放課後、踏切……)
頭の隅で、顧問の声がリフレインする。
「結果が出ないなら解散」
解散。枠が消える。終わる。
(でも、踏切で待てって……誰が?何が?)
笑ってしまいそうになる。
僕は今、学校の図書室で、謎の指示に心を揺らしている。
まるで安いミステリーの主人公だ。
いや、主人公なら、ここで颯爽と動くだろ。
僕は主人公どころか、編集室でカットされる通行人Aだ。
それでも。
(……行くしかないだろ)
答えが欲しい。
自分がまだ何かできると証明できるものが欲しい。
最悪、踏切に行って何も起きなければ、笑い話にすればいい。
僕はしおりをそっと文庫本から抜き、ページを閉じた。
本を戻すべきか迷って、結局、棚に戻せなかった。
(これ、僕の鍵かもしれない)
自分で言って、また笑いそうになる。
鍵って。
映画部の未来の鍵?
僕の逃げ癖を閉じ込める鍵?
――そんな都合のいいもの、あるわけない。
でも、穴の向こうに言葉が見えたのは事実だ。
僕は立ち上がり、しおりをポケットの奥に滑り込ませた。
外の廊下はすでに放課後になっていた。
秋人先輩の声が、部室の空気をいっぺんに冷やした。
ここは視聴覚室の隅を「映画部の部室」と呼び張っている場所で、実態は古い編集用パソコンと三脚と埃の集合体だ。蛍光灯の片方が点滅していて、まるで「時間がないぞ」とモールス信号でも打っているみたいにチカチカしている。
「仮って……え、どういうこと?」
桃が眉を上げる。
秋人先輩は生徒会から回ってきた紙をひらひらさせた。
紙の上の文字は、見慣れた学校印刷のフォントなのに、やけに刺さる。
「提出物が揃ってないと、文化祭の上映枠は確定できない、だって。企画書と仮編集。今週中。出なけりゃ、枠は他の団体に回すってさ」
「今週中!?」
春斗が椅子の背にもたれたまま声を裏返した。「無理じゃね?俺たち、まだ撮影半分――」
「無理かどうか決めるのは生徒会じゃない」
顧問の佐伯先生が、机の角に指を置いて言った。声は低い。怒鳴っていないのに、怒鳴られるより怖いタイプのトーンだ。
先生はいつも淡々とを装う。装ってるだけで、内心はまあまあ怒ってる。
「君たちが出すか出さないか。それだけだ」
僕――和真は、編集用パソコンの前で固まっていた。
画面に映っているのは編集ソフトのタイムライン。素材の箱は空っぽじゃない。空っぽじゃない、はず。入っているのに、入っていないみたいに見える。
細切れの動画。途切れた音声。手ブレ。風の音。誰かの笑い声。
映像を繋げらない焦りがふつふつと湧き上がる。
「和真」
名前を呼ばれて、肩が跳ねた。秋人先輩が僕を見ている。みんなも。
視線って、映像より重い。編集してカットできないから。
「仮編集、どうなってる?」
秋人先輩は穏やかに聞いた。穏やかに聞いてるのが一番怖い。
「……いま、組んでます」
口が勝手に答えていた。
「組んでます」という言葉は便利だ。どの段階でも言える。言い訳の万能選手。タイムラインに何か並んでいるふりをしていれば、努力している人間に見える……たぶん。
桃が、ため息をついた。
「和真、ここ一週間ずっと『組んでます』って言ってない?さすがに……」
「素材が、足りないんだよ」
言い返してしまう。
言い返した瞬間、(あ、これ、嫌われるやつだ)と自分で思う。
「足りないって」春斗が手を振った。「撮影予定、ずっと和真の編集に合わせて空けてたじゃん。逆だろ。編集が遅いから撮影が止まってんの」
「止めてるのは和真じゃない」
秋人先輩が言う。
否定してくれたように見えて、その次の一言で僕の心臓は落ちた。
「でも、最後に形にするのは編集だ。和真、そこは頼む。頼むから――」
頼む。頼まれる。
頼まれるのは嫌いじゃない。むしろ、好きだ。
だけどそれは、できるときに限る。
できないときの「頼む」は、首にかけられるロープのようだ。
顧問の佐伯先生が、紙を机に置いた。
コツン、と音がして、全員の呼吸が揃った気がした。
「はっきり言う」
先生は僕らを見回し、最後に僕の目のあたりを通り過ぎた。真正面からは見ない。見られたら崩れるのが分かってるから。
「文化祭までに結果が出ないなら、映画部は――解散だ」
「……っ」
桃が息を吸い込む音。
春斗が「え、マジで?」と小さく言う音。
秋人先輩が歯を噛む音。
僕は、音が遠くなるのを感じた。
耳の奥に薄い膜が張って、世界が一段、ガラス越しになる。
解散という二文字が、画面の中央に字幕みたいに浮かぶ。白いゴシック体で、無慈悲に。
(ああ、これ、僕のせいだ)
そう思うのと同時に、(違う。僕だけのせいじゃない)とも思ってしまう。
自分を守る言い訳が先に立つ。逃げ癖は、こういうときに一番よく動く。
「……先生」秋人先輩が声を絞った。「最低でも、上映枠だけは――」
「枠を守りたいなら、結果を示せ」
佐伯先生は言い切った。
「情熱は提出物にならない。泣くのは上映が終わってからにしろ」
その言葉は正しい。正しすぎて、喉に刺さる。
僕は、椅子から立ち上がった。
立ち上がる理由は思いつく。いつだって思いつく。
人間は逃げる理由だけ、天才になれる。
「……トイレ」
それだけ言って、部室を出た。
返事が返ってくる前に、廊下に出た。
ドアが閉まる音が、背中に貼りついた。
(最悪だ)
廊下の窓から校庭が見える。夕方の光が、グラウンドの白線をやけに白く見せていた。
白線。境界。ここから外に出るな、って線。
僕は足早に階段を下り、職員室の前を通り過ぎ、正面玄関の方向へ……行かない。
帰ったら終わる。帰ったら、明日も同じだ。
だから、行く場所を変える。
いつもの逃げ道――図書室。
図書室のドアを押すと、冷えた空気が頬に触れた。
学校の中で、ここだけ時間の流れ方が違う。
紙の匂いと、インクの匂いと、静けさ。
人の声がないだけで、こんなに呼吸がしやすいのか、と情けなくなる。
カウンターの向こうに、図書委員の二年生が一人いた。
背筋を伸ばして、何かを書いている。顔は上げない。
僕が誰かなんて、興味もないのだろう。――羨ましい。
(編集は、いい。タイムラインの上では、誰も僕を責めない。ミスしても、Ctrl+Zで戻れる。現実にはないキーだ)
僕は棚の間を抜け、いちばん奥の席に座った。
机の木目に指を這わせる。ざらざらしている。
触れるものがあると、自分がここにいることが確かになる。
(どうすればいいんだ)
頭の中に、部室の空気が戻ってくる。
「解散」
「頼む」
「遅い」
「枠が消える」
映像は好きだ。
好きだから、怖い。
好きなものが壊れる瞬間を自分のせいで迎えるのは、耐えられない。
僕は適当に手に取った本を開いた。
古い文庫本だった。表紙は色褪せて、角が丸い。タイトルは薄くて読みづらい。
借りられた回数を示す貸出票が、何十人分も埋まっている。
ページをめくろうとしたとき、何かが指に当たった。
――しおり?
挟まっていたのは、紐のしおりじゃない。紙片だ。
厚紙を切って作ったみたいな、不格好な形。
そして、いくつもの穴が開いている。
(穴あき……?)
穴は、ただの丸じゃない。配置が妙に整っている。
星座みたいに点が散っていて、見ていると勝手に線で繋ぎたくなる。
僕は栞を抜き取り、光に透かした。
穴の向こうで蛍光灯がぼんやり滲む。
その瞬間、胸の奥が、ほんの少しだけざわついた。
(これ……誰のだ)
「誰の」なんて、考える必要はないはずだ。忘れ物のしおり。図書室にはよくある。
けれど、指先が離れなかった。
紙の端が微妙に毛羽立っていて、手作りの匂いがした。
作った人の時間が染み込んでいる感じがした。
ふと、挟んであった場所のページを見る。
そこには、文章じゃなかった。
短い行が四つ。
意味のある単語に見えない、ひらがなや漢字が混ざった文字列。
(なにこれ……)
僕は思わず周囲を見回した。図書室は静かで、誰も僕を見ていない。
カウンターの図書委員も、相変わらず顔を上げない。
(落書き?いや、印刷ミス……?)
文字列は、手書きじゃない。整っている。
まるで、最初から「こういうページ」として作られたみたいに。
僕は、さっきの穴あきしおりを、そのページの上に置いた。
ただの気まぐれだ。
意味なんてない。
……ない、はずだった。
穴の位置に、ページの文字がぴたりと収まる。
――放
――課
――後
――、
――踏
――切
――。
――白
――線
――の
――外
――側
――で
――待
――て
僕は息を止めた。
(……読めた)
穴の中に見える文字だけが、言葉になっていた。
紙の上の無意味が、穴によって意味になる。
僕の頭の中のごちゃごちゃが、一瞬だけ一本の線で繋がるみたいに。
「放課後、踏切。白線の外側で待て」
声に出して読んでしまい、慌てて口を押さえた。
静けさが、僕の声を吸い込んで、さらに静かになる。
踏切。
学校から十分のところに、古い踏切がある。
白線の外側――遮断機の前に引いてある、あの線。
越えたら危ない、って線。
(誰が、こんな……)
胸の奥で、さっきより大きくざわつく。
恐怖じゃない。興奮とも違う。
「呼ばれている」感覚に近い。
僕みたいな人間を、誰かが名指ししている気がした。
(なんだよ、これ)
笑い飛ばせばいい。
気味悪い。やめよう。忘れよう。
そう思うのに、指はしおりを離せなかった。
穴の向こうに、言葉がある。
穴の外には、いつもの現実がある。
僕はしおりを握りしめて、もう一度ページを見た。
文字列は、相変わらず意味不明のままそこに並んでいる。
穴を通して見ると、確かに言葉が見える。
まるで、僕にだけ読む許可が与えられたみたいに。
(放課後、踏切……)
頭の隅で、顧問の声がリフレインする。
「結果が出ないなら解散」
解散。枠が消える。終わる。
(でも、踏切で待てって……誰が?何が?)
笑ってしまいそうになる。
僕は今、学校の図書室で、謎の指示に心を揺らしている。
まるで安いミステリーの主人公だ。
いや、主人公なら、ここで颯爽と動くだろ。
僕は主人公どころか、編集室でカットされる通行人Aだ。
それでも。
(……行くしかないだろ)
答えが欲しい。
自分がまだ何かできると証明できるものが欲しい。
最悪、踏切に行って何も起きなければ、笑い話にすればいい。
僕はしおりをそっと文庫本から抜き、ページを閉じた。
本を戻すべきか迷って、結局、棚に戻せなかった。
(これ、僕の鍵かもしれない)
自分で言って、また笑いそうになる。
鍵って。
映画部の未来の鍵?
僕の逃げ癖を閉じ込める鍵?
――そんな都合のいいもの、あるわけない。
でも、穴の向こうに言葉が見えたのは事実だ。
僕は立ち上がり、しおりをポケットの奥に滑り込ませた。
外の廊下はすでに放課後になっていた。