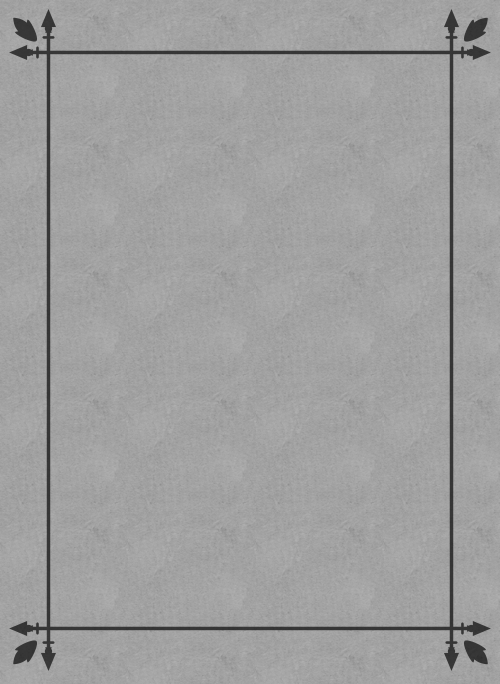編集室は、夜になると水槽みたいに静かだった。
静か、というより――外の世界の音が、ここには届かない。届かせない。そんな意志が壁に染み込んでいる。
蛍光灯の白は、昼間より少しだけ冷たく見えて、机の角をやけに鋭く照らす。光が鋭い分、影だけが濃くなる。影は輪郭を持ち、輪郭は刃みたいに見える。
昼間なら、誰かの足音や笑い声が混じっていたはずの空気が、今はファンの音と、ハードディスクの回転音だけで出来ている。
ブォン、という一定の低音。カリ、という微かな回転の気配。
生命の音というより、機械が「まだ動ける」と証明している音。
人間の声より信用できる、と一瞬思ってしまう自分がいて、すぐに苦くなる。
僕――和真は、椅子に深く腰を落として、マウスを握った。
掌の中のプラスチックの冷たさが、妙に安心に近い。クリックは裏切らない。戻るも進むも、僕が決めた通りに反応する。
指先に、薄い紙の感触が残っている気がする。
穴あきしおり。
あの紙片の角は、何度も僕の指を刺して、何度も僕を現実に引き戻した。
現実っていうのは、痛い。痛いから、今ここにいる。
(……最初のカット)
タイムラインの一番左端。
一番古いクリップ。
踏切。
そのアイコンを見ただけで、胸の奥が小さく鳴った気がした。
「起点」って言葉は、綺麗すぎる。
僕にとってあれは、逃げの始まりで、同時に、逃げの終わりでもあった。
クリックして、再生する。
画面の中で、遮断機がゆっくり降りる。
白線。
その外側に立つ僕の影。
凛の肩が、ほんの少しだけフレームに入り込む。
空気の揺れ、風の気配、遠い車の動き。
そして――頭の中で鳴る。
カン、カン、カン。
同じ映像なのに、今は違って見えた。
映像は変わっていない。フレームも、揺れも、色味も。
変わったのは僕だけだ。
それが怖い。
同じ映像を、違う意味に編集できてしまう自分が怖い。
最初に見たときは、ただの記録だった。
白線の外側で待つ僕の、情けない待機時間。
「何を撮ればいいか分からない」っていう、逃げの映像。
言い換えれば、責任から視線を逸らしたままの映像。
でも今は――
白線が、境界じゃなく見える。
越えちゃいけない線じゃなくて、越えるための線。
あれは「止まれ」じゃなく、「ここからだ」だった。
白線の外側で立ち尽くす僕は、怖がっているだけじゃない。
怖がりながらも、ちゃんと待っていた。
何かが来るのを。誰かが現れるのを。
あるいは、自分が変わる瞬間を。
(僕は、あの日からずっと、何かに追い立てられてたんじゃない。ずっと、何かを選びに行ってたんだ)
凛の手が、僕の手を止める。
その一瞬が、やけに鮮明だった。
触れていないのに、触れている。
声がないのに、会話がある。
言葉にすると軽いのに、映像にすると重い。
映像は、時々、嘘をつかない。
嘘をつかないというより、嘘をつけない部分が勝手に映ってしまう。
……それなのに。
全部、意味なんてなかった。
暗号は、ただの記号だった。
撮影指示なんか、じゃなかった。
それは、あの子が仕掛けた、ただのいたずらだった。
(……そうだ。そうだと分かったのに、僕はまだこの映像を見ている。いたずらでも、ここに僕の息が残っているのは事実だ)
あの日の僕は、確かにそこにいた。
白線の外側に立って、震えながらRECを押した。
凛も、そこにいた。
肩だけ。手だけ。息だけ。
でもいた。
(……紗季先輩)
意識のないベッドの上の顔が浮かぶ。
瞼が閉じて、頬が白くて、機械の音だけが彼女の時間を刻んでいる。
炎上の動画の中の、動く口元が浮かぶ。
『りんにきょかをとれ』
その字幕のような言葉が、何度も僕の脳内で点滅する。
そして、屋上の冷たい金網の感触が、背中に蘇る。
背中の痛みはもう消えているはずなのに、覚えている。
覚えているということは、そこに現実があったということだ。
(凛)
いつもの凛。
おどおどした凛。
そして――いつもの凛じゃない凛。
同じ顔。同じ声。
でも、目の温度が違う。呼吸の仕方が違う。
世界との距離の取り方が違う。
僕は、それを分類したくなる。
名前をつけて安心したくなる。
でも、名前をつけた瞬間、刃先が尖る気がして、飲み込むしかなかった。
タイムラインを少し進める。
河川敷。夕焼け。
商店街のネオン。
息だけのカット。
顔のない映画。
声のない映画。
それなのに、うるさいほど感情がある。
言葉がない分、感情が画面の端から漏れてくる。
僕はスロー再生を止めて、通常速度に戻した。
そして、もう一度最初から繋げて見る。
途切れていたはずのものが、今は一本の線になる。
踏切の白線が、河川敷の影に繋がる。
ネオンの粒が、夕焼けの残光に繋がる。
手の動きが、息の動きに繋がる。
そして、息が――僕の覚悟に繋がる。
(……繋がる)
やっと、繋がる。
繋げてしまった以上、もう切れない。
切るのは得意だった。
でも、繋げる責任を持つのは――今まで避けてきた。
切れば楽だ。不要を捨てた気になれる。
けど、繋ぐのは違う。
繋ぐということは、「これを残す」と決めることだ。
残すということは、誰かの人生に触れることだ。
触れるなら、許可がいる。
許可を取るということは、逃げないということだ。
机の上に置いてあった穴あきしおりを手に取る。
指で穴の縁をなぞると、紙が少し毛羽立っている。
誰かが作った痕跡。
誰かが使った痕跡。
そして――僕が握った痕跡。
僕は椅子を回して、窓の方を向いた。
夜の校舎の外。
遠くの街の灯り。
その向こうに、黒い空。
星は見えない。曇っているのかもしれない。
でも、空は空だ。
見えないからって、なくなるわけじゃない。
見えないものほど、勝手に意味を与えられる。
噂みたいに。炎上みたいに。
だから、見えないものを見えないままにしておく勇気が、たぶん必要なんだ。
穴あきしおりを目の前にかざす。
穴の向こうに、切り取られた空が見える。
星座みたいな配置。
覗くと、世界が少しだけ映画っぽくなる。
画面が狭くなるぶん、目が離せなくなる。
見せない優しさって、こういうことなのかもしれない。
全部を見せない。全部を言わない。
でも、伝えたいところだけは、ちゃんと残す。
「君のお遊びに振り回された結果だとしても、僕はこれを映画にするよ、凛」
文化祭の締切りまでは、あともう少し。
時間は少ない。
現実は容赦がない。
削れば短くなる。切れば綺麗になる。
でも、綺麗にした瞬間に嘘になることもある。
だから、綺麗にしない。
ちゃんと、汚れたまま繋ぐ。
でも――もう逃げない。
白線の外側で待っていた僕は、いま、白線の内側へ手を伸ばしている。
触れたら切れるかもしれない。
触れたら燃えるかもしれない。
それでも、触れないまま終わるよりはいい。
触れたうえで、刃先を丸める。
それが僕の仕事だ。
編集担当って、そういう意味だったんだ。
僕はしおりを机に置き、マウスを握り直した。
タイムラインの先へ、カーソルを進める。
進めるというだけで、少し怖い。
怖いのに、進む。
カットを繋げる。
音を選ぶ。
見せるものと、見せないものを決める。
編集室のファンが、一定のリズムで鳴る。
それは踏切のベルよりずっと静かで、ずっと優しいリズムだった。
僕は、そのリズムに背中を押されるみたいに、最後にもう一度深く息を吐いてから――
僕は、再生ボタンを押した。
静か、というより――外の世界の音が、ここには届かない。届かせない。そんな意志が壁に染み込んでいる。
蛍光灯の白は、昼間より少しだけ冷たく見えて、机の角をやけに鋭く照らす。光が鋭い分、影だけが濃くなる。影は輪郭を持ち、輪郭は刃みたいに見える。
昼間なら、誰かの足音や笑い声が混じっていたはずの空気が、今はファンの音と、ハードディスクの回転音だけで出来ている。
ブォン、という一定の低音。カリ、という微かな回転の気配。
生命の音というより、機械が「まだ動ける」と証明している音。
人間の声より信用できる、と一瞬思ってしまう自分がいて、すぐに苦くなる。
僕――和真は、椅子に深く腰を落として、マウスを握った。
掌の中のプラスチックの冷たさが、妙に安心に近い。クリックは裏切らない。戻るも進むも、僕が決めた通りに反応する。
指先に、薄い紙の感触が残っている気がする。
穴あきしおり。
あの紙片の角は、何度も僕の指を刺して、何度も僕を現実に引き戻した。
現実っていうのは、痛い。痛いから、今ここにいる。
(……最初のカット)
タイムラインの一番左端。
一番古いクリップ。
踏切。
そのアイコンを見ただけで、胸の奥が小さく鳴った気がした。
「起点」って言葉は、綺麗すぎる。
僕にとってあれは、逃げの始まりで、同時に、逃げの終わりでもあった。
クリックして、再生する。
画面の中で、遮断機がゆっくり降りる。
白線。
その外側に立つ僕の影。
凛の肩が、ほんの少しだけフレームに入り込む。
空気の揺れ、風の気配、遠い車の動き。
そして――頭の中で鳴る。
カン、カン、カン。
同じ映像なのに、今は違って見えた。
映像は変わっていない。フレームも、揺れも、色味も。
変わったのは僕だけだ。
それが怖い。
同じ映像を、違う意味に編集できてしまう自分が怖い。
最初に見たときは、ただの記録だった。
白線の外側で待つ僕の、情けない待機時間。
「何を撮ればいいか分からない」っていう、逃げの映像。
言い換えれば、責任から視線を逸らしたままの映像。
でも今は――
白線が、境界じゃなく見える。
越えちゃいけない線じゃなくて、越えるための線。
あれは「止まれ」じゃなく、「ここからだ」だった。
白線の外側で立ち尽くす僕は、怖がっているだけじゃない。
怖がりながらも、ちゃんと待っていた。
何かが来るのを。誰かが現れるのを。
あるいは、自分が変わる瞬間を。
(僕は、あの日からずっと、何かに追い立てられてたんじゃない。ずっと、何かを選びに行ってたんだ)
凛の手が、僕の手を止める。
その一瞬が、やけに鮮明だった。
触れていないのに、触れている。
声がないのに、会話がある。
言葉にすると軽いのに、映像にすると重い。
映像は、時々、嘘をつかない。
嘘をつかないというより、嘘をつけない部分が勝手に映ってしまう。
……それなのに。
全部、意味なんてなかった。
暗号は、ただの記号だった。
撮影指示なんか、じゃなかった。
それは、あの子が仕掛けた、ただのいたずらだった。
(……そうだ。そうだと分かったのに、僕はまだこの映像を見ている。いたずらでも、ここに僕の息が残っているのは事実だ)
あの日の僕は、確かにそこにいた。
白線の外側に立って、震えながらRECを押した。
凛も、そこにいた。
肩だけ。手だけ。息だけ。
でもいた。
(……紗季先輩)
意識のないベッドの上の顔が浮かぶ。
瞼が閉じて、頬が白くて、機械の音だけが彼女の時間を刻んでいる。
炎上の動画の中の、動く口元が浮かぶ。
『りんにきょかをとれ』
その字幕のような言葉が、何度も僕の脳内で点滅する。
そして、屋上の冷たい金網の感触が、背中に蘇る。
背中の痛みはもう消えているはずなのに、覚えている。
覚えているということは、そこに現実があったということだ。
(凛)
いつもの凛。
おどおどした凛。
そして――いつもの凛じゃない凛。
同じ顔。同じ声。
でも、目の温度が違う。呼吸の仕方が違う。
世界との距離の取り方が違う。
僕は、それを分類したくなる。
名前をつけて安心したくなる。
でも、名前をつけた瞬間、刃先が尖る気がして、飲み込むしかなかった。
タイムラインを少し進める。
河川敷。夕焼け。
商店街のネオン。
息だけのカット。
顔のない映画。
声のない映画。
それなのに、うるさいほど感情がある。
言葉がない分、感情が画面の端から漏れてくる。
僕はスロー再生を止めて、通常速度に戻した。
そして、もう一度最初から繋げて見る。
途切れていたはずのものが、今は一本の線になる。
踏切の白線が、河川敷の影に繋がる。
ネオンの粒が、夕焼けの残光に繋がる。
手の動きが、息の動きに繋がる。
そして、息が――僕の覚悟に繋がる。
(……繋がる)
やっと、繋がる。
繋げてしまった以上、もう切れない。
切るのは得意だった。
でも、繋げる責任を持つのは――今まで避けてきた。
切れば楽だ。不要を捨てた気になれる。
けど、繋ぐのは違う。
繋ぐということは、「これを残す」と決めることだ。
残すということは、誰かの人生に触れることだ。
触れるなら、許可がいる。
許可を取るということは、逃げないということだ。
机の上に置いてあった穴あきしおりを手に取る。
指で穴の縁をなぞると、紙が少し毛羽立っている。
誰かが作った痕跡。
誰かが使った痕跡。
そして――僕が握った痕跡。
僕は椅子を回して、窓の方を向いた。
夜の校舎の外。
遠くの街の灯り。
その向こうに、黒い空。
星は見えない。曇っているのかもしれない。
でも、空は空だ。
見えないからって、なくなるわけじゃない。
見えないものほど、勝手に意味を与えられる。
噂みたいに。炎上みたいに。
だから、見えないものを見えないままにしておく勇気が、たぶん必要なんだ。
穴あきしおりを目の前にかざす。
穴の向こうに、切り取られた空が見える。
星座みたいな配置。
覗くと、世界が少しだけ映画っぽくなる。
画面が狭くなるぶん、目が離せなくなる。
見せない優しさって、こういうことなのかもしれない。
全部を見せない。全部を言わない。
でも、伝えたいところだけは、ちゃんと残す。
「君のお遊びに振り回された結果だとしても、僕はこれを映画にするよ、凛」
文化祭の締切りまでは、あともう少し。
時間は少ない。
現実は容赦がない。
削れば短くなる。切れば綺麗になる。
でも、綺麗にした瞬間に嘘になることもある。
だから、綺麗にしない。
ちゃんと、汚れたまま繋ぐ。
でも――もう逃げない。
白線の外側で待っていた僕は、いま、白線の内側へ手を伸ばしている。
触れたら切れるかもしれない。
触れたら燃えるかもしれない。
それでも、触れないまま終わるよりはいい。
触れたうえで、刃先を丸める。
それが僕の仕事だ。
編集担当って、そういう意味だったんだ。
僕はしおりを机に置き、マウスを握り直した。
タイムラインの先へ、カーソルを進める。
進めるというだけで、少し怖い。
怖いのに、進む。
カットを繋げる。
音を選ぶ。
見せるものと、見せないものを決める。
編集室のファンが、一定のリズムで鳴る。
それは踏切のベルよりずっと静かで、ずっと優しいリズムだった。
僕は、そのリズムに背中を押されるみたいに、最後にもう一度深く息を吐いてから――
僕は、再生ボタンを押した。