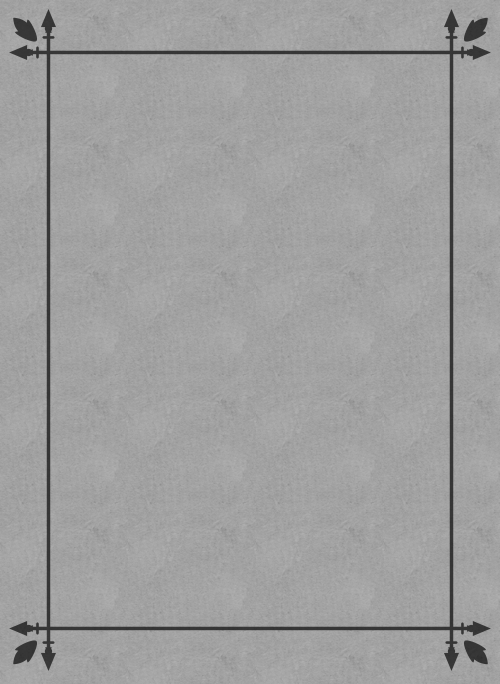背中に食い込む金網の冷たさが、じわじわ痛みに変わっていく。
フェンスの網目がシャツ越しに肌へ押し付けられて、呼吸のたびに擦れた。
(痛い。強い。――この凛は、また別の凛だ)
目の前の凛は、笑っていないのに笑っているみたいな顔をしていた。
口角だけが、薄く上がっている。
目は、僕の逃げる場所を探すのを楽しんでいる。
「本当のことを知りたい?」
僕の胸の奥が、嫌な音を立てた。
知りたい。
でも、知ったら戻れない気がする。
僕は、震える声で言った。
「……知りたい。もう……逃げたくない」
凛は、ふっと鼻で笑った。
「じゃあ、話す」
凛は言った。
「今までの暗号――あれ、全部あたしが仕組んだの」
「……え?」
「半年前の、ただのいたずら」
凛はさらっと言う。
「寄贈棚とか、文庫本とか。穴あきしおりとか。紙の暗号とか。そういうの、面白いじゃない?」
背中が冷える。
紙の中から始まったものが、急に地面に落とされたみたいに、軽く言われる。
「……いたずら?」
声が裏返る。
「うん。だって学校って退屈だし」
凛の目が細くなる。
「でもね、そこにたまたま紗季先輩が引っかかった」
僕の喉が鳴った。
凛は続ける。止まらない。止める気がない。
「先輩が暗号を見つけてさ。『これ、映画にできる』って目を輝かせたの」
凛は、まるで他人事のように言った。
「コンクール用の作品にしようとしてた。あたしの遊びを、勝手に作品にしようとしてた」
「……勝手に、って」
僕は反射で言い返しそうになって、飲み込んだ。
今は、反論したら負ける気がする。
いや、勝ち負けじゃない。
でも、この凛のペースに乗ったら、僕は息ができなくなる。
凛は、僕の胸元を掴んだまま言った。
「映画を作る過程でね、二人目の凛を泣かせたの」
二人目――おどおどした凛。
僕の胸が、痛む。
「……泣かせた?」
僕は聞き返す。
凛は口角を上げた。
「あの子、久しぶりに外側に出てきたのに。先輩、勝手に撮った」
凛の声が少しだけ荒くなる。
「作品のためって顔して。許可も取らないで。あの子、パニックになって泣いた」
(先輩……)
手紙の文字が、胸に刺さる。
> 私は過ちを犯した。
その過ちの輪郭が、今、歪な形で一致していく。
「許せなくて」
凛が言った。
「制裁のため、勝手に動画を撮ったことは許す――って、あたしは先輩に言ったの」
「……許す?」
僕の声が掠れた。
「そう」
凛は淡々と頷く。
「『許すから、公民館の裏で撮り直そう』って誘い出した。優しいふりしてね」
背中の金網が、急に痛い。
痛いのに、痛みが遠い。
現実感が薄い。
「……火事」
僕はやっと絞り出す。
「火事は……事故じゃ……」
凛は、笑った。今度はちゃんと笑った。
薄い笑い。軽い笑い。人を踏むときの笑い。
「動画を撮ってあげるって言って」
凛は言った。
「火事を起こしたの。先輩が燃えるところまで、ちゃんとね」
僕の頭の中が、真っ白になる。
(何を言ってる?何を――言ってる?)
「それで、その動画を拡散させた」
凛の声が、平坦に続く。
「炎上って言葉、ぴったりでしょ。物理でも、比喩でも」
胃が、ひっくり返りそうだった。
「……何を言ってる?」
僕はやっと言えた。
声が、怒りなのか恐怖なのか分からない震え方をしていた。
凛は肩をすくめる。
「本の暗号だけじゃ面白くないから」
凛は言う。
「新しく、紗季先輩が書いた風に見える手紙とかも追加した。フェンスに引っかかっていた封筒とか、病院の自販機とかね」
(……全部。全部、あれも、これも)
僕の中で、今まで積み上げてきた意味が、崩れていく。
踏切も、夕焼けも、息も。
全部、誰かの遊びだった?
凛は楽しそうに続けた。
「皆、紗季先輩が反省したように美談としてまとめようとしてるのが楽しい」
凛の目が光る。
「『見せない優しさ』とか『許可を獲れ』とかさ。いい言葉だよね。気持ちよくなれる」
僕は、喉が張り付いて、声が出ない。
出たとしても、刃になる気がする。
でも、言わなきゃいけない。
「……お前」
言い方が乱れて、自分で自分に驚いた。
「何してるんだよ……」
凛は、急に顔を歪めた。
怒りの歪み。冷たい怒り。
「悪気がなかった?」
凛が吐き捨てる。
「そんなことで許されるはずがないのよ」
僕の胸元を掴む指に、力が入る。
背中が金網に押し付けられ、痛みが鮮明になる。
「見せない優しさ?許可を獲れ?」
凛は笑う。笑っていない目で。
「ねえ、そんなこと人に迷惑かける前提じゃない?」
「……」
「私、そういうの大っ嫌いなのよ」
凛の声が、低く震える。
「それで人を傷つけても、反省した顔をすれば許されると思ってるのよ。いえ、気にも留めてないのよ、そういう人たちは」
息が詰まる。
凛の言葉は、刃だ。
刃先が丸まっていない。むしろ刃を研いでいる。
(お前が言うな)
そう叫びたかった。
火を起こして、人を半年眠らせておいて。
動画を拡散しておいて。
それでもなお、嫌いだと正義みたいに言うのか。
でも僕は叫べない。
叫んだら、この人は本当に何かする。
僕の喉の奥が、それを理解している。
「……俺に何をしてほしいんだ?」
僕は、絞り出すように言った。
「真実を言ったってことは、何か――」
凛は、肩をすくめた。
驚くほどあっさり。
「あんたは最後まで、あたしのお遊びに付き合ってくれたから真実を話しただけ」
凛は言った。
「殺したりはしないわ。ただ――」
凛の顔が、ぐっと近づく。
息がぶつかる距離。
「誰にも話さなければ」
喉の奥が冷たくなる。
僕は、頷く以外の選択肢を見つけられなかった。
「……分かった」
僕は言った。
「約束する」
約束。
その言葉が、今は汚れて聞こえた。
でも、生き残るためには必要な言葉だった。
凛は満足したみたいに、指の力を少しだけ緩める。
背中の痛みが、呼吸に追いついてくる。
その隙間で、僕は最後の質問を投げた。
投げるのが怖い。
でも、投げなければ僕はここで壊れる。
「ただもう一つだけ聞かせてくれ」
僕は言う。
「いつもの凜は、このことを知っているのか?」
凛は、目を細めた。
そして、唇だけで笑う。
「知らないわ」
凛は言った。
「……たぶん」
その「たぶん」が、妙に残酷だった。
凛の中で、記憶は共有されていない。
罪も、痛みも、誰かの内側に封じ込められている。
次の瞬間、凛の目の光がふっと変わった。
肩が落ち、呼吸が整い、背筋がいつもの角度に戻る。
手が離れる。
凛が一歩下がって、眉をひそめた。
「……何してるの、こんなところで」
凛が言った。
いつもの凛の声。いつもの凛の温度。
僕は背中を押さえた。金網の跡がじんと痛い。
痛いのに、凛はまるで見えないみたいに僕を見る。
「和真?」
凛が首を傾げる。
「顔色悪い。……朝から屋上は寒いって言ったじゃん」
(……忘れてる。いや、なかったことになってる)
凛は腕時計を見て、舌打ちしそうな勢いで言った。
「やばい。もうすぐチャイム。行くよ」
そう言って、凛は何事もなかったように屋上の扉へ向かった。
背中が、いつもの凛の背中だ。
さっきの凶暴さなんて、最初から存在しなかったみたいに。
僕は、動けなかった。
動けないまま、凛が扉を開ける音を聞いた。
「ほら、和真。遅刻する」
凛が振り返って言う。
いつも通りの言い方。いつも通りの刺さる声。
僕は、ふらつく足で一歩踏み出した。
そして、凛の後ろ姿を追いながら思った。
(凛の記憶が、すっぽり抜け落ちてる。抜け落ちてるというより――誰かが、抜き取ってる)
寄贈棚の白い背表紙。
「抜け」。
あの暗号が、今になって別の意味を持つ。
紙じゃない。
記憶が、抜けている。
凛は階段を下りながら、いつもの調子で言った。
「……で、さっき言いかけた許可って何の話?続きは昼休みにして」
僕は、喉の奥で苦いものを飲み込んだ。
「……うん」
僕は言った。
約束したばかりの嘘を、すぐに口にする。
(誰にも話さない。――本当に?)
心臓がうるさい。
でも、今日はその音すら、見せないしかなかった。
フェンスの網目がシャツ越しに肌へ押し付けられて、呼吸のたびに擦れた。
(痛い。強い。――この凛は、また別の凛だ)
目の前の凛は、笑っていないのに笑っているみたいな顔をしていた。
口角だけが、薄く上がっている。
目は、僕の逃げる場所を探すのを楽しんでいる。
「本当のことを知りたい?」
僕の胸の奥が、嫌な音を立てた。
知りたい。
でも、知ったら戻れない気がする。
僕は、震える声で言った。
「……知りたい。もう……逃げたくない」
凛は、ふっと鼻で笑った。
「じゃあ、話す」
凛は言った。
「今までの暗号――あれ、全部あたしが仕組んだの」
「……え?」
「半年前の、ただのいたずら」
凛はさらっと言う。
「寄贈棚とか、文庫本とか。穴あきしおりとか。紙の暗号とか。そういうの、面白いじゃない?」
背中が冷える。
紙の中から始まったものが、急に地面に落とされたみたいに、軽く言われる。
「……いたずら?」
声が裏返る。
「うん。だって学校って退屈だし」
凛の目が細くなる。
「でもね、そこにたまたま紗季先輩が引っかかった」
僕の喉が鳴った。
凛は続ける。止まらない。止める気がない。
「先輩が暗号を見つけてさ。『これ、映画にできる』って目を輝かせたの」
凛は、まるで他人事のように言った。
「コンクール用の作品にしようとしてた。あたしの遊びを、勝手に作品にしようとしてた」
「……勝手に、って」
僕は反射で言い返しそうになって、飲み込んだ。
今は、反論したら負ける気がする。
いや、勝ち負けじゃない。
でも、この凛のペースに乗ったら、僕は息ができなくなる。
凛は、僕の胸元を掴んだまま言った。
「映画を作る過程でね、二人目の凛を泣かせたの」
二人目――おどおどした凛。
僕の胸が、痛む。
「……泣かせた?」
僕は聞き返す。
凛は口角を上げた。
「あの子、久しぶりに外側に出てきたのに。先輩、勝手に撮った」
凛の声が少しだけ荒くなる。
「作品のためって顔して。許可も取らないで。あの子、パニックになって泣いた」
(先輩……)
手紙の文字が、胸に刺さる。
> 私は過ちを犯した。
その過ちの輪郭が、今、歪な形で一致していく。
「許せなくて」
凛が言った。
「制裁のため、勝手に動画を撮ったことは許す――って、あたしは先輩に言ったの」
「……許す?」
僕の声が掠れた。
「そう」
凛は淡々と頷く。
「『許すから、公民館の裏で撮り直そう』って誘い出した。優しいふりしてね」
背中の金網が、急に痛い。
痛いのに、痛みが遠い。
現実感が薄い。
「……火事」
僕はやっと絞り出す。
「火事は……事故じゃ……」
凛は、笑った。今度はちゃんと笑った。
薄い笑い。軽い笑い。人を踏むときの笑い。
「動画を撮ってあげるって言って」
凛は言った。
「火事を起こしたの。先輩が燃えるところまで、ちゃんとね」
僕の頭の中が、真っ白になる。
(何を言ってる?何を――言ってる?)
「それで、その動画を拡散させた」
凛の声が、平坦に続く。
「炎上って言葉、ぴったりでしょ。物理でも、比喩でも」
胃が、ひっくり返りそうだった。
「……何を言ってる?」
僕はやっと言えた。
声が、怒りなのか恐怖なのか分からない震え方をしていた。
凛は肩をすくめる。
「本の暗号だけじゃ面白くないから」
凛は言う。
「新しく、紗季先輩が書いた風に見える手紙とかも追加した。フェンスに引っかかっていた封筒とか、病院の自販機とかね」
(……全部。全部、あれも、これも)
僕の中で、今まで積み上げてきた意味が、崩れていく。
踏切も、夕焼けも、息も。
全部、誰かの遊びだった?
凛は楽しそうに続けた。
「皆、紗季先輩が反省したように美談としてまとめようとしてるのが楽しい」
凛の目が光る。
「『見せない優しさ』とか『許可を獲れ』とかさ。いい言葉だよね。気持ちよくなれる」
僕は、喉が張り付いて、声が出ない。
出たとしても、刃になる気がする。
でも、言わなきゃいけない。
「……お前」
言い方が乱れて、自分で自分に驚いた。
「何してるんだよ……」
凛は、急に顔を歪めた。
怒りの歪み。冷たい怒り。
「悪気がなかった?」
凛が吐き捨てる。
「そんなことで許されるはずがないのよ」
僕の胸元を掴む指に、力が入る。
背中が金網に押し付けられ、痛みが鮮明になる。
「見せない優しさ?許可を獲れ?」
凛は笑う。笑っていない目で。
「ねえ、そんなこと人に迷惑かける前提じゃない?」
「……」
「私、そういうの大っ嫌いなのよ」
凛の声が、低く震える。
「それで人を傷つけても、反省した顔をすれば許されると思ってるのよ。いえ、気にも留めてないのよ、そういう人たちは」
息が詰まる。
凛の言葉は、刃だ。
刃先が丸まっていない。むしろ刃を研いでいる。
(お前が言うな)
そう叫びたかった。
火を起こして、人を半年眠らせておいて。
動画を拡散しておいて。
それでもなお、嫌いだと正義みたいに言うのか。
でも僕は叫べない。
叫んだら、この人は本当に何かする。
僕の喉の奥が、それを理解している。
「……俺に何をしてほしいんだ?」
僕は、絞り出すように言った。
「真実を言ったってことは、何か――」
凛は、肩をすくめた。
驚くほどあっさり。
「あんたは最後まで、あたしのお遊びに付き合ってくれたから真実を話しただけ」
凛は言った。
「殺したりはしないわ。ただ――」
凛の顔が、ぐっと近づく。
息がぶつかる距離。
「誰にも話さなければ」
喉の奥が冷たくなる。
僕は、頷く以外の選択肢を見つけられなかった。
「……分かった」
僕は言った。
「約束する」
約束。
その言葉が、今は汚れて聞こえた。
でも、生き残るためには必要な言葉だった。
凛は満足したみたいに、指の力を少しだけ緩める。
背中の痛みが、呼吸に追いついてくる。
その隙間で、僕は最後の質問を投げた。
投げるのが怖い。
でも、投げなければ僕はここで壊れる。
「ただもう一つだけ聞かせてくれ」
僕は言う。
「いつもの凜は、このことを知っているのか?」
凛は、目を細めた。
そして、唇だけで笑う。
「知らないわ」
凛は言った。
「……たぶん」
その「たぶん」が、妙に残酷だった。
凛の中で、記憶は共有されていない。
罪も、痛みも、誰かの内側に封じ込められている。
次の瞬間、凛の目の光がふっと変わった。
肩が落ち、呼吸が整い、背筋がいつもの角度に戻る。
手が離れる。
凛が一歩下がって、眉をひそめた。
「……何してるの、こんなところで」
凛が言った。
いつもの凛の声。いつもの凛の温度。
僕は背中を押さえた。金網の跡がじんと痛い。
痛いのに、凛はまるで見えないみたいに僕を見る。
「和真?」
凛が首を傾げる。
「顔色悪い。……朝から屋上は寒いって言ったじゃん」
(……忘れてる。いや、なかったことになってる)
凛は腕時計を見て、舌打ちしそうな勢いで言った。
「やばい。もうすぐチャイム。行くよ」
そう言って、凛は何事もなかったように屋上の扉へ向かった。
背中が、いつもの凛の背中だ。
さっきの凶暴さなんて、最初から存在しなかったみたいに。
僕は、動けなかった。
動けないまま、凛が扉を開ける音を聞いた。
「ほら、和真。遅刻する」
凛が振り返って言う。
いつも通りの言い方。いつも通りの刺さる声。
僕は、ふらつく足で一歩踏み出した。
そして、凛の後ろ姿を追いながら思った。
(凛の記憶が、すっぽり抜け落ちてる。抜け落ちてるというより――誰かが、抜き取ってる)
寄贈棚の白い背表紙。
「抜け」。
あの暗号が、今になって別の意味を持つ。
紙じゃない。
記憶が、抜けている。
凛は階段を下りながら、いつもの調子で言った。
「……で、さっき言いかけた許可って何の話?続きは昼休みにして」
僕は、喉の奥で苦いものを飲み込んだ。
「……うん」
僕は言った。
約束したばかりの嘘を、すぐに口にする。
(誰にも話さない。――本当に?)
心臓がうるさい。
でも、今日はその音すら、見せないしかなかった。