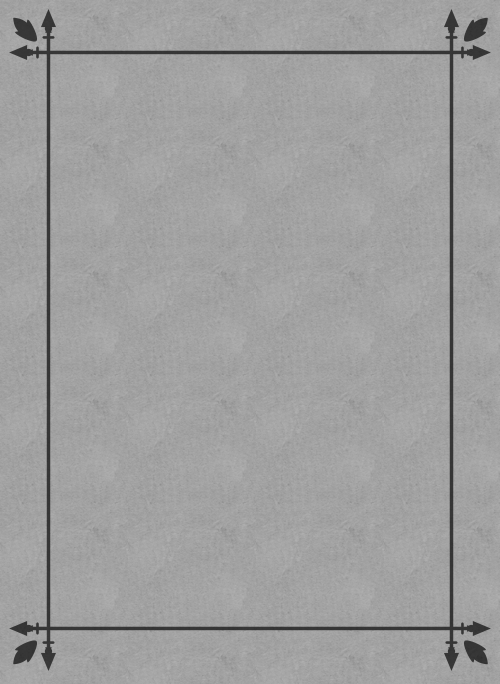凛はフェンスに手を置き、深く息を吸った。
そして、吐いた。
ふっと肩の力が抜ける。
背筋が、いつものきちんとから崩れる。
指先がフェンスを掴む。まるで、落ちないために。
「凛?」
僕が呼ぶと、凛は答えない。
代わりに、小さく首を振った。否定じゃない。何かを譲るみたいな動き。
次の瞬間。
凛が、ゆっくり振り返った。
その顔は、凛の顔なのに、凛じゃなかった。
目が泳いでいる。呼吸が浅い。口元が震えている。
いつも僕を刺すみたいにまっすぐ見てくる目が、今日は、僕の胸元あたりを恐る恐るなぞるだけだった。
(……誰だ)
喉が固まる。
僕は言った。声が裏返りそうになるのを必死で抑えながら。
「君は凜?いつもと違う……」
凛――いや、いつもと違う凛が、小さく頷いた。
頷き方が、控えめすぎて、痛い。
「……私も凜よ」
声は細い。風にさらわれそうな声。
それでも、言葉は言葉だった。
「びっくりした?……ごめんなさい」
「……謝らなくていい」
僕は反射で言ってしまって、すぐに自分に腹が立った。
(いいって何だよ。何がいいんだ。僕は今、何をどう受け止めればいいんだ)
凛は視線を落として、指をいじった。
制服の袖口を、くしゃっと握っている。
その仕草が、妙に子どもっぽく見える。
(この人――この凛は、怖がってる)
僕は、喉の奥の火を押し込めるみたいに息を吐いた。
そして、言うべきことを言う。
「……許可を獲れって?もしかして君に?」
凛の肩がぴくっと跳ねた。
それだけで、僕の胸が痛む。
質問が刃になった気がしたから。
けれど凛は、逃げなかった。
逃げられない、というより、逃げ方が分からないみたいに、そこに立っていた。
「……うん」
凛は小さく頷いた。
「紗季先輩は……久しぶりに、私が外側に出てきた時に……勝手に撮影したの」
「外側……?」
僕が言った言葉は、空気に落ちて、すぐに意味を持った。
凛は、その意味を当然のように扱う。
「表に出る、っていうか……」
凛は言い直そうとして、上手くできずに唇を噛んだ。
「……いつも和真が見てる凜、いるでしょ?きちんとしてて、強くて、言うことが刺さる凜」
「刺さるは余計だろ」
思わず言ってしまって、凛がほんの一瞬だけ困った顔をした。
僕は慌てて付け足す。
「……ごめん。今のは、場を軽くしたかっただけ」
凛は小さく首を振った。
「……いいの。刺さるの、ほんとだから」
(肯定するなよ)
笑えないのに、少しだけ救われる自分がいる。
この凛が、僕の言葉を受け取ってくれている。
それだけで、呼吸がしやすくなる。
凛は続けた。
言葉を探すみたいに、ところどころ途切れながら。
「私……撮られたくなかったのに」
凛の指が、さらに強く袖を握る。
「でも、先輩……カメラ構えて、止めなかった。……作品のためって顔してた」
(先輩……)
あの手紙の文字が、胸に浮かぶ。
「作品のため」って言い訳をして、許可を取らずに、撮って、残してしまった。
凛は、声が少しだけ震えた。
「それで……パニックになった」
凛は言った。
「頭が真っ白になって、息が苦しくなって……逃げようとしても、足が動かなくて。……なのに、レンズだけがこっちを見てた」
僕の喉が鳴った。
(レンズは目だ。しかも、逃げられない目だ)
凛は、風に煽られて目を細める。
涙じゃない。ただ、乾いた目の防御反応。
「紗季先輩も……ひどく動揺してた」
凛は言った。
「だって、先輩がいつも見ている凜は……きっと、そんな感じの子じゃないんでしょ?」
僕は答えに詰まる。
いつもの凛は、ここまでおどおどしない。
誰かの許可なんて待たないで、先に手続きを済ませてしまう。
「……うん」
僕はやっと頷いた。
「違う……違う、けど」
違うと言っていいのか分からない。
同じ顔で、同じ名前で、同じ制服で。
なのに、違う。
(いや、違わない。どっちも凛だ)
だから、僕の言葉はこうなるしかなかった。
「君は凛だ」
僕は言った。
「……ただ、僕が知らなかっただけだ」
凛は、その言葉を聞いて、少しだけ息を吐いた。
呼吸の仕方を、思い出したみたいに。
僕は、怖い質問を口にした。
でも、聞かないと進めない。
「……紗季先輩のあの人は、凛に許可を獲れって――」
僕は一度言葉を切り、目を逸らさないように努力して続けた。
「――君の時の、凛のこと、ってこと?」
凛は頷いた。
頷き方が、さっきより少しだけ確かになっている。
「うん。たぶん……」
凛が言いかけて、慌てて口を押さえた。
「……あ、ごめん。たぶんはダメだったね」
「今日はいい」
僕は即答した。
「たぶんでもいいから、教えて」
凛は、小さく微笑んだ。
本当に小さい。ネオンみたいに派手じゃない。朝の光みたいに薄い。
「……私、ずっと外側に出てなかったの」
凛は言う。
「出ると、怖いから。……誰かに見られるのも、撮られるのも、言葉を向けられるのも」
「……」
「でも、その日は……」
凛は言葉を詰まらせてから、絞り出す。
「うまく隠れられなかった。だから出てきた。……そこに、紗季先輩がいて」
(偶然じゃない。でも、意図でもない。最悪のタイミングだけが、綺麗に重なった)
僕は、頭の中で整理しようとして、すぐに諦めた。
整理の仕方を間違えたら、また誰かを切る。
今は、分類じゃなくて、受け止める。
それでも、思考が勝手にラベルを貼ろうとする。
(二重人格?)
その言葉が脳裏に浮かんだ瞬間、僕は自分で自分を殴りたくなった。
僕は、ぎこちなく首を振った。
(違う。僕は診断したいんじゃない)
「……じゃあ」
僕は、ゆっくり言った。
「僕は、君に何の許可を取ればいい?」
凛は、少し考えてから、首をすくめた。
「……全部、って言ったら困る?」
「困る」
僕は正直に言ってしまって、すぐに言い直す。
「……でも、困りながらやる。逃げない」
凛は、風に肩をすぼめた。
「撮るなら、聞いて。……私が外側にいる時は、特に」
「分かった」
僕は頷く。
「勝手に撮らない。勝手に使わない。勝手にわかったつもりにならない」
凛はその言葉を聞いて、目を伏せた。
泣いているわけじゃない。
でも、今にも崩れそうな顔だった。
「……ありがとう」
凛が言った。
「それ、紗季先輩にも言ってほしかった」
胸の奥が、ずきんと痛んだ。
遅い。
意識のない先輩に、言葉は届かない。
凛は目を閉じた。
深く息を吸って――吐いた。
「……時間、使いすぎた」
凛――さっきまでの、おどおどした凛だった人とは別の、いつもの凛が、そう言った。
背筋は真っすぐで、目はまっすぐで、言葉は短い。
僕――和真は頷いた。頷くしかなかった。
頭の中に、整理するための棚がいくつも増えた気分だ。しかもラベルが全部「未分類」。
(……同じ顔で、同じ名前で、違う凛がいる)
「凛」
僕はようやく口を開く。声が思ったより掠れた。
「さっきの……」
さっきのが何を指しているのか、自分でも分かっていない。
おどおどした凛のことか。先輩のことか。許可のことか。
全部だ。
凛は一瞬だけ僕を見て、扉の方へ顎をしゃくった。
「続きは、後で」
(後で、って。後で何か話してくれるのか?)
そう思った瞬間、風が強く吹いた。
制服の襟が少しだけ持ち上がり、屋上の金網が細く鳴いた。
凛が歩き出す。
僕も半歩遅れてついていく。
足音が二つ、コンクリの上で軽く反響する。
そのときだった。
凛が、ぴたりと止まった。
止まり方が、違った。
普段の凛は止まるときでも姿勢が崩れない。ところが今の凛は、ほんのわずか肩が落ち、首の角度が変わった。
まるで誰かが、凛の中のスイッチを別の位置に切り替えたみたいに。
(……まさか)
僕の喉が勝手に鳴る。
凛がゆっくり振り返った。
目が――さっきの凛とも、いつもの凛とも違う。
まっすぐだけど、冷たい。刺すためのまっすぐさだ。
「凛?」
僕は反射で呼んだ。
凛は、口元だけで笑った。
笑っているのに、温度がない。
「ええ」
凛は言う。声は低く、硬い。
「ただし、いつもの凜じゃないわ」
背中に、ぞわっと寒気が走った。
(……三人目?)
次の瞬間、世界が近づいた。
凛が一歩、僕の懐に入ってくる。
制服の胸元を掴まれた――と思った瞬間、視界が横に流れた。
ガン。
背中が、フェンスに叩きつけられる。
金網の冷たさが、シャツ越しに皮膚へ刺さる。
肺の中の空気が、短く漏れた。
(痛い、強い、この人はまた別の凛なのか?)
思考が追いつかないまま、体だけが現実に反応する。
肩甲骨のあたりがじんと痺れて、フェンスの網目が背中に食い込む。
凛の手は、驚くほど力が強い。細い指なのに、逃げ道を作らない掴み方をしている。
「な、何を……」
声が情けなくなる。屋上の風のせいにしたい。
凛は僕の顔を覗き込む。
距離が近い。怖いくらい近い。
でも――これは甘さの近さじゃない。恐怖を示す近さだ。
「あなた」
凛が囁く。
「本当のことが知りたい?」
そして、吐いた。
ふっと肩の力が抜ける。
背筋が、いつものきちんとから崩れる。
指先がフェンスを掴む。まるで、落ちないために。
「凛?」
僕が呼ぶと、凛は答えない。
代わりに、小さく首を振った。否定じゃない。何かを譲るみたいな動き。
次の瞬間。
凛が、ゆっくり振り返った。
その顔は、凛の顔なのに、凛じゃなかった。
目が泳いでいる。呼吸が浅い。口元が震えている。
いつも僕を刺すみたいにまっすぐ見てくる目が、今日は、僕の胸元あたりを恐る恐るなぞるだけだった。
(……誰だ)
喉が固まる。
僕は言った。声が裏返りそうになるのを必死で抑えながら。
「君は凜?いつもと違う……」
凛――いや、いつもと違う凛が、小さく頷いた。
頷き方が、控えめすぎて、痛い。
「……私も凜よ」
声は細い。風にさらわれそうな声。
それでも、言葉は言葉だった。
「びっくりした?……ごめんなさい」
「……謝らなくていい」
僕は反射で言ってしまって、すぐに自分に腹が立った。
(いいって何だよ。何がいいんだ。僕は今、何をどう受け止めればいいんだ)
凛は視線を落として、指をいじった。
制服の袖口を、くしゃっと握っている。
その仕草が、妙に子どもっぽく見える。
(この人――この凛は、怖がってる)
僕は、喉の奥の火を押し込めるみたいに息を吐いた。
そして、言うべきことを言う。
「……許可を獲れって?もしかして君に?」
凛の肩がぴくっと跳ねた。
それだけで、僕の胸が痛む。
質問が刃になった気がしたから。
けれど凛は、逃げなかった。
逃げられない、というより、逃げ方が分からないみたいに、そこに立っていた。
「……うん」
凛は小さく頷いた。
「紗季先輩は……久しぶりに、私が外側に出てきた時に……勝手に撮影したの」
「外側……?」
僕が言った言葉は、空気に落ちて、すぐに意味を持った。
凛は、その意味を当然のように扱う。
「表に出る、っていうか……」
凛は言い直そうとして、上手くできずに唇を噛んだ。
「……いつも和真が見てる凜、いるでしょ?きちんとしてて、強くて、言うことが刺さる凜」
「刺さるは余計だろ」
思わず言ってしまって、凛がほんの一瞬だけ困った顔をした。
僕は慌てて付け足す。
「……ごめん。今のは、場を軽くしたかっただけ」
凛は小さく首を振った。
「……いいの。刺さるの、ほんとだから」
(肯定するなよ)
笑えないのに、少しだけ救われる自分がいる。
この凛が、僕の言葉を受け取ってくれている。
それだけで、呼吸がしやすくなる。
凛は続けた。
言葉を探すみたいに、ところどころ途切れながら。
「私……撮られたくなかったのに」
凛の指が、さらに強く袖を握る。
「でも、先輩……カメラ構えて、止めなかった。……作品のためって顔してた」
(先輩……)
あの手紙の文字が、胸に浮かぶ。
「作品のため」って言い訳をして、許可を取らずに、撮って、残してしまった。
凛は、声が少しだけ震えた。
「それで……パニックになった」
凛は言った。
「頭が真っ白になって、息が苦しくなって……逃げようとしても、足が動かなくて。……なのに、レンズだけがこっちを見てた」
僕の喉が鳴った。
(レンズは目だ。しかも、逃げられない目だ)
凛は、風に煽られて目を細める。
涙じゃない。ただ、乾いた目の防御反応。
「紗季先輩も……ひどく動揺してた」
凛は言った。
「だって、先輩がいつも見ている凜は……きっと、そんな感じの子じゃないんでしょ?」
僕は答えに詰まる。
いつもの凛は、ここまでおどおどしない。
誰かの許可なんて待たないで、先に手続きを済ませてしまう。
「……うん」
僕はやっと頷いた。
「違う……違う、けど」
違うと言っていいのか分からない。
同じ顔で、同じ名前で、同じ制服で。
なのに、違う。
(いや、違わない。どっちも凛だ)
だから、僕の言葉はこうなるしかなかった。
「君は凛だ」
僕は言った。
「……ただ、僕が知らなかっただけだ」
凛は、その言葉を聞いて、少しだけ息を吐いた。
呼吸の仕方を、思い出したみたいに。
僕は、怖い質問を口にした。
でも、聞かないと進めない。
「……紗季先輩のあの人は、凛に許可を獲れって――」
僕は一度言葉を切り、目を逸らさないように努力して続けた。
「――君の時の、凛のこと、ってこと?」
凛は頷いた。
頷き方が、さっきより少しだけ確かになっている。
「うん。たぶん……」
凛が言いかけて、慌てて口を押さえた。
「……あ、ごめん。たぶんはダメだったね」
「今日はいい」
僕は即答した。
「たぶんでもいいから、教えて」
凛は、小さく微笑んだ。
本当に小さい。ネオンみたいに派手じゃない。朝の光みたいに薄い。
「……私、ずっと外側に出てなかったの」
凛は言う。
「出ると、怖いから。……誰かに見られるのも、撮られるのも、言葉を向けられるのも」
「……」
「でも、その日は……」
凛は言葉を詰まらせてから、絞り出す。
「うまく隠れられなかった。だから出てきた。……そこに、紗季先輩がいて」
(偶然じゃない。でも、意図でもない。最悪のタイミングだけが、綺麗に重なった)
僕は、頭の中で整理しようとして、すぐに諦めた。
整理の仕方を間違えたら、また誰かを切る。
今は、分類じゃなくて、受け止める。
それでも、思考が勝手にラベルを貼ろうとする。
(二重人格?)
その言葉が脳裏に浮かんだ瞬間、僕は自分で自分を殴りたくなった。
僕は、ぎこちなく首を振った。
(違う。僕は診断したいんじゃない)
「……じゃあ」
僕は、ゆっくり言った。
「僕は、君に何の許可を取ればいい?」
凛は、少し考えてから、首をすくめた。
「……全部、って言ったら困る?」
「困る」
僕は正直に言ってしまって、すぐに言い直す。
「……でも、困りながらやる。逃げない」
凛は、風に肩をすぼめた。
「撮るなら、聞いて。……私が外側にいる時は、特に」
「分かった」
僕は頷く。
「勝手に撮らない。勝手に使わない。勝手にわかったつもりにならない」
凛はその言葉を聞いて、目を伏せた。
泣いているわけじゃない。
でも、今にも崩れそうな顔だった。
「……ありがとう」
凛が言った。
「それ、紗季先輩にも言ってほしかった」
胸の奥が、ずきんと痛んだ。
遅い。
意識のない先輩に、言葉は届かない。
凛は目を閉じた。
深く息を吸って――吐いた。
「……時間、使いすぎた」
凛――さっきまでの、おどおどした凛だった人とは別の、いつもの凛が、そう言った。
背筋は真っすぐで、目はまっすぐで、言葉は短い。
僕――和真は頷いた。頷くしかなかった。
頭の中に、整理するための棚がいくつも増えた気分だ。しかもラベルが全部「未分類」。
(……同じ顔で、同じ名前で、違う凛がいる)
「凛」
僕はようやく口を開く。声が思ったより掠れた。
「さっきの……」
さっきのが何を指しているのか、自分でも分かっていない。
おどおどした凛のことか。先輩のことか。許可のことか。
全部だ。
凛は一瞬だけ僕を見て、扉の方へ顎をしゃくった。
「続きは、後で」
(後で、って。後で何か話してくれるのか?)
そう思った瞬間、風が強く吹いた。
制服の襟が少しだけ持ち上がり、屋上の金網が細く鳴いた。
凛が歩き出す。
僕も半歩遅れてついていく。
足音が二つ、コンクリの上で軽く反響する。
そのときだった。
凛が、ぴたりと止まった。
止まり方が、違った。
普段の凛は止まるときでも姿勢が崩れない。ところが今の凛は、ほんのわずか肩が落ち、首の角度が変わった。
まるで誰かが、凛の中のスイッチを別の位置に切り替えたみたいに。
(……まさか)
僕の喉が勝手に鳴る。
凛がゆっくり振り返った。
目が――さっきの凛とも、いつもの凛とも違う。
まっすぐだけど、冷たい。刺すためのまっすぐさだ。
「凛?」
僕は反射で呼んだ。
凛は、口元だけで笑った。
笑っているのに、温度がない。
「ええ」
凛は言う。声は低く、硬い。
「ただし、いつもの凜じゃないわ」
背中に、ぞわっと寒気が走った。
(……三人目?)
次の瞬間、世界が近づいた。
凛が一歩、僕の懐に入ってくる。
制服の胸元を掴まれた――と思った瞬間、視界が横に流れた。
ガン。
背中が、フェンスに叩きつけられる。
金網の冷たさが、シャツ越しに皮膚へ刺さる。
肺の中の空気が、短く漏れた。
(痛い、強い、この人はまた別の凛なのか?)
思考が追いつかないまま、体だけが現実に反応する。
肩甲骨のあたりがじんと痺れて、フェンスの網目が背中に食い込む。
凛の手は、驚くほど力が強い。細い指なのに、逃げ道を作らない掴み方をしている。
「な、何を……」
声が情けなくなる。屋上の風のせいにしたい。
凛は僕の顔を覗き込む。
距離が近い。怖いくらい近い。
でも――これは甘さの近さじゃない。恐怖を示す近さだ。
「あなた」
凛が囁く。
「本当のことが知りたい?」