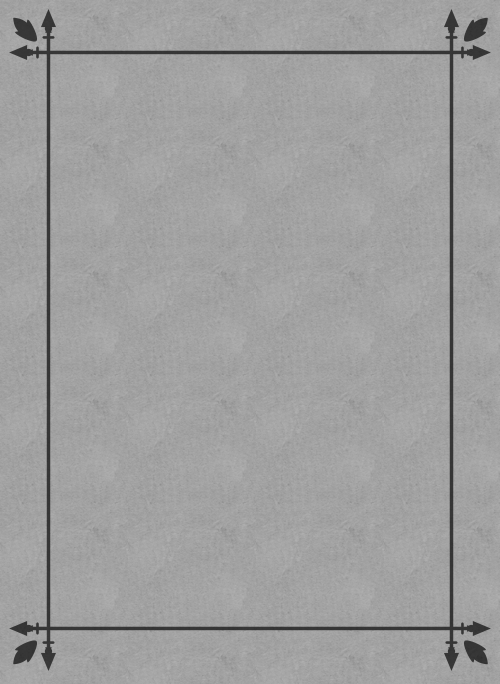その朝、目覚ましが鳴る前に目が覚めた。
というより、眠っていなかった。
瞼を閉じるたび、あの動画の火が裏側に焼き付いて、勝手に再生される。
炎の中で紗季先輩の口が動く。音のない言葉が、字幕みたいに浮かぶ。
『りんにきょかをとれ』
(凛に、許可を取れ)
その一文が、僕の中でずっと点滅していた。
赤いRECランプみたいに。
(許可って、何の許可だよ)
答えがないのに、行動だけは決まっていた。
撮るなら、許可を取れ。
紗季先輩が、自分の過ちを言葉にしてまで残した警告だ。
それを無視して進んだら、僕も同じ刃を握ることになる。
同じ刃先で、誰かを切る。
(嫌だ)
制服を着ながら、僕は何度もスマホの画面を見た。
凛に送るメッセージを打っては消し、打っては消し。
「屋上に来て」
それだけ。理由を書こうとすると、言葉が全部軽くなる。
軽くなる言葉は、刃になりやすい。
だから最小にした。
送信。
既読がつくまでの数秒が、妙に長い。
――既読。
返事は短かった。
「分かった。始業前なら10分だけ」
(10分で、何を言える?10分で、許可が取れるのか)
でも、10分でもいい。
今の僕に必要なのは、時間じゃない。
逃げないことだ。
屋上への階段は、朝の匂いがした。
誰もいない廊下、窓から差し込む光、掃除のモップの湿った匂い。
屋上の扉は、いつもは鍵がかかっている。
今日は、点検の札がぶら下がっていて、半分だけ開いていた。
風が、隙間からヒュッと鳴く。
(入れってことかよ)
勝手にそう思ってしまう自分が、少し怖い。
でも僕は扉を押して、屋上に出た。
空が広い。
朝の青がまだ薄くて、風が冷たい。
フェンスが高くて、下を覗くと足がすくむ。
(ここに呼び出すの、正しいのか)
でも、ここは声が届きにくい。
教室みたいに誰かが聞き耳を立てる場所じゃない。
噂の火種が転がりにくい。
僕はフェンスから少し離れたところに立って、凛を待った。
手が、勝手にポケットの中で穴あきしおりを握りしめている。
紙の角が指に刺さって、痛い。
痛いのはいい。現実だ。
扉が開く音がした。
振り向くと、凛がいた。
髪はきちんと結ばれていて、顔はいつも通り落ち着いている。
だけど目の下が、ほんの少しだけ濃い。
(凛も、寝てない?)
「……おはよう」
凛が言う。声は小さい。
「おはよう」
僕も返す。
返したのに、次の言葉が出ない。
言葉の順番が、分からなくなる。
凛が腕を組んだ。
「で。用件は?」
僕は、息を吸った。
胸の中の火が、煙になって喉に上がってくる。
(言え。逃げるな)
僕は一歩、凛の方に近づいた。
近づきすぎると声が大きくなる。
だから、ちょうどいい距離で止まる。
そして言った。
「許可を取りに来た」
「何の?」
(そうだよな。そう言うよな)
僕は手のひらに汗が滲むのを感じながら、言葉を押し出した。
「わからない、でも紗季先輩が凜に許可を獲れって言っていた」
凛の眉がわずかに動いた。
「……紗季先輩が?」
凛は僕をじっと見た。
嘘を見抜く目じゃない。
言葉の重さを測る目。
僕はスマホを取り出して、動画の一場面を見せた。
炎の中で、口が動くところ。
「……これ」
僕は小さく言う。
「口、動いてた。読み取った」
凛は画面を見たまま、息を止めたみたいに動かなかった。
数秒後、ゆっくり息を吐く。
「……わからないなら許可を出せないよ」
(凛の正論は、いつも僕の逃げ道を塞ぐ)
僕は喉の奥で笑いそうになって、すぐに止めた。
笑える状況じゃない。
「……でも」
僕は必死に続ける。
「許可を取れって言われた。だから、取らないと進めない」
凛は淡々と返す。
「進むって何に?」
「映画に」
僕の口が勝手に答えた。
「文化祭。映画部。解散。……全部」
言いながら、胸が痛くなる。
僕は、紗季先輩のために動いているのか。
映画部を守りたいだけなのか。
自分が安心したいだけなのか。
全部、混ざっている。
混ざっているから、恥ずかしい。
凛は視線を上げて、風に髪を揺らしながら言った。
「許可って、便利な言葉じゃない。免罪符にしないで」
「……免罪符にしたいわけじゃない」
僕は言った。声が少し震えた。
「同じことを繰り返したくない」
凛の目が、ほんの少しだけ柔らかくなる。
でも次の瞬間、また硬くなる。
「和真」
凛が言う。
「あなた、いま誰を疑ってる?」
その問いが鋭すぎて、僕は一瞬、息を止めた。
(疑ってる?)
でも、疑ってる。
「りん」は凛のことだと思った。
なら、紗季先輩が傷つけた「ある人」も凛なのかもしれない。
そうやって辻褄を合わせようとしている。
そして、その辻褄合わせが、また勝手な編集だと気づいている。
それでも、口から出てしまった。
「紗季先輩が傷つけたあの人って、凛なのか?」
凛は、即答しなかった。
風がフェンスに当たって、金属がかすかに鳴る。
遠くの校庭から、朝練の掛け声が聞こえる。
世界はいつも通りなのに、僕の頭だけが違う速度で回っている。
やがて凛は、静かに言った。
「私であって、私じゃないわ」
「……は?」
思わず声が漏れた。
「どういうことだ」
凛は僕を見て、ほんの少しだけ目を細めた。
いつもの「説明する気はあるけど、簡単には言わない」顔。
「和真」
凛はゆっくり言う。
「あなた、「りん」って文字を見た瞬間、凛=私って決めたでしょ」
「……決めた。だって」
僕は言いかけて止まる。
だって、名前が同じだから。
だって、他に思いつかないから。
だって――。
その「だって」は、言い訳だ。
編集点を勝手に打つ癖だ。
凛は続けた。
「紗季先輩が言いたかったのは、あなたが考えている「凛」かもしれないし、「凛」じゃないかもしれない」
「余計分からない」
凛が、少しだけ口角を上げた。
「分からないって言えるのは、進歩」
「褒めるならもっと分かりやすく褒めて」
「それは許可しない」
凛が淡々と言って、僕は今度こそ笑いそうになった。
(最悪のタイミングで、凛は凛だ)
凛は風に前髪を押さえながら、言葉を選ぶ。
「私であって、私じゃないっていうのはね……」
言いかけて、凛は一度口を閉じた。
そして、こちらを見て言った。
「見せてあげるわ、来て」
「……え」
僕は間抜けな声を出した。
「どこに」
僕は、凛を見ながら、胸の奥で何かがほどけるのを感じた。
答えに近づく怖さと、答えが出る安心が、同じ速度で押し寄せていた。
というより、眠っていなかった。
瞼を閉じるたび、あの動画の火が裏側に焼き付いて、勝手に再生される。
炎の中で紗季先輩の口が動く。音のない言葉が、字幕みたいに浮かぶ。
『りんにきょかをとれ』
(凛に、許可を取れ)
その一文が、僕の中でずっと点滅していた。
赤いRECランプみたいに。
(許可って、何の許可だよ)
答えがないのに、行動だけは決まっていた。
撮るなら、許可を取れ。
紗季先輩が、自分の過ちを言葉にしてまで残した警告だ。
それを無視して進んだら、僕も同じ刃を握ることになる。
同じ刃先で、誰かを切る。
(嫌だ)
制服を着ながら、僕は何度もスマホの画面を見た。
凛に送るメッセージを打っては消し、打っては消し。
「屋上に来て」
それだけ。理由を書こうとすると、言葉が全部軽くなる。
軽くなる言葉は、刃になりやすい。
だから最小にした。
送信。
既読がつくまでの数秒が、妙に長い。
――既読。
返事は短かった。
「分かった。始業前なら10分だけ」
(10分で、何を言える?10分で、許可が取れるのか)
でも、10分でもいい。
今の僕に必要なのは、時間じゃない。
逃げないことだ。
屋上への階段は、朝の匂いがした。
誰もいない廊下、窓から差し込む光、掃除のモップの湿った匂い。
屋上の扉は、いつもは鍵がかかっている。
今日は、点検の札がぶら下がっていて、半分だけ開いていた。
風が、隙間からヒュッと鳴く。
(入れってことかよ)
勝手にそう思ってしまう自分が、少し怖い。
でも僕は扉を押して、屋上に出た。
空が広い。
朝の青がまだ薄くて、風が冷たい。
フェンスが高くて、下を覗くと足がすくむ。
(ここに呼び出すの、正しいのか)
でも、ここは声が届きにくい。
教室みたいに誰かが聞き耳を立てる場所じゃない。
噂の火種が転がりにくい。
僕はフェンスから少し離れたところに立って、凛を待った。
手が、勝手にポケットの中で穴あきしおりを握りしめている。
紙の角が指に刺さって、痛い。
痛いのはいい。現実だ。
扉が開く音がした。
振り向くと、凛がいた。
髪はきちんと結ばれていて、顔はいつも通り落ち着いている。
だけど目の下が、ほんの少しだけ濃い。
(凛も、寝てない?)
「……おはよう」
凛が言う。声は小さい。
「おはよう」
僕も返す。
返したのに、次の言葉が出ない。
言葉の順番が、分からなくなる。
凛が腕を組んだ。
「で。用件は?」
僕は、息を吸った。
胸の中の火が、煙になって喉に上がってくる。
(言え。逃げるな)
僕は一歩、凛の方に近づいた。
近づきすぎると声が大きくなる。
だから、ちょうどいい距離で止まる。
そして言った。
「許可を取りに来た」
「何の?」
(そうだよな。そう言うよな)
僕は手のひらに汗が滲むのを感じながら、言葉を押し出した。
「わからない、でも紗季先輩が凜に許可を獲れって言っていた」
凛の眉がわずかに動いた。
「……紗季先輩が?」
凛は僕をじっと見た。
嘘を見抜く目じゃない。
言葉の重さを測る目。
僕はスマホを取り出して、動画の一場面を見せた。
炎の中で、口が動くところ。
「……これ」
僕は小さく言う。
「口、動いてた。読み取った」
凛は画面を見たまま、息を止めたみたいに動かなかった。
数秒後、ゆっくり息を吐く。
「……わからないなら許可を出せないよ」
(凛の正論は、いつも僕の逃げ道を塞ぐ)
僕は喉の奥で笑いそうになって、すぐに止めた。
笑える状況じゃない。
「……でも」
僕は必死に続ける。
「許可を取れって言われた。だから、取らないと進めない」
凛は淡々と返す。
「進むって何に?」
「映画に」
僕の口が勝手に答えた。
「文化祭。映画部。解散。……全部」
言いながら、胸が痛くなる。
僕は、紗季先輩のために動いているのか。
映画部を守りたいだけなのか。
自分が安心したいだけなのか。
全部、混ざっている。
混ざっているから、恥ずかしい。
凛は視線を上げて、風に髪を揺らしながら言った。
「許可って、便利な言葉じゃない。免罪符にしないで」
「……免罪符にしたいわけじゃない」
僕は言った。声が少し震えた。
「同じことを繰り返したくない」
凛の目が、ほんの少しだけ柔らかくなる。
でも次の瞬間、また硬くなる。
「和真」
凛が言う。
「あなた、いま誰を疑ってる?」
その問いが鋭すぎて、僕は一瞬、息を止めた。
(疑ってる?)
でも、疑ってる。
「りん」は凛のことだと思った。
なら、紗季先輩が傷つけた「ある人」も凛なのかもしれない。
そうやって辻褄を合わせようとしている。
そして、その辻褄合わせが、また勝手な編集だと気づいている。
それでも、口から出てしまった。
「紗季先輩が傷つけたあの人って、凛なのか?」
凛は、即答しなかった。
風がフェンスに当たって、金属がかすかに鳴る。
遠くの校庭から、朝練の掛け声が聞こえる。
世界はいつも通りなのに、僕の頭だけが違う速度で回っている。
やがて凛は、静かに言った。
「私であって、私じゃないわ」
「……は?」
思わず声が漏れた。
「どういうことだ」
凛は僕を見て、ほんの少しだけ目を細めた。
いつもの「説明する気はあるけど、簡単には言わない」顔。
「和真」
凛はゆっくり言う。
「あなた、「りん」って文字を見た瞬間、凛=私って決めたでしょ」
「……決めた。だって」
僕は言いかけて止まる。
だって、名前が同じだから。
だって、他に思いつかないから。
だって――。
その「だって」は、言い訳だ。
編集点を勝手に打つ癖だ。
凛は続けた。
「紗季先輩が言いたかったのは、あなたが考えている「凛」かもしれないし、「凛」じゃないかもしれない」
「余計分からない」
凛が、少しだけ口角を上げた。
「分からないって言えるのは、進歩」
「褒めるならもっと分かりやすく褒めて」
「それは許可しない」
凛が淡々と言って、僕は今度こそ笑いそうになった。
(最悪のタイミングで、凛は凛だ)
凛は風に前髪を押さえながら、言葉を選ぶ。
「私であって、私じゃないっていうのはね……」
言いかけて、凛は一度口を閉じた。
そして、こちらを見て言った。
「見せてあげるわ、来て」
「……え」
僕は間抜けな声を出した。
「どこに」
僕は、凛を見ながら、胸の奥で何かがほどけるのを感じた。
答えに近づく怖さと、答えが出る安心が、同じ速度で押し寄せていた。