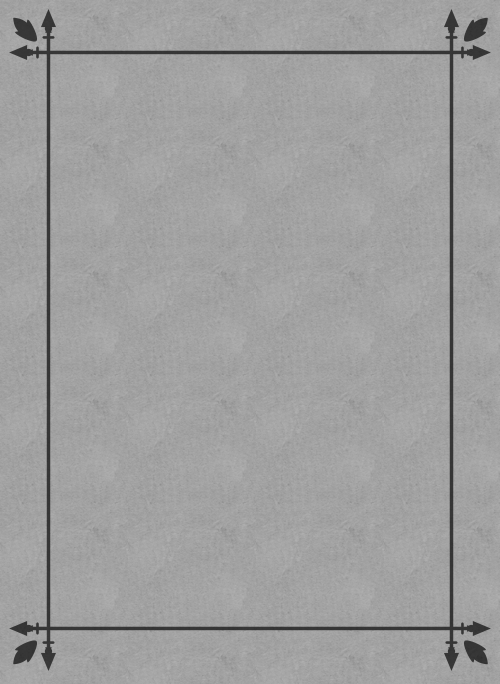「紗季と同じ高校の制服……。もしかして、紗季のお友達かしら?」
その言葉を受け止めた瞬間、僕――和真は、息の吸い方を忘れた。
(紗季先輩のお母さん……?)
凛が、いつもの速度で一歩前に出た。
こういうときの凛は、迷いがない。迷いがないというより、迷っている暇を他人に与えない。
「はい。同じ高校です」
凛は丁寧に頭を下げた。声のトーンは、図書室のカウンターで使う丁寧だ。
「私たち、映画部の者で……紗季先輩のことを心配していて。あの……」
凛の言葉が途切れた。
桃が、かすれた声で言った。
「紗季先輩……いま、どこに……」
女性は、僕らの制服をもう一度見て、ほんの少しだけ安心したように頷いた。
「お見舞いに来てくれたのね。ありがとう」
言葉が見つからないまま、僕はただ頭を下げた。
女性は、静かに言った。
「……会ってあげて。紗季、きっと……いえ、分からないけど。会ってあげてほしい」
凛が目で僕に合図する。
行くよの合図。
僕は喉の奥で唾を飲み込み、頷いた。
病棟の廊下は、歩く音がやけに響く。
昼間のざわつきが薄くなった分、空調の音と機械の作動音が、空気の骨格みたいに目立つ。
紗季先輩のお母さんは、歩きながら名乗った。
「私、紗季の母です。……今さらだけど」
「いえ……」
凛がすぐに返す。
「案内してくださって、ありがとうございます」
桃は、黙ったままだった。
手をぎゅっと握っている。
僕は、廊下の白さに目が痛くなった。
白い壁、白い床、白い看板。
寄贈棚の白い背表紙と同じ種類の白。
(ここに先輩は……)
思考がそこに触れた瞬間、心臓が強く鳴った。
「ここです」
お母さんが立ち止まり、病室の前で深く息を吐いた。
ノックを一回。
返事はない。
ドアが静かに開く。
病室の中は、時間が遅かった。
テレビは消えている。窓の外は暗い。
薄いカーテンの向こうに、機械の小さな光がいくつも瞬いている。
ベッドの上に、紗季先輩がいた。
(……紗季先輩)
顔色は白い。
髪は短く整えられていて、寝顔は驚くほど静かだった。
眠っている、というより、眠りに固定されているように見えた。
管や線が、彼女の命をこの場所に繋ぎ止めている。
機械の一定の音が、呼吸の代わりみたいに響く。
桃が、一歩だけ前に出て、止まった。
声を出せない。
でも、目だけは泣きそうに揺れている。
凛が、僕の袖を小さく引いた。
落ち着いての合図。
紗季先輩のお母さんが、ベッド脇の椅子に手を置き、僕らに向き直った。
表情は穏やかにしようとしている。
でも、その穏やかさは、毎日練習してやっと作れた仮面みたいだった。
「紗季ね……」
お母さんは、言葉を慎重に選ぶように続けた。
「半年前、公民館の裏で……何かを撮っていたんです。ひとりで」
僕の背中が冷えた。
公民館の裏。芝生。焼け跡。
「撮っていた、って……」
僕は声が小さくなった。
「映画……ですか」
「そう」
お母さんは頷いた。
「コンクール用だって。誰にも言わないで、勝手にやって……。止めればよかったのに、って、今でも思う」
勝手に。
手紙の中の言葉が、胸に戻ってくる。
「作品のため」って言い訳をして、許可を取らずに、撮って、残してしまった。
お母さんは、淡々と続けた。淡々としないと、崩れるから。
「機材が、発火したんです。火事になって……」
そこで一度、息を詰まらせた。
「紗季が重症になって……それで、半年間。ずっと、意識が戻らないまま」
半年。
僕の足元がふわっと浮く。
半年。
噂が熟成されるのに十分な時間。
消えたと勝手に言われるのに十分な時間。
桃がかすれる声で言った。
「……先輩、ずっと、ここに……」
お母さんは小さく頷いた。
凛が、静かに聞いた。
「……火事のことは、学校には……」
「伝えました。でも」
お母さんは眉を寄せた。
「学校は配慮してくれたんだと思う。けれど……配慮の仕方が、難しいのよね」
その一言が、胸に刺さった。
見せない優しさは、時々、見ないで済ませるに変わってしまう。
お母さんは、僕らをまっすぐ見た。
「あなた達、映画部なんでしょう?」
僕が頷く。
「はい」
「……お願いがあるの」
お母さんは言った。
「紗季のこと、もうこれ以上、燃やさないでほしい」
燃やさないでほしい。
火事の話をした直後に出る燃やすは、比喩でもあり、現実でもあった。
僕は息を吸って、吐いた。
「……炎上して消えたって噂が……学校で」
お母さんの瞳が、揺れた。
「……そう」
そして、次の言葉が、僕の胃を冷たく掴んだ。
「事故の時の様子の動画が、なぜか拡散されているらしいの」
「……え」
桃が小さく声を漏らす。
凛が眉を寄せる。
「事故の……動画?」
お母さんはスマホを取り出し、手が少し震えるのを押さえるように両手で持った。
「見て。見たくないと思うけど……でも、あなた達には見てほしい」
画面が僕らに向けられる。
そこに映っていたのは、夕方の芝生だった。
遠目のズーム。手ブレ。
フェンスの外から撮っている角度。
次の瞬間、煙が上がる。
誰かが叫ぶ声が入っている。
そして――火。
火が、ひとつの人影に絡みつく。
人影が、よろける。
走る。
助けようとする誰かの影。
でもカメラは、助けない。
ただ、撮り続ける。
(……紗季先輩)
炎の中で、紗季先輩の制服みたいな布が見えた。
燃える、という言葉が、意味を失うくらい、画面は生々しい。
桃が手で口を押さえた。
凛の瞳が硬くなる。
僕の喉が、変な音を立てた。
お母さんは画面の下を指でなぞった。
そこには、コメント欄のスクロール。
「草」
「マジで燃えてて草」
「これ本物?」
「炎上(物理)」
「やば」
一文字一文字が、刃だった。
刃先が丸まっていない。尖っている。楽しそうに。
「……削除依頼も出したの」
お母さんが、声を絞った。
「でも、消しても消しても……誰かが持っていて、また上げるの。切り抜かれて、また回るの」
切り抜き。
拡散。
戻せない。
僕の仕事の単語が、全部、罪の単語に変わっていく。
凛が、静かに言った。
「撮ったのは……誰なんですか」
お母さんは首を振った。
「分からない。……だから、お願い。映画部なら、映像を見て分かることがあるかもしれない」
「……この動画、データでもらえますか」
僕は、自分の声が震えているのを自覚しながら言った。
「……編集のことは、僕が一番分かる。僕、編集担当で」
凛が僕を見る。
お母さんは少し迷ってから、頷いた。
「ありがとう。……ここから送れるかしら。容量が大きくて」
「僕のスマホに、一度送ってください」
僕は言った。
「あとでPCに移します」
お母さんが操作を始め、数十秒の沈黙が生まれる。
その沈黙が、病室の機械音を余計に際立たせた。
ピロン、と僕のスマホが震えた。
動画ファイルが届いた通知。
(これが、炎上して消えたの正体)
炎上は比喩じゃなかった。
そして比喩より残酷だった。
燃えている本人の映像が、娯楽として流れている。
僕はスマホを握りしめた。
握りしめることで、画面の中の火を押し込められる気がしたから。
お母さんは最後に、僕らに向かって深く頭を下げた。
「来てくれて、ありがとう。紗季……きっと、嬉しいと思う」
(嬉しいのか?嬉しいって、何だ?)
答えは出ない。
病室を出るとき、僕はベッドの紗季先輩を見た。
眠っている顔。動かない指先。
それでも――何かが言いたい顔に見えた。
僕の都合かもしれない。
でも、映像を扱う人間は、都合で読み取ってしまう。
家に帰ってからも、手が落ち着かなかった。
夕飯の味がしない。
家族の声が遠い。
部室の解散宣告より、踏切のベルより、今日見た動画の火が、目の奥で燃え続ける。
僕は自室に籠もり、PCを立ち上げた。
動画ファイルを取り込む。
編集ソフトに読み込む。
タイムラインに、あの火の映像が置かれる。
(……これを編集するの?)
罪悪感が喉に張り付く。
でも、編集は刃だ。
刃を持ったまま、手を引っ込めたら、次に誰かが刺される。
僕は再生した。
画面の中で煙が上がり、火が出て、紗季先輩が燃える。
耐えられなくて一度停止した。
それでも、もう一度再生する。
「……ごめんなさい」
誰に向けた謝罪か分からないまま、僕は呟いた。
僕はフレームを進めた。
一コマずつ。
指先が機械的になる。
感情を殺して、仕事にする。編集のときの癖だ。
(この動画、撮ってる人……)
カメラの位置。揺れ方。ズーム。
撮影者は、助けるより先に撮っている。
それが許せない。
でも、そういう人がいるから、こういう動画が残る。
そのとき――画面の中央あたりで、紗季先輩が一瞬だけこちらを向いた。
炎の中で、顔の輪郭がぼやける。
けれど、口が――動いている。
(……え)
僕は息を止め、さらにスローにした。
拡大する。ノイズが増える。
それでも、口元の動きは確かに言葉だった。
(何て言ってる?)
音は入っている。でも、聞き取りたくない。
そもそも周囲の叫びで埋もれている。
だから、僕は読む。
唇の形。開き方。舌の位置。
何度も巻き戻して、指でタイムコードを押さえた。
「……り」
「ん」
「に」
「きょ……か」
「を」
「とれ」
僕の背中が、冷たくなる。
『りんにきょかをとれ』
(凛……?)
凛に許可を取れ。
手紙の中の「ある人」が、突然、輪郭を持ってしまった。
僕の頭の中で、あの台詞テープが再生される。
僕は、画面を見たまま動けなくなった。
PCのファンの音だけが、部屋に残る。
ここで初めて、僕は気づいた。
次の指示は、もう紙の中だけじゃない。
映像の中に、残されている。
(明日、凛に……話さないと)
僕は息を吸って、吐いた。
笑うでも泣くでもない。
ただ、生きるための息。
そして、画面の中の紗季先輩の口元を、もう一度見た。
『りんにきょかをとれ』
消えない字幕みたいに、そこにあった。
その言葉を受け止めた瞬間、僕――和真は、息の吸い方を忘れた。
(紗季先輩のお母さん……?)
凛が、いつもの速度で一歩前に出た。
こういうときの凛は、迷いがない。迷いがないというより、迷っている暇を他人に与えない。
「はい。同じ高校です」
凛は丁寧に頭を下げた。声のトーンは、図書室のカウンターで使う丁寧だ。
「私たち、映画部の者で……紗季先輩のことを心配していて。あの……」
凛の言葉が途切れた。
桃が、かすれた声で言った。
「紗季先輩……いま、どこに……」
女性は、僕らの制服をもう一度見て、ほんの少しだけ安心したように頷いた。
「お見舞いに来てくれたのね。ありがとう」
言葉が見つからないまま、僕はただ頭を下げた。
女性は、静かに言った。
「……会ってあげて。紗季、きっと……いえ、分からないけど。会ってあげてほしい」
凛が目で僕に合図する。
行くよの合図。
僕は喉の奥で唾を飲み込み、頷いた。
病棟の廊下は、歩く音がやけに響く。
昼間のざわつきが薄くなった分、空調の音と機械の作動音が、空気の骨格みたいに目立つ。
紗季先輩のお母さんは、歩きながら名乗った。
「私、紗季の母です。……今さらだけど」
「いえ……」
凛がすぐに返す。
「案内してくださって、ありがとうございます」
桃は、黙ったままだった。
手をぎゅっと握っている。
僕は、廊下の白さに目が痛くなった。
白い壁、白い床、白い看板。
寄贈棚の白い背表紙と同じ種類の白。
(ここに先輩は……)
思考がそこに触れた瞬間、心臓が強く鳴った。
「ここです」
お母さんが立ち止まり、病室の前で深く息を吐いた。
ノックを一回。
返事はない。
ドアが静かに開く。
病室の中は、時間が遅かった。
テレビは消えている。窓の外は暗い。
薄いカーテンの向こうに、機械の小さな光がいくつも瞬いている。
ベッドの上に、紗季先輩がいた。
(……紗季先輩)
顔色は白い。
髪は短く整えられていて、寝顔は驚くほど静かだった。
眠っている、というより、眠りに固定されているように見えた。
管や線が、彼女の命をこの場所に繋ぎ止めている。
機械の一定の音が、呼吸の代わりみたいに響く。
桃が、一歩だけ前に出て、止まった。
声を出せない。
でも、目だけは泣きそうに揺れている。
凛が、僕の袖を小さく引いた。
落ち着いての合図。
紗季先輩のお母さんが、ベッド脇の椅子に手を置き、僕らに向き直った。
表情は穏やかにしようとしている。
でも、その穏やかさは、毎日練習してやっと作れた仮面みたいだった。
「紗季ね……」
お母さんは、言葉を慎重に選ぶように続けた。
「半年前、公民館の裏で……何かを撮っていたんです。ひとりで」
僕の背中が冷えた。
公民館の裏。芝生。焼け跡。
「撮っていた、って……」
僕は声が小さくなった。
「映画……ですか」
「そう」
お母さんは頷いた。
「コンクール用だって。誰にも言わないで、勝手にやって……。止めればよかったのに、って、今でも思う」
勝手に。
手紙の中の言葉が、胸に戻ってくる。
「作品のため」って言い訳をして、許可を取らずに、撮って、残してしまった。
お母さんは、淡々と続けた。淡々としないと、崩れるから。
「機材が、発火したんです。火事になって……」
そこで一度、息を詰まらせた。
「紗季が重症になって……それで、半年間。ずっと、意識が戻らないまま」
半年。
僕の足元がふわっと浮く。
半年。
噂が熟成されるのに十分な時間。
消えたと勝手に言われるのに十分な時間。
桃がかすれる声で言った。
「……先輩、ずっと、ここに……」
お母さんは小さく頷いた。
凛が、静かに聞いた。
「……火事のことは、学校には……」
「伝えました。でも」
お母さんは眉を寄せた。
「学校は配慮してくれたんだと思う。けれど……配慮の仕方が、難しいのよね」
その一言が、胸に刺さった。
見せない優しさは、時々、見ないで済ませるに変わってしまう。
お母さんは、僕らをまっすぐ見た。
「あなた達、映画部なんでしょう?」
僕が頷く。
「はい」
「……お願いがあるの」
お母さんは言った。
「紗季のこと、もうこれ以上、燃やさないでほしい」
燃やさないでほしい。
火事の話をした直後に出る燃やすは、比喩でもあり、現実でもあった。
僕は息を吸って、吐いた。
「……炎上して消えたって噂が……学校で」
お母さんの瞳が、揺れた。
「……そう」
そして、次の言葉が、僕の胃を冷たく掴んだ。
「事故の時の様子の動画が、なぜか拡散されているらしいの」
「……え」
桃が小さく声を漏らす。
凛が眉を寄せる。
「事故の……動画?」
お母さんはスマホを取り出し、手が少し震えるのを押さえるように両手で持った。
「見て。見たくないと思うけど……でも、あなた達には見てほしい」
画面が僕らに向けられる。
そこに映っていたのは、夕方の芝生だった。
遠目のズーム。手ブレ。
フェンスの外から撮っている角度。
次の瞬間、煙が上がる。
誰かが叫ぶ声が入っている。
そして――火。
火が、ひとつの人影に絡みつく。
人影が、よろける。
走る。
助けようとする誰かの影。
でもカメラは、助けない。
ただ、撮り続ける。
(……紗季先輩)
炎の中で、紗季先輩の制服みたいな布が見えた。
燃える、という言葉が、意味を失うくらい、画面は生々しい。
桃が手で口を押さえた。
凛の瞳が硬くなる。
僕の喉が、変な音を立てた。
お母さんは画面の下を指でなぞった。
そこには、コメント欄のスクロール。
「草」
「マジで燃えてて草」
「これ本物?」
「炎上(物理)」
「やば」
一文字一文字が、刃だった。
刃先が丸まっていない。尖っている。楽しそうに。
「……削除依頼も出したの」
お母さんが、声を絞った。
「でも、消しても消しても……誰かが持っていて、また上げるの。切り抜かれて、また回るの」
切り抜き。
拡散。
戻せない。
僕の仕事の単語が、全部、罪の単語に変わっていく。
凛が、静かに言った。
「撮ったのは……誰なんですか」
お母さんは首を振った。
「分からない。……だから、お願い。映画部なら、映像を見て分かることがあるかもしれない」
「……この動画、データでもらえますか」
僕は、自分の声が震えているのを自覚しながら言った。
「……編集のことは、僕が一番分かる。僕、編集担当で」
凛が僕を見る。
お母さんは少し迷ってから、頷いた。
「ありがとう。……ここから送れるかしら。容量が大きくて」
「僕のスマホに、一度送ってください」
僕は言った。
「あとでPCに移します」
お母さんが操作を始め、数十秒の沈黙が生まれる。
その沈黙が、病室の機械音を余計に際立たせた。
ピロン、と僕のスマホが震えた。
動画ファイルが届いた通知。
(これが、炎上して消えたの正体)
炎上は比喩じゃなかった。
そして比喩より残酷だった。
燃えている本人の映像が、娯楽として流れている。
僕はスマホを握りしめた。
握りしめることで、画面の中の火を押し込められる気がしたから。
お母さんは最後に、僕らに向かって深く頭を下げた。
「来てくれて、ありがとう。紗季……きっと、嬉しいと思う」
(嬉しいのか?嬉しいって、何だ?)
答えは出ない。
病室を出るとき、僕はベッドの紗季先輩を見た。
眠っている顔。動かない指先。
それでも――何かが言いたい顔に見えた。
僕の都合かもしれない。
でも、映像を扱う人間は、都合で読み取ってしまう。
家に帰ってからも、手が落ち着かなかった。
夕飯の味がしない。
家族の声が遠い。
部室の解散宣告より、踏切のベルより、今日見た動画の火が、目の奥で燃え続ける。
僕は自室に籠もり、PCを立ち上げた。
動画ファイルを取り込む。
編集ソフトに読み込む。
タイムラインに、あの火の映像が置かれる。
(……これを編集するの?)
罪悪感が喉に張り付く。
でも、編集は刃だ。
刃を持ったまま、手を引っ込めたら、次に誰かが刺される。
僕は再生した。
画面の中で煙が上がり、火が出て、紗季先輩が燃える。
耐えられなくて一度停止した。
それでも、もう一度再生する。
「……ごめんなさい」
誰に向けた謝罪か分からないまま、僕は呟いた。
僕はフレームを進めた。
一コマずつ。
指先が機械的になる。
感情を殺して、仕事にする。編集のときの癖だ。
(この動画、撮ってる人……)
カメラの位置。揺れ方。ズーム。
撮影者は、助けるより先に撮っている。
それが許せない。
でも、そういう人がいるから、こういう動画が残る。
そのとき――画面の中央あたりで、紗季先輩が一瞬だけこちらを向いた。
炎の中で、顔の輪郭がぼやける。
けれど、口が――動いている。
(……え)
僕は息を止め、さらにスローにした。
拡大する。ノイズが増える。
それでも、口元の動きは確かに言葉だった。
(何て言ってる?)
音は入っている。でも、聞き取りたくない。
そもそも周囲の叫びで埋もれている。
だから、僕は読む。
唇の形。開き方。舌の位置。
何度も巻き戻して、指でタイムコードを押さえた。
「……り」
「ん」
「に」
「きょ……か」
「を」
「とれ」
僕の背中が、冷たくなる。
『りんにきょかをとれ』
(凛……?)
凛に許可を取れ。
手紙の中の「ある人」が、突然、輪郭を持ってしまった。
僕の頭の中で、あの台詞テープが再生される。
僕は、画面を見たまま動けなくなった。
PCのファンの音だけが、部屋に残る。
ここで初めて、僕は気づいた。
次の指示は、もう紙の中だけじゃない。
映像の中に、残されている。
(明日、凛に……話さないと)
僕は息を吸って、吐いた。
笑うでも泣くでもない。
ただ、生きるための息。
そして、画面の中の紗季先輩の口元を、もう一度見た。
『りんにきょかをとれ』
消えない字幕みたいに、そこにあった。