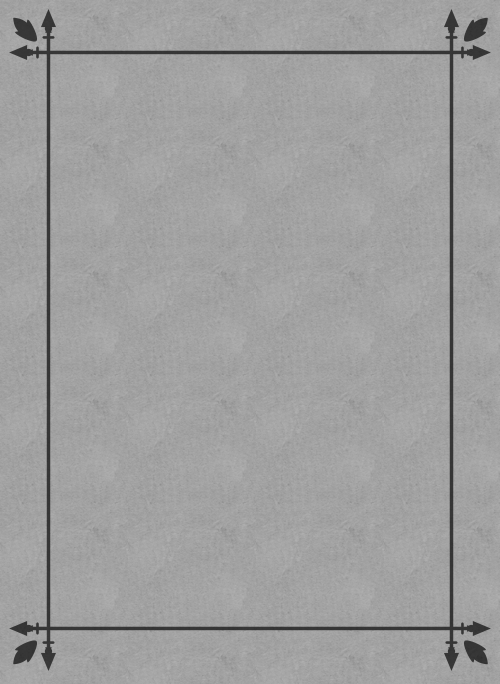病院の前って、どうしてこんなに明るいんだろう。
夜に向かって暗くなる街の中で、総合病院だけが蛍光灯の白を大量に吐き出している。
「……ここ?」
桃が、入口の看板を見上げながら小声で言った。
「近隣で一番大きい総合病院だし、まずはここから」
凛が淡々と答える。
「病院の自販機なんて曖昧すぎる指示、当てに行くなら最大公約数」
僕――和真は頷いた。
(最大公約数。凛は言い方がいつも数学的だ)
ポケットの中で、穴あきしおりの紙の角をこすった。
「水ばっかり」。
あの言葉だけが、やけに具体的で、やけに情けない。
(病院に来て、自販機を探す高校生って何だよ……)
そう思ったのに、心臓は速い。
怖い。
けど、ここまで来たら戻れない。
病院の中は、消毒液の匂いと、遠くの咳払いと、靴音の反響でできていた。
受付の前を通ると、制服の僕らは少し浮く。
見られる。けど、誰も声をかけてこない。
みんな、自分の不安で手一杯なんだ。
廊下の端に、自販機コーナーがあった。
赤い缶の列、甘い炭酸、栄養ドリンク、コーヒー。
普通の自販機だ。
「水ばっかりじゃない」
桃が肩を落とした。
「ここじゃないだけ」
凛は迷いがない。
「病棟側かも。付き添いの人が水を買う場所」
(付き添い……)
その言葉が胸を軽く叩いた。
僕らは案内板を見て、病棟の方へ歩いた。
エレベーター前の待合スペース。
椅子に座っている人たちの表情が、どれも沈んでいる。
テレビの音だけが妙に明るい。
「……なんか、喋りづらいね」
桃が囁く。
角を曲がった先、壁際に並んだ自販機の列があった。
その中に――一台だけ、妙に地味なやつがある。
ラベルが全部「水」。
ミネラルウォーター、炭酸水、常温水、やわらかい水。
「……水ばっかりだ」
桃が、感心半分で言った。
「見つけた」
凛は短く頷いた。
僕は息を吸って、吐いた。
(当たった。ということは――)
「で、何を探すの?」
桃が僕を見る。
「分からない」
僕は正直に答えた。
「でも、何かがあるって言われてる気がする」
凛が壁と自販機の隙間を覗き込んだ。
「裏、見れる?」
「店員みたいだな」
僕は言いながら、膝をついた。
自販機の横は狭い。手を突っ込むと埃が指に付く。
病院の中なのに、こういう場所は現実的に汚い。
自販機の裏側――壁との隙間に、透明なビニールが見えた。
テープで軽く留めてある。防水のためか、二重にされている。
「……あった」
僕の声が、思ったより小さく震えた。
凛がすぐに周囲を見る。
「人、いない。取って」
僕は慎重にビニールを剥がした。
ペリ、と音がして、妙に大きく響いた気がして、心臓が跳ねる。
中に入っていたのは、折りたたまれた便箋。
「読む?」
桃が囁く。
僕は頷いて、便箋を開いた。
文字は、印刷じゃない。手書き。
筆圧が強い。真面目な字。
『暗号を辿ってくれた人へ
ここまで来てくれて、ありがとう。
この手紙を読んでいるあなたは、たぶん「知りたい」と思ってしまった人だと思う。
私も同じだった。
私は、勝手に撮った映像で、ある人を傷つけました。
「作品のため」って言い訳をして、許可を取らずに、撮って、残してしまった。
その人の弱さを、私が素材にしてしまった。
その映像は、私の手を離れて切り抜かれて、拡散されました。
私がやったことは、刃の柄を握ったつもりで、刃先を人に向けたことだった。
私は、誰かの人生を勝手に編集した。
もしあなたが、まだ撮るなら。
どうか、刃先を丸めて。
見せない優しさを覚えて。
そして、誰かに許可を取って。
紗季』
手紙を読み終えたとき、僕の喉が変な音を立てた。
息を吸うのも、吐くのも、下手になる。
(勝手に撮った映像で、人を傷つけた)
ある人。
名前は書かれていない。
隣を見ると、桃は唇を噛んでいた。
目は潤んでいるのに、泣かない。
泣くなって、誰も言ってないのに。
自分で自分に命令しているみたいだった。
僕は手紙を折りたたんで、ビニールに戻した。
見せない。
これは、誰かに見せて回るための手紙じゃない。
その瞬間だった。
「――あの」
背後から声をかけられて、僕はびくっと肩を跳ねさせた。
振り向くと、中年の女性が立っていた。
上品なコートに、少し疲れた目。手には病院の売店の袋。
女性の視線が、僕らの制服に落ちる。
そして、息を吸うように言った。
「紗季と同じ高校の制服……。もしかして、紗季のお友達かしら?」
僕の心臓が、一拍遅れて鳴った。
(……紗季先輩のお母さん?)
凛が一歩前に出る。
桃は、言葉を失ったまま女性を見ている。
僕は手紙の重さを、ポケットの中で確かめた。
(ここまで来た続きは――もう、逃げられない)
夜に向かって暗くなる街の中で、総合病院だけが蛍光灯の白を大量に吐き出している。
「……ここ?」
桃が、入口の看板を見上げながら小声で言った。
「近隣で一番大きい総合病院だし、まずはここから」
凛が淡々と答える。
「病院の自販機なんて曖昧すぎる指示、当てに行くなら最大公約数」
僕――和真は頷いた。
(最大公約数。凛は言い方がいつも数学的だ)
ポケットの中で、穴あきしおりの紙の角をこすった。
「水ばっかり」。
あの言葉だけが、やけに具体的で、やけに情けない。
(病院に来て、自販機を探す高校生って何だよ……)
そう思ったのに、心臓は速い。
怖い。
けど、ここまで来たら戻れない。
病院の中は、消毒液の匂いと、遠くの咳払いと、靴音の反響でできていた。
受付の前を通ると、制服の僕らは少し浮く。
見られる。けど、誰も声をかけてこない。
みんな、自分の不安で手一杯なんだ。
廊下の端に、自販機コーナーがあった。
赤い缶の列、甘い炭酸、栄養ドリンク、コーヒー。
普通の自販機だ。
「水ばっかりじゃない」
桃が肩を落とした。
「ここじゃないだけ」
凛は迷いがない。
「病棟側かも。付き添いの人が水を買う場所」
(付き添い……)
その言葉が胸を軽く叩いた。
僕らは案内板を見て、病棟の方へ歩いた。
エレベーター前の待合スペース。
椅子に座っている人たちの表情が、どれも沈んでいる。
テレビの音だけが妙に明るい。
「……なんか、喋りづらいね」
桃が囁く。
角を曲がった先、壁際に並んだ自販機の列があった。
その中に――一台だけ、妙に地味なやつがある。
ラベルが全部「水」。
ミネラルウォーター、炭酸水、常温水、やわらかい水。
「……水ばっかりだ」
桃が、感心半分で言った。
「見つけた」
凛は短く頷いた。
僕は息を吸って、吐いた。
(当たった。ということは――)
「で、何を探すの?」
桃が僕を見る。
「分からない」
僕は正直に答えた。
「でも、何かがあるって言われてる気がする」
凛が壁と自販機の隙間を覗き込んだ。
「裏、見れる?」
「店員みたいだな」
僕は言いながら、膝をついた。
自販機の横は狭い。手を突っ込むと埃が指に付く。
病院の中なのに、こういう場所は現実的に汚い。
自販機の裏側――壁との隙間に、透明なビニールが見えた。
テープで軽く留めてある。防水のためか、二重にされている。
「……あった」
僕の声が、思ったより小さく震えた。
凛がすぐに周囲を見る。
「人、いない。取って」
僕は慎重にビニールを剥がした。
ペリ、と音がして、妙に大きく響いた気がして、心臓が跳ねる。
中に入っていたのは、折りたたまれた便箋。
「読む?」
桃が囁く。
僕は頷いて、便箋を開いた。
文字は、印刷じゃない。手書き。
筆圧が強い。真面目な字。
『暗号を辿ってくれた人へ
ここまで来てくれて、ありがとう。
この手紙を読んでいるあなたは、たぶん「知りたい」と思ってしまった人だと思う。
私も同じだった。
私は、勝手に撮った映像で、ある人を傷つけました。
「作品のため」って言い訳をして、許可を取らずに、撮って、残してしまった。
その人の弱さを、私が素材にしてしまった。
その映像は、私の手を離れて切り抜かれて、拡散されました。
私がやったことは、刃の柄を握ったつもりで、刃先を人に向けたことだった。
私は、誰かの人生を勝手に編集した。
もしあなたが、まだ撮るなら。
どうか、刃先を丸めて。
見せない優しさを覚えて。
そして、誰かに許可を取って。
紗季』
手紙を読み終えたとき、僕の喉が変な音を立てた。
息を吸うのも、吐くのも、下手になる。
(勝手に撮った映像で、人を傷つけた)
ある人。
名前は書かれていない。
隣を見ると、桃は唇を噛んでいた。
目は潤んでいるのに、泣かない。
泣くなって、誰も言ってないのに。
自分で自分に命令しているみたいだった。
僕は手紙を折りたたんで、ビニールに戻した。
見せない。
これは、誰かに見せて回るための手紙じゃない。
その瞬間だった。
「――あの」
背後から声をかけられて、僕はびくっと肩を跳ねさせた。
振り向くと、中年の女性が立っていた。
上品なコートに、少し疲れた目。手には病院の売店の袋。
女性の視線が、僕らの制服に落ちる。
そして、息を吸うように言った。
「紗季と同じ高校の制服……。もしかして、紗季のお友達かしら?」
僕の心臓が、一拍遅れて鳴った。
(……紗季先輩のお母さん?)
凛が一歩前に出る。
桃は、言葉を失ったまま女性を見ている。
僕は手紙の重さを、ポケットの中で確かめた。
(ここまで来た続きは――もう、逃げられない)