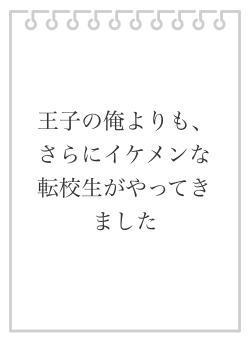俺が生きている中で一番思い出に残っていることは、小2の頃に出会った女の子のことだ。今でもあの子に出会ったことは運命ではないかと思ってしまう。
『うわあぁぁぁぁん。どこ…?ここ、どこ…?』
河川敷でサッカーをやっているとき、突然泣き声が聞こえたもんだからびっくりした。そしていつまでたっても泣き止まないから、俺は声をかけた。
『どうしたの?大丈夫?』
彼女は涙でぐしゃぐしゃになった顔を向けて、
『ここ、どこだかわかんなくなっちゃった…。遊んでたら、どこだか…わかんなくなって……』
『どっちから来たの?』
彼女は記憶を呼び起こしているのかちょっと考えた顔をしてはっとする。
『あっち!』
『あっちか。俺の家も向こうだから一緒に行こうぜ』
『うん!』
向こうにあるタンポポ畑に案内しようと思っていた。彼女の気持ちが少しでもやわらぎそうだったから。そう思って歩いていると、
『お兄ちゃん、何歳?お名前なーに?』
と聞いてきた。俺は、
『小学校2年生だよ。名前は涼介』
『あ!一緒だ!私も2年生!私は、美優』
ずいぶん可愛らしい名前だなと思った。でも、ふっと暗い顔を見せて、
『でも…、お母さんに嫌われてるんだ……。だから、逃げて…きたのっ…』
最後の方は涙が滲んできている声だった。また、大泣きするかなと思いきや
『もう、泣かないもん!』
と我慢していた。その顔に胸が抉られる気持ちになった。だから俺は、
『嫌になったら泣いてもいいんだよ。誰も怒らない。悲しくなったら俺のとこに来なよ』
小2でよくこんなキザなこと言えたなと思う。でも、彼女の反応をみていってよかったなと思う。
『うん!ありがとっ!』
そんな話をしている間に目的に着く。
綺麗なタンポポ畑。きっと自然に生えてきたものなのに、なぜこんな美しいのだろう。
『う、わぁ………』
彼女は驚いて何も話せないようだった。俺も同じ気持ちだった。すると彼女が突然走り出す。そしてタンポポ畑の真ん中あたりにいって、こちらを振り返る。
『お兄ちゃんもおいでよ!』
帽子を押さえて言ってくる。ふわりと風が吹いているからだろう。白いワンピースと可愛らしい麦わら帽子がマッチしている。
俺はその瞬間、彼女が消えてしまいそうな感覚に襲われて、思わず抱きついてしまった。
『お兄、ちゃん……?』
『また、絶対会おう。絶対に』
『もちろん!毎日ここにいるし、会えるよ!』
その彼女の微笑みがひどく愛おしくなる。絶対に会おうと思った。
それからも何度も彼女と会って
『どこ小学校?』
『俺、西小だよ。』
『あ!近い!私中央小』
『おおぉ。毎日会えるじゃん』
いつものタンポポ畑で、いくつもの思い出を作ってきた。でも、それも束の間の出来事だった。
小2のクリスマス。ちょうど雪が降っていた。タンポポの花はもちろん咲いていないが、そこで話していた。いつもの場所、いつもの時間で待っていた。
でも、いつまでたっても美優は来ない。
『せっかく、プレゼント持ってきたのにな』
震える手を息で温めながら河川敷でまつ。
すると彼女が紙袋を握りしめて走ってきた。
『ご…めん…!』
『全然。俺もさっき着いたから』
嘘だ。本当は30分くらい待っていたのに。
『でも…』
『はい。クリスマスプレゼント。美優のために用意した』
『ありがとう。開けていい?』
涙目になりながら聞いてきた。そんなに嬉しいことだったのだろうか。
『あ、手袋!あり…がとっ…。っ…うぅ』
声が漏れ出ている。そんな彼女のことを抱きしめる。どんな彼女でも受け入れる。
『涼介、ぎゅーしちゃ恥ずかしい…よっ……』
幼い言葉が口から出ている。可愛い、可愛い。
『大丈夫』
それからしばらく、彼女が泣き止むのを待った。
『涼介に、プレゼント』
美優が口を開いていった。
『開けるね』
それは、手袋だった。
『同じだね』
『うん』
幸せなホワイトクリスマス。2年生の俺らながらの幸せのかたち。
『ばいばい』
『またね。また一緒にタンポポ畑に行こうね』
短い言葉を交わして、この日は終わった。また美優に会えると思っていた。
でも、さよならは突然やってくる。
俺は家に帰って、美優からもらった紙袋の中身を開けた。するとそこには手作りのお菓子と手紙が入っていた。何だろうと思い、開けると
涼介へ
私たちの出会いは、すごくかんたんなものだったね。私を助けてくれたりょうすけ、すごくかっこよかった。
たんぽぽばたけに連れてってくれたのが、すごくうれしかったよ。多分、今まででいちばん幸せな思い出だと思う。
さて、この手紙を書いたのは、りょうすけにおねがいがあるからなの。
もう、川にきても私はいません。きたいしないでください。なぜかというと、となりまちにひっこすことになったから。ごめんね、言えなくて。
小学校も向こうのところになるの。ごめんね。
いつかはここに戻ってくるから、それまで待ってて。
美優より
『え……。もう、会えないの……?』
心の中を絶望という感情が渦巻く。
その年、俺はずっと泣き叫び続けた。
何度も河川敷に、タンポポ畑に行った。でも美優はいなかった。
『もう会えないんだ…。なら、いつか戻ってくるのを待とう』
そうやって心の整理がついたのは小学校6年生のときだった。
俺は6年生から4年歳をとり、高校一年生になった。どこかで美優も同じように歳をとっていることを信じて。
俺が入った高校に、美優、いや美優と思われる人物がいた。
まさかこの辺では結構学力が高い日野坂高校にいるなんて。
でも、昔見た美優とは正反対だった。
自分の意見は言わないし、物静か。
あの笑顔も見せていない。
この、俺のいない8年間の間に何があったのだろうか。
聞きたい質問はたくさんある。
[小学校はどうだった?]
[中学校はどうだった?]
[何でここ入ったの?]
そして
[俺のこと覚えてる?]
昔会った美優ではないかもしれないから何とも言えない。いや、美優じゃないだろう。
もしあの子が美優だったとしたら、願いは一つ。
『また一緒にタンポポ畑にいこうね』
この彼女の願いを叶えること。夕日にあたってきらきらと輝くタンポポを一緒に見ること。
2年生になって同じクラスになって心が舞上がる思いだった。そして隣の席にもなれた。
奇跡だ。
でも、きっと向こうは覚えていないし、あの美優じゃない。それにしても、どうして俺のことを嫌がっているのだろう?
「何でだろ……」
ふとした疑問が口からこぼれる。
「え?どうしたのー?」
高梨綾乃の甘い(わざとらしい)声が聞こえる。
「別に。なんでもないよ。」
「えぇー?あ、今日の午後遊びに行こ!」
「いいよ」
短く答える。本当はめんどくさいし、できることなら美優といたい。でもここで、もしここで断ってしまったら、綾乃の怒りの矛先は美優に向くだろう。
今までも、ちょくちょく悪口を言っているのを見ていた。
「……仕方ないだろ」
ぼそっと言った一言は誰にも聞かれずに人の波に飲み込まれる。
結局仕方ないで終わらせてしまう自分、話しかけられない自分、そして怖くて逃げてしまう自分。
いつか変えたいと思っても変わらないのが現状。こんな自分に嫌気がさす。
いつか、誰かに話せたら。
美優はあの"美優"じゃないと思考に区切りをつけた。
☁︎☔︎
「ね、笠野さん?今日、放課後、図書室ね」
彼女は一瞬嫌そうな顔をしたが、
「いいよ」
と冷たい一言を伝えて去っていった。
まあ、無理もないだろう。だってこないだ無理矢理何があったのか聞き出そうとして、逃げられたもんな。
「涼介ー!一緒に移動行こ」
「おう。ちょっと待って」
「いいよー」
また高梨綾乃と矢伊那あかりが寄ってくる。正直言って、俺が苦手なのは、高梨綾乃よりも矢伊那あかり。
彼女はいつも横にいるだけで何も言わない。口を開くのはごくわずかな時間のみ。
そして、この間、みんなで集まって遊ぶ予定を話したとき、矢伊那あかりは綾乃のことを刺すような目で見ていた。恨みでもあるかのように。
俺は彼女のミステリアスな空気が苦手だ。
でも、綾乃も苦手。あからさまな嘘をすぐにつくし、ぶりっ子でもある。
『どっちも苦手』これが俺の結論。
「ふわぁぁ〜」
大きなあくびが出た。そういえばここ数日、3時間ほどしか寝ていない。
彼女に認めてもらえるように勉強に本気で取り組んでいるのだ。
「もう、早くいこーよ」
「はいはい。お前は俺のお母さんか」
「違うもん」
わざとらしいふてくされ顔を見せられて何ともいえない気持ちになる。俺が見たいのはこんな嘘まみれの笑顔じゃない。
もっと透明で繊細で……。
「それでさー。でね?」
「そうなんだ。てかさー」
綾乃やあかりたちのグループが楽しそうに話しているのが耳の端っこで聞こえる。
「聞いてる?」
心配している彼女たちの声。
「もちろん」
無理な笑顔を作りすぎたか。前にもこんな状況を見た気がする。
あぁ。あのときだ。笠野さんと追いかけっこをしたあの日だ。あのときの笠野さんは、作り笑いをしていた。バレバレの。
でも、一瞬暗い顔をしていた。何としてでも、聞き出さないと。
彼女を守るために、寄り添うために。
『うわあぁぁぁぁん。どこ…?ここ、どこ…?』
河川敷でサッカーをやっているとき、突然泣き声が聞こえたもんだからびっくりした。そしていつまでたっても泣き止まないから、俺は声をかけた。
『どうしたの?大丈夫?』
彼女は涙でぐしゃぐしゃになった顔を向けて、
『ここ、どこだかわかんなくなっちゃった…。遊んでたら、どこだか…わかんなくなって……』
『どっちから来たの?』
彼女は記憶を呼び起こしているのかちょっと考えた顔をしてはっとする。
『あっち!』
『あっちか。俺の家も向こうだから一緒に行こうぜ』
『うん!』
向こうにあるタンポポ畑に案内しようと思っていた。彼女の気持ちが少しでもやわらぎそうだったから。そう思って歩いていると、
『お兄ちゃん、何歳?お名前なーに?』
と聞いてきた。俺は、
『小学校2年生だよ。名前は涼介』
『あ!一緒だ!私も2年生!私は、美優』
ずいぶん可愛らしい名前だなと思った。でも、ふっと暗い顔を見せて、
『でも…、お母さんに嫌われてるんだ……。だから、逃げて…きたのっ…』
最後の方は涙が滲んできている声だった。また、大泣きするかなと思いきや
『もう、泣かないもん!』
と我慢していた。その顔に胸が抉られる気持ちになった。だから俺は、
『嫌になったら泣いてもいいんだよ。誰も怒らない。悲しくなったら俺のとこに来なよ』
小2でよくこんなキザなこと言えたなと思う。でも、彼女の反応をみていってよかったなと思う。
『うん!ありがとっ!』
そんな話をしている間に目的に着く。
綺麗なタンポポ畑。きっと自然に生えてきたものなのに、なぜこんな美しいのだろう。
『う、わぁ………』
彼女は驚いて何も話せないようだった。俺も同じ気持ちだった。すると彼女が突然走り出す。そしてタンポポ畑の真ん中あたりにいって、こちらを振り返る。
『お兄ちゃんもおいでよ!』
帽子を押さえて言ってくる。ふわりと風が吹いているからだろう。白いワンピースと可愛らしい麦わら帽子がマッチしている。
俺はその瞬間、彼女が消えてしまいそうな感覚に襲われて、思わず抱きついてしまった。
『お兄、ちゃん……?』
『また、絶対会おう。絶対に』
『もちろん!毎日ここにいるし、会えるよ!』
その彼女の微笑みがひどく愛おしくなる。絶対に会おうと思った。
それからも何度も彼女と会って
『どこ小学校?』
『俺、西小だよ。』
『あ!近い!私中央小』
『おおぉ。毎日会えるじゃん』
いつものタンポポ畑で、いくつもの思い出を作ってきた。でも、それも束の間の出来事だった。
小2のクリスマス。ちょうど雪が降っていた。タンポポの花はもちろん咲いていないが、そこで話していた。いつもの場所、いつもの時間で待っていた。
でも、いつまでたっても美優は来ない。
『せっかく、プレゼント持ってきたのにな』
震える手を息で温めながら河川敷でまつ。
すると彼女が紙袋を握りしめて走ってきた。
『ご…めん…!』
『全然。俺もさっき着いたから』
嘘だ。本当は30分くらい待っていたのに。
『でも…』
『はい。クリスマスプレゼント。美優のために用意した』
『ありがとう。開けていい?』
涙目になりながら聞いてきた。そんなに嬉しいことだったのだろうか。
『あ、手袋!あり…がとっ…。っ…うぅ』
声が漏れ出ている。そんな彼女のことを抱きしめる。どんな彼女でも受け入れる。
『涼介、ぎゅーしちゃ恥ずかしい…よっ……』
幼い言葉が口から出ている。可愛い、可愛い。
『大丈夫』
それからしばらく、彼女が泣き止むのを待った。
『涼介に、プレゼント』
美優が口を開いていった。
『開けるね』
それは、手袋だった。
『同じだね』
『うん』
幸せなホワイトクリスマス。2年生の俺らながらの幸せのかたち。
『ばいばい』
『またね。また一緒にタンポポ畑に行こうね』
短い言葉を交わして、この日は終わった。また美優に会えると思っていた。
でも、さよならは突然やってくる。
俺は家に帰って、美優からもらった紙袋の中身を開けた。するとそこには手作りのお菓子と手紙が入っていた。何だろうと思い、開けると
涼介へ
私たちの出会いは、すごくかんたんなものだったね。私を助けてくれたりょうすけ、すごくかっこよかった。
たんぽぽばたけに連れてってくれたのが、すごくうれしかったよ。多分、今まででいちばん幸せな思い出だと思う。
さて、この手紙を書いたのは、りょうすけにおねがいがあるからなの。
もう、川にきても私はいません。きたいしないでください。なぜかというと、となりまちにひっこすことになったから。ごめんね、言えなくて。
小学校も向こうのところになるの。ごめんね。
いつかはここに戻ってくるから、それまで待ってて。
美優より
『え……。もう、会えないの……?』
心の中を絶望という感情が渦巻く。
その年、俺はずっと泣き叫び続けた。
何度も河川敷に、タンポポ畑に行った。でも美優はいなかった。
『もう会えないんだ…。なら、いつか戻ってくるのを待とう』
そうやって心の整理がついたのは小学校6年生のときだった。
俺は6年生から4年歳をとり、高校一年生になった。どこかで美優も同じように歳をとっていることを信じて。
俺が入った高校に、美優、いや美優と思われる人物がいた。
まさかこの辺では結構学力が高い日野坂高校にいるなんて。
でも、昔見た美優とは正反対だった。
自分の意見は言わないし、物静か。
あの笑顔も見せていない。
この、俺のいない8年間の間に何があったのだろうか。
聞きたい質問はたくさんある。
[小学校はどうだった?]
[中学校はどうだった?]
[何でここ入ったの?]
そして
[俺のこと覚えてる?]
昔会った美優ではないかもしれないから何とも言えない。いや、美優じゃないだろう。
もしあの子が美優だったとしたら、願いは一つ。
『また一緒にタンポポ畑にいこうね』
この彼女の願いを叶えること。夕日にあたってきらきらと輝くタンポポを一緒に見ること。
2年生になって同じクラスになって心が舞上がる思いだった。そして隣の席にもなれた。
奇跡だ。
でも、きっと向こうは覚えていないし、あの美優じゃない。それにしても、どうして俺のことを嫌がっているのだろう?
「何でだろ……」
ふとした疑問が口からこぼれる。
「え?どうしたのー?」
高梨綾乃の甘い(わざとらしい)声が聞こえる。
「別に。なんでもないよ。」
「えぇー?あ、今日の午後遊びに行こ!」
「いいよ」
短く答える。本当はめんどくさいし、できることなら美優といたい。でもここで、もしここで断ってしまったら、綾乃の怒りの矛先は美優に向くだろう。
今までも、ちょくちょく悪口を言っているのを見ていた。
「……仕方ないだろ」
ぼそっと言った一言は誰にも聞かれずに人の波に飲み込まれる。
結局仕方ないで終わらせてしまう自分、話しかけられない自分、そして怖くて逃げてしまう自分。
いつか変えたいと思っても変わらないのが現状。こんな自分に嫌気がさす。
いつか、誰かに話せたら。
美優はあの"美優"じゃないと思考に区切りをつけた。
☁︎☔︎
「ね、笠野さん?今日、放課後、図書室ね」
彼女は一瞬嫌そうな顔をしたが、
「いいよ」
と冷たい一言を伝えて去っていった。
まあ、無理もないだろう。だってこないだ無理矢理何があったのか聞き出そうとして、逃げられたもんな。
「涼介ー!一緒に移動行こ」
「おう。ちょっと待って」
「いいよー」
また高梨綾乃と矢伊那あかりが寄ってくる。正直言って、俺が苦手なのは、高梨綾乃よりも矢伊那あかり。
彼女はいつも横にいるだけで何も言わない。口を開くのはごくわずかな時間のみ。
そして、この間、みんなで集まって遊ぶ予定を話したとき、矢伊那あかりは綾乃のことを刺すような目で見ていた。恨みでもあるかのように。
俺は彼女のミステリアスな空気が苦手だ。
でも、綾乃も苦手。あからさまな嘘をすぐにつくし、ぶりっ子でもある。
『どっちも苦手』これが俺の結論。
「ふわぁぁ〜」
大きなあくびが出た。そういえばここ数日、3時間ほどしか寝ていない。
彼女に認めてもらえるように勉強に本気で取り組んでいるのだ。
「もう、早くいこーよ」
「はいはい。お前は俺のお母さんか」
「違うもん」
わざとらしいふてくされ顔を見せられて何ともいえない気持ちになる。俺が見たいのはこんな嘘まみれの笑顔じゃない。
もっと透明で繊細で……。
「それでさー。でね?」
「そうなんだ。てかさー」
綾乃やあかりたちのグループが楽しそうに話しているのが耳の端っこで聞こえる。
「聞いてる?」
心配している彼女たちの声。
「もちろん」
無理な笑顔を作りすぎたか。前にもこんな状況を見た気がする。
あぁ。あのときだ。笠野さんと追いかけっこをしたあの日だ。あのときの笠野さんは、作り笑いをしていた。バレバレの。
でも、一瞬暗い顔をしていた。何としてでも、聞き出さないと。
彼女を守るために、寄り添うために。