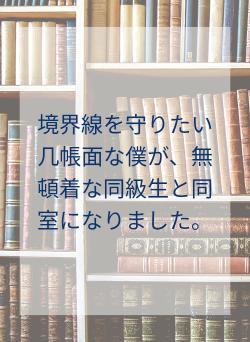『ところで、氷室。お前、学園祭には参加すんのか?」
「しねぇつもりだったけど、強制参加なんだってよ」
「まあ、うちの学園、出席率は98%超えが義務だからな。たぶん勝手に休んだら担任から説教来るぞ」
「げ。面倒くせえ」
「同感だ」
俺は氷室が準備してくれた焼きそばに箸をつけながら、奴を盗み見る。学園では孤高を貫く不良だが、ここで一緒に過ごす氷室はどこか年相応で親しみやすい雰囲気を持っていた。しかも意外と世話を焼いてくる。面倒見が良いのはお互い様だと思う。
「……お前、バイトは?」
「今は少し減らしてる。土日どっちかで篠宮が来ない日だけ。後はシフト抜けまくってるから、その分給料減るけどしょうがねえな。成績がマジやべぇし」
口を出すのは憚られたが、やはり家庭環境的に厳しいらしい。体調は大丈夫なのだろうか。そんなことを気にかけるのは、余計なお世話なのだろうが、心配になってしまう。
「……勉強は、俺が責任持って教えるから」
「頼もしいな。ありがとな」
氷室は素直に礼を言った。その口調には嫌みはなく、むしろ誠実さが滲んでいた。さっきも面と向かって褒めてきたし、ずっと他人を見下している怖い不良だと思っていたが、見た目と違っていい奴なのだと改めて認識してしまう。
……なんだか、変に照れくさい気持ちになった俺は、慌てて話題を変えた。
「お前、学園祭の手伝いとかしてるのか?」
「ちょっと別口で頼まれたことはあるけど、クラスの準備には全然参加してねえな。そもそもA組の催し物の内容を詳しく知らねえし。なんか喫茶店やるんだろ? 実行委員の奴から、給仕担当やれって言われたから、まあ、当日の労働義務くらいは果たすか……」
「ほほう……給仕担当?」
「なんだよ」
「いや、別に」
俺はニヤリと笑った。
この様子では、氷室は俺たちのクラスがコンセプトカフェにする計画までは把握していないのだろう。俺のコスプレは桐谷が阻止してくれたが、情報網の粗い氷室には伝わっていないようだ。
当日、氷室がどういう格好をさせられるか想像すると、少しだけ愉快な気分になった。背も高いし、執事姿は意外と似合う気がする。案外周りから人気になるのではないだろうか。
ニヤついていると、すぐ隣からシャッター音が聞こえた。反射的に振り向くと、氷室がいつの間にかカメラを構えていた。小型だが高性能そうな一眼レフだ。
「ちょ、おまっ、また!! 勝手に撮るな!」
「悪い。なんか面白い顔してたからさ」
「消せよ!」
「冗談だよ」
氷室は肩を竦めてカメラを操作する。液晶画面に表示された写真を確認し、頷いた。……やっぱり、またデータを残す気か?
この部屋で唯一落ち着かない出来事がコレだ。最近、氷室が頻繁に俺を撮影してくる。しかも本人曰く、面白画像フォルダに保存するらしい。趣味の悪さに呆れる。俺のプライベートが流出するのは死活問題なので、念の為釘を刺しておいた。
「おい、氷室。お前、その写真どうする気だ?」
「どうって、前にも言ったけど、面白画像として個人的に永久保存」
「消せ、と言ったはずだが?」
「勿体無い。結構いいショットだぜ?」
「どこがだよ! お前の感覚おかしいだろ!」
俺の抗議をまるっと無視して、氷室はカメラを片付け始める。その姿にため息をついた。
「ったく……」
「そんな怒んなよ。ほら、ポテチでも食うか? 好きだろ?」
「いらねーよ! ていうか、この流れで餌付けしようとするな!」
「遠慮すんなって」
「遠慮じゃねぇ!」
抗議する俺をよそに、氷室は袋からポテチを取り出して俺に向かって差し出す。本当にマイペースで自分勝手な奴。……そう思っていたが、慣れてくると案外憎めない。むしろ、俺に対する遠慮が全くない所が、一周回って清々しくさえある。
「ほら」
「……」
口を開けると、氷室がポテチを一枚差し込んできた。俺はそのまま齧りついた。カリカリとした歯触りが心地良い。塩味が口の中に広がる。甘いものを摂取した後の塩味サイコー。
ああ、もうダメだ。完全に油断してしまう。
「うまい」
「やっぱり、こういったジャンクなものが好きなんだな」
「違う。これは非常食だ。疲れた心に必要な栄養素を摂取しているだけだ」
「へえ」
氷室が何故か再びポテチを俺の口元に運んでくる。抗う気力もなく、つい反射的に口を開いてしまった。
「さっきまで怒ってたのに、素直に食うんだな」
「……うるさい。お前が勝手に突っ込んでくるからだ」
「そういうことにしておく」
「……」
無言で咀嚼する。その間も氷室は楽しそうに新しいポテチを俺に差し出してくる。普通に美味しい。俺はもはや抵抗することを諦め、されるがまま、氷室から与えられるポテチの虜になっている。
しかし、これは間違いなくダメなパターンだ。いつの間にか氷室のペースに嵌ってしまっている自分が恨めしい。こいつといると調子が狂うばかりだ。
「お前、もしかして俺のこと飼育しようとでも思ってるんじゃねえだろうな?」
「は? 何言ってんだ」
氷室に懐柔されつつある事実に、俺は危機感を感じていた。このままではまずい。現状について、少し考える時間が必要だ。俺は立ち上がった。
「……もういい。今日は終わりにする。帰る」
「え? いいのか? 今日はまだゲームやってねえだろ。一体どうした?」
氷室が首を傾げる。その顔は本当に分からないといった様子だ。天然なのか、確信犯なのか判別できない。
「今日はいい。お前は課題ちゃんとやっておけよ。あと来週は学園祭だから、来られるか分からない。なんかあったらメッセージ寄越せ。……くれぐれも学園で話しかけんなよ」
「分かった。じゃあ、またな」
氷室がひらひらと手を振る。意外とアッサリしたものだ。俺は鞄を持って出口へ向かった。靴を履き、扉を開けようと手を掛けたところで、後ろから声が掛かった。
「理久」
いきなり下の名前を呼ばれて硬直した。
普段は『お前』とか名字呼びばっかりだったのに。名前なんて初めて呼ばれた気がする。驚きすぎて振り返るタイミングを失ってしまった。動揺を悟られたくない。
幸いなことに、氷室は特に気にする様子もなく続けた。
「……がんばりすぎんなよ? いつでもここに来ていいからな」
予想外の優しさを感じる言葉に戸惑ってしまう。一瞬、氷室が本気で心配してくれているのではないかと思いかけたが、すぐに思い直した。それはない。あり得ない。
「……言われなくても適当に抜けるし。そんなに根性据わってねえからな」
精一杯虚勢を張って返事をすると、後ろから笑い声が聞こえた。何笑ってんだよ。
「じゃあな!!」
振り返ることなく、扉を閉めた。階段を降りて外に出ると既に夕暮れが迫っていた。空には綺麗な茜色が広がっている。
俺は力が抜けてその場にしゃがみ込み、頭を抱えた。鼓動が早い。なんだこれ。顔に熱が集まってくるのが分かる。
この感情は、誰にも知られる訳にはいかない。当然氷室自身にも。
多分、俺は今、すごく情けない顔をしているのだろう。