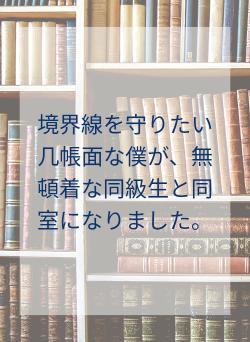「随分忙しそうだな」
「学園祭の準備か?」
氷室がコーヒーを俺の前に置いて言う。俺のために炭酸飲料は常に準備してくれているが、氷室カフェには温かい飲み物もラインナップにあるらしい。……と言っても、インスタントだが。
最初にミルクと砂糖を所望したら、「へえ、甘党なんだな」などと言いながらドバドバ入れてくれた。ありがたい。やっぱりこれくらい甘い方がコーヒーの苦味も程よく感じる。ブラックなんて喉が焼けるかと思った。
「本当にクソ忙しいんだよ!学園祭の準備のせいで、勉強以外でもやるべきことが山積みでさ。おまけに生徒会の通常業務まで加わって、俺のプライベートタイムがどんどん削られてくのなんの!」
愚痴を零しながら氷室が淹れてくれたコーヒーカップに口をつけると、丁度いい具合に砂糖とミルクが溶けたまろやかな甘さが口の中に広がった。ああ、これだよ。これこそが至福だ。
学園の王子様モードで消費したエネルギーを一気に補填していくような充足感。
「そりゃ、お疲れ」
「しかもさ、何故かみんな俺にあれこれ頼ってくるんだぜ?中途半端な対応したら、俺のイメージに傷がつくからどれもこれも疎かにできないし、全力でやらざるを得ないだろ?要領よくこなさないと、時間が足りねぇよ」
「優等生様も大変だな」
週末、氷室が実家の写真館兼私邸として利用している古い建物の中で、俺は愚痴をこぼしていた。
二階にある畳敷きのスペース。そこが俺の新たな憩いの場所となりつつあった。ここには人目がないので、本当の自分をさらけ出せるし、完璧で立派な自分を演じ続ける必要もない。
そして何より、氷室は甘党の俺のためにコーヒーにたっぷり砂糖を入れてくれる。至極の贅沢である。
「で、俺が指示した課題。ちゃんとやったか?」
「全部やってるぞ。毎回鬼みたいな量出してきやがって」
「何言ってんだ。お前にやらせる前に俺自身も全部解いてみて、その上で取捨選択してんだよ。まだまだ足りないくらいだ」
「……いや、学年首位のお前と比較すんなよ」
氷室は溜息を漏らしながら、机の上に広げていたノートや問題集をまとめて俺に見せる。俺が渡した問題集の範囲をほぼ網羅していた。指示通りきちんと自己採点もしてある。
口では足りない、と言っているが、実際はかなりの課題量を指示している。にもかかわらず、氷室は毎回キッチリこなしている。
「氷室って、意外と根性あるよな」
「お前、俺をなんだと思ってるんだ?」
「授業中に爆睡したりサボったりする不良?」
「最近はサボってねえし、授業も一応聞いてるぞ。あまりにもつまらないと寝るけど」
「やっぱり不良じゃん。課題の解答は……まあまあだな」
ぱらぱらとページを捲りながら、一つ一つの解答をチェックしていく。正直、氷室の学力は予想以上だった。理解力はあるし、基礎知識もきちんと身についている。ただ、圧倒的に勉強量が足りていなかったのだろう。地頭だけで乗り切ってきたせいか、学習習慣が身に付いていないのだ。公式や論述の書き方があやふやだし、応用力も足りていない。
テストは時間との戦いでもある。与えられた制限時間内で最適な解答を導き出せるかどうか。そこを訓練できれば、氷室の成績は飛躍的に伸びるだろう。
平日は俺が忙しすぎて時間が取れないので、週末を中心に課題を提示して、氷室がそれに1週間取り組み、翌週末に結果を確認しながら解説を行う。そんなサイクルが出来上がりつつあった。
要は毎週末、氷室宅に押し掛けては勉強漬けにするというものだ。俺の貴重なプライベートタイムはさらに減っていくのではあるが、この件に関しては今のところ大きな不満はない。
「分からなかった問題とかあるか?」
「そうだな、この数学の問題とか、解法が曖昧でな。何とか答えを出せたが自信ねえ」
「ああ、それはこうやって式変形して、さらに……」
数学の解説を始めると、氷室は真剣な眼差しで俺の話に耳を傾けていた。地頭が良いだけに、要点さえ押さえればすんなり理解してくれる。もともとセンスはあるのだろう。
「ああ、そうか。なるほど」
「理解できたなら良かった」
「……お前、教え方上手いし分かりやすいな。意外と面倒見もいいし」
氷室がポツリと呟いた言葉に思わず手が止まる。
「面倒見?」
「生徒会の雑務もそうだけど、愚痴こぼしながらも、周囲から頼られたら、その期待にちゃんと応えようと行動してるし。自分自身の勉強もやりながら、俺の依頼にも真摯に付き合ってくれるだろ。なんだかんだ言っても偉いと思う。俺も正直助かってる、ありがとな」
珍しくストレートに褒められ、感謝を述べてきた氷室に、一瞬面食らってしまう。だがすぐに思い出したように目を吊り上げて睨む。
「あー、そういう理由じゃねえからな! そもそも俺はお前が脅してきたから、仕方なくやってるだけであって……」
「分かってるって。いちいち突っかかんなよ。……それより、なんか食うか?」
「じゃあ、カップ焼きそば」
「りょーかい」
氷室が戸棚を開け、カップ麺を取り出すのを眺めながら、俺は小さく溜息をついた。
母親の再婚前は何度かカップ麺を食すこともあったが、今は自宅でカップ麺なんて絶対に食べられない。学園でも当然だ。毎食だと身体に悪いのかもしれないが、たまに無性に食べたくなるのだ。所詮自分は庶民なのだと痛感してしまう。
「いいなぁ、こういう生活……」
「なんか言ったか?」
「別に。なんでもねぇよ」
氷室が戻ってきた時には、俺は既に教科書を閉じ、ゴロリとこたつに寝そべっていた。来週までの課題は既に奴に指示済みだし。完全に寛ぎモードに入った俺を見て、氷室が「本当に猫みてえだな」と呟いたのが聞こえた。