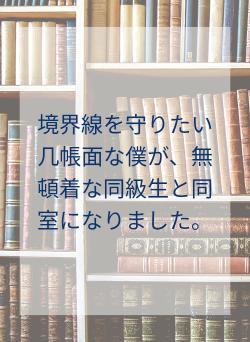氷室の窮地というのは、端的に言えば「成績がヤバい」ということだった。
A組は基本的に成績優秀者のみが集うクラスだ。そのため、赤点を取ったり退学レベルの問題を起こす生徒はほぼいない。氷室はその中でもなんと授業料免除の特待生枠に入っているらしい。人は見かけによらないものだ。
しかしその優遇措置にも条件があり、成績を維持できなければ特待生から外され、高額な授業料も通常通り支払う必要が出てくるとのこと。そうなると氷室は経済的な理由から進学すら難しいというのだ。
そんな事情があるなら、何故桐水学園みたいな金持ちしか通えないハイソサエティな私立高校を選んだのかと問い詰めてみれば、何でも公立高校の入試の日に同居していた祖父が倒れて病院に搬送されたのに付き添ったため、公立高校は受験できなかったらしい。
「一応、特待生制度あるからって滑り止めで受かってた私立入ったら、こんなことになっちまった」
氷室が『滑り止め』にした私立桐水学園はこれでも一応中高一貫の超進学校であり、所謂エリート養成校である。高等部からの編入も受け入れてはいるが狭き門だ。
そんな学園に合格できたこと自体が氷室の地頭の良さを証明しているはずだが、いかんせん生活費を稼ぐためのバイトや祖父の介護などで勉強の時間が割けず、ここ最近の成績は悲惨極まりないという。
授業中の居眠りやサボりには、一応理由があったという訳だ。
「……お前、両親とか親戚は?」
「父親は物心ついた頃から存在しないし、母親は……今はどこにいるか分からんな。ずっと人を捜してるみたいでさ。たまに帰ってきて金を置いてくだけで、失踪中だ。……じいちゃん以外の親戚には会ったことねえ」
「……」
『親殺し』という学園に蔓延る氷室の都市伝説は、半分本当で半分嘘といったところか。親が不在なのは確かだが、物理的に殺害したわけではないようだ。よかった……のか? よくわからんが。
氷室は淡々と話すが、内容はなかなかハードだ。母親失踪中とのことだが、氷室は特に深刻な様子はない。もう諦めているのかもしれない。
俺の悩みなど、まだまだ甘えていると言われても仕方ないレベルに感じる。しかし氷室は同情を求める素振りも見せず、あくまで客観的に「取引」の条件を提示してきた。
「特待生外されたら、バイトの許可も取り消されるし、学費も払えねえからさ。中退して働くつもりだったんだが……じいちゃんが、高校くらいは卒業しておけって泣くもんだから、困ってる」
「それで学年で成績トップの俺に勉強教わろうってか?」
「ああ。助けてくれ、篠宮。とりあえず次の期末までの間でいいからさ。今度の期末の結果が不味いと、流石に後がねえ」
代わりにこの部屋にあるものは好きな時に使っていいし、俺にできる範囲の協力なら何でもする──と氷室は素直に頭を下げた。見てくれが不良な上に一匹狼気質とはいえ、根は存外真面目らしい。
最初の警戒心が嘘のように、俺は急速に氷室に対する認識を改めていた。
俺は氷室が剥き始めたみかんを眺めながら、思案する。
コイツの抱える事情には同情の余地はあるし、適切な助言をしてやるなら、意固地にならずにサッサと公的機関に相談すべきだと思う。所詮俺たちは何の力もないただの学生なのだ。
氷室が助けを求める相手は俺ではなく、もっと適任がいるはずだ。氷室自身の今の希望を叶えてやった所で、根本的な解決にはなっていない。
でもまぁ、それは俺には関係ないことだし、本人にとっては余計な世話になるのかもしれない。
とりあえず、氷室からの依頼内容は単純だ。成績を上げるための手助けをすればいい。面倒なことに巻き込まれてしまった感はあるが、代わりに俺の秘密は守ってくれるし、この場所を拠点として自由に使えるという特典までついてくるというなら、悪い取引ではない。
……こいつの性格なら言いふらすこともないだろうし、それなりに信用できる気がする。現時点では。
「分かった。取引に応じる。ただし条件がある」
「なんだよ?」
「学園では俺たちが関わることは一切ないと協定を結ぼう。今回の取引の件も含めて」
「いいけど……理由は?」
「俺は学園では優等生で王子様キャラだからだ。お前みたいなのと仲良くしてたら、イメージダウンに繋がる」
「了解。じゃあ休日限定の秘密の関係ってことで」
「そういうこと、だ」
……いや、ちょっと待て。なんか違和感。『秘密の関係』って言葉に、背徳的な響きが含まれてないか? 別にこいつとそういう仲になるつもりはないが、勘違いされても困る。
「その言い方はやめろ。紛らわしい」
「じゃあ何て言えばいいんだよ。秘密裏に勉強するだけなんだから事実だろ?」
「いや、そうだけど……とにかく、誤解されるような表現はやめろ。あと、俺がここに出入りすることは誰にも言うな」
「言われなくても言わねえよ。お前だってバレたくねえんだろうが」
氷室は鼻で笑いながら、俺の皿に剥いたミカンを分けた。俺は当たり前のようにそれを受け取って口に入れた。甘酸っぱい果汁が口いっぱいに広がる。うまい……。もうひと口、と手を伸ばした所で、俺は我に返った。マズい。あまりに自然にこの環境に馴染んでしまっていた。
「……こたつにミカンが危険なコンボを形成している……」
「お前、警戒心強いんだか弱いんだかわかんねえな」
「うるさい。たまたまだ。偶然だ」
俺は無理矢理ミカンを飲み込むと、咳払いした。気を取り直して氷室に向き直る。
「やるからには俺は妥協はしないぞ。まずは成績低下の原因探りからだな。中間テストの答案を全部出せ」
「……おー」
氷室は苦笑しながら、俺の言葉に頷いた。
こうして、学園の優等生と問題児による休日限定の秘密特訓が始まった。
本来ならプライベートタイムに他人との交流など御免被りたいはずなのに、氷室と一緒に過ごす空間は妙に居心地が良かった。
学園や家とは違い、仮面を被る必要はないし、氷室も何かを期待する目で俺を見てくるわけでもない。ただそこにいて、勝手に好きな事をしているだけだ。それが新鮮で、思っていたよりも息がしやすい。
この部屋にあるゲームや漫画も、別に俺のために買い揃えたものではなく、元々氷室が個人的に所有していたものらしい。コイツも普通の男子高校生なんだな、と思ったら妙に親近感が湧いた。
意外と悪くないかも、と俺は心の奥底で思った。