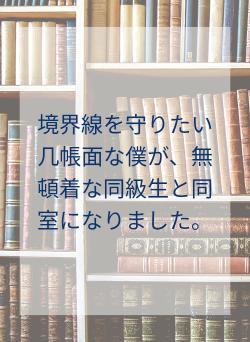日曜日、午前10時。
「珍しいわね、今日も出かけるの?」
朝、家を出ようと玄関で靴を履いていると、ダイニングの扉からひょいっと顔を覗かせた母が声をかけてきた。眉間には今日も皺が刻まれているが、声色にはほんの少し驚きが混じっている。
普段、俺が休日に外出することはほとんどない。プライベートで交流がある友人もおらず、家で勉強したり読書したりとインドアな生活を送ることが多いからだろう。連日外出する俺が珍しいらしい。
「友だちと一緒に勉強する約束してるんだ。夕方には帰るよ」
ちなみにこの言い訳は嘘ではない。少なくとも、目的は勉強にある。……はずだ。まあ、その実態はちょっと特殊だけど。
「そう。遅くなるようなら連絡しなさいね」
母の表情は特に変わらなかった。俺の外出理由を特に追究せず、興味もなさそうだ。もちろん俺の行動を監視するつもりもないのだろう。一応、学園の王子様を演じる俺の外面的な評価は高いので、親としての面目は保てているということか。
「うん。行ってきます」
心の中で溜息をつきながら家を出る。扉が閉まる音と共に、再び自由になったような解放感を味わう。
学園でも家でも仮面を被り続けている生活に、俺のストレスはジワジワと限界を迎えていた。あのネットカフェが使えないのならば、別の憩いの場所を見つけなければならない。そうでなければ精神が壊れてしまいそうだ。
とりあえず、今日は『取引』相手が指定した駅前へまず向かう。その相手というのが例の氷室だ。まさか学園の不良と二人で会うことになるとは夢にも思わなかった。
(……なんで貴重な休日まで、あんなヤツと過ごさなきゃいけねえんだ……)
俺は苛々しながら改札を通る。学園では爽やかに振る舞っているが、俺の本性は大雑把で横柄、そして怠惰で人見知りだ。基本的に他人との接触は最小限にしたいタイプだ。ましてやあの氷室とかいう無愛想な男と一日過ごすなど、考えるだけで胃が痛くなる。
約束の場所に着くと、すでに氷室が先に来ていた。昨日と同じ無表情で、壁にもたれている。相変わらず周囲の人間を寄せ付けない鋭い目つきだ。服装はラフなジャケットにTシャツ、ボトムスはジーンズというシンプルなものだが、それでもスタイルの良さが際立っていた。不良ぶっていてもどこか洗練されている。腹立つ。
「……お。今日は王子様モードか」
氷室は俺を見て片眉を上げた。俺はいつもの学園で演じる優等生風のシャツにカーディガンという爽やかスタイルだ。髪もきちんとセットしている。万が一、知り合いに遭遇しても言い訳が効くようにと選んだ正装である。まあ、実際は内心イライラを抑えられない状態だが。それでも表面的には笑顔で丁寧に会釈する。
「待たせたみたいだね。すまない。この先は、君に案内をお願いしてもいいのかな?」
「ああ。構わないぞ。あと、そのキモい口調やめろ。鳥肌が立つ」
「はあああぁぁ!? おま、お前! 人がせっかく外面を取り繕ってやってるっていうのに……!」
「俺にバレた時点で擬態の意味ねえだろ」
氷室は面倒くさそうに目を細めながら言った。……確かに。昨日の昼間のネカフェ遭遇事件以来、コイツには俺の素の人格がバレてしまっている。つまり、今更優等生の外面を保つ必要はない。
俺は周囲を見渡し、他に人がいないことを確認してから、盛大な舌打ちをした。
「……クソが。わーったよ。しゃーねーな! 案内しろよ、テメェが言う『秘密基地』とやらをよお!」
俺がガラの悪い口調で凄むと、氷室は口元を僅かに緩ませた。どうやら今の態度の方が氷室には受けが良いらしい。逆に俺が馬鹿正直に外面を繕っていたら「気持ち悪い」と切り捨てられそうな雰囲気だ。
「よし。じゃあ行くぞ」
氷室はスマホを懐にしまい、スタスタと先に歩き出す。俺もその後ろを黙ってついて行く。街中を歩く二人の図は、学園にいる人間がもし見かけたら奇妙に見えるだろう。学園の王子様と不良の組み合わせ。
まあ、学園から離れた場所だし、誰かに見つかる可能性は低そうだから、どうでもいいか。
付近は寂れた商店街と古いアパートが並ぶ住宅街だ。人通りは少なく、休日の午前中にしては閑散としている。しばらく歩くと、古びた看板がかかった小さな建物が見えてきた。入り口には『氷室写真館』という金属製のプレートが打ち込まれている。
「ここが、『秘密基地』?」
氷室は「……まあな」と短く答え、躊躇いなく建物の中へ入って行く。俺も後に続く。
入口をくぐると、独特の古い木の匂いが鼻をついた。薄暗い店内には、アンティーク調のカメラや大量のフィルムケース、古びたアルバムなどが所狭しと並んでいた。
ただし、どれもが埃を被っており、長期間放置されていた形跡が窺える。壁には黄ばんだ家族写真や肖像画が飾られているが、ほとんどは額縁も傷んでいる。
「俺のじいちゃんが昔やってた写真館なんだ。今は施設にいるから、放ったらかしになってる。目的地は二階。……こっちだ」
氷室は階段を示し、さっさと登って行く。俺も後を追う。木製の階段を踏みしめると、ギシギシと不安定な音が鳴った。大丈夫なのか、これ。
「二階には何があるんだ?」
「俺の家みたいなもんだ」
「家?」
「じいちゃんが施設に入ってしまったから、管理役みたいなもん。俺はここに住んでる」
「へえ。ひょっとして、一人暮らしか」
「……そうなるな」
氷室は淡々と答えながら、二階の一室へ俺を招き入れた。室内は思ったより広々としており、畳敷きだ。奥の方には簡易ベッドとパソコンデスクがあり、小さな冷蔵庫もある。壁一面には写真を飾るための大きな棚がしつらえてあり、数枚の写真が立て掛けられている。
全体的にシンプルだが、どこか雑然としている。衣類が畳まれずに積まれたり、本棚から飛び出したマンガ本が床に散らばっていたりと、生活感がある。
「おい、氷室。なんかけしからんものが置いてあるぞ」
畳敷きの部屋の中央には昔懐かしいこたつが鎮座していた。……妙に居心地の良さそうな雰囲気と存在感を放っている。
いや、俺は騙されない。絶対にあんなものに誘惑されてはいけないのだ。俺は学園の王子様であり、完璧な優等生なのだから。
「あ? なんだよ」
氷室は部屋の隅にある冷凍庫から炭酸飲料のペットボトルを取り出し、俺に投げてよこした。それをキャッチしながら、俺は部屋の中央に置いてあるこたつを指差す。
「氷室、これは罠だ! この部屋にこたつがあるということは、つまり人を堕落させるための……」
「罠じゃねえ。何、理由のわかんねえこと言ってんだ。じいちゃんが使ってた、ただのこたつだ。寒い時に入れ。夏はしまってあるけど」
氷室は呆れたような目で俺を見る。
クソ。なんだその目は。まるで俺が可哀想な奴みたいじゃないか。ああ、そうさ。俺は可哀想な奴なんだよ! ネットカフェでダラダラするのが唯一の楽しみという、社会不適合者なんだから!
「まあ、そこ座れよ。楽にしていいぞ」
氷室がそう言いながら、こたつを指差す。俺は内心で葛藤しながらも、結局はその誘惑に負けて腰を下ろした。こたつ布団が予想以上に暖かく、全身の力が抜けてしまう。
「くっ……この……! 何なんだこれは……!」
「さっきから何ブツブツ言ってんだよ。ほら、炭酸飲料好きなんだろ?遠慮せず飲めよ」
氷室は俺の手からペットボトルを奪い、栓を開けて手渡してくる。プシュッという小気味よい音に思わず反応しそうになるが、必死で堪える。落ち着け、俺。学園の王子様たるもの、こんな俗世の誘惑に負けてはいけないのだ。
そんな俺の目の前に氷室が漫画本の束をどさりと置いた。俺が昨日読もうとネカフェのブースに持ち込んでいたバトル漫画だ。なんと最新刊まで揃っていやがる。思わず「うおっ」と声が出そうになった。こいつ、まさか……!
「お前が昨日やってたゲームソフトもあるぞ。Wi-Fi繋げるから、オンライン対戦も好きなだけできる」
「え、マジで?」
思わず目を輝かせてしまった。いや待て待て! 冷静になれ! これは罠だ! 氷室の策謀だ! こいつは俺を籠絡しようとしているに違いない!俺は咳払いをして自分を戒めた。だとしても、目の前に並べられた娯楽の誘惑は強烈だった。ああ……俺の心の闇を抉るこのチョイス。
しかしコイツ、よく見てんな。ネカフェで俺のブースを覗いたあの僅かな時間に俺の趣味嗜好を把握して、俺の弱点を突いてきやがった。なんて野郎だ。
「とりあえず、取引の詳しい話をしてもいいか?」
「……わ、わかった」
俺は頷きながら、氷室が開けてくれた炭酸飲料を口に含んだ。甘い炭酸が染み渡り、疲れた脳をリセットしてくれるような感覚だ。……ああ、やっぱり最高だな、この刺激。
既に半分くらい氷室のペースに乗せられている感があるが、俺はそれに気がつかないふりをした。