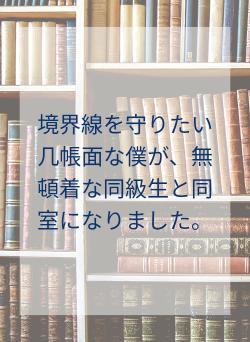結局、全く癒されないまま一日が終わり、憂々とした気持ちを抱えたまま帰宅すれば、玄関に綺麗に揃えられた革靴が目に入る。見慣れた兄の靴だ。
(げ……玲央が帰ってきてるのかよ……)
無意識に背筋を伸ばしてしまう。兄の玲央の前では、学園で演じる王子様スタイルほどではないにせよ、最低限の「自立した出来のいい弟」像を保たなければならないのだ。
帰宅の挨拶を省略して自室に直行し、急いで着替えはじめる。休日のダルダルラフコーデのまま玲央の前に出るのは避けたい。
「理久?帰ってきたのか?」
着替えの途中でノックもなしにドアが開き、兄の玲央が俺の部屋に顔を出してきて、危うく舌打ちしそうになった。
相変わらず、この家では俺のプライベートエリアは存在しないらしい。
玲央は俺より三歳年上の大学生二年生。身長は氷室と同じくらいだろうか。しかし奴とは対照的に、どこか柔らかい雰囲気と華やかさを纏っている。洗練された端正な顔立ちと穏やかな物腰の持ち主だ。
俺は一応学園では学年主席・生徒会長という肩書きを持つが、玲央の経歴の前では霞むばかりだ。中学高校時代は全国模試トップ常連。大学は国内最高学府にストレート合格。現在は海外留学も視野に入れているという状況だ。
しかも性格は温厚篤実で、誰にでも優しく社交性も抜群、周囲からの人望も厚い。まさに完璧超人を絵に描いたような男──それが俺の兄『篠宮玲央』だ。
俺のような作り物の偽物とは違い、玲央は本物の天才であり、天性の人たらしなのだ。コイツは俺がどれだけ努力しても到達できない領域に住む生き物。
「おかえり玲央。帰ってきてたんだ。……ごめん、外から帰宅したばかりで、ちょうど今シャワー浴びようと思ってたところなんだ」
俺は鏡で練習した爽やかな笑顔を貼り付け、シャツのボタンを留めながら着替えている事情を誤魔化した。勿論、今日のネットカフェでの出来事などおくびにも出さない。
「ああ。定期的に実家に帰って、母さんと理久の様子をみてこいって、父さんがうるさいからな。……シャワー浴びるなら、手伝おうか?」
玲央は穏やかに微笑みながら、サラッとそんな提案をしてきた。
高校生の弟のシャワーを手伝うとは意味不明である。相変わらずだな、このブラコン兄貴は。
この男の唯一の欠点と言えば、過保護なまでに俺を溺愛していることだろう。隙を見せれば秒でベタベタ触ってくるし、独占欲も人一倍強い気がする。
玲央と俺は血がつながっていない。俺が小学生の頃、俺の母親と玲央の父親が再婚したことによって兄弟となった義理の関係だ。
幼い頃は、兄となった玲央が遊んでくれる事が純粋に嬉しくて、ずっとべったりだった時期もあるが、次第に俺は優秀な玲央に劣等感を覚えるようになり、徐々に距離を置くようになった。
「……いや、やっぱりシャワーは後にするよ。折角玲央が帰ってきているんだし。コーヒーでも淹れようか?」
「なら、俺が淹れてやるよ。 今日はちょっといい豆を使ったコーヒーがあるんだ」
「え? いいよそんな。自分でやるよ」
「遠慮するな。絶対美味しく淹れてやるから。ほら、行くぞ」
自然な流れで肩を抱かれ、キッチンへ連れ出される。相変わらずスキンシップが多いが、なんとなく抵抗できず、俺はされるがままだ。玲央の距離感は昔からこうだ。ごく自然に人との間に境界線を作らずに入り込んでくる。俺には真似できない。
ダイニングテーブルの席に座るよう促され、キッチンに立つ玲央の姿を眺める。慣れた手つきでミルを使いコーヒー豆を挽く音が耳に心地好い。漂う芳香が鼻腔をくすぐる。
俺自身もコーヒーは好きだが、本当はインスタントで充分満足できる人間だ。この家にはインスタントコーヒーなんて存在しない。あるのは専門店から取り寄せた玲央好みの高品質な豆と、それに合わせた器具だけだ。
「たまには理久も俺のマンションに遊びに来いよ。いつ来てもいいし、泊まっていくのも歓迎だぞ。大学のことや将来のこととか、色々母さんには話しにくいことも相談に乗るぞ」
大学生の玲央は、現在家を出て一人暮らしをしている。都内の有名大学の近くの高級マンションだ。父が買い与えたものだが、そこに住み始めてからも時々こうして実家に帰ってきて、俺に優しく声を掛けてくるのだ。
単身赴任中の父に命令されて、とは言っているが、実際は俺のことを心配して自分の意志で戻ってきていることは、言葉の端々から伝わってくる。
俺は玲央の部屋を一度だけ訪れたことがある。掃除が行き届いた綺麗な部屋で、本棚には難解そうな学術書とファッション誌が混在していた。インテリアはシンプルでスタイリッシュで、俺なんかには到底辿り着けない洗練された大人の雰囲気があった。
完璧な兄の完璧な居住空間は、出来損ないの俺にとっては劣等感を刺激される場所だった。
「……玲央の恋人に迷惑になるから、遠慮しとくよ」
玲央には同棲しているわけではないものの、頻繁に行き来する恋人が最近できたらしいという話を母から聞いている。玲央に迷惑をかけないようにしろ、との忠告付きで。
「気にしなくていいのに。理久が嫌なら部屋に来るなって彼女に言っとくから」
玲央は笑いながら湯を沸かす。恋人より弟を優先させるような発言をする辺り、やはりどこか天然で鈍いところがあるのかもしれない。俺は内心で溜息をついた。この様子ではまた長続きしないだろう。玲央が恋人をすぐに入れ替えるのはいつものことだ。
「学校はどうだ? 生徒会の仕事は大変じゃないか?変な奴に脅されたりしてないか?」
「うん、大丈夫だよ。生徒会の仲間には恵まれてるし、皆で協力しながら上手くやれてる。変な奴に脅されたりとかも全くないよ。心配しないで」
実際は、生徒会の仕事は死ぬ程忙しくてストレスが溜まりまくっているし、今日はクラスメイトの氷室に脅迫紛いの取引を持ちかけられたばかりなのだが、玲央に言えばどんな騒ぎになるか分からない。下手をすれば、学校に乗り込んで関係者をぶん殴りかねない勢いだ。
「そうか? 良かった。……理久が充実した学園生活送れてるようで安心した。でも何かあったらいつでも俺に言うんだぞ。何でもしてやるから」
何でもって、相変わらずスケールがでかい。しかも本気で言っているのが分かるから恐ろしい。これが兄としての愛情なのか、それともただの過保護なのか。もしくは別の何かなのかは未だにはかりかねている。
やがて芳醇な香りが立ち込め、玲央はカップに淹れたコーヒーを差し出した。
「熱いから気をつけろよ」
「……ありがとう」
カップを受け取ると、掌からじんわりと温もりが広がる。一口啜る。やはり舌の肥えていない俺には違いはよくわからない。
「美味しいか?」
「うん。すごく美味しいよ」
本音を押し殺して微笑む。本当は砂糖とミルクを大量にぶち込みたい衝動に駆られている。甘党の俺にはこの苦味が少しきつい。だが玲央の手前、そんなことは言えない。
「良かった。理久が喜んでくれるのが一番嬉しいよ」
玲央はほっとしたように笑うと、俺の頭をポンポンと撫でた。もう高校生なのに、完全に子供扱いである。玲央はそのまま掌を滑らせて俺の頬に添えると、じっと顔を覗き込んできた。
「何? 玲央……」
「いや、なんだかお疲れ気味の顔してるからさ。お前、少し痩せたか?」
至近距離で見つめられると、何もかも見透かされているような錯覚に陥る。学園での完璧な演技も家での不器用な仮面もすべて剥がされて、本物の篠宮理久の孤独な魂を晒されるのではないかと恐ろしくなる。
「……大丈夫だって。ちゃんと食べてるから。今日も友だちとご飯食べてきただけだし」
まあ、友だちではなく不良に脅されながら、ネットカフェでジャンクフードを摂取してきたわけだが。
その時、リビングのドアが静かに開いた。
「あら。玲央さん。帰ってきてたのね」
現れたのは、眉を顰めた母・千尋だ。俺は慌てて頬に添えられていた玲央の手を振りほどいた。
母は四十代後半という年齢を感じさせないほど美しい女性だが、その整った顔立ちには常に緊張感が貼り付いている。華奢な身体にブランドもののスーツを纏い、常に完璧にセットされた髪には白髪など一本もない。絵に描いたようなキャリアウーマンである。
「母さん、お邪魔してます。久しぶりですね。父さんも会いたがってましたよ」
「そう。貴方も元気そうで安心したわ」
玲央は母に対して敬語で話す。元々は他人だったのだから当然といえば当然なのだが、この二人の間にはどこか奇妙な距離感がある。玲央と俺を一瞥すると、母は淡々とした口調で続けた。
「理久、ちゃんと勉強は進んでる?」
「うん。問題ないよ」
即答すると母は満足げに頷いた。学園での成績や生徒会活動については報告済みだ。完璧にこなしている限り母からの干渉は少ない。それは逆に言えば、少しでも隙を見せれば容赦なく非難されるということでもある。
「ならいいわ。この先が大事な時期だからね。貴方は危機感が足りない所があるから、気を抜かないように」
母はそれだけ告げると、ソファに浅く腰掛けた。昔から母は厳しい人だったが、再婚してからは更に拍車がかかっているように感じる。
再婚後、俺と母の生活は大きく変化した。
我が家はもともと一般家庭だった。だが玲央の父は大企業の重役という肩書きを持ち、経済的にも裕福な環境にいた。賃貸アパートから高級住宅街の一軒家に移り住み、生活水準は格段に向上した。しかし同時に、以前より遥かに母は張り詰めた表情をするようになった。
俺がお小遣いやお年玉でコツコツと買い揃えていた漫画やゲームを、中学受験の妨げになるからと没収され、塾や家庭教師との毎日が始まったのはこの頃からだ。成績を落とせば容赦なく叱責されたが、兄である玲央のように常にトップの成績であれば、母は何も言わなかった。それでも決して褒めてはくれなかったが。
「母さんもコーヒー飲みますか?」
玲央が席を立ち、母に声をかける。母は黙って頷いた。玲央はすぐに母の分のコーヒーを淹れ始めた。優しいな、と思いつつも、俺は何故か居心地の悪さを感じていた。
「玲央さん、大学はどうなの?」
「特に変わりませんよ。大学も充実していますし」
「留学先は決まった?」
「まだ検討中です。いくつか候補先は絞ってるんですけど……」
「そう。玲央さんならどこでも上手くやれると思うわ」
「ありがとうございます」
二人の会話は淡々としているが、どこか距離を感じる。母と玲央の会話を他人事のように聞きながら、俺はコーヒーを啜った。口の中に広がる苦味がいつもより強く感じられる。
自分の家なのに、帰りたい、と感じるのはこんな時だ。自分の居場所はどこにもないような気がする。
この家にはインスタントコーヒーなんて存在しない。
ネットカフェで飲んだぬるい炭酸飲料の、刺激の中に感じた甘さが、何故か恋しく感じた。