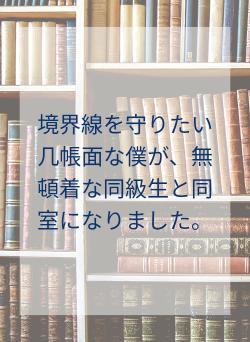「篠宮くん、凄いね」
「今回は文句なしの1位だよ。おめでとう!」
「流石、完璧王子の称号は伊達じゃないな」
廊下の掲示板の前で、クラスメイトたちが歓喜の声を上げている。三学期の中間テストにおいて、俺は無事にトップに返り咲きを果たしたのだ。しかも総合点だけでなく、各科目も満遍なく高得点をマークしており、万全の態勢で仕上げてきた結果と言えるだろう。
母に啖呵を切った以上、絶対に1位を獲る以外に選択肢はなかったのと、氷室に負けて悔しかったのもあり、俺は密かに必死になって勉強した。正直ほっとしたというのが本音だ。
「篠宮会長、おめでとうございます。やはり会長は完璧ですね」
背後から桐谷の声が飛んできて、反射的に身構える。いつもながら全く気配が読めない。周囲の生徒たちも突然出現した彼に騒然としている。
「ありがとう、桐谷くん。君も2位で素晴らしいね。今回の試験は皆全体的に高得点だったので、学年全体の底上げが成功して嬉しいよ」
「恐縮です」
いつもの王子様スマイルを貼り付けて応じると、桐谷は眼鏡のブリッジをクイッと押し上げながら、澄ました表情で返してきた。成績に関しては、実際満更でもない感情を持ち合わせているようだ。
「あの、氷室くん。今回は惜しかったね……」
甘ったるい女子生徒の声が耳に届き、意識が逸れる。俺は声がした方に顔を向けた。廊下の端で、派手目な女子グループ数人が氷室を囲んでいるのが視界に入った。真ん中には、俺にせっせと手作り菓子を貢いでいた佐伯由美の姿が見える。どうやら彼女が氷室に話しかけているらしい。
ちなみに氷室は、今回8位だった。前回の首位からは陥落したが、その前は50番代だったので、まだ成績を保っていると言えるだろう。
今回俺は自分の勉強に集中していたので、氷室のことは構ってやれなかった。別にライバルを蹴落とそうと企んだのではなく、母との停戦条約があったので、成績が首位に返り咲くまではケジメをつけておこうと、氷室の自宅に入り浸るのを控えていたのだ。
しかし、氷室め。まさか、その間に一軍女子たちと交流を深めていたのだろうか?
佐伯さんは、潤んだ上目遣いになりながら、氷室に言い募っている。自分が一番可愛く見える角度を熟知しているアピールポーズだ。あざとすぎる。
「あの、……試験で疲れてるんじゃないかなと思って、マフィン焼いてきたの。……良かったら受け取って」
(おいコラ! 佐伯!! 貴様、俺から氷室に乗り換えやがったのか!? 早すぎじゃねえか?!)
俺は内心盛大に罵倒しまくったが、表向きは完璧な笑顔を保ったままその様子を眺め続けていた。俺に対して「好き好き光線」をこれでもかと放っていた癖に、今更氷室狙いに転向するとは何事か。
彼女の周囲の取り巻き女子たちが「ユミちゃんファイト!」等と小声でエールを送っているのが丸聞こえだ。
「……ああ、ありがとう。けど、悪い。受け取れねぇ」
氷室は彼女の甘い視線やモーションには一切靡かず、平坦な声音でさらりと躱した。これまでのように冷たく露骨に拒否するという対応ではなく、ごく自然体で丁重に断る大人の対応であった。
氷室が彼女から手造り菓子を受け取らなかったのを確認して、何となく胸を撫で下ろす。
「ど、どうして? 私、割とお菓子作り上手いのよ? 美味しいって評判なの」
「……いや、そうじゃなくて。ごめん、俺、付き合ってる奴いるから。受け取る訳にはいかない」
「え!?」
佐伯さんの驚愕の叫び声と共に、俺も心の中で叫んだ。
(は? お前恋人いたのか!? 初耳だぞ!?)
「そ、そうなんだ……。ちなみに、その彼女さんは私より可愛いのかな?」
ここで負けてたまるか!とばかりに、佐伯さんはコテンと首を傾げながら最大限に庇護欲を煽る大技を披露してくる。周囲の男子生徒が野太い悲鳴をあげる程の破壊力を持つ攻撃だが、残念ながら氷室には通用しないようだ。
「めちゃくちゃ可愛いよ」
氷室は即答すると、何故か群集の中に紛れ込んでいる俺の方に視線を向けてきた。俺は瞠目してしまう。視線が絡まると、彼は目を細めて僅かに口角を上げた。……ん? アレ?
「強がりで格好つけてて外面を飾ってるけど、実は負けず嫌いで努力家で。それでいて脆くて危ういから放っておけない。何より、俺の前でだけ曝け出してくれる本心が可愛いくてたまらないし。あー、あと勉強教えてくれるから、助かるな」
「え?」
氷室の惚気とも取れる発言に、佐伯さんは完全に面食らった様子だ。周囲のギャラリーもザワつき始める。俺はといえば、思考が完全に停止した。そして次の瞬間、耳や首筋が燃えるように熱くなり、心拍数が急上昇してしまう。顔が熱くて堪らない。
(あいつの語ってる恋人って、もしかしなくても……)
「篠宮会長。御顔が茹でダコのように紅潮していますが、ご体調が優れないのでは?」
「へ!? あ、いや、き、気のせいだよ。桐谷くん」
桐谷から冷静沈着な指摘が入り、俺は咄嗟に誤魔化した。自分でもはっきり土分かるくらい声が裏返っている。額から脂汗が流れ落ち、鼓動がうるさいくらいに高鳴っている。
マズい。これ以上氷室を野放しにしては何を暴露されるか分からない。俺は即座に行動を起こすことにした。
俺は平静を装いながら大股で氷室の元へ歩み寄り、佐伯さんの前に身体を滑り込ませた。彼女は驚いた顔をしているが、そんなものは知ったことではない。
爽やかな笑顔を氷室に向けて、努めて落ち着いた口調で呼びかける。
「氷室くん、少し騒ぎになっているようだから、もうその辺にしておいたらどうかな? 佐伯さんも困っているようだし。あまり人前でプライベートなことを話題にするのは、相手の人にも良くないと思うよ」
「……ああ、そりゃ悪かったな、篠宮」
氷室は俺を真っ直ぐ見据えたまま、俺に対して謝罪の言葉を述べた。
(いやだからそこで俺に目を合わせてくるんじゃねえよ! 不自然だろうが!!)
心の中で激しくツッコミを入れるが、氷室は飄々とした態度を崩さない。
「じゃあ、もうすぐ授業も始まるし教室に戻ろうか? ほら、佐伯さんも行こう?」
「あ、はい……」
俺は笑顔を崩さぬまま、その場を強制解散させるべく周囲へ声をかけ、この場から離れるよう促した。佐伯さんも俺の勢いに圧倒されたのか、大人しく従ってくれた。
俺も教室へ移動しようと足を踏み出した瞬間、手首を掴まれる。振り返ると、悪戯っぽい笑みを浮かべた氷室が立っていた。氷室はゆっくりと顔を近付けてきて、俺の耳元で囁く。
「さっきの顔、最高に可愛いかった。今度写真撮らせてくれ」
「……っ!!」
内緒話のように告げられた言葉に、俺はまたしても顔面に熱が籠るのが分かった。氷室は手を離して俺の頭を軽く撫でると、颯爽と教室へ歩いて行った。
完全に掌の上で転がされている。悔しい筈なのに、鼓動の高鳴りが止まない。
俺はその場で棒立ちになりながら、彼の後ろ姿を見送った。
【終】