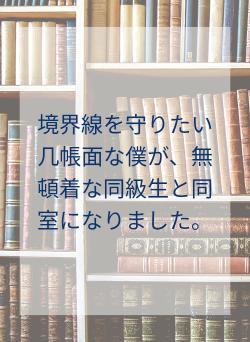コタツで寝ると告げたのだが、「風邪を引くからダメだ」と却下され、ベッドに引きずり込まれた。
1人用のシングルサイズのベッドに、2人で横になると狭くて、必然的に身体が密着してしまう状況だ。ベッドの端に逃げようとしたが、氷室に腰をつかまれてしまい阻止される。俺は完全に硬直していた。
「そんなに怖がるなよ。心配しなくても、少ししか触らねえし」
「……少し!?」
「これでも我慢してるんだけど」
俺の抗議を受け流しつつ、氷室は俺の身体にしがみつくように密着して四肢を絡め、俺の肩に額を押し付けてきた。柔らかな髪が肌を擽り、こそばゆい。
何と言うか、大型犬に抱きつかれているような感覚だ。
「……暖かい」
「……うん」
「こうやって誰かと一緒に寝るの、はじめてだ」
氷室の独り言のような呟きが聞こえてきて、彼の抱えている孤独な過去の一端が垣間見えた気がした。
どんな言葉を紡げばいいのか分からず、、俺は腰に回されていた氷室の手をとり、彼の指に自分の指を絡ませた。
繋いでみると、氷室の手の大きさがよくわかる。骨張っていてゴツゴツしており、俺よりひと回りほど大きい。掌の温もりがじんわりと伝わってきて、胸の奥が甘く疼く。
「理久」
「ん?」
名前を呼ばれて顔を向ければ、再び唇が塞がれた。触れるだけの優しいキスだ。
何度目か数えることも忘れるくらい、その行為を繰り返す。角度を変えながら互いを求め合うような甘美な時間が続く。
氷室の舌先が唇を舐めてきて、僅かに隙間ができた途端、ぬるりと侵入してきた。咄嗟に身を竦めると、宥めるように髪を撫でられる。口腔内を探る動きに翻弄され、呼吸さえ忘れそうになる。酸欠状態になりながらも必死に縋り付く。
「……ん、……ふぁ」
初めて知る粘膜同士の交わりは、想像を遥かに超えて、甘くて官能的な刺激に満ちていた。柔らかく濡れたその感覚に酔いしれる。キスだけでどうしようもなく気持ちが昂り、涙が滲む。
唇が離れたときには、お互い荒い息遣いになっていた。こんな感情を知ってしまって、俺たちはどうなってしまうのだろう。
「ヤバい。俺、お前に夢中になる自信しかない」
「何だよ、それ」
結局朝まで、ずっとベッドの中で2人で抱き合ったまま過ごしていた。
といっても、ただひたすらハグしたり、キスしたりしていただけだ。お互いの体温を共有して、心音に耳を傾けて、時折笑いながら他愛もない会話を楽しみ、寄り添いあって微睡むだけ。
それでも、日常から大きく乖離した非現実的な空間とその時間は、とても幸福に満ちていた。
***
翌朝、目を覚ますと既に氷室の姿はベッドにはなかった。昨夜のあれは夢だったのかも、と思うほど室内は静かだった。
「おはよう。起きたか? 朝飯食うか?」
キッチンの方から声がかかる。顔を向ければ、氷室がコーヒーを淹れてくれていた。彼は既に着替えている。
朝陽の眩しさに目を細めながら、ぼんやりと室内を見渡すと、棚に飾られた一枚の写真が目に入った。
昨日、俺が無断で閲覧してしまったデジタルファイルの画像と同じ、麦わら帽子と花柄ワンピースの美女が写っているものだ。どこかで見たことがあると感じたのは、この部屋にあるフォトスタンドだったようだ。
もしかして、氷室の恋人とかだったのだろうか?モデルや女優と言われても違和感のない美しさだ。
「どうした?」
「あ、いや」
俺が写真に見惚れていると、氷室が近づいてきた。咄嗟に目を逸らすが、勘の鋭い男だ。きっと俺が写真を気にしていることに気がついている。
「気になる?」
「……少し」
「俺の母親だよ」
「は!?」
あっさりと告げられた内容に、俺は目を見開いた。確かに雰囲気が似ていると言えば似ているのだろうが、美女すぎるだろう。それに、母親にしては若すぎないか?
「アレしか写真がないんだ。たまにしか帰ってこないから、顔を忘れないために飾ってる」
「……」
そうか。やっぱり帰ってきていないのか。
氷室の場合は、そもそも反抗したり、喧嘩ができる家族が側にいないのだと、あらためて思い知らされる。
母親の顔を忘れるくらい会えない状況というのは、どんな心境なんだろう。
氷室は淡々と告げるだけで、母親に対する執着が全く感じられない。割り切ってしまっているように見える。この部屋で、一人で、それが当たり前のように毎日生活している彼を感じて、少し複雑な心境になる。
「昨日お前が着ていた服、乾燥かけたから、そこに畳んである。……悪い、今日バイトなんだ。しかも朝からシフト入れててさ。理久が泊まるって分かってたら休みにしてたのに」
氷室は申し訳なさそうに謝罪した。特に約束していたわけではないし、俺の方が土壇場で押し掛けた形だから、気にしなくていいのに。俺が家出するという異常事態に、文句も言わず、しかも一夜を共に過ごしてくれたのだ。
ここまでしてくれたことに感謝しきれないくらいだ。
「別にいいよ。十分、助かったし」
そう告げながらも、俺は少し寂しく感じていた。もう少し一緒に居たかったと本音が過る。
氷室は苦笑しながら俺の髪を撫でると顔を寄せてきて、触れるだけのキスを落としてきた。
「そんな顔するなよ、俺だって寂しいんだから」
「……どんな顔だよ」
唇を尖らせていると、氷室はもう一度軽く口づけをしてきた。以心伝心というべきか。俺の複雑な心境は、氷室にはお見通しらしい。
「俺もう行くけど、朝飯適当に食べててくれ。ちゃんと家に帰れよ。帰るとき、鍵かけといてくれ」
「……ん、分かった」
俺に家の鍵を渡すと、支度を終えた氷室は荷物を肩に担ぎながら玄関に向かっていく。先程までの胸やけがしそうな甘い空気は何処へ去っていったのか、氷室はすぐに切り替えてしまったようだ。
心細くなった俺はベッドから抜け出して、彼の背中を追いかけた。
「なあ、鍵はポストに入れておけばいいか?」
扉を開けようとしていた氷室に背後から尋ねると、彼は振り向いてくれた。
「それ合鍵だから、理久にやるよ」
「……え?」
「いつでもここに来ていいから。じゃあな」
「ちょ、ま、て!」
俺は立ち去ろうとしている氷室の袖口を慌てて掴んだ。予想外の展開だ。いきなり合鍵を渡されるなんて思っていなかった。
しかし、氷室は涼しい顔をしている。
「何だ?」
「……あ、えと。い、行ってらっしゃい」
心の中では飛び上がる程嬉しいのに、気の利いた台詞なんて思い浮かばなかった。シンプルなお決まりの別れの挨拶が精一杯だ。
氷室は一瞬だけ虚を突かれた表情をした後、柔らかく微笑んだ。そのまま軽く俺を抱きしめると、もう一度唇にキスを落としてきた。
「行ってきます」
***
「ただいま」
「……理久!」
俺が実家に戻ると、母がリビングから血相を変えて走り出てきた。目の下に薄っすらと隈があるし、髪も乱れて服装もヨレヨレである。彼女のこんな姿は初めて見た。どうやら相当心配をかけたらしい。
「母さん、心配かけてごめん。それと昨日は怒鳴ったりしてごめんなさい」
素直に頭を下げると、母は言葉を詰まらせた。彼女が躊躇いがちに口を開こうとした瞬間、俺は畳み掛けるように話を続けた。
「……だけど、俺の友だちを侮辱したことは許さないから。昨日の母さんの言葉は間違いなく本心だったよね?いくら訂正されても、もう聞かないし、俺の交友関係に口出ししないで欲しい」
それが、俺にとっての妥協点であった。俺の態度が軟化しないことに、母は明らかに動揺した。どうしたらいいのか戸惑っている様子がうかがえる。
「次の試験は挽回するよ。成績は落とさない。俺を信じて欲しい」
「……」
「母さん」
しばらく膠着状態が続いた後、ようやく母は重苦しく溜息を吐いた。俺が引かないことを察して諦めたのだろう。
「……分かったわ。理久の気持ちを尊重します。貴方の成績や生活態度が変わらない限りは、理久の交友関係には干渉しないと誓うわ」
「ありがとう」
「ただし、今後は絶対に黙って外泊しないで。連絡を絶つのだけはやめてちょうだい。お願いよ」
母は俯いたまま小さな声で懇願した。いつも凛として毅然とした態度で接してくるイメージのある彼女からは想像できない弱々しい姿だ。
胸の奥がチクリと痛み、同時に今まで知ろうともしなかった母親の本質の一端を垣間見ることができたようで、感慨深い部分もある。
「うん。約束する」
俺がはっきりと返事をすると、ようやく母の表情が少し和らいだ。
こうして、俺はなんとか停戦条約を締結させることに成功した。あとは、次のテストで成果を上げるのみだ。
自室に戻ると、緊張の糸が解れたからか、ドッと疲れが押し寄せてくる。久しぶりに氷室以外に本音でぶつかって消耗したのもあるし、ずっと気を張っていた反動かもしれない。母とは本質的に考え方が違うので、完全に分かり合えることはないと思う。
以前の俺なら、表面上穏便に収めることだけを考えて、母の望む理想的な息子のフリをして誤魔化していただろう。今回はどうしても譲れない部分があり、正面切って対立する形になった。
この行動が正解かどうかなんて分からないけれど、本音を曝け出したことで、俺はかなりスッキリしていた。
鞄の中から、氷室にもらった合鍵を取り出してみる。掌に乗せた小さな金属の塊が、何故かズシリと重い。俺にとっては宝物のように眩く輝いて見えてしまうのは、単なる惚れた腫れたの恋愛フィルターの影響だけではないだろう。
彼が、不器用な俺のために、居場所を共有してくれた事実が、純粋に嬉しかった。
こうして俺の唐突な家出騒動は幕を閉じた。