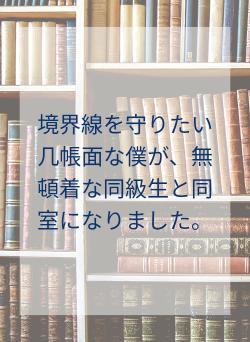「篠宮、お前なにしてんだ」
翌日。土曜日。午前11時。
『王子様』の仮面を脱ぎ捨てた俺は、自宅から六つ離れた駅前の寂れたネットカフェにいた。個室ブースの狭いスペースに埋もれ、ヘッドホンで耳を塞ぎ、モニターに映る画面を睨みつけている。
そこには血飛沫が舞うアクションゲームの世界が広がっていた。現実世界からは完全遮断。ここが俺の唯一無二の憩いの場所であり、聖域なのだ。
先程自分の名前を呼ばれた気がするが、きっと気のせいだろう。こんな場所で俺を知っている者がいるはずがない。そう自分に言い聞かせた瞬間、ヘッドホンを強引に外され、聞き覚えのある低い声が直接鼓膜を揺らした。
「篠宮理久だろ? 珍しいな、こんなとこで」
どうやら空耳ではなかったようだ。
直接会話したことは殆どないが、俺はその声の持ち主を知っていた。何しろ俺は生徒会長として学園に君臨し、全校生徒の顔と名前をほぼ完璧に記憶している超人優等生なのだ。
振り返らなくても分かる。この低い声、無駄に落ち着いた喋り方。
同じクラスの『氷室朔弥』だ。
高等部から編入してきた外部生で、誰ともつるまない学園の一匹狼。たまに授業中堂々と寝ていたり、サボったりしている不良生徒である。常に無表情で冷徹な雰囲気をまとい、人を見下すような目をした、教師ですら畏怖する存在だ。
外部生なので、奴の中学生時代は謎に包まれているのだが、噂によると某有名不良校をシメた男だとか、ヤクザと喧嘩して勝ったとか、街中で暴漢集団を一掃したとか、とにかく武勇伝が尽きない。
実は親をブチ殺して刑務所に入っていた過去があり、改名して桐水学園に潜り込んでいるとの都市伝説まで囁かれている。
しかし、身長百八十センチ以上、スタイル抜群の強面イケメンでもあるため、「キケンな雰囲気が堪らない!」と一部の女子には密かに人気があることを俺の情報網は掴んでいた。いけ好かない野郎である。
「人違いですけど」
俺はシレッとした顔で堂々と否定した。
汗が滝のように流れるのを感じながらも、表に出さないよう努める。こんな危険な奴に俺の素顔を知られる訳にはいかない。口止め料として法外な金銭を請求される可能性だってある。
大丈夫だ。今の俺の姿は学園での爽やか王子様とは完全な別物。
ヨレヨレのパーカーにダルダルのパンツ、髪も適当に寝癖を直しただけのラフスタイル。コンタクトではなく眼鏡だし、個室ブースのテーブルの上には、後で読もうと持ち込んだ流行りのバトル漫画と身体に悪い炭酸飲料が並んでいる。
完璧に冴えない陰キャオーラを醸し出しているはずだ。
休日にネットカフェでダラダラ過ごす『篠宮理久』という名の王子様なんて存在する訳ないのだと早く納得しろ! すぐに立ち去れ!
「いや、普通に篠宮じゃん。ちょっと……いや、かなり?学校にいるときと印象違うが……。あ、注文された山盛りポテトセットです。お待たせしました」
そう言って氷室は俺に薄いトレイをすっと差し出した。トレイには揚げたてアツアツのポテトが乗っている。待ってました! ……じゃなくて。
おい、なぜ氷室がそんなものを運んでくる? つか、そもそも知り合いに会わないように、隠れた憩いの場所として学園から離れた駅の寂れたネカフェを選んでいるのに、なぜ同じ学園のしかも同じクラスのお前がここにいる? どういう因果だ?
俺が山盛りポテトを手に怪訝な目で見上げれば、以心伝心したのか、氷室は涼しい顔で答えを述べた。
「ああ、俺、最近ここでバイトはじめたんだよ」
言われてみれば、確かに氷室は店員用のエプロンを身につけている。背が高く手足の長い体格に黒いエプロンは妙に似合っていた。……イラつくほどに。
今までこの店には何度か足を運んだが、コイツに遭遇しなかったのは運が良かったのか。つか、校則ではバイト禁止のはずだが? いやいや、それよりこの身バレ危機をどう切り抜けるかだ。
俺は受け取ったポテトを口に運んでモグモグしながら、脳内で必死に言い訳を考える。
ヤバい、このポテト、サクサクで超美味い。久し振りに食すジャンクフードに顔を綻ばせながら現実逃避していると、なぜかシャッター音が響いた。
「!?」
見れば、いつの間にかスマホを取り出した氷室がこちらにカメラを向けていた。証拠写真を撮られたらしい。最悪すぎる。何やってるんだコイツは!
「おい、消せ!!」
慌てて立ち上がり奴のスマホを奪おうとするが、ヒョイッと躱される。クソ、腹立つ。
どうする? 暴力沙汰はマズい。俺は一応表向き清廉潔白な善良生徒なんだから。いや、そもそも数々の逸話を持つ伝説級の不良である氷室に力で敵うとは思えない。しかし、証拠隠滅はしなければならない……!
「そう焦んなよ。学園の王子様の素顔が意外過ぎて、撮っちまっただけだ。普通に優雅に紅茶とか飲んでいそうな雰囲気あったのに、こんなジャンキーなもの頼むんだな」
「うっせえな! お洒落カフェでお上品に紅茶飲んでも腹は膨れねえだろ!」
俺の趣味は表向き「カフェ巡り」となっているが、それは情報収集のためのカモフラージュだ。実際は重度の炭酸中毒者&ジャンクフード信者なのである。こんな事実を知られたらイメージダウンに繋がる。俺の学園生活の死活問題である。
「しかも、意外と食う方なんだな? この山盛りポテトセット、一人で食べ切るつもりなのか?」
「余裕だっつの!」
俺は開き直った。もう誤魔化しようがないのであれば、逆ギレしてしまえ。つかよく考えたら、コイツも校則違反でバイトしてるんだから、お互い様じゃないか。弱みを握られる前にこっちも握っておけ!と、テーブルの端に置いてあった自分のスマホを取り出し、威嚇のためレンズを突き付ける。
「俺も撮ってやろうか? 校則違反な不良のバイト姿をよぉ!」
「……別にいいけど」
挑発的な笑みを浮かべたつもりが、逆にサラリと返されてしまった。……動じないどころか余裕しゃくしゃく。なんか悔しい。
「俺、一応学園にはバイト許可貰ってるから」
「へ? マジか」
「親がいなくてさ、家庭の事情で。成績クリアできている限りは、問題視されないことになってる。先生に聞いてもいいぜ」
「嘘だろ……」
まさかの合法バイトだった。完全に俺の負け。自爆である。しかもなんか重めの家庭事情まで出してきた。
俺は大人しくリクライニングチェアに座り直し、残っていた炭酸を一気に飲んだ。気が抜けて生温かった。
「篠宮はわりとここ来るのか?」
「……金かかるから、たまにしか来れないけどな。家だと息苦しいから」
「息苦しい?」
「……ほっとけ」
つい素で答えてしまった。コイツにプライベートを話すつもりなど毛頭なかったのに。
しかしこの状況は絶望的だ。氷室に証拠写真とともに面白可笑しく学園中に暴露されたら、俺の偽装王子様は即終了となるだろう。いっそコイツを始末して……いやいや、それはダメだ。
「ふーん、そうか。……なあ、いいこと思いついたぞ、篠宮」
氷室はスマホをヒラヒラさせながら、悪巧みするような、少しだけ子供っぽい笑みを口元に浮かべた。普段の冷たい無表情からは想像できない、初めて見るような人間臭い顔だった。見たことのない表情だ。コイツもこういう顔するんだな、と思ったのも束の間、
「俺と取引しないか? 」
「取引、だと?」
ゴクリと喉が鳴る。嫌な予感しかしなかった。だって、学園トップの優等生に対して、謎多き一匹狼が持ちかける秘密の取引なんて、絶対に碌なことにならない気がするからだ。
氷室は俺がいる一人用ブースに入り込み、俺が寛いでいたリクライニングチェアに無理やり座り込んできた。狭い。そして近い。何だこの距離感は。
奴は長い足を窮屈そうに曲げながら、壁際に追い詰められた俺を見下ろしてくる。その圧が凄まじい。
「俺は、篠宮の秘密──学園の王子様の本当の素顔、そして今この瞬間のダルダルラフコーデを撮影したデータを持ってる。これをバラされたくないなら」
「あ、悪魔かお前は!? わざわざ言うな!」
圧倒的に弱みを握られた状況に俺は青ざめた。この状況ではたして何を要求されるのか……! 金か? 俺の魂か? 学園に居られなくなるような要求じゃないといいが……。
「──お前に、俺の危機を救ってもらいたい」
「は? 危機?」
ポカンとする俺を横目に、氷室は少し間を置いてから、無表情のまま話し始めた。