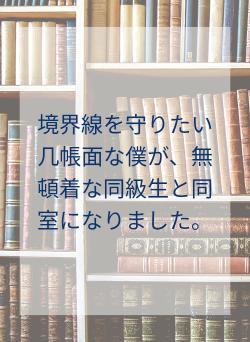「俺も風呂入ってくるから、適当に寛いでてくれ。先に寝ててもいいから、ベッド使えよ」
氷室からそう声をかけられたが、流石に勝手に人のベッドを使える神経は持ち合わせていない。俺は先ほどから気になっていたパソコンのディスプレイを指差した。
「コレってさ。ひょっとして……」
「見ての通り、学園祭の写真だよ」
画面に映し出されているのは、学園祭の際に氷室が撮影したであろう写真データだった。随分たくさんありそうだ。
「委員会で写真集発刊の依頼が来たから、編集してるところだ」
「……ちょっと見てもいいか?」
「いいけど。消すなよ」
そう言い残して、氷室は浴室に向かっていった。
俺は机の椅子に座り、早速学園祭の写真データを眺め始めた。氷室の視点から切り取られた学園祭の様子が、鮮明に映し出されている。
クラスごとの展示風景、体育館での催し、ステージ上でパフォーマンスする生徒たち。食べ物の屋台で楽しそうに談笑する人々の姿。
撮影技術に詳しくないので上手いか下手かまでは判別できないが、どれも臨場感に溢れていた。
当日だけでなく、準備中の姿も撮影していて、どの写真も被写体の活き活きとした表情を捉えており、見ているだけでこちらの頬が緩んでしまう。素直にいい写真だなと感じられるのだが。
(俺が写ってる写真、一枚もねえな……)
撮られていたことは把握していた。ただ、学園祭前日に会ったときに、氷室は俺の写真を全部消す、と言っていた。本当に実行しているのかもしれない。変なところで律義というか。
この部屋で撮られたときも、氷室には俺から消せと命令していたわけだし、その要望に応えてくれただけだ。それなのに。
(無くなったと思うと惜しくなるっていうか、寂しいというか……)
我ながら自分勝手だと思う。一番下までスクロールし終わると、溜息をつきながら画像フォルダを閉じた。すると、日付順に並べられたたくさんのフォルダの存在に気がついた。これまで彼が撮り溜めた写真を整理したものなのだろう。試しにいくつかクリックしてみて、画像を表示させてみる。
最初に出てきたのは、真っ白な砂浜と青い海をバックに、若い女性が幸せそうに笑顔を向けている写真だ。陽の光を浴びてキラキラ輝く麦わら帽子と、真夏らしい花柄のワンピースを身に纏っている。かなり美人だ。
ていうか、誰だ?
見知らぬ、けれどどこか見覚えのある女性の写真に心臓が早鐘を打ち出した。氷室とどういう関係なのだろうか。何故か、見てはいけないものを見てしまった罪悪感に囚われて、慌てて画像を閉じた。
その上の、最近の日付のフォルダの画像を見てみれば、見慣れた男の姿が飛び込んできた。
「……これ、俺?」
そこには、ネットカフェで幸せそうな笑顔のままポテトを頬張る俺の姿が映し出されていた。多分はじめて氷室に撮られた写真だ。最初はこの写真をネタに脅されたのだが、肝心の撮られた写真を見たことがなかった。
数ヶ月前のことなのに、随分と昔のことのように感じる。
「これも。え?これもかよ!?」
氷室が撮影した俺の写真が次々と出てくる。どうやら、このフォルダには俺の写真ばかりが集められているようだ。
この部屋で過ごした気の抜けた瞬間や、屈託のない笑顔を晒している俺の姿。中には、ゲームに熱中して叫んでいる情けない瞬間や、アイスを咥えながら漫画を読んでいる油断した姿もある。さらには、コタツに潜り込んだまま眠っている無防備な俺の寝顔まで記録されていた。
いつの間にこんなにたくさん撮られたのだろうか。
撮られていたのは気が付いていたのに、何だか急激に恥ずかしくなってきて、赤面してしまう。まるで自分の素顔のアルバムを見せつけられている気分だ。
(それにしても、こんなに気を抜いて、笑ってるんだな。……俺)
色々と自省しながらも、心がざわめき出す。自分を客観的に眺めてみて、改めて思う。どれだけ俺が氷室のことを信用して、油断していたか。
それこそ、本当の家族以上の気安さを無意識のうちに覚えていたということだ。
途中から、学園内で撮られたものも混じっていた。俺だけでなく、桐谷やクラスメイトなど他の生徒と一緒に映っているものもあり、和気あいあいと盛り上がっているシーンが記録されている。学園祭の準備期間に撮影されたものらしい。
腹の中で毒を吐きながら、表面的には笑顔を保っていると信じていたが、時々眉を顰めてイラついている瞬間や、桐谷の馬鹿話を聞いて呆れ果てている俺の素顔が、しっかりと捉えられていた。
そのくせ、心底楽しんで笑っている俺の本物の笑顔や、誇らしげに微笑んでいる写真もちらほら混ざっている。
そうなのだ。
俺は学園では王子様として自分を取り繕ってはいたが、実際に学園の仲間たちと毎日楽しく過ごしていたことは紛れもない事実だ。
何でも頼られることを面倒だと感じながらも、人に必要とされて嬉しく思う一面もあったし、純粋にやりがいや達成感を覚えていたのだ。
何なんだ、この男は。
どこまでカメラマンとして優秀なのだろうか。自分ですら意識しなかった俺の本心を暴いて、鮮やかに収めていたとは。
そして、フォルダの中の一番新しい日付の写真を見た瞬間、俺は悶絶してしまう。そこには、学園祭の日、綺羅びやかな王子様の衣装を身に纏い、二階の窓から飛び降りようとしている俺の姿が写っていた。
カメラの向こうの氷室を見つめ、泣きそうな顔をしながら、笑っている表情だ。
俺は椅子に座ったまま、両手で顔を覆って俯いた。羞恥心で身体が震える。穴があったら入りたいし、この場から逃げ去りたい気分だ。
これ、絶対氷室にバレてる。
俺は証拠隠滅のため、即座にその画像データを削除しようとした。しかし、後ろから伸びてきた別の手が、俺の手を掴んで制止してくる。
「勝手に消すなよ」
あまりに動揺していたので、氷室が風呂から上がったことに気が付かなかった。
後ろから抱きすくめるように覆いかぶさりながら、氷室は俺の顔を覗き込んできた。身体が暑くてたまらないのは、暖房が入って蒸し暑いせいなのか、体温が上がっているせいなのか。もはや判別不能だ。
「……嘘つき」
「何が?」
「全部消すって言ったじゃん!!」
「ああ、そうだったな」
氷室は悪びれもなく嘯きながら、俺の耳や頬に触れてきた。最近やたらと触られ過ぎて、慣れてしまった感はあるが、流石に限界を迎えている。
「ちょ、お前、触りすぎ!」
「お前の反応が可愛くて、つい」
「……可愛いとか言われても、嬉しくねぇって!」
耳元で囁かれ、鼓膜がビリビリと痺れるような感覚に襲われる。
本当は嬉しくないとか嘘だ。他の人に言われたら、殴りつけたくなるほど腹が立つ言葉も、氷室から言われれば嬉しい。気持ちが舞い上がってしまう。
「照れてる。やっぱり可愛いな。キスしていいか?」
「何でそうなんだよ!!」
言われた言葉が信じられなくて、反射的に叫んでしまった。俺が抵抗できないと分かった上で揶揄ってくるのは、卑怯というものだ。
「だって、理久。俺のこと好きだろ?」
氷室がサラリと追い詰めてきた。
ほら、やっぱりバレてる。俺は心の中で盛大に舌打ちした。背後から羽交い絞めにされているから、逃げ場はない。どうすればいい?
写真に残されていた俺の表情は、完全に氷室への恋慕に染まっていた。全身で奴への『好き』を訴えていたのだ。
聡い氷室が俺のその想いに気が付かないはずがないのだ。迂闊すぎる。恥ずかしくて顔を逸らそうとするが、両頬を押さえられて強制的に正面を向かされる。
「あ、けど、この言い方は良くないな」
そう呟きながら、氷室はゆっくりと顔を近づけてくる。心臓が破裂しそうなくらい大きく跳ねている。
「好きだよ、理久。そのままの理久が好きだ。俺の前では飾らなくていてくれ」
予想外の告白に思考停止した直後、唇が重なった。