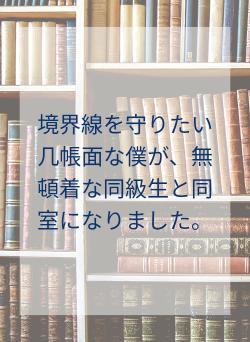湯船に浸かりながら、ぼんやりと思考を巡らせる。
家族と言い争いをして家を飛び出した挙句、真夜中に友人宅を訪ねるなんて常識外れもいいところだ。自分が情けなくなってくる。
そろそろ出ようと腰を浮かせかけた時、浴室の扉がノックされた。
「理久。着替え。ここに置いておくから」
「……ん、了解」
浴室の外から氷室の声が聞こえた。外へ出ると、バスタオルと共にスウェットの上下が洗濯機の上に畳んで置かれていた。氷室の私服だろう。下着は新品が置かれていたので、先ほどコンビニで買ってきたようだ。
タオルで全身の水分を拭き取りながら着替えた。下は裾が余っているし、上も肩幅が合わずダボついている。氷室の方が俺より一回りは大きいので、当然かもしれないが、何だか面白くない。
ほのかに氷室の匂いがして、安心感が増すと共に鼓動も速くなる。そんな些細なこと一つでも気恥ずかしくなり、妙に落ち着かない。
脱衣所から出ると、氷室はパソコンの前で何か作業をしていた。俺の視線に気づくと、顔を上げて少し笑った。切れ長の瞳が柔和に細められる。
「温まったか?」
「うん。ありがとう」
「……服ブカブカだな」
「……うるさい」
氷室は苦笑しながら立ち上がって俺の髪に触れ、まだ湿っている髪を撫で始めた。
「ちゃんと乾かさないとまた風邪ひくぞ」
「いい。そのうち乾くから大丈夫だ」
「良くねぇよ。お前、意外と大雑把なところあるよな」
「……」
氷室は文句を言いつつ、俺の手を掴んで引き寄せると、ベッドの端に腰かけるよう促す。そして、ドライヤーを持って来ると、俺の背後に陣取り、わしゃわしゃと俺の髪をかき混ぜながら乾かしはじめた。指先が心地よく頭皮をかすめ、思わず目を閉じそうになる。
氷室自身はクールで怖い印象なのに、実は世話焼きで優しい。
「……何かあった?」
「ん?」
「喧嘩でもしたか?家で」
氷室は視線を合わせずに、静かな声で問いかけてきた。ドライヤーのファンの音だけが室内に響いている。俺は口ごもりながら、小さく呟いた。
「ちょっと、母さんと揉めた」
「成績?俺のせいか?」
「……まあ、それも少しあるけど、大部分は俺が悪い。何かムカついて勝手に怒っただけ」
「らしくねえな」
氷室は俺の髪を梳きながら、さらりと言ってのけた。本人は自覚していないが、奴は結構察しがいい。こういう時にいちいち細かく問い詰めず、適当に流してくれる距離感が有難い。
「で、明日からはどうするんだ?家出少年」
「明日にはちゃんと帰るよ。母さんには言い過ぎた。一応、謝るべきところは謝っておく」
ボソボソと誤魔化さずに告げると、氷室はドライヤーのスイッチを切った。どうやら、俺の髪を乾かし終わったらしい。
「……つか、いつも通り笑顔で媚び売っとけばよかったんだよな……」
自嘲気味に苦笑すると、氷室の手が伸びてきて俺の両頬を強く摘んできた。左右にグニグニと伸ばされる。何故かまた弄られてしまった。
「痛いって。何だよ、離せ」
「ムカついて親に怒鳴りつけるなんて普通だろ?偽物の仮面なんか捨てちまえ」
「え?」
「普通にしてりゃいいんだよ。周りに忖度せず、思ったことはちゃんと口に出せばいい。別に喧嘩したって、嫌われたって関係ねえし、堂々としてりゃいいんだよ」
「……簡単に言うなよ。俺はお前と違って、そういうのは胃が痛くなるんだよ」
俺が唇を尖らせると、氷室はふっと鼻で笑い飛ばした。そのまま俺の頭を乱暴に撫でてから、立ち上がる。
人からどう思われても構わないと、堂々と言い切れる氷室が羨ましい。俺は他人との衝突を極力避けたいと思ってしまう性分なので、仮面が外せない。彼の強さと勇気は尊敬に値する。
「泊めてやるけど、家族には連絡しておけよ」
再びパソコンの前に座って作業をしながら告げられた氷室からの指令に、俺は口をヘの字に曲げて唸った。
「今はまだ、母さんと会話したくない」
「だったらメッセージだけでもいいし。母親が嫌なら単身赴任中の父親でも、この間学園祭に来ていた兄貴でもいい。俺の家にいるってだけでいいから連絡しとけ。お前もまだ学生だし、成人前のガキが無断外泊はまずいだろ」
不良のくせに至極まっとうな意見だ。納得はしているものの、やっぱり母とは今はまだ話し合いたくはない。多分喧嘩になってしまう。
俺はとりあえず、兄の玲央に電話を掛けることにした。それに、玲央には文句の一つや二つ言っておかなければならないこともあるし。玲央が氷室のことを母に悪く吹き込んだのは明白で、それについては許せない。
スマホの電源を入れると、不在着信とメッセージ通知が大量に入っていた。大半が母からだが、玲央からもいくつか着信とメッセージが残されていた。恐らく俺の家出のことを聞いたのだろう。俺の家出先は、玲央の所だと思われたのかもしれない。
母からの連絡は一旦無視して、玲央の番号に掛け直す。するとすぐに繋がった。
『理久?良かった。電話くれて。お前、今どこにいるんだ?』
「……友だちの家」
『住所言え。すぐ迎えにいくから』
玲央の声には明らかな焦りが滲んでいた。もしかすると、母から愚痴られたり詰問されたりしたのかもしれない。
「今晩は友だちの家に泊まるから大丈夫。明日にはちゃんと家に帰るよ」
『危ないから駄目だ。その友だちのご家族にも迷惑だ。お前、母さんと喧嘩したんだろ?母さんも反省してるみたいだし、一緒に謝ってやるから』
「……」
『理久、黙ってないでちゃんと返事してくれ。俺も母さんも心配してるんだから』
玲央は優しく諭すように語りかけてくる。いつもなら、心の中で毒を吐きながらも、笑顔で指示に従ってしまうパターンだ。
俺の視線は氷室の姿を捉えている。氷室はこちらに背を向けており、パソコンのキーボードを叩いているようだ。その姿にほんの少し勇気を与えられる。
俺は深呼吸をして、できるだけ穏やかな声色で返答した。
「何で俺が謝る前提で話進めてるの?」
『え? だってお前、母さんに酷いこと言ったんだろ?』
「言ってしまったのは事実だけど、俺だけが全面的に悪いわけじゃないから」
玲央に説明しているうちに段々苛立ちが増してきて、声が震えてしまった。電話越しに玲央の戸惑った気配が伝わってくる。
「そもそも、玲央が、母さんに俺の友だちを貶めることを吹聴したのが原因だし」
『え? ちょっと待てよ。何だよそれ。……ああ、いや、何となく理解したぞ。氷室くんのことか?』
玲央によれば、学園祭のときの氷室の対応が好印象だったそうで、俺の友だちに家庭環境が複雑なのにしっかりしている子がいると母に褒めて伝えたそうだ。……しかし、母にはそう伝わらず、氷室と俺の付き合いを快く思わなかったらしい。完全なミスコミュニケーションというか、盛大なすれ違いというか。
『……母さん、頭固いからちょっと偏見持ってるんだよな。人の考え方ってなかなか変わることじゃないし。一応、もう一回俺からもちゃんと話しておく。まあ、俺も少し配慮が足りなかったよな。……ごめん。理久』
「……うん」
ここですぐ冷静に謝罪の言葉が出てくる辺り、玲央はやはり人間が出来ている。俺とは大違いだ。玲央には、これからも足元にも及ばないんだろう。
『で、お前が今いる友だちの家ってもしかして、その氷室くん?』
「そうだよ」
『……なんで、そこで俺を頼ってくれないのかなあ? 家族だろ?』
「ごめん、考えもしなかった。敵だと思って腹が立ってたから」
玲央は電話口で大きく溜息をついた。少し気まずい雰囲気になる。
『……お前の言い分もあるだろうけど、母さんも俺も本気でお前のこと心配してるから、そのことは忘れないで欲しい。今日はもういいから、明日には絶対に帰って来いよ。母さんにも俺からそう伝えておくから』
「うん。分かった。……ありがとう」
玲央に言いたかったことを伝えることができて、俺自身も僅かではあるが素直になれた気がする。自分の中に溜め込んでいた膿のようなものが少し剥がれ落ちたような感覚があった。
一方的に距離を作っていた俺に対して、頼って欲しかったと漏らす玲央の言葉は、申し訳なかったと感じる一方で、単純に嬉しく思えた。
『……理久。ちょっと、氷室くんに代われるか?』
不意に玲央がそんな要求をしてきた。流石に困惑する。何故そこに繋げようとするのだろう。
「何で?」
『そりゃ、大事な弟が厄介にになってるなら、きちんとご挨拶しとかないといけないだろ?』
「……本人に確認してくる」
兄の玲央が話をしたがっていることを告げると、氷室はアッサリ「いいよ」と、了承してくれた。スマホを渡すと、氷室は無造作に肩と耳で挟んで、再びPCの操作を開始した。
「代わりました。氷室です。理久さんには普段から大変お世話になっています」
不良とは思えない丁寧な口調で氷室は玲央に対応している。クラスメイトや俺の前では見せない顔だ。多分、電話口では礼儀正しい好青年を演じていることだろう。流石、アルバイトで培われたプロフェッショナル精神だ。俺は半ば呆れながら傍観することにした。
「ええ。理久さんは明日にはこちらから帰します。迷惑だなんてとんでもないです。あ、いえ、大丈夫です。お気になさらず。……理久さんは俺の大切な友人ですから。俺にとっても大切な時間です。はい」
俺がソワソワしながら聞き耳を立てていると、話が終わったらしい。氷室はスマホを俺に返しながら、何故かニヤニヤしている。
「理久のこと、よろしくって。……あと、お前、俺のために母親に怒ってくれたんだって?」
「……!?」
何を勝手にバラしてんだよ、バカ兄貴! そういう所だぞ!? 俺は心の中で玲央を激しく罵倒したが、もちろん本人には届かない。恥ずかしさが爆発して、顔が熱くなっていくのを感じる。
「ありがとな。嬉しかった」
俺の心情を知ってか知らずか、氷室は淡々と感謝の言葉を述べてきた。照れ隠しのために睨みつけると、彼はそんな俺の様子を眺めて愉快そうに笑った。