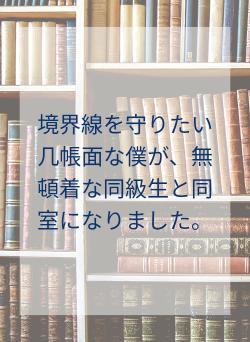「理久、この結果はどういうこと?」
その夜、仕事から帰宅した母は、ダイニングテーブルに置かれていた俺の期末考査の成績表を確認したらしく、俺の部屋のドアを開けるなり低い声で詰問してきた。
やはりそうなるよな……と内心溜息をつきつつ、「すみません」と即座に謝罪する。入学以来、学年首位をキープしていたのに、初めて2位に陥落してしまったのだ。母の性格を考えれば、叱責されるのは当然だろう。
「貴方、最近毎週のように週末外出してたけれど、一体何をしてたの?」
「友だちの家で勉強してた」
「友だち、……友だちね」
母は腕組みをして壁にもたれかかり、冷ややかな視線を向けてきた。室内灯の照明が母の輪郭をくっきりと際立たせている。
「その友だちと遊ぶのに夢中になりすぎて、勉強が疎かになったということでしょ?」
「それは……違う」
反射的に否定したが、語尾が揺れる。実際は氷室の勉強を指導したり、ダラダラと他愛もない会話を楽しんだりしていたので、すべてが勉強漬けというわけではない。ただ、それを母親に正直に説明する気はなかった。告げれば余計に反感を買いそうだったからだ。
「違うわけないでしょ。今まで1位を維持してきた理久が突然成績を落とすなんて。高校生の本分は学業よ。遊んでばかりいたら将来困るのは貴方自身なんだから。……それに、友だちはきちんと選びなさい」
「どういう意味だよ」
母の物言いに引っかかりを感じ、俺は思わず眉を寄せた。
「玲央さんに聞いたわ。最近家庭環境に問題がある子と交流しているらしいじゃない。そんな子と一緒にいたら、いずれ理久に悪影響が出るんじゃないかと心配していたら……案の定ね」
「俺の友だちの悪口言うのやめてくれる? 何も知らない癖に勝手なこと言うな」
母の言葉に憤慨し、腹の底から苛立ちが沸騰する。この反論は悪手だと理性では理解しているのに、勝手に口から言葉が漏れ出てしまった。どうしても抑えることができなかった。
「理久のために注意しているの。貴方はまだ未熟だから、周囲の人間を見極めることができないのよ」
「……だとしても、母さんに関係ないだろ。俺は母さんの所有物じゃない」
これまで母に対して反抗したことなど一度もなかった俺が、初めて歯向かってしまった。室内の空気がピリッと張り詰める。次の瞬間、母の溜息が耳朶を打った。
「親として、私は貴方を育てる義務があるの。子どもを悪影響があるものから遠ざけるのは当然だわ。この家に住む以上、うちのルールに従ってもらいます」
冷静さを失わない母の一方的で強い主張に、俺は言葉を詰まらせた。確かに今の俺は未成年であり、保護者の庇護が必要な立場だ。
「……全く、折角中等部から桐水学園に通わせていたのに、よりにもよって親のいない不良生徒と関わりはじめるなんて」
母の見下すようなその言葉を聞いた瞬間、もう無理だ、と感じた。こんな考え方をする人が自分の肉親だと思うだけで、今は気分が悪くなる。
俺は無言で立ち上がると、スマホと財布だけを小さなバッグに詰め込んで部屋を後にした。玄関に向かい靴を履きかけたところで、後ろから追いかけてきた母が腕を掴んできた。
「待ちなさい。こんな時間にどこに行くつもり?」
怒りを孕んだ母の声音に構うことなく、俺はその手を乱暴に振り払った。
「もうこんな家にいたくない。母さんの考え方に従えないから、出て行く」
「……本気で言ってるの? 私は貴方の為を思って」
「うるせぇよ!!」
母の言葉を途中で遮り、怒りのままに叫んだ。母は目を見開いて固まっているが、俺はそのまま続けた。
「俺の気持ちなんて分からないくせにっ……! 表の顔でしか人を判断できない最低人間が、偉そうに説教してくんな!!」
母に向かって声を荒げるなんてはじめてかもしれない。これまで積もり積もった鬱憤が爆発し、溢れ出てくる。
「……理久っ!」
狼狽えた母の呼びかけを無視し、俺は扉を開けて家を飛び出した。
しんと静まり返った高級住宅街を、早足で歩き続ける。孤独感と焦燥感が胸の内で渦巻き、涙が滲んでくる。母の罵声がいつまでも頭から離れず、耳鳴りが響いた。
失敗だ、ということは分かっている。いつもの自分らしくない行動だ。殊勝な態度で母に反省を示し、次回のテストで挽回すればいいだけだったのに。こんな風に啖呵を切って衝動的に家を飛び出すなんて、ただのアタマの悪い子どもだ。
けれど、どうしても我慢ができなかった。氷室の事情について勝手に憶測を立て、非難されることが何よりも許せなかった。
スマホが頻繁に震えている。おそらく母が何度も連絡してきているのだろう。鬱陶しくて電源をオフにしてしまう。
駅の改札を通り、電車に乗り込んだ。行き先は特に考えていなかった。とにかく今は冷静になる時間が欲しかった。明日は土曜日で学校が休みとはいえ、夜遅くまでこのまま彷徨っていると補導される恐れがある。
気が付いたら、最近馴染みになってしまった駅のホームに降り立っていた。上着は自宅に置いてきたままで、首元が冷たくて堪らない。しかも最悪なことに雨が降っていて、傘も持っていなかった。寒さと濡れた感触が相まって、どんどん気分が沈んでいく。
改札を出て、シャッターの閉まった商店街を通り抜ける。人通りの全くない路地を歩いていけば、見慣れた小さな建物が前方に聳え立っているのが見えてきた。古びているけれど、趣があって、居心地の良い場所。自然と足が向かってしまうくらい、俺にとって安らぎを与えてくれる特別な空間だ。
(……こんな時間に迷惑だよな)
何度も訪れてはいるが、約束もなく突然押しかけたことは一度もない。しかも時間が時間だ。もし拒絶されたらどうしよう。目の前まで来てしまっているのに、チャイムを鳴らす勇気が出ない。
電源の入っていないスマホを片手に、俺はその場に立ちすくんでいた。
「……理久?」
どのくらい時間が経ったのだろう。背後から静かに呼びかけられた。ノロノロと振り返れば、そこには傘を差した氷室が立っていた。右手にはビニール袋を提げており、コンビニ帰りか何かかもしれない。
「なんで……」
「俺ん家の前だし」
驚きを隠せず掠れた声で問いかけると、氷室は淡々と答えながらも足早に近づいてきた。
「何してんだよ。こんな雨の中で、傘もささないで。お前ずぶ濡れじゃん」
氷室は自分がさしていた傘を俺に差し向けてきた。近距離で見ると、彼の瞳が心配そうに揺れているのが分かる。正面から顔を見れば、思わず崩れ落ちそうになってしまう。
「……今日、泊めてくれ。家に帰りたくない」
「いいよ」
震える声で懇願すれば、氷室は特に躊躇うことなく即答した。その潔さに驚きながらも、内心ホッとした。今夜、もう一度あの家に戻る気には到底なれなかった。
「風邪ぶり返すぞ。……とりあえず、入れよ」
氷室は何も問い詰めることなく俺の手を握ると、家の鍵を開け、建物の中へ招き入れてくれた。狭い階段を上がり、二階の居住スペースへと移動する。足元の床板がギシギシと軋む音が響く。この感覚ですら安心感を覚え、涙腺が緩んでしまいそうだ。
玄関で靴を脱ぐと、氷室がバスタオルを持って来て、俺の頭から被せてくれる。
「お湯沸かしてやるから、ゆっくり風呂に浸かって温まってろ」
「……でも」
「俺はもう一回コンビニ行ってくる」
俺を浴室まで案内し、氷室は再び外へ出て行ってしまった。一人取り残された俺は、暫し呆然とするしかなかった。