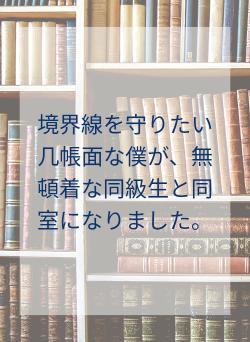学園祭が終わると、期末テスト前の最終週となり、授業時間以外は各自自習時間となって、全校生徒が勉強モードに突入する。この時期は通常授業がないので、朝礼も含めHRも行われない。部活動なども全て休止扱いとなっているので、運動部の生徒にとっては逆に恨めしい期間と言えるかもしれない。
流石の氷室もこの期間はバイトを控え、ひたすら自習時間を設けているようだ。
俺はといえば、学園祭の残務整理をするために放課後生徒会室に寄ったのだが、「精算書類と報告書は作成完了しておりますので、会長は最終チェックだけお願いします。」と桐谷や他の役員たちが既に仕上げていたので、俺の業務は確認作業のみで数十分で完了した。どうやら異常なほど俺を大事に保護しようと動いているようだ。
複雑な心境だが、皆の優しさには感謝しなければならない。
実際、今回の期末テストに関してはほとんど勉強ができていないので、万全の対策は講じられていない。俺は密かに焦っていた。入学以来、学年首位をキープし続けていたが、ここで順位を落としてしまえば、母から何と言われるか分からない。
そして、その懸念は現実となった。
***
テストの結果が貼り出され、渡り廊下に群がった生徒たちが一斉に騒ぎ出した。
上位者の名前を凝視する者、ため息をつく者、互いに健闘を称え合う者など様々だ。そんな中、俺は目を疑う光景を目の当たりにしていた。
【ニ年】
1位 氷室 朔弥 825点/900点満点
2位 篠宮 理久 776点
二学期の期末考査における俺の順位は、まさかの2位だった。なんと、氷室が首位を獲得したのだ。しかも、奴は特待生制度に必要な700点以上を軽々と突破してみせた。ぶっちぎりだ。
(……やりすぎだ、バカ)
努力した者が評価されるのは当たり前で、正直氷室の成績が向上したこと自体は喜ばしい。俺の指導の甲斐あっての成果なのかもしれないが、短期間でこれだけの結果を叩き出した彼の努力は、並大抵ではないだろう。
(凄い……本当にすごいよ。氷室……)
しかし、同時に大きな喪失感に襲われていた。学年首位という俺の居場所が奪われてしまった。これがたとえ奴の正当な努力による賜物であっても、これまでのプライドが打ち砕かれたことに変わりない。何故か胸が締め付けられるように苦しくなる。
自分の存在意義さえ揺らいでしまう感覚に襲われた。
***
その日の放課後、帰宅するために教室から出ようとしたとき、後ろから腕を掴まれて引き留められた。振り返ると、氷室が何故か厳しい表情で立っていた。
「篠宮、ちょっと時間取れるか?」
その瞬間、クラス中が俄に色めき立った。俺と氷室の期末考査の順位は知れ渡っている。好奇の視線が集中しているのが肌で感じられた。
「……少しなら」
俺が同意すると、氷室は人目を避けるように廊下へ促してきた。氷室と直接会話するのは、学園祭以来だ。学園内では接触しない方がいいと言った俺の発言を、忠実に守ってきた結果である。
二人で辿り着いたのは、学園内の裏庭だった。放課後の時間帯なので、辺りには人影もない。冬の訪れが近いせいか、木々の葉は殆ど散っており、物寂しい雰囲気が漂っている。
「これ、返す。ありがとな」
氷室は俺の前に立ち、鞄から何冊かの参考書を取り出した。俺から貸していたものだ。
「ああ、うん。どういたしまして」
「お前のお陰で、特待生制度の条件クリアできた。マジで助かった」
「……そう。よかった」
表面上は平静を装いながら笑顔で返答するが、内心は乱れっぱなしだった。学園での通常モードなのだが、ちゃんと笑えているか不安になり、俺はそのまま俯いてしまう。
すると、氷室の両手が俺の頬を包み込み、無理矢理顔を上げさせられた。掌の温度が、火照った俺の頬に伝わってくる。
「何か俺に言うことあるだろ?」
「……別に。おめでとう?って言えばいいか?」
「ちげぇよ」
氷室は俺の左頬を抓った。そして、そのまま引っ張ってくる。痛い。
「俺の前で偽物の笑顔貼り付けんなって前も言ったよな?素顔でいろよ」
氷室の視線が鋭く射貫いてくる。真摯な眼差しに絡め取られ、心の奥底にある脆い部分を曝け出されてしまう。王子様の仮面は、やはり氷室には通用しない。
「……ずっと学年首位だったのに、お前のせいで全部台無しだ。帰ったら母さんにスゲー怒られるし」
「うん、それで?」
「……お前に成績抜かれて、めちゃくちゃ悔しい」
言葉にしてみると、やけに幼稚に聞こえてしまう。自分の感情を露呈することが苦手で、つい他人の機嫌を窺ってばかりだった俺にとって、弱音を吐くこと自体が不得意なのだ。
それでもこの男にだけは本音で語ることができるのだと、今更気がついた。
「悪かったな。お前のプライド傷付けて」
「氷室が悪いわけじゃないから。謝る必要ない」
「俺はお前が居てくれなかったら、勉強法も分からなかったし、ここまでの結果も出てなかった。だからお前には心の底から感謝してる。俺に教えてくれてありがとな」
「……うん」
氷室は俺の頬を解放すると、その掌で俺の頭を優しく撫で始めた。まるで幼児をあやすかのような動作だ。
「次は手を抜けとか、命令しないでいいのか?」
「必要ない。ちゃんと実力で首位に返り咲くから」
氷室の挑発に乗るように睨み付けながら宣言すると、氷室はフッと表情を崩して柔らかく微笑んだ。その笑顔に釣られて、俺も口元が弛んでいく。
「……けど、お前の成績が上がったのもちゃんと嬉しいし、凄い努力家だと素直に尊敬してる。……おめでとうって思う気持ちも、嘘じゃねえから」
「わかってる」
心からの祝福を送ると、氷室は目を細め、噛みしめるように頷いた。