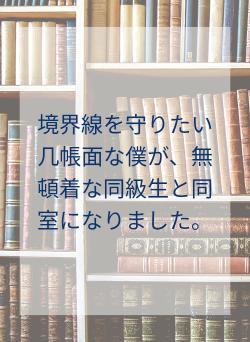───暗闇の中から這い上がるような感覚が全身を襲い、唐突に覚醒した。
薄ぼんやりとした視界に映ったのは、天井の白色灯だった。どうやら保健室のベッドで横になっているらしい。消毒液の匂いが鼻をつく。少しずつ意識が明瞭になっていくにつれ、周囲の状況が徐々に認識されていった。
「起きたか?」
「……玲央?」
「そう。理久の大好きな兄ちゃんの玲央だ。よく寝てたな」
「……」
いや、大好きじゃねえし、と心の中で即座に突っ込む。口に出さずに済んだのは、未だ身体が怠いからだ。全身が重く、身体が動かない。
「……なんで玲央がここに?」
「いや、学園祭参観するって俺、連絡したよな?理久に案内してもらうのめちゃくちゃ楽しみだったのに、お前迎えに来ないし。お前の教室に行ったら、弟が倒れて保健室で寝てるって聞いて驚愕したわ」
そういえば、そんなメッセージが玲央から届いていたような気がするが、正直ほとんど記憶にない。学園祭が始まる直前で、それどころではなかったのだ。
「同じクラスだっていう氷室君?彼から状況説明してもらったけど。睡眠不足で目眩がして、二階の校舎の窓から落ちたって……本気なのか?」
玲央はニコニコと微笑んでいるが、目が笑っていない。明らかに怒っている気配を感じ取り、背筋に冷たいものが走る。自分から飛び降りたという真実は、流石に氷室も玲央には隠してくれたようだ。一応フォローされていることに感謝しつつ、今は黙っておくことにする。
もし、心配症の玲央が真実を知ったら、学校なんて行かなくてもいいと、監禁されて閉じ込められる未来しか見えない。それだけは避けたい。
「養護教諭の先生から念のため救急車呼ぼうかって言われたけど、頭打ったわけでもないし、外傷も無いから遠慮しておいた。ただ、一応今から病院行くぞ」
「いや、いいよ。多分、寝不足が原因だろうし」
「そういう問題じゃない。念のために検査したほうが安全だから」
玲央の有無を言わせぬ圧力に、俺はしぶしぶ頷いた。抵抗するだけ無駄だというのが、長年の付き合いで熟知している。玲央が一旦決定したら曲げる気配はない。
「母さんにも学校から連絡があったみたいで、今こっちに向かってる。車の手配も頼んでおいたから。クラスメイトも皆心配してたぞ」
「……うん」
玲央の言葉に曖昧な返事をしながら、俺は項垂れた。あの時は氷室を捕まえて謝らなければという一心で突き進んでいたが、冷静に振り返ると随分と恥ずかしい真似をしたものだ。俺が醜態を晒す現場を目撃した生徒はかなりいるはずで、学園での王子様像は完全に瓦解しただろう。明後日からどんな風に接されるか、今から憂鬱になる。
「それと、氷室君。俺が来るまで理久に付き添ってくれてたみたいだから。あと、理久の荷物もまとめて持ってきてもらってる。せっかくの学園祭だからもう戻ってもらったけど、後でお礼言っとけよ。仲がいい友だちなのか?」
玲央に問われて一瞬口ごもる。仲がいい? 友だち? どういう関係と言えばいいのだろう。
「仲がいいってか、毎週末一緒に勉強してるけど」
「理久がか? へえ、珍しいな」
兄と会話をしながら、ふと自分の服装に違和感を覚えた。あれ?と思いながら掛け布団を持ち上げて自分の身体を確認すると、きちんと制服に着替えている。王子様衣装は跡形もなく消え去っていた。どういうことだ?
「俺、兄さんが来たとき制服着てた?」
「……どういう意味だ?」
玲央が訝しげに眉を寄せる。この様子では、俺が王子様衣装を着用させられていたことには気が付いていないようだ。
「いや、何でもない」
俺は慌てて誤魔化した。
自分で着替えた記憶はないから、玲央が来る前に氷室が着替えさせてくれたのだろうか? 玲央に見られなくて助かったと安堵する反面、氷室にそんな世話まで焼いてもらったとしたら申し訳なくも思う。あいつも、いろいろと多忙な中で俺なんかの為に貴重な時間を費やしてくれたのだろう。
改めて氷室には詫びと感謝を述べておくべきだと強く感じた。
***
結局、保健室の先生にも勧められ、医療センターでMRI検査などを受けたが、脳や骨に異常は認められず、医師からは「過労や睡眠不足による一時的な体調不良で、単なる風邪でしょう」と診断された。脱水症状を起こしかけていたらしく、点滴を投与され、安静にするように指示を受けた。
病院から自宅に戻ったときにはもう夜になっていた。自己管理が疎かになっていると、帰宅しながら母に叱責され、非常に居たたまれない気持ちになる。
自室で一人になり、スマホの電源を入れてみると、氷室からのメッセージが届いていた。
『体調はどうだ? 無理すんなよ。何かあったらまた連絡しろ』
短い言葉の中に滲む気遣いに胸が暖かくなる。思わず口元が綻んでしまい、自然と笑みが零れた。既に帰宅している時間帯だったので、直接声が聞きたくなってしまい、反射的に通話ボタンを押していた。
呼び出し音が数回鳴ったあと、『はい』と、耳に馴染んだ低い声が響く。ちゃんと繋がっただけで心が躍る。我ながらチョロすぎる。
「氷室? 俺。まだ少し熱はあるけど、体調はかなり良くなった。明後日からは登校もできると思う。ただ今週末は家で安静にしておくように言われてるから、勉強は教えられない。すまん」
『ん。そうか。いいよ、気にすんな』
どうでもよさそうな平坦な声が返ってくる。だが、その奥に安堵の色が含まれていることが分かる。注意深く観察してみれば、奴の感情は存外分かりやすい。
「最後の追い込みなのに申し訳ない。今日は迷惑かけて悪かった。それと、ありがとう……その、色々と」
『別にいい、お前こそ、あんま無茶すんなよ』
「……肝に銘じる。それで、結局学園祭どうなった?俺、途中で投げ出す羽目になったから」
『学園祭か……』
「……どうしたんだ?」
『いや、……学園祭自体は、特に問題なく終わった』
俺がそう問いかけると、氷室は言葉を濁した。何か変だ。氷室は基本的に歯に衣着せぬタイプなので、こうやって言い淀むことは稀だ。少なくとも俺と話すときはそうだった。
「何かあった?」
『……あんま深刻に捉えないでほしいんだけど、今日のお前と俺の写真を誰かが撮ってたみたいで、SNSにアップされてた。……それが、ちょっと腹立つ写真で』
氷室の言葉を受けて、俺は青ざめた。王子様らしからぬ奇行を公衆の面前で披露してしまった自覚があるので、非難や嘲笑の対象となるのは容易に想像がつく。噂程度で収まるかと思ったが、実害が出てしまっているらしい。俺のみっともない姿が拡散されてしまったようだ。
「……うわ、マジか。すまん。迷惑かける」
『俺は別に……気にしないから平気だ。それよりお前は大丈夫か?』
気遣わしげな声が届く。これから起こりうるであろう周囲の反応を考えると、正直憂鬱でしかない。完璧な優等生だった王子様像の崩壊は免れないだろうし、下手すれば新たなイジメのネタ提供になってしまう。
『周囲からいろいろと言われるかも知れないけど、そのうち沈静化するだろうから。気にするなよ』
「……そうする」
氷室の言葉が幾分か心強い。
「けど、そんな状況になってるなら、やっぱりこれまでどおり学園では接触しない方がいいかもな。お互いの為にも。まあ、すぐに期末テストだし、お互い勉強に集中しよう」
俺の評判が地に落ちてしまった以上、学園ではもう完璧な王子様として振舞うことも難しいかもしれない。これまでの化けの皮が剥がれ、嘲笑の対象となる可能性もある。そんな俺と交流を持つことは、氷室にとっても不利益になるだろう。
『……お前がそうしたいなら、それでいいけど』
「悪いな。参考書返すのは、期末テスト終わってからでいいから」
電話越しだが、氷室が言葉を選んでいる様子が伝わってくる。たぶん、俺の意思を尊重して、無理強いはしてこない。そんな奴なのだ。だからこそ余計に申し訳なくなる。
「じゃあ、氷室。おやすみ」
それ以上の言葉を交わすのが辛くて、一方的に通話を切り上げた。スマホを枕元に置いて仰向けに転がると、白い天井が視界に入る。ぼんやりと見つめながら、湧き上がる寂寥感に押しつぶされそうになる。
「……しばらく一人で耐えるしかないよな」
ぽつりと独り言を漏らすと、自分で宣言したくせに自己嫌悪の波が押し寄せてくる。
期末テストが終わったら、完全に氷室との取引は終了だ。もう氷室の家に行く理由がなくなってしまう。単純に、寂しいと感じてしまう。
視界が滲み、じわりと熱いものが込み上げてくるのを感じた。