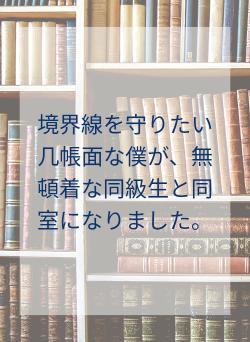プラカードを片手に持ちながら、人混みのなかを練り歩く。途中、すれ違う人たちはほぼ全員俺を二度見してきた。好奇の視線が突き刺さる。公開処刑状態である。
そんな中、見知った友人や後輩と出会ってしまった場合は、「篠宮、その恰好似合いすぎー!!」「さすが篠宮先輩、美しすぎて倒れそうですぅ」「王子様、素敵~~!!」などと黄色い歓声を浴びせられた。
これは普通の人なら喜ぶシチュエーションなのかもしれないが、今の俺にとって拷問以外の何者でもない。
胃薬が飲みたい。でもそんな悠長な時間を許してくれる様子はなかった。女子たちに引っ張られては立ち止まり、握手を求められたり、記念撮影をせがまれたり。表面的には笑顔で対応しているが、内心はかなり追い詰められている。
一刻も早く氷室を探さなければと焦燥感が募る。
(お前、どこにいるんだよ!?)
何故か寒気が止まらず、視界がぼやけてきた。足元がふらつく。身体が鉛のように重くて、一歩踏み出すのも億劫だ。
一度吐いた方がスッキリするかもしれないと、二階の校舎の窓から中庭を眺めながら考えていると、すぐ下の庭園に探し求めていた人物の姿が目に映った。やっと見つけた。
カメラを片手に、中庭のイベント風景を撮影している氷室がそこにいた。制服を着用し、左腕に広報部の腕章をしている。
良かった、一応学園祭に参加はしているらしい。
声をかけようとして、一瞬だけ躊躇ってしまう。記録写真の撮影をしている氷室の表情が、あまりにも真剣だったからだ。今、俺が呼びかければ、集中力が途切れて気が散るかもしれない。邪魔をしてしまうことになる。
氷室がカメラを構えている時の眼差しは、普段の粗暴な態度からは想像もつかないくらい、静謐な雰囲気を纏っていた。
カメラ越しに世界を見つめる横顔は、驚くほど綺麗で惹き込まれる。俺は吸い寄せられるように窓枠に寄りかかり、夢中でその姿を見つめていた。
はじめて氷室に写真を撮られたとき、素顔が意外すぎて撮ってしまったと言われたことを、不意に思い出す。そういえば、何度も写真を撮られているのに、アイツが撮った写真を一度も見たことがないのに気が付いた。
ファインダーを覗いたその先には何が見えるのだろう? 氷室の世界を垣間見たいと、叶うなら、その空間を共有したいと何故かその時の俺は願ってしまった。
氷室は何枚か写真を撮影した後、液晶画面を確認し始めた。自分が今撮影した画像を確認しているのだろう。そして、ほんの少しだけ口角をあげた。あの表情は知っている。俺の写真を眺めている時にもよく見かける顔だ。
自分以外の写真撮影で、あの穏やかな表情を見せられるのはなんとなく面白くない。けれど、奴の感情はそれとなく伝わってきた。きっといい写真が撮れたんだろう。
暫く眺めていると、氷室がこちらに背中を向けて歩きはじめた。場所を移動する気のようだ。当然ながら俺には気が付いていない。このままではまた見失ってしまう。
「氷室!!」
咄嗟に叫んでいた。考えるよりも先に口が動き、声が迸り出た。窓枠から身を乗り出して、人目も憚らず大声で名を呼んでしまったが、今はそんなことどうでもよかった。
とにかく奴をこのまま行かせるわけにはいかない。しかし周囲の喧騒に掻き消されたのか、氷室はこちらに気づかず遠ざかっていく。
今から階段を降りて追っても追いつけないだろう。
「おいコラ!!氷室朔弥!!止まれ!!!」
焦燥感に駆られ、再び叫ぶ。今度こそ確実に届くように、肺一杯に空気を吸い込んで、ありったけの声量を振り絞った。
多分、体調が悪過ぎて俺の情緒は少しバグっていたのかもしれない。言葉遣いを構っていられなかったし、周りが見えなくなっていた。この時の俺の思考回路は、とにかく氷室を確保することだけに特化していた。
俺が窓枠に足を掛けたその瞬間、漸く氷室が異変に気づいたのか、こちらを振り向いた。視線が緩やかに交錯する。
氷室は目を大きく見開き、そのまま何故か俺に向かって素早くカメラを構えた。
まさかこんな瞬間まで狙い撮りするつもりか?非常識な奴め。……って、んなこと今はどうでもいい。
俺は迷うことなく窓枠を蹴り上げた。
自由落下の感覚と共に、まるでスローモーションのように地面が迫る。降下速度は凄い速さのはずなのに、身体が軽かった。
このまま地面に激突すればただでは済まないので、とりあえず衝撃を和らげるために受け身の姿勢だけ取っておく。骨折は回避できるはずだ。多分。
衝突の痛みを覚悟してぎゅっと目を瞑った次の瞬間、激しい勢いのまま、全身を誰かに抱きとめられた感覚があった。そのまま芝生の上を盛大に転がる。
一回、二回、三回──何度か回転して、ようやく勢いが収まった。
恐る恐る目を開ければ、至近距離に氷室の顔があった。鼻先同士が触れそうな距離で、彫刻のように整った容貌が視界いっぱいに広がる。……あ、睫毛意外と長い。
切れ長の目は、怒っているのか呆れているのか。氷室からは睨み付けられていて、客観的に見たら怯みそうな鋭い眼光なのだが、奴の本質を知っているからか、全然怖くない。
「バカ!! テメェは死にてぇのか!?」
耳元で怒鳴りつけられ、鼓膜が痺れる。こんな風に真正面から怒られたのは、はじめてだ。
俺たちは二人揃って芝生の上に横たわっていた。というか、俺が氷室を下敷きにしている。氷室が庇ってくれたから助かったようだ。流石運動神経の塊な男。素直に感謝したい。
「悪い、無事か?」
「無事じゃねえよ。全身痛ぇわ」
「……ケガしてないよな?」
咄嗟に半身を起こして氷室の全身を確認する。地面が柔らかく芝生だったのも幸いだったのか、血の気配はない。擦り傷や打ち身は多少あるかもしれないが、重篤な怪我は無さそうだ。安堵のあまり脱力感に襲われる。
「なんで二階から飛び降りて来るんだよ?」
氷室も起き上がると、頭をガシガシと掻きながら苛立たしげに尋ねてくる。不機嫌そうな声音で怒られているのに、何故かそれが心地好くて安堵感を覚えてしまう。氷室をやっと捕まえることができてほっとしていた俺は、少し感情が昂ぶっていた。
「ごめん、氷室。俺、めちゃくちゃ傲慢で嫌な奴だったみたいだ。……本当にごめん、反省してる」
「……おい、何の話だ? とりあえず、いい加減降りて離れろ。注目されてんぞ」
「いやだ、離れない」
また居なくなったら困る。
氷室に跨ったまま、渾身の力を込めて抱きしめると、氷室は「はあ?」と混乱した声を上げた。しかし、本格的な抵抗はせず、諦めたように盛大な溜息をつき肩を落とす。その反応に俺はさらに強く抱きついた。
「イメージ壊れるから話しかけるなとか、失礼極まりないことを言った俺に嫌気差したか? 正直ムカついたか? 本当は最初から会話したくなかった? あれからお前、連絡もなかったし」
「あー……いや、別に怒ってねぇよ」
氷室は俺にしがみつかれたまま、アッサリ否定した。背中を軽く撫でられる。
「お前、学園で自分がどう見られてるか、かなり気にして怖がってただろ? ……元々俺が脅して無理やり付き合わせた関係だし、俺のせいでお前の日常を脅かしてしまうなら、安心させてやろうと思っただけだ」
氷室の言葉は静かだったが、核心を突いている。
俺が最も恐れているのは、優等生の王子様像が壊れることによって周囲から失望されること。自分に自信がないから、それが唯一の居場所を失う行為だと思っていたから、常に必死に演じてきた。
でも、今の俺には他人からの評価より、氷室との関係の方が遥かに重要なのだ。俺の唯一の安息の場所。氷室には本音を晒しても、受け止めてくれる安心感がある。
「……じゃあ、俺に嫌気は差してないんだな?」
「別に。お前面白いし、いまのところ嫌になる要素なんかねえよ」
「……よかった」
安堵の息が漏れる。緊張で張り詰めていた神経が緩んでいくのを感じた。安心できた途端に猛烈な眠気に襲われて瞼が重くなる。胃の辺りがグルグルと蠕動しており、吐き気が波のように押し寄せる。身体が限界を訴えていた。
「おい、大丈夫か? お前、どこかぶつけたのか?」
俺の異変に気がついたらしい氷室が、心配そうに声をけてくる。
「ぶつけてない。……昨日から眠れてなくて、寝不足なだけ」
「……ちょっと触るぞ」
氷室はそう前置きして、俺の額に掌を当ててきた。熱く火照った額に感じる氷室の手は冷たくて気持ちいい。次第に視界が霞んできて、思考能力が低下していく。もう目を開けていられない。
「風邪か? 少し熱があるみてぇだけど」
「わかんね……でも、この衣装のまま保健室行きたくない。恥ずかしい」
「……まあ、確かに本物の王子様みてぇだな」
俺が漏らした本音に、氷室が小さく笑う気配がした。俺は唇を尖らせる。
「笑いたきゃ笑え」
「いや、よく似合ってる」
「……嘘つけ」
冗談なのか慰めなのか分からない言葉に戸惑いつつも、僅かに沈黙が流れ、何故か照れくさい気分になる。他人から容姿を褒められることは珍しくないはずなのに、妙に意識してしまう自分がいる。
「本気で言ってるし。学園の皆も多分そう思ってる。少しは信用して自信持てよ」
「……そんなの」
無理だ、と紡ぎかけた言葉は途切れた。俺の唇に、なぜか氷室の指が伸びてきて触れていたからだ。奴の親指がゆっくりと唇の輪郭をなぞる。その感触に背筋が粟立つ。
急激に心拍数が跳ね上がり、顔に熱が集まっていく。呼吸が浅くなる。一体何をしてるんだ、この男は。
「なあ、これ化粧してる?口紅塗ってるみてぇだけど」
「……こ、これは、クラスの女子から無理やり塗られて」
「……ふうん」
思考が鈍くなっているせいなのか、普段なら躊躇なく突っぱねる行動に対して、何も抵抗できない。
氷室の顔がわずかに傾き、吐息が混じるほどの距離に近づく。
「素顔のほうが可愛いのにな」
そう囁かれた瞬間、全身の血液が逆流しているような感覚に支配される。目の前がかすむのは、酸欠のせいなのか、それとも俺の都合のいい妄想なのか。
(……ダメだ)
俺はもう、限界だった。
「……氷室、あのプラカードをお前に託す。あれを持って校内を歩いてくれ」
「は? プラカード??」
全く意味が分からないといった様子で困惑した表情を浮かべている氷室の肩に手を置き、「頼んだぞ」と苦しげに呟いた俺は、そのまま奴の膝の上で意識を手放した。