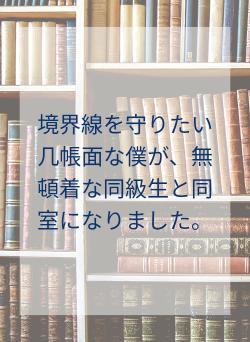篠宮理久。17歳。
私立桐水学園高等部2年A組。生徒会所属で役職は会長。成績は常に学年トップをキープ。スポーツ万能でバスケットボール部のエース(ただし、生徒会の仕事が忙しくてあまり部活の練習に出られていない)。
人当たりは良く、誰に対しても平等で親切。身長175cmで程よく筋肉質。整った甘いマスクに明るい栗色のさらさらヘア。趣味はクラシック音楽鑑賞とカフェ巡り。
常に穏やかな笑顔を絶やさず、周囲から頼られ慕われる、皆の憧れ。
ついた呼び名は───『王子様』
これが俺の公式プロフィールであり、表の顔だ。
***
「篠宮君。来週の学園祭実行委員会の資料チェックと議事録作成を君に任せたいんだ。他のメンバーがどうしても頼りなくてね……」
放課後、生徒会室で作業をしていると、学年主任の五十嵐先生が申し訳なさそうな顔をして、新たなプリントの束をデスクに置いた。俺のデスク周りには既に高層ビルのような書類の山脈が幾つもそびえ立っている。
今日は金曜日。来週に持ち越したくない仕事を全て今日中に片付けなければと思っていた矢先の追加業務の発生だ。俺は反射的に張り付いた笑顔を作り、首を傾げた。
「はい、構いませんよ。僕でお役に立てるのでしたら喜んで」
口から自動的に出たのは学園中で評判の爽やかな低音ボイス。しかしその裏側では、俺の脳細胞は阿鼻叫喚の地獄絵図を呈していた。
(はぁ~~? 学園祭実行委員会? そんなの担当者にやらせろよクソ教師が! こちとら来週のテスト範囲もまだ暗記できてないってのに!! 議事録くらいテメェでまとめろやァ!! このボケ!!)
心の声は猛毒だが、表情筋はプロ級の演技力を発揮している。これが俺の学園生活における日常であり、唯一の戦闘スタイルでもあるのだ。
「先生! 篠宮会長がいくら仕事が出来るからって、あまりに任せすぎじゃないですか? 頼りすぎだと思いますが」
横から割込んできたのは生徒会副会長の桐谷凛太郎。眼鏡の奥の瞳が怒りに燃えて、教師を睨みつけている。彼は俺の右腕として生徒会を支えてくれる戦友だ。どうやら俺の過剰な仕事量を心配してくれているらしい。時折暴走することもあるが、根は非常に良い奴なのだ。
「ありがとう、桐谷くん。でも大丈夫だよ。これは僕が皆の役に立ちたくてやっていることだから」
俺はにっこりと微笑みながら桐谷の肩を叩く。その手が微妙に震えているのは寒さのせいではない。怒りでプルプルしているだけだ。
(そうだ桐谷! もっと言ってやれ! このハゲ教師をぶん殴ってくれ! お前、単なる脳筋バカかと思ってたけど見直したぞ!)
「会長……!」
だが、何故か桐谷が感激して涙ぐんでいる。
「……私が間違ってました。篠宮会長が一般人と同じレベルの訳ないですよね。会長は特別な御方ですから。全てを完璧にこなすのが当然で、それが会長にとってのやり甲斐に繋がってるんですね! 私なんかが口を挟むなど身の程知らずでした……」
あれ?なんかスイッチ入っちゃった?お前、違う方向に行った??
桐谷は勝手に自己解決してしまい、尊敬の眼差しと共に手をあわせて俺を拝みながら深々と頭を下げた。彼の中で俺は「人智を超えたパーフェクト・ヒューマン」として認識されてしまったらしい。
ああ、また一人俺の信者が増えてしまった。
桐谷は勘違いしたまま「いったん頭を冷やしてきます、失礼します」と宣い、部屋をダッシュで去って行った。
「流石は篠宮君だね。そう言ってもらえると助かるよ。それじゃあ任せたよ」
五十嵐先生は満足げにニコニコ笑いながらそそくさと退室していった。残されたのは静寂と新たな書類の山。俺はゆっくりと椅子に座り直し、ボールペンを握りしめた。
(あのクソ教師め。俺を便利屋扱いしやがって。今度職員室のコーヒーメーカーにこっそり激辛唐辛子でも入れてやろうか? 桐谷も桐谷だ。アイツ、どさくさに紛れて逃げやがったな)
心の中で呪詛を撒き散らしながらも、手は正確に書類の束を分類し始めている。数々の修羅場を潜り抜けた俺の左手は、思考とは無関係に自動処理を開始していた。これが俺の日常。しかし、俺の試練はこれだけではないのだ。
数十分後。集中力が途切れ始め、糖分補給のためにこっそりコンビニで買ったチョコレートバーを噛っていたところだった。
不意にコンコンとノックの音が響いた。「……失礼します」というか細い声とともに入室してきたのは、学園内カースト最上位女子グループの中心人物で、超絶可愛いと持て囃されている佐伯由美だ。その後ろには取り巻きの女子たちが数人控えている。皆一様に頬を赤らめ、期待に満ちた目で俺を見ている。
(来た……今日もか……)
「あの……篠宮君、ちょっといいかな? じ、実は昨日クッキー焼いたんだけど、良かったら食べてもらえたりしないかな……?」
佐伯さんは背中に隠していた小さな紙袋を差し出しながら、恥ずかしそうに俯いている。後ろの取り巻きたちは「ユミちゃんガンバレ!」とか「王子様喜ぶよ!」と小声で囁いている。
俺は即座にチョコレートバーを机の引き出しに隠し、最大限に甘く優しい笑顔を作った。学園の王子様スマイルLv.99MAXである。この笑顔を見るだけで女子の大半は腰砕けになるというデータ付きだ。
「ありがとう、佐伯さん。後で生徒会の皆で頂かせてもらうね」
俺はそっと紙袋を受け取り、自然な流れで桐谷がいつも使っている隣の席に置いた。すぐにでも処分したい気持ちを抑え込む。あくまで紳士的に。
まあ、桐谷なら俺が命じれば喜んで食べるだろうから、無駄にはならないはずだ。
「そ、そうなの……? みんなと……」
佐伯さんの瞳がかすかに揺らいだ。明らかに落胆の色が見える。勿論彼女が俺のためだけに作ったことは理解している。だが、申し訳ないが俺に恋愛感情はない。こんな時は誰にでも平等に接することこそがトラブル回避の秘訣なのだ。
「うん。でも本当に嬉しいよ。佐伯さんの作るお菓子は美味しいって評判だからね。おかげで生徒会の仕事も大変だけど頑張れるよ」
社交辞令のフルスロットルで畳みかける。こうすることで相手に一定の満足感を与え、かつ自分の逃げ道も確保するのがベストなのだ。
案の定、佐伯さんは複雑な表情ながらも「そ、そう? 良かった……」と僅かに頬を緩ませた。後ろの取り巻きたちが「王子様マジ優しい……」「笑顔眩しすぎ」と歓声を上げている。
それでいい。それで平和は保たれる。俺の心は荒れ果てた戦場だが。
「……じゃあお仕事頑張ってね。私たちは帰るね」
本当は「一緒に帰ろう攻撃」を仕掛けたかったのかもしれないが、俺の傍らにそびえ立つ書類タワーに恐れをなしてあきらめたようだ。女子軍団は恭しく一礼して退室していった。扉が閉まる音が響いた瞬間、俺は額に手を当てて大きく溜め息を吐く。全身の力が抜け落ちる感覚だ。
(やっと行ったか。毎回これだ。……面倒くせぇ)
思わず本音が漏れる。これが学園の王子様の実態だ。優しい笑顔の裏には常にストレスという名のモンスターが蠢いている。最近は特に女子からの猛烈アピール攻撃が日々エスカレートし、俺の神経を確実に削っていく。
(ヤバいな、そろそろ限界が近い。明日の休みは久しぶりに例の憩いの場所に行くか。癒されないと死ぬ。……本当はテスト勉強に充てたいところだが)
明日の休日の予定を頭の中で組み立てていたところ、再びノックなしに勢いよく生徒会室のドアが開いた。今度は運動部のマネージャー連合の面々である。いや、後ろには文化部の奴もいた。
「篠宮先輩! 大変です! バレー部の倉庫の鍵が壊れちゃって! 道具が出せません!」
「篠宮! 聞いてくれ!! うちの陸上部の練習用具が盗まれたんだ! 犯人が誰か探してくれ!」
「美術部の学園祭展示準備が全然進んでなくて……」
一斉に降り注ぐ嘆願の嵐。まさに怒涛の如し。俺の理性が静かに崩壊していく音が聞こえた。
「みんな落ち着いて。一つずつ順番に教えてくれるかな?」
俺は精一杯穏やかな声を出し、笑顔を崩さなかった。来週も王子様でいるためには、明日は絶対に癒される必要がある。俺は確信した。
さもなければ学園の王子様の仮面が剥がれ落ち、本来の凶暴で怠惰な一面が全世界に露呈してしまうだろう。それは俺の社会的抹殺を意味していた。それは何としても避けなければならない。
その時の俺はまだ知らなかった。明日俺が密かに訪れる憩いの場所で、俺を更なる災厄に巻き込む出会いが待ち受けていることを。
そしてその出会いが、俺の鬱屈した学園生活に思わぬ変化をもたらすことになるなどとは、微塵も予想だにしなかったのである。