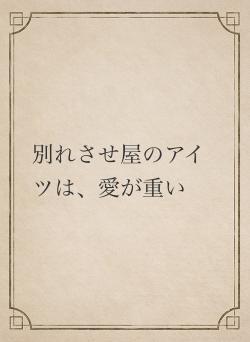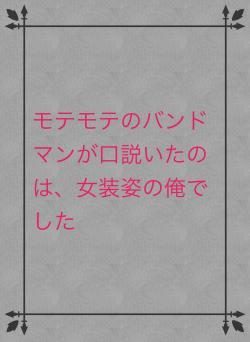月末の金曜日。
「あ、宮ちゃんおはよー」
「おはよう」
席に着くなり仁科がルンルンで話しかけてくる。
「宮ちゃん、今なら俺に言ってもいいよ!」
「え、何が?」
「ほら、今日あれじゃん」
「あれ?…あ、今日ハロウィンか!」
よく見ると仁科の机の上には大量のお菓子がある。
「そう。言っちゃってよ、さぁ!」
「あはっ!普通言われるより言いたいんじゃねーの?」
「俺たちはねー、すでにいろんな人に言ってほしいってお願いされ過ぎて、逆に言われたいんだよー」
峰岸が話に加わってきた。
「つまりお前らは今、お菓子いっぱい持ってんだ」
「そゆことっ!」
「人からもらったお菓子を俺にくれていいの?」
「…みんなの気持ちは俺だけがもらったから、これは誰にあげてもいいんだよ」
「おい、ドヤ顔してるけど、それ俺の言葉パクってるから」
「あはは、イケメン発言してみたくて」
「なになにー、みやみやそんなかっこいいこと言ったのぉ?」
「もう峰岸までイジってくんなよ」
昼休み、屋上で弁当を食べる延岡、木津、俺の3人。
話し声が聞こえる距離でパンを食べている3年の女子たちが何やら盛り上がっている。
「メッセージ見てくれたかな!?」
「まだ食べてないかもよ」
「あーほんと仁科くんかっこいい。いつ話しかけても愛想良いしさ、やばいわぁ」
「峰岸くんのあの雰囲気も最高だよね」
「私は断然砂田くんかな!あのクールで大人っぽい感じ最高。お菓子もらってくれるか不安だったけど、無事受け取ってくれたし」
どうやら、あの先輩たちはモテモテ3人組にハロウィンのお菓子を渡したみたいだ。
「なんかバレンタインみたいになってるな」
「そのうちハロウィンは仮装登校オッケーになるかもな!」
「あれ、延岡って去年バスケ部でハロウィン楽しんでなかったっけ?」
「あー、なんか先輩マネージャーがコスプレで更衣室に来て、お菓子配ってくれたな。弓道部は何もなく?」
「去年は特に。今年も…え、律樹なんか用意してる?」
「してるわけねーじゃん。え、袴着て練習する?コスプレ的な」
「いや、コスプレ感ゼロだからそれ」
5、6時間目は、文化祭の準備だった。俺や延岡含む制作チームは、先日決めた室内のレイアウトを元に内装デザインを考えていた。
「デザインつっても基本真っ暗だよな?黒ベースに赤とか散らす感じ?」
「赤や紫のライトで照らしたいな」
「洋風にするか和風にするかで変わるくない?」
「そもそもそこのコンセプトは、クラス全体で決めるとこじゃない?」
「確かに。仁科たちに相談して、みんなで決めるようにしようか」
「どっちにしろ段ボールや机はたくさん必要だよな」
「誰か2号館の準備室に使える段ボールあるか確認してきてほしーい」
「俺行くよー」
「宮、ありがとー!」
誰もいない2号館の廊下を1人歩いていた。
ー準備室久々だな。去年の文化祭の時は、よく来てたけど。
「宮ちゃん…」
振り向くと仁科がいた。
「仁科、何でここ…っ」
「こっち来て…!」
「え、なに…」
急に腕を引っ張られ、準備室の中でしゃがんだ途端、後ろから耳を塞がれた。
えっ……
「えー、そうなの!?でもさぁ…」
ーあ…。
廊下から微かに元カノが友達と話す声が聞こえた。
俺が未練モードにならないようにしてくれたのかな。それとも、俺の意識が元カノにいくのが嫌だったのかな。…どっちにしろ何だよこの可愛い行動は…。
そっと仁科の手に自分の手を重ねて、ゆっくりと耳から離した。
「…!」
「ありがとう。でも、大丈夫だから。…俺いま…仁科の声しか聞こえてないから」
「…。」
強がりを言ったのかもしれない。それでも振り向いて見た仁科の顔がめちゃくちゃ不安そうで、どうにか安心させなきゃって思った。
「仁科……」
「なに?」
「トリックオアトリート…」
俺の言葉にポカンとする仁科。
「……えぇ!?い、今!?」
「ふはっ!…くれなきゃイタズラしちゃうけど?」
わざと意地悪な顔で言ってみせた。
「…ま、それは冗談だけど、そういやお菓子にっ…」
どさっ…
ーえっ…
仁科に軽く押し倒され、重ねられた段ボールの上に寝転んだ。俺に覆い被さる形になった仁科は、じっと見つめてくる。
「…宮ちゃんになら、どんなイジワルされてもいいよ…どうする?何する?」
想像すらしていなかった仁科の色気に心臓が激しくなる。
ドクドクドクッ……
目を逸らしたいのに仁科の綺麗な瞳が離してくれない。…どうしよう、吸い込まれそう…。
タッタッタ…ー
廊下から足音が聞こえ、急いで起き上がった。
ガラガラー…
「宮ー、いるー?」
ドアを開けたのは延岡だった。
「あ、いた。お、仁科もいるじゃん。衣装チームのリーダーが仁科のこと探してたぞ?」
「うん、分かった。…俺、先に戻るから在庫確認よろしく!」
「…。」
仁科は何事もなかったように出て行った。
「段ボールどうだった?」
「ごめん、まだ確認できてない」
「あ、分かった!サボってたんだろー?ここあんま人来ないもんなぁ」
「違うから…」
仁科の表情を思い出して、自分の頬が染まっていくのが分かった。あの雰囲気は冗談なんかじゃない…だってあいつ…俺のこと好きなんだから。
週明けの火曜日、SHRで担任が席替えをすると言い出した。
…席替え…。
男女別で番号くじを引き、黒板に書かれた席順と見合わせる。
えっと俺の席は…あ、ラッキー。
「はい、時間ないからさっさと移動しろー」
俺は前回と違う列の一番後ろの席になった。
「あ、みやみやの前だぁ。1学期の最初振りの前後だねぇ。よろしくねーん」
前の席は峰岸らしい。
「うん、よろしく」
周りを確認すると、仁科は窓際の2番目の席だった。
結構離れたな…。
ハロウィンの日から約2週間。その間ずっと、地味に仁科を意識し続けている俺がいる。
来週末に迫る文化祭当日に向け、各チームの準備は着々と進んでいた。
「宮ちゃん、のべくん、放送用の原稿出来た?」
「一応ざっくり出来たけど、なんかインパクトのある言葉が欲しいんだよなぁ!」
「キャッチコピー的な?」
「そーそー!恐怖の世界へお連れします、みたいなさ」
「それでもいいと思うけど。明日確認するからそれまでに考えておいてくれると助かる」
「千影ー、これ確認してほしいー」
「なにー」
衣装チームの峰岸に呼ばれ離れていった仁科。
「…。」
…仁科忙しそうだな。各チームの進捗管理して、会計係も担って、実行委員と交渉して。それなのに大変そうな素振り見せず、いつも通り誰にでも明るく接して…すげぇよな。
放課後、練習場に着くと茅野しか居なかった。
「あれ、1人?」
「あ、お疲れ様です。みんな文化祭準備で少し遅れるみたいで」
「そうなんだ。木津も30分遅れるって言ってたわ。茅野は大丈夫なの?クラスの準備」
「うちのクラス、ヨーヨー釣りやスーパーボールすくいとかなので、そこまでやることなくて。その代わり当日の朝がバタバタする予定です」
「そっか。早起き頑張んないとな」
「ですね。……あの、宮先輩…」
「ん、なに?」
「その…、後夜祭って、誰かと見る予定ありますか?」
「えっ…」
仁科の顔が頭に浮かんだ。約束した日から後夜祭のこと話してないけど、一緒に見るのは決定のままだよな?
「…クラスの奴と見ると思う」
「そうですか」
「なに、俺がぼっちかもって心配してくれた?」
「うーん、そうかもしれません。寂しいなら付き添おうかと思って」
「あはは。茅野は優しいなぁ。もしドタキャンされたら誘いに行くわ」
「…絶対ですよ?」
「あはっ、約束約束」
次の日、朝の予鈴が鳴った後、仁科にメッセージを送ってみた。
『後夜祭、一緒に見るよな?』
自分で送ったくせに、なんて返ってくるんだろうって、若干ドキドキしている。
スマホを確認したであろう仁科は、文字を打ち返さず、俺の席までやってきた。
「…もしかして、気分変わった?」
「あ、いや…再確認したくて…」
「なんだ…」
椅子の背に手を置き、耳元でこっそり伝えてくる。
「…宮ちゃん以外と見る選択肢、俺にはないよ」
ードキッ…
「…うん、分かった」
仁科からの言葉や言い方に少しずつ、ほんの少しずつ甘さが増えていくことに気付いてしまう。仲良しの峰岸や砂田も知らない仁科の特別な一面に、俺だけが触れている。
5時間目の文化祭準備中。来週から配り始めるチラシを印刷するため、仁科と職員室へ向かった。
「10枚だけB3に印刷して、廊下や壁に貼るからね」
「了解」
「にしても、このデザイン完璧。美術部の力はさすがだね!」
「だよな。しかも1日で3パターンも考えてきてくれてさ、もう神かと思ったわ」
「ありがとうございましたー。失礼します」
思ったよりも時間がかかってしまい、5時間目終了のチャイムが鳴り響いた。
「あのコピー機、結構古かったね。途中何回か停止したし」
「だな」
ふと廊下の窓から下を見ると1人で歩く元カノの姿があった。
「…。」
たまたま視界に入っただけ…。あぁ、今日も可愛いな……えっ…ー
後ろから駆けてきた3年の男子が、元カノのすぐ横にいき、頭を優しく撫でた。照れ臭そうに微笑む彼女は幸せなオーラを纏う。
…多分あれは……付き合っ…て……
「宮ちゃん、どうしたの?」
立ち止まっている俺に仁科が声をかける。
「…っ!」
窓の外を見る俺の視線をたどり、瞬時に状況を把握したと思う。
…やべ、泣きそう…。
「…宮ちゃん、ついてきて」
俺の手からチラシを奪い、歩き出した仁科。
誰も居ない屋上に連れてこられ、俺はすぐにしゃがみ込んだ。
「…ぐずっ…」
勝手に涙が出てくる。
そんな俺の横に心配そうに仁科はしゃがみ、「…ハンカチ使う?」と言ってくれたが、首を横に振った。
あぁ、ほんと情けねぇな。こんなことで泣くとかダサ過ぎ…。
「…1人になりたいなら、俺先に教室戻るけど…居ても大丈夫?」
こんな時まで仁科は優しく寄り添ってくれる。バカみたいに女々しい俺なんかほっとけばいいのに…。
「…ごめん…俺……仁科が真っ直ぐに気持ち伝えてくれてんのに…まだ、全然……」
少しずつ仁科のこと意識してたし、だいぶ吹っ切れたって思い込んでた。
けど…まだよりを戻せる可能性があるかもって、心のどっかで期待してた自分がいたんだって痛感した。
「何で謝るの」
「…だって……つうか、俺のこと好きなの…もうやめていいかっ…」
ぎゅっ……
チラシを下に置き、仁科が俺を抱きしめた。
「……っ」
「そんなこと言わないでよ……。俺、最初に言ったよね、500日で好きにって。まだ50日しか経ってないよ?」
「…だけど俺…」
「宮ちゃんが一途で、未練ありまくりなの知ってて、俺は気持ちを伝えたから。…こんなことで諦めるような覚悟じゃないんだって…」
「……。」
「…いつか宮ちゃんの俺への気持ちが100%…ううん、120%になるぐらい好きにさせるから。だからさ、俺のこの気持ちを勝手にやめさせないで…」
俺は知ってる。誰かを本気で好きな気持ちは、簡単に無くならないって。
だからこそ、仁科の俺への気持ちが分かれば分かるほど苦しくなる。想いに応えたくても嘘をつけない自分が嫌になる。
こんなに真っ直ぐ想ってくれてんのに、何で俺…お前のこと早く好きになれないんだろう…。
風でチラシがひらひらと飛んでいく中、色んな感情が込み上がって、仁科にハグされたまま子供みたいに泣いた。