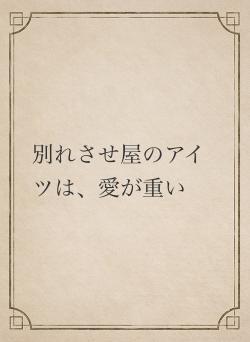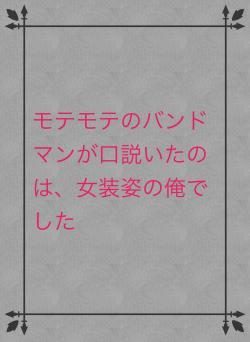始業式から数日後の放課後、部活を早めに終えた俺や木津は、茅野たち1年を連れ体育館に向かった。
我が校の伝統行事として、毎年1月に体育館で受験生である3年生を応援する【キャンドルナイト祈願】というものが実施される。
3年生はキャンドルに受験への願いを込め火を灯す。そして炎がゆらめく幻想的な空間で、日頃の勉強からくるストレスを癒すのだ。
1、2年生は事前に希望した生徒のみ参加ができ、お世話になった先輩たちの合格祈願をする。
体育館に着いた時、3年生はすでに中に入っていて、入り口前には1、2年生が列を作っていた。
「先輩たちと話せるかな」
「どうだろうな。2階の通路とかにいたらむずそう」
「どんな感じなんだろう。ワクワクするね」
「だね!」
茅野たち1年は、初めてのキャンドルナイトを心待ちにしているようだ。
「来年は俺たちのために、死ぬほど願ってくれな」
「もちろんですよ!呪い並みに願います」
「いや、怖ぇよ」
入り口でキャンドルを受け取り、火を灯した。
「どの辺に置く?」
「うーん、星マークのとこは?」
「おっけ」
キャンドルを置いたタイミングで、引退した弓道部の先輩たちが声をかけてくれた。
「木津!仁科!」
「あ、お疲れ様です!」
「お疲れ。ちゃんと願い込めてくれたかぁ?」
「もちろんですよ!呪い並に」
「あー!それ私が言ったやつ!」
「お、茅野たちも来てくれたんだ」
「お久しぶりです!」
「相変わらず茅野は宮ラブだなぁ」
「はい!?そんなことないですって!」
「でも見る目あるよ。ああいうモテ男より宮みたいな男の方が余計な心配せず安心して恋愛できるぞ」
そう言った先輩の目線の先には、仁科と砂田が女子の先輩に囲まれ、一緒に写真を撮ろうとお願いされていた。
「…。」
…仁科も来てたんだ。
「俺ら、これから2階に行くんだけど、お前らも行く?」
「え、いいんスか」
「上からの方が綺麗に見えるしな」
先輩たちと一緒に階段へ移動していると「宮ちゃん」と仁科の声がした。
「お疲れ」
「宮ちゃんやっぱり来てたんだ」
「うん。つうか、砂田はサッカー部だから分かるけど、仁科何でいんの?」
「俺は、生徒会長の合格祈願!」
…あぁ、そういや創立記念館の鍵手に入れるために仲良くなったって言ってたな。
「2階で見るの?」
「うん、弓道部のみんなで」
「…。」
「…どした?」
「一緒に見たいなぁと」
「いや、無理。久々に集まってるし」
「そうだよね、ごめんごめん」
「……後で会いに行くから」
「ありがとう!!」
開始時間になり、校長先生が挨拶を始めた。
「えー、3年生の皆さん。受験日がすぐそこに迫り、不安な気持ちや焦る気持ちもあるかと思います。時にはイライラしてしまうこともあるでしょう。そんな時、今日のこの景色を思い出してください。自分たちの願い、後輩たちの思いを信じてください。君たちなら絶対に大丈夫!!」
校長の挨拶が終わり、館内には事前に募集した教師や3年生からのリクエスト曲である応援ソングが流れ始めた。
2階の通路部分から見るキャンドルは、寒さを忘れるくらい綺麗で、あったかい気持ちになる。それと同時に、あと少しで先輩たちがいなくなってしまうことへの寂しさが募る。
「キャンドル背景にみんなで写真撮るか!」
「お、いいっすね」
「あ、私自撮り棒持ってきてます!」
「はい、茅野っち神ー!」
写真を撮り終えた俺は、一度部員達と離れ仁科を探しに1階へ降りた。
ーあ、いた…。
仁科はまた先輩に囲まれていた。さすがに声をかけに行く勇気はなくて、入り口付近の階段に座り待つことにした。
階段にも大きなキャンドルが置かれている。これは先生たちからの願いが込められているもの。
「宮ちゃん、ごめん!」
中から仁科が駆けて出てきた。
「全然。もう大丈夫なん?」
「うん」
「中で見る?」
「寒いけど、せっかく誰もいないし、ここで少し見ようよ」
「俺、去年参加してないからさ、すんごい感動してる」
「良いよな、この行事。…キャンドルの炎が揺れてんのって、焚き火とおんなしで1/fゆらぎっていう癒し効果、ストレス軽減効果があるらしい。去年参加した時校長が言ってた」
「へぇー、なんか良いね。宮ちゃんも1/fゆらぎの力持ってるってことか」
「は?どういう意味だよ」
「俺にとって宮ちゃんは癒しでもあるから」
「ごめんけど、どう考えても俺に癒し効果はねぇから。どっちかっていうと峰岸とか延岡のほうがあるくね?」
「そうかなぁ。宮ちゃんの隣にいるとさ、ドキドキもするけど、安心するんだよね。頑張んなくていい、素の俺でいいって思える」
「…仁科はさ、その…何で俺のこと好きになったの?正直、仁科に好きになられる要素が見当たらないというか…」
ずっと不思議だった。何で人気者でモテモテの仁科が、どこにでもいそうな俺を好きなのか。
「去年の体育祭で、俺と話したの覚えてる?」
「え、去年の体育祭?…ごめん、覚えてねぇかも」
「俺ね、その日朝から体調悪くてさ。前半終わった時に砂田たちと先輩たちに囲まれてたんだけど、一旦離れようとしたの。そん時に何人かの先輩が、仁科くん思ったよりノリ悪い、とか、せめて写真撮ってから抜けてよ、とか言い出して。なんとか離れた時に宮ちゃんが声かけてくれたんだよ」
「え、俺?」
「うん。体調悪そうだけど、保健室行かなくて大丈夫か?って。顔は知ってたけど話したことないのに、俺の変化に気付いてくれて、声までかけてくれてびっくりしたよ。それで、一緒に保健室まで付いてきてくれて」
「…あ!なんか思い出したかも。内容までは分かんねぇけど、保健室で話したのはなんとなく覚えてる」
「ベッドで休むことになった俺に、人気者も大変だな、みんなに優しいのすげーよ。でもさ、疲れたり体調悪りぃ時ぐらい自分の心と身体大事にしろよ、って優しく言ってくれたんだ。…その言葉にめちゃくちゃ救われた。そのことがきっかけで宮ちゃんのことを意識するようになって、気付いたら恋愛として好きになってた。同じクラスになれて、色んな一面を知ってもっと好きになった…って感じかな」
「そんな素振り全然なかったから気付かなかった」
「宮ちゃん彼女一筋で、俺からのアピールなんてガン無視なんだもん」
「え、アピールした!?」
「してたよー。宮ちゃんが彼女とケンカした話聞かされた時は、俺にしとけばいいのにって言ってみたり、弓道の試合見に行ったり…。なのに宮ちゃんってば、冗談だと思って適当に返事したり、応援に来た彼女しか見てなかったり」
「なんか…すげぇ頑張ってんじゃん」
「そうだよ!…だから、宮ちゃんには悪いけど別れたって知って、やっと俺にもチャンスが来たって思えた」
「…。」
俺が彼女との出来事に一喜一憂している間、仁科は俺に一生懸命気持ちを伝えていたのか…。
「あ、こんなとこにいた」
俺を探していた木津が外に出てきた。
「そろそろ集合写真撮る時間だから」
「もうそんな時間か。おっけ、中戻るわ」
本気の想いを聞いたら、中途半端な気持ちで返事はできないと思った。
三連休明けの朝、後ろの席の延岡に挨拶した俺は、仮眠するため机に伏せた。
「宮、寝不足?」
「うん、二十歳の集いで店の手伝い忙しくて、夜までバタバタしてた」
「そうか」
「もしチャイム鳴っても夢ん中だったら起こして」
「了解」
「宮ちゃん…」
…ん?
「…みーやちゃん、起きてー」
目を開けると仁科が顔を覗き込んでいた。
「…!?なに!?」
「次、移動教室」
「えっ…」
見渡すと教室内には誰も居なかった。
「え、でも1時間目って…」
「宮ちゃん、時計見て」
時計を見ると1時間目はすでに終わっていた。
「は!?嘘!俺、授業中ずっと寝てたの!?」
「急きょ1時間目が自習になって、のべくんが疲れてるだろうからって、気を利かせて寝させたままにしてたの」
「あ、そうなんだ…。で、何で延岡は俺を置いて行ったわけ?」
「俺が、代わりに起こしておくから先に行っていいよって言ったから」
「そっか。ごめん、待たせて」
机の中から教科書、ノートを取り出し教室を出た。
仁科と移動中の廊下で、見覚えのある後ろ姿が見えた。
…茅野か。ちょっとからかうか。
「おーい、愛莉ーっ」
俺の声に勢いよく振り返った茅野は、何故か顔が赤い。
「えっ…あ…な、何で、下の名前呼んだんですか!?…ありえないんですけど!…サイテーです…」
「え、そんな怒る!?わぁ、なんかごめんな?」
「もぉ…心臓に悪いんでやめてください」
「反省してます」
「ていうか、私の下の名前知ってたんですね」
「そりゃ、部員のフルネームくらい把握してるわ。それに愛莉って名前可愛いなって思ってたし」
「…っ」
「宮ちゃん、そろそろ行かないと」
「あ、そだな。じゃ、また放課後な」
「お疲れ様です…」
「宮ちゃん、無自覚で惚れさせにいってるよね」
「は?」
「やっぱ俺のライバルは茅野さんだな…」
「え、なんか言った?」
「別にー。…あのまま2人で教室でサボればよかったなぁ」
「…じゃあ、サボる?」
「え!?」
「なんかまだ頭回んねーし、家庭科だし大丈夫だろ。…どうする?」
「…大賛成!」
「宮ちゃん、もう少し寝る?」
教室に戻った俺に仁科は聞いてきた。
「いや、十分寝たから大丈夫。仁科、眠かったら寝てていいからな?」
「うーん、じゃあ少し寝よっかな」
そう言って延岡の席に座り、机に伏せた仁科は上目遣いで俺に言ってくる。
「寝てる間寒いし、手握りたーい」
「…は?」
「左手貸してー」
「……はぁ…」
仕方なく出した左手は、嬉しそうな笑みを浮かべた仁科の右手にぎゅっと握られた。
俺の手を握り、スヤスヤ眠る仁科の寝顔は安心しきった子供みたいだ。
ー…なのにかっこいいとかなんなんだよ。
寝顔をぼんやり見続けていたら、急に手をぐっと引き寄せられ、逆さまに見える仁科の顔が前にきて目が合った。
「…っ!」
「おはよ…」
「…おはよう」
「…。」
「…え、なんの無言?」
「…あのさ、2人きりの時だけ…下の名前で呼んでほしい」
「…へ?」
「前に一回呼んでくれたのが、今も忘れらんない…」
…ドキッ…
こんな至近距離で、そんな表情で言ってくるとか…。お前こそ無自覚に惚れさせにきてんだろ…。
「そういえば宮ちゃん、今欲しいものある?」
身体を起こした仁科は突然聞いてくる。
「え、欲しいもの?んー、なんだろ。パッと思いつかねーなぁ」
「宮ちゃん物欲ないのー?」
「いや、あるけど。そういう仁科は今何が欲しいの?」
「俺?…俺は…それは宮ちゃんが1番分かってるじゃん。え、なに、言葉で言っていいの?」
仁科は意地悪な顔を向けてくる。
あ、これって…まさか……
「宮ちゃんが欲しい…」
俺の首に手を回し、耳元で囁いた仁科の声は、いつもに増して甘くて柔らかい。
やっぱり1人でサボればよかった。雑音の無い室内じゃ、この心臓の音がバレてしまう…。
我が校の伝統行事として、毎年1月に体育館で受験生である3年生を応援する【キャンドルナイト祈願】というものが実施される。
3年生はキャンドルに受験への願いを込め火を灯す。そして炎がゆらめく幻想的な空間で、日頃の勉強からくるストレスを癒すのだ。
1、2年生は事前に希望した生徒のみ参加ができ、お世話になった先輩たちの合格祈願をする。
体育館に着いた時、3年生はすでに中に入っていて、入り口前には1、2年生が列を作っていた。
「先輩たちと話せるかな」
「どうだろうな。2階の通路とかにいたらむずそう」
「どんな感じなんだろう。ワクワクするね」
「だね!」
茅野たち1年は、初めてのキャンドルナイトを心待ちにしているようだ。
「来年は俺たちのために、死ぬほど願ってくれな」
「もちろんですよ!呪い並みに願います」
「いや、怖ぇよ」
入り口でキャンドルを受け取り、火を灯した。
「どの辺に置く?」
「うーん、星マークのとこは?」
「おっけ」
キャンドルを置いたタイミングで、引退した弓道部の先輩たちが声をかけてくれた。
「木津!仁科!」
「あ、お疲れ様です!」
「お疲れ。ちゃんと願い込めてくれたかぁ?」
「もちろんですよ!呪い並に」
「あー!それ私が言ったやつ!」
「お、茅野たちも来てくれたんだ」
「お久しぶりです!」
「相変わらず茅野は宮ラブだなぁ」
「はい!?そんなことないですって!」
「でも見る目あるよ。ああいうモテ男より宮みたいな男の方が余計な心配せず安心して恋愛できるぞ」
そう言った先輩の目線の先には、仁科と砂田が女子の先輩に囲まれ、一緒に写真を撮ろうとお願いされていた。
「…。」
…仁科も来てたんだ。
「俺ら、これから2階に行くんだけど、お前らも行く?」
「え、いいんスか」
「上からの方が綺麗に見えるしな」
先輩たちと一緒に階段へ移動していると「宮ちゃん」と仁科の声がした。
「お疲れ」
「宮ちゃんやっぱり来てたんだ」
「うん。つうか、砂田はサッカー部だから分かるけど、仁科何でいんの?」
「俺は、生徒会長の合格祈願!」
…あぁ、そういや創立記念館の鍵手に入れるために仲良くなったって言ってたな。
「2階で見るの?」
「うん、弓道部のみんなで」
「…。」
「…どした?」
「一緒に見たいなぁと」
「いや、無理。久々に集まってるし」
「そうだよね、ごめんごめん」
「……後で会いに行くから」
「ありがとう!!」
開始時間になり、校長先生が挨拶を始めた。
「えー、3年生の皆さん。受験日がすぐそこに迫り、不安な気持ちや焦る気持ちもあるかと思います。時にはイライラしてしまうこともあるでしょう。そんな時、今日のこの景色を思い出してください。自分たちの願い、後輩たちの思いを信じてください。君たちなら絶対に大丈夫!!」
校長の挨拶が終わり、館内には事前に募集した教師や3年生からのリクエスト曲である応援ソングが流れ始めた。
2階の通路部分から見るキャンドルは、寒さを忘れるくらい綺麗で、あったかい気持ちになる。それと同時に、あと少しで先輩たちがいなくなってしまうことへの寂しさが募る。
「キャンドル背景にみんなで写真撮るか!」
「お、いいっすね」
「あ、私自撮り棒持ってきてます!」
「はい、茅野っち神ー!」
写真を撮り終えた俺は、一度部員達と離れ仁科を探しに1階へ降りた。
ーあ、いた…。
仁科はまた先輩に囲まれていた。さすがに声をかけに行く勇気はなくて、入り口付近の階段に座り待つことにした。
階段にも大きなキャンドルが置かれている。これは先生たちからの願いが込められているもの。
「宮ちゃん、ごめん!」
中から仁科が駆けて出てきた。
「全然。もう大丈夫なん?」
「うん」
「中で見る?」
「寒いけど、せっかく誰もいないし、ここで少し見ようよ」
「俺、去年参加してないからさ、すんごい感動してる」
「良いよな、この行事。…キャンドルの炎が揺れてんのって、焚き火とおんなしで1/fゆらぎっていう癒し効果、ストレス軽減効果があるらしい。去年参加した時校長が言ってた」
「へぇー、なんか良いね。宮ちゃんも1/fゆらぎの力持ってるってことか」
「は?どういう意味だよ」
「俺にとって宮ちゃんは癒しでもあるから」
「ごめんけど、どう考えても俺に癒し効果はねぇから。どっちかっていうと峰岸とか延岡のほうがあるくね?」
「そうかなぁ。宮ちゃんの隣にいるとさ、ドキドキもするけど、安心するんだよね。頑張んなくていい、素の俺でいいって思える」
「…仁科はさ、その…何で俺のこと好きになったの?正直、仁科に好きになられる要素が見当たらないというか…」
ずっと不思議だった。何で人気者でモテモテの仁科が、どこにでもいそうな俺を好きなのか。
「去年の体育祭で、俺と話したの覚えてる?」
「え、去年の体育祭?…ごめん、覚えてねぇかも」
「俺ね、その日朝から体調悪くてさ。前半終わった時に砂田たちと先輩たちに囲まれてたんだけど、一旦離れようとしたの。そん時に何人かの先輩が、仁科くん思ったよりノリ悪い、とか、せめて写真撮ってから抜けてよ、とか言い出して。なんとか離れた時に宮ちゃんが声かけてくれたんだよ」
「え、俺?」
「うん。体調悪そうだけど、保健室行かなくて大丈夫か?って。顔は知ってたけど話したことないのに、俺の変化に気付いてくれて、声までかけてくれてびっくりしたよ。それで、一緒に保健室まで付いてきてくれて」
「…あ!なんか思い出したかも。内容までは分かんねぇけど、保健室で話したのはなんとなく覚えてる」
「ベッドで休むことになった俺に、人気者も大変だな、みんなに優しいのすげーよ。でもさ、疲れたり体調悪りぃ時ぐらい自分の心と身体大事にしろよ、って優しく言ってくれたんだ。…その言葉にめちゃくちゃ救われた。そのことがきっかけで宮ちゃんのことを意識するようになって、気付いたら恋愛として好きになってた。同じクラスになれて、色んな一面を知ってもっと好きになった…って感じかな」
「そんな素振り全然なかったから気付かなかった」
「宮ちゃん彼女一筋で、俺からのアピールなんてガン無視なんだもん」
「え、アピールした!?」
「してたよー。宮ちゃんが彼女とケンカした話聞かされた時は、俺にしとけばいいのにって言ってみたり、弓道の試合見に行ったり…。なのに宮ちゃんってば、冗談だと思って適当に返事したり、応援に来た彼女しか見てなかったり」
「なんか…すげぇ頑張ってんじゃん」
「そうだよ!…だから、宮ちゃんには悪いけど別れたって知って、やっと俺にもチャンスが来たって思えた」
「…。」
俺が彼女との出来事に一喜一憂している間、仁科は俺に一生懸命気持ちを伝えていたのか…。
「あ、こんなとこにいた」
俺を探していた木津が外に出てきた。
「そろそろ集合写真撮る時間だから」
「もうそんな時間か。おっけ、中戻るわ」
本気の想いを聞いたら、中途半端な気持ちで返事はできないと思った。
三連休明けの朝、後ろの席の延岡に挨拶した俺は、仮眠するため机に伏せた。
「宮、寝不足?」
「うん、二十歳の集いで店の手伝い忙しくて、夜までバタバタしてた」
「そうか」
「もしチャイム鳴っても夢ん中だったら起こして」
「了解」
「宮ちゃん…」
…ん?
「…みーやちゃん、起きてー」
目を開けると仁科が顔を覗き込んでいた。
「…!?なに!?」
「次、移動教室」
「えっ…」
見渡すと教室内には誰も居なかった。
「え、でも1時間目って…」
「宮ちゃん、時計見て」
時計を見ると1時間目はすでに終わっていた。
「は!?嘘!俺、授業中ずっと寝てたの!?」
「急きょ1時間目が自習になって、のべくんが疲れてるだろうからって、気を利かせて寝させたままにしてたの」
「あ、そうなんだ…。で、何で延岡は俺を置いて行ったわけ?」
「俺が、代わりに起こしておくから先に行っていいよって言ったから」
「そっか。ごめん、待たせて」
机の中から教科書、ノートを取り出し教室を出た。
仁科と移動中の廊下で、見覚えのある後ろ姿が見えた。
…茅野か。ちょっとからかうか。
「おーい、愛莉ーっ」
俺の声に勢いよく振り返った茅野は、何故か顔が赤い。
「えっ…あ…な、何で、下の名前呼んだんですか!?…ありえないんですけど!…サイテーです…」
「え、そんな怒る!?わぁ、なんかごめんな?」
「もぉ…心臓に悪いんでやめてください」
「反省してます」
「ていうか、私の下の名前知ってたんですね」
「そりゃ、部員のフルネームくらい把握してるわ。それに愛莉って名前可愛いなって思ってたし」
「…っ」
「宮ちゃん、そろそろ行かないと」
「あ、そだな。じゃ、また放課後な」
「お疲れ様です…」
「宮ちゃん、無自覚で惚れさせにいってるよね」
「は?」
「やっぱ俺のライバルは茅野さんだな…」
「え、なんか言った?」
「別にー。…あのまま2人で教室でサボればよかったなぁ」
「…じゃあ、サボる?」
「え!?」
「なんかまだ頭回んねーし、家庭科だし大丈夫だろ。…どうする?」
「…大賛成!」
「宮ちゃん、もう少し寝る?」
教室に戻った俺に仁科は聞いてきた。
「いや、十分寝たから大丈夫。仁科、眠かったら寝てていいからな?」
「うーん、じゃあ少し寝よっかな」
そう言って延岡の席に座り、机に伏せた仁科は上目遣いで俺に言ってくる。
「寝てる間寒いし、手握りたーい」
「…は?」
「左手貸してー」
「……はぁ…」
仕方なく出した左手は、嬉しそうな笑みを浮かべた仁科の右手にぎゅっと握られた。
俺の手を握り、スヤスヤ眠る仁科の寝顔は安心しきった子供みたいだ。
ー…なのにかっこいいとかなんなんだよ。
寝顔をぼんやり見続けていたら、急に手をぐっと引き寄せられ、逆さまに見える仁科の顔が前にきて目が合った。
「…っ!」
「おはよ…」
「…おはよう」
「…。」
「…え、なんの無言?」
「…あのさ、2人きりの時だけ…下の名前で呼んでほしい」
「…へ?」
「前に一回呼んでくれたのが、今も忘れらんない…」
…ドキッ…
こんな至近距離で、そんな表情で言ってくるとか…。お前こそ無自覚に惚れさせにきてんだろ…。
「そういえば宮ちゃん、今欲しいものある?」
身体を起こした仁科は突然聞いてくる。
「え、欲しいもの?んー、なんだろ。パッと思いつかねーなぁ」
「宮ちゃん物欲ないのー?」
「いや、あるけど。そういう仁科は今何が欲しいの?」
「俺?…俺は…それは宮ちゃんが1番分かってるじゃん。え、なに、言葉で言っていいの?」
仁科は意地悪な顔を向けてくる。
あ、これって…まさか……
「宮ちゃんが欲しい…」
俺の首に手を回し、耳元で囁いた仁科の声は、いつもに増して甘くて柔らかい。
やっぱり1人でサボればよかった。雑音の無い室内じゃ、この心臓の音がバレてしまう…。