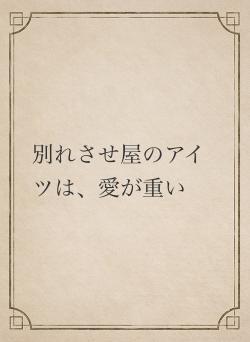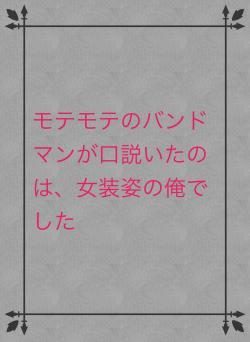今日から待ちに待った冬休み。昼過ぎまで店の手伝いをした俺は、仁科との待ち合わせ場所へ急いだ。
待ち合わせ場所には、すでに仁科が待っていた。遠くからでもすぐに仁科を見つられた自分がいて、それだけ仁科の存在が特別なんだと気付いてしまう。
「お待たせ」
「お疲れ様!お店大丈夫だった?」
「うん、クリスマスつっても平日だし、そんな忙しくなさそうだった」
「そっか。…じゃあ、行こっか」
「…うん」
屋外のクリスマスマーケットに来た俺たちは、お洒落に装飾された飲食店や雑貨屋に目を輝かせる。
「やべー!テンション上がるな」
「うんうん!ひと通りどんな店がある見てみよう」
「だな」
様々な店を見て回り、ホットドッグやスープを飲食スペースに座り食べ始めた。
「ふぅー、あったまるー」
「うまっ」
「宮ちゃん、それ一口ちょーだいっ」
「…いいけど」
食べかけのホットドッグを仁科の口に運びながら、これは間接キスになんのかな、とか考えている。
「うん、美味しい!」
意識してんのは俺だけか…。
「今日あったかくて良かったよなぁ」
「だねー。明日から急に寒くなるって言ってたから、宮ちゃん体調気をつけてね」
「俺そんなか弱くねーから。あん時はたまたまで」
「ふふっ。先週の今頃は関西にいたのが信じられないなぁ。あ、みっちゃんに昨日会ったんだよね?」
「うん、安定の可愛さ、癒しでした。お土産と一緒にクリスマスのお菓子も渡したんだけど、ありがとう!って抱きついてきてくれて。あ、もう俺この子のために生きるって思ったわ」
「あはは。みっちゃんに好きな人出来たら、宮ちゃんヤバそう」
「想像したくねぇ…。…そういや修学旅行中、告られたりしなかったの?」
「…え…それ、クリスマスに聞いちゃう?」
「なんだよそれ。クリスマスだから聞いたんだよ」
「えー。うーん…一緒にアトラクション乗ろうとかそういう誘いはあったけど、告白は直接じゃなかったというか」
「ん?どゆこと?」
「違う方面に行った組の子からメッセージとか電話で告白された…かな」
「え!?まさかの遠距離告白!?やべーじゃん。それ完全に修学旅行ハイになってんじゃん」
「びっくりだよね。まぁ、断りやすかったけど。…宮ちゃんは、なかったの?」
「…クリスマスに悲しい質問すんな」
「あはっ、安心した」
「いや、何の安心だよ。人生最後の修学旅行で告られないって…男としてどうなんだ」
「木津くんも言ってたけど、宮ちゃんはモテるよ」
「仁科に言われてもなぁ」
「褒めてるのにひどいなー。…ホットココア買ってくるけど、宮ちゃんも飲む?」
「飲みたい!」
「じゃあ、買ってくるから待ってて」
仁科が告白を断ったことに安心した自分がいた。不安に思う権利なんて俺にはないのに。
次の目的地である高層タワーに着いた俺たちは、展望台行きのエレベーターに乗り込んだ。中はカップルだらけで場違いな気もしたが、階数表示の数字が大きくなるたびに胸を躍らせる自分がいる。
「うぉー!!めっちゃ綺麗じゃん!」
「すっごいね!雲も少なくて、遠くの光までしっかり見える」
地上67階からの夜景は、心が浄化されるほど綺麗だった。夜景なんて女子を喜ばせるために男が連れてくる場所だなんて思っていたが、男同士で見る夜景は想像以上に良くて、幸せな気持ちになった。
もし俺たちが付き合ってたら、他のカップルみたいに手を繋いで、もっと寄り添い合って見ていたんだろうな…。
「この景色、宮ちゃんと見れて良かった」
優しいトーンで言われ、俺も何か伝えなきゃと思ったが、うまく言葉がまとまらない。
…ふわっ
仁科が俺の首に鞄から取り出したマフラーをかけた。
「え…」
「クリスマスプレゼント」
「ありがと。…あ、俺も用意してて…」
ラッピングされた袋を手渡した。
「大したものじゃなくてごめんなんだけど…」
「開けていい?」
「だめ。帰ってから開けて」
「えー、意地悪じゃん」
「あはっ、宮サンタは優しくねーから」
プレゼントを交換し、夜景に満足した俺たちはエレベーターに向かう。
「…あっ」
「…んっ!?」
突然手を引かれ、誰もいないトイレ近くに連れて行かれた。
「なに!?どしたの?」
「…宮ちゃんの元カノがいて…」
「えっ……いや、俺もう大丈夫…なんだけど」
「いや、うん、それは分かってんだけどさ…吹っ切れててもやっぱ見ちゃうじゃん?知り合いいたら見るのと同じで。…今日は、俺だけを見ててほしいから……宮ちゃんが帰って思い出すのは、俺と食べた物、俺と見た景色、俺と行った場所…俺の表情だけにしてほしいんだよ」
「…。」
…仁科の独占欲が俺にだけ向けられている。それがこんなに嬉しいなんて…。
頬を染め、照れている仁科の頬を両手で包んだ。
「ばーか。誰に会おうが、仁科のことしか記憶に残らねぇよ」
「…宮ちゃん」
「腹減った。早く飯食いに行こうぜ」
「…うん!」
夜ご飯を食べ終え、駅までゆっくり歩く俺たちは、どこか寂しげな雰囲気だ。
「年内に会うのは、今日が最後だね」
「そうだな」
「まぁ、年明けたらすぐ学校で会えるし、しんみりせずにお別れしよっかな」
「…。」
新年が来るなんてただ日にちが過ぎていくだけなのに、どうして年内にやり残したことはないかと考えちゃうんだろう。俺に年内やり残したことがあるとすれば、これぐらいしか思い浮かばない。
「…あのさ、仁科」
「ん?」
「…俺、ちゃんと仁科のこと考えてるから…だから、もう少しだけ返事待ってほしい…」
「……うん、ありがとう。何日でも待つよ」
仁科に想いを伝えられてからもうすぐ100日。少しずつ、だけど確実に進んでいるこの関係。
来年は仁科にだけ向き合いたい、そう願った2人で過ごしたクリスマス。
年が明け、休みモードが抜けないまま今日から3学期だ。
極寒の体育館では始業式が行われ、俺は眠い目を必死で開けながら、前に並ぶ峰岸の後ろ姿をボーッと見ていた。
HR後、延岡が俺の席に来る。
「宮ー、昼飯行こうぜー」
「おー」
「のーべたちご飯行くのー?」
峰岸が振り向き聞いてくる。
「うん」
「俺も行きたぁい」
「おー来い来い。な、宮」
「うん、普通にファミレスでいいなら」
「ありがとぉ。ファミレス好き好きー」
「仁科誘わなくて大丈夫か?」
「千影は予定あるみたい」
「…。」
延岡たちと別れ、家に帰り着いた俺は自宅玄関ではなく、美容院の入り口へ向かった。
「ただいまー」
「あ、リツおかえり」
「おかえり!」
母さんの横に制服姿の仁科が立っている。
仁科はカフェのバイトを辞め、今月から我が家の美容院で働くことになった。年始の営業は明日からのため、今日は業務について母さんからマンツーマンで教わる時間を設けたらしい。
「いいとこに帰ってきたわ!これからシャンプーの練習したいから、リツ練習台になって」
「いいけど、母さんが練習台になった方がいいんじゃねーの?長い髪の方が難しいし」
「あー確かにね。じゃあ、リツが横で教えてあげてね」
「え、宮ちゃんもシャンプーしたことあるの!?」
「あたりめーだろ。ほら、練習すんぞ」
「お湯の温度こんくらいが目安だけど、お客様に湯加減大丈夫か確認してな」
「はい」
「シャンプーは最初の予洗いが大事だから、地肌までしっかり濡らして、汚れ取るイメージで」
「分かりました」
「なんで敬語なんだよ」
「いや、一応仕事中だし」
「俺には使わなくていいって」
「そうよ、仁科くん。ちなみに私も仕事中以外は、友達のお母さんとして接してね!」
「ありがとうございます」
練習が終わり、3人で2階の自宅に上がった。
「仁科くん、夜ご飯食べていって」
「え、いいんですか!?」
「もちろんよ。今日お父さんは新年会で帰り遅いから安心して」
「ありがとうございます!」
「準備するから、リツの部屋でゆっくりしてて」
部屋に移動し、いつもの帰った時の癖でシャツを脱ぎ始めた俺に「え、宮ちゃん着替える?」と仁科は少し驚いてる。
「部屋着に着替えようかなって。だめだった?」
「いや、全然大丈夫…だけど」
「別に体育の時に着替えんのと一緒じゃん。何で気まずそうな顔すんだよ」
「…一緒じゃないから」
「…え?」
「好きな人の部屋で2人きりになって、目の前で着替えられたら…意識するでしょ」
…なんだよそれ…。
「……仁科って、俺とキスしたいとか思うの…?」
俺の問いかけに、仁科はじっと見つめてきながら答える。
「したいよ。キスも…それ以上のこともしたいと思ってるよ…」
…ドクンッ…
ー…それ以上のこと…。
「だからそれも含めて、俺と付き合えるか考えてほしい」
「……わかった」
夕飯が出来上がり、リビングへ行くと渚がダイニングテーブルに座っていた。
「あ、渚くん!久しぶり」
「こんばんは、お久しぶりです」
「仁科くん、ナギの前に座ってねー」
「ありがとうございまーす!」
我が家のリビングで、仁科と一緒に飯を食っていることが不思議で仕方ないし、すでに母さんや渚の中に溶け込んでいるのが流石だなと思う。
「そういえば、仁科くんって彼女いるの?」
「母さん、そういう質問やめろって」
母さんの隣に座る渚は、冷静に注意する。
「えー、だってこんなイケメンなら彼女いるって思うじゃない」
「いませんよ」
「えー勿体ない!あれね、モテ過ぎて逆に選べないってやつよ!」
「いえいえ、そんな」
「リツもねぇ、モテないけどこれでも一応夏頃までは彼女いたのよ。可愛い子だったから別れて残念だったけどねぇ」
…おいっ、仁科の前でその話すんなよっ!
チラッと横を見たが、特に気にしていない様子だった。
「遅くまでお邪魔しました」
「いえいえ。これからよろしくね!気をつけて帰って」
「はい、失礼します」
自転車を押しながら仁科を駅まで送る俺は、クリスマスにもらったマフラーをぐるぐる巻いてる。
「仕事、大丈夫そ?」
「まだ他のスタッフの人と会ってないから、何とも言えないけど、頑張れる気がする。お母さんも宮ちゃんも、教えるの上手くて覚えやすかったし」
「ふっ、シャンプーや雑用以外俺に教えられることはねぇけどな。あ、これからは母さんに髪切ってもらえば?多分、バイトの立場でもタダで切ってくれると思うぞ」
「いや、それはさすがにだめでしょ」
「うちの母さん、メンズのカットもめちゃくちゃうめぇから。俺もなぎも反抗の時でさえ、他の人に任せず母さんに切ってもらったぐらい。ま、多分母さんの方から言ってくると思うわ」
「ほんと宮親子は優しさの塊だなぁ。…色々迷惑かけると思いますがよろしくお願いします!」
「こちらこそ貴重な人材に感謝です」
「あはは。…じゃあ、また明日」
「うん、また学校で」
翌日、朝のHRでは席替えが行われた。
このクラスで最後の席替え…。仁科と近くになれっかな…。
くじ引きの結果、俺は延岡と前後になりハイタッチをした。
「うぇーい!」
「俺らクジ運強すぎ」
横の列を見ると女子を1人挟んだ席に仁科がいた。
…良かった、まぁまぁ近いな。
10分休憩中、俺と仁科の間に座る女子が仁科に話しかけていた。
「…その子がカフェに行ってみたけど居なかったって言ってたよ」
「あー、カフェのバイト辞めたんだよ」
「そうなの!?え、じゃあ他のバイト始めたんだ」
「うん」
「え、何のバイト?」
「んー、まだ始めたばっかだから慣れるまで内緒っ!」
「…。」
やりとりを聞いた俺は、緩む口元を隠した。
…2人だけの思い出がどんどん増えていく。それに比例して俺の気持ちも変化していってる。
付き合いたいのか、好きなのか、キスしたいのか…。その答えに気付く日は近づいている。