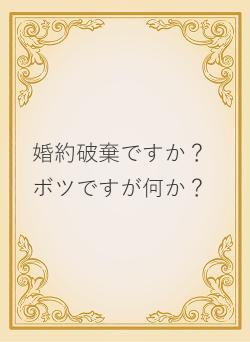小学校に上がっても、中学に行っても、俺達は何も変わらなかった。
クラス替えで離れても休み時間には自然と合流していたし、部活が違っても帰り道は一緒だった。
「お前ら、ほんといつも一緒だな」
そう言われるたび、いつからか俺は少しだけ居心地が悪くなった。
特別だと決めつけられるのが、怖かったのかもしれない。
俺達はそんな友人たちに、いつも同じ返しをした。
「腐れ縁だから」
その言葉が便利だったんだ。
深掘りされないし、笑い話で終わる。
腐れ縁。
切れないけど、誇るほどでもない。
依存してるわけじゃない、という顔ができる。
本当は、切れる想像なんてしたこともなかったくせに。
高校三年の進路相談の日、担任に聞かれた。
「大学、誰かと一緒に受けるのか?」
「別に……」
そう答えた直後、悠人と目が合った。
少し照れたように笑われて、胸の奥が妙にざわついた。
結局、同じ大学を受けた。
合格発表の日、電話越しに聞いた悠人の声は、いつもより少し高かった。
「また一緒かよ!!」
それを聞いて、そんな憎まれ口を叩きながらも、どこかほっとした自分がいた。
それが当たり前だと思っていた。
疑う理由が、どこにもなかった。
大学に入る前の春休み。
二人で歩いた夜道を、今でも覚えている。
コンビニの前で立ち止まって、どうでもいい話を延々としていた。
将来のこと。
やりたいこと。
結局、何一つ決まらなかった。
「まあ、なんとかなるだろ」
悠人はそう言って笑った。
俺も頷いた。
そのときの距離は、腕が触れるくらい近かった。
近すぎて逆に意識しない、俺達にとっては普通の距離。
その距離が、ずっと続くと思っていた。
でも今なら分かる。
当たり前は、意識した瞬間に形を変える。
あの頃の俺は、悠人の名前を呼ぶことを「選択」だと思っていなかった。
呼ばない未来なんて、想像もしていなかった。