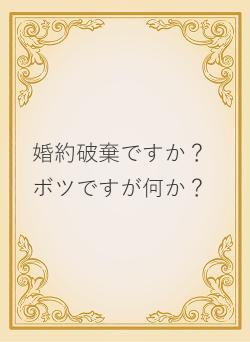名前を呼ぶ、という行為について、特別何かを考えたことはなかった。
呼びたいと思った瞬間に、声が出ていた。
それがあいつ──浅島悠人《あさじまゆうと》だった。
「はやとー!!」
幼稚園の園庭で、砂場の端に座っていた俺を呼ぶ声。
振り返ると、悠人が両手を振っていた。なぜかいつも、全身で。子犬のように。
あの頃の俺たちは、特別に仲良くなろうとしたわけじゃない。
同じクラスで、席が近くて、帰る方向が同じで。
気づいたら、いつも一緒にいただけだ。
それなのに、悠人が呼ぶ俺の名前は、その頃から特別、やけに大きく聞こえた。
「隼人《はやと》!!」
転んだとき。
先生に叱られたとき。
知らない子に囲まれて、どうしていいか分からなくなったとき。
その声が聞こえると、不思議と泣かずにいられた。
だから俺も、悠人の名前を呼んだ。
「悠斗」──って。
特に意味なんてなかった。
ただ、呼べば振り返ってくれると知っていたから。
――名前を呼ぶ距離なんて、考えたこともなかったんだ。