成英大学心理学部教授・関谷和樹氏による論文
「空間に残る感情痕跡、死の場所と心理的投影」より抜粋
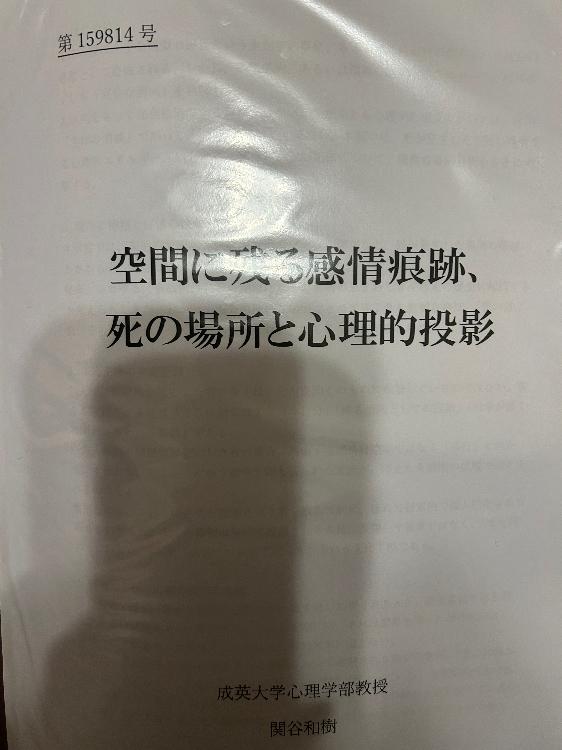
(論文表紙)
人は死をもって完全に消失するわけではない。
少なくとも心理学的観点においては、死は「肉体の消滅」であって、「感情の消滅」ではない。
本研究では、交通事故現場、住居内、自室、浴室、車内など、死が発生した場所の種類にかかわらず、共通して残留する感情の性質に着目した。
調査の結果、場所ごとの差異よりも重要なのは、「死の直前、その人物が最も強く意識していた対象」であることが示唆された。
例えば、住居内で死亡した者の多くは、その空間そのものに執着しているのではない。
彼らが固着させるのは「ここに居るはずだった自分」「帰る場所としての認識」「日常が続くはずだったという確信」である。
一方、車内や移動中に死亡した者の場合、残留する感情は空間ではなく「移行」に向かう。
すなわち、どこかへ向かう途中で断ち切られた意識が、停止した瞬間の状態で固定されるのである。
重要なのは、これらの感情が怨念という形を取る以前に、極めて日常的で個人的なものであるという点だ。
多くの事例において観測されるのは、復讐心や悪意ではなく、「まだ終わっていない」「本来は続いているはずだった」という未完了感である。
この未完了感が、場所や物品に投影され、繰り返し知覚されるとき、第三者はそれを怨念、あるいは怪異として認識する。
しかし実際には、それは意思を持った存在ではなく、感情が行き場を失った結果として生じる心理的残滓に過ぎない。
ゆえに、事故物件や曰く付きとされる車両において観測される異常現象は、「そこに何かがいる」のではなく、「そこに、終われなかった感情が留まっている」と理解すべきである。
死者は何かを伝えようとしているのではない。
ただ、自らの終わりが完結していないことを、同じ空間に入った人間の感情を通して、反射的に再生しているだけなのである。
「空間に残る感情痕跡、死の場所と心理的投影」より抜粋
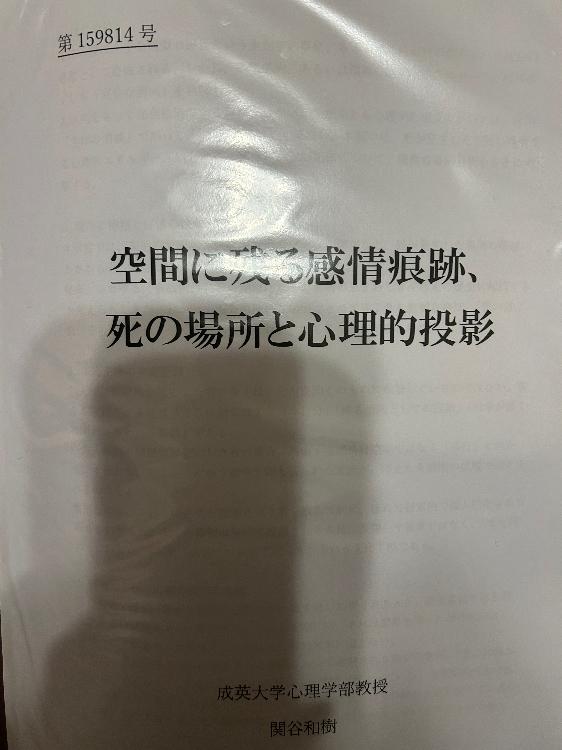
(論文表紙)
人は死をもって完全に消失するわけではない。
少なくとも心理学的観点においては、死は「肉体の消滅」であって、「感情の消滅」ではない。
本研究では、交通事故現場、住居内、自室、浴室、車内など、死が発生した場所の種類にかかわらず、共通して残留する感情の性質に着目した。
調査の結果、場所ごとの差異よりも重要なのは、「死の直前、その人物が最も強く意識していた対象」であることが示唆された。
例えば、住居内で死亡した者の多くは、その空間そのものに執着しているのではない。
彼らが固着させるのは「ここに居るはずだった自分」「帰る場所としての認識」「日常が続くはずだったという確信」である。
一方、車内や移動中に死亡した者の場合、残留する感情は空間ではなく「移行」に向かう。
すなわち、どこかへ向かう途中で断ち切られた意識が、停止した瞬間の状態で固定されるのである。
重要なのは、これらの感情が怨念という形を取る以前に、極めて日常的で個人的なものであるという点だ。
多くの事例において観測されるのは、復讐心や悪意ではなく、「まだ終わっていない」「本来は続いているはずだった」という未完了感である。
この未完了感が、場所や物品に投影され、繰り返し知覚されるとき、第三者はそれを怨念、あるいは怪異として認識する。
しかし実際には、それは意思を持った存在ではなく、感情が行き場を失った結果として生じる心理的残滓に過ぎない。
ゆえに、事故物件や曰く付きとされる車両において観測される異常現象は、「そこに何かがいる」のではなく、「そこに、終われなかった感情が留まっている」と理解すべきである。
死者は何かを伝えようとしているのではない。
ただ、自らの終わりが完結していないことを、同じ空間に入った人間の感情を通して、反射的に再生しているだけなのである。



