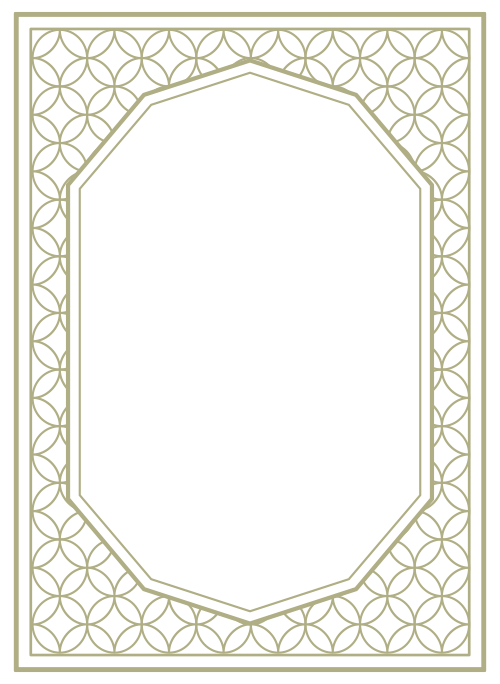「チェルシー、そっちに行ったぞ!」
とある戦場で、クライブの大きな声が響いた。
「えっ、ちょ!? まってまって、あたし、今詠唱中で……って、今ので魔力が散っちゃったじゃん!」
「ティト、チェルシーの援護を!」
「無茶言わないでくれ! 見ての通り、僕は今、三匹を相手にしているんだ!」
「ああもうっ! なら、私がやるしかないじゃない。スカウトなのに!」
ルルカは文句を言いつつ、両手に持つ短剣で、チェルシーに迫る魔物の首を切り裂いた。
「チェルシー、早くしろ!」
「う、うん!」
その間にチェルシーは再び詠唱をして、ティトに群がる魔物を蹴散らそうとするが……
「フレアストーム!」
「うわっ!?」
炎の嵐が吹き荒れて、魔物が炭と化す。
ただ、ティトも巻き込まれそうになっていた。
際どいタイミングで回避したものの、危うく魔物と同じ運命を辿るところだ。
「おいっ、なにをしているんだよ!? まだ僕がいただろう!?」
「だって、今のはクライブが……」
「そもそも、もっと早く詠唱してくれればよかったんだ!」
「そ、そう言われても、ティトが焦らせるようなことを言うから……」
「言い争いをしている場合じゃない、次が来るぞ! 集中しろ!」
クライブの強い声に、二人は渋々言い争いを止めた。
それぞれ戦闘に集中する。
そして……
――――――――――
「くそっ、なんでこんなことに!」
魔物の住処となっていた洞窟を制圧して、野営地に戻り……
クライブは地面を強く殴りつけた。
「いつもと同じような任務なのに、どうして、こうもうまくいかない!?」
「ねえ、クライブ。みんな、そこそこ怪我をしているよ。治療をしてくれないかな?」
「……俺の魔力は無限にあるわけじゃないぞ」
「でも、回復魔法が使えるのはクライブだけじゃないか」
「ちっ……仕方ないな。エリア・フルヒール!」
ルルカ達は淡い光に包まれた。
時間を逆に戻したかのように、それぞれが負っていた傷が消えていく。
「ほら、これでいいだろ?」
「えっと……え、これで終わりかい?」
「なんだ、ティト。ちゃんと怪我は治したのに、不満なのか?」
「いや、しかしね……だるさとか使っちゃった魔力とか、そのままなんだけど」
「は? そんなもの、回復魔法で治せるわけがないだろう。常識でものを言え」
「いや、今までは治せていただろう? セイルの時は、体力も魔力も、全部回復してくれていた。セイルならできたのに」
「……っ……」
セイルと聞いて、クライブは顔を大きく歪めた。
ただ、それは一瞬で、すぐに平静を装う。
「……怪我が治ったのなら、それでいいだろう。魔物は討伐した。今日はもう、休むだけだ」
「まあ、そうだけどさ……」
「その前に、反省会をしない?」
チェルシーが、そう提案した。
「今日は、けっこう危ない戦いだったと思うんだよねー。なんで、こんなことになったのか? 油断はなかったか? きちんと原因を考えたおいた方がいいと思うんだけど」
「……原因ならハッキリしているだろう?」
ティトがルルカを睨みつけた。
「キミのせいだよ、ルルカ」
「えっ、ちょ……なんで私のせいになるわけ!?」
「当然だろう? 会敵するまで魔物に気づかない。罠もいくらか見逃していた。このせいで戦闘前に被害が出ていた……全部ルルカのせいだよね?」
「待って。それ、全部私のせいにされるのは心外よ。まず、あの洞窟は複雑な作りになっていて、視界が効かないの。気配で探知しようにも、小動物もたくさん混じっていたから、魔物だけを探知することは無理なのよ。罠も同様の理由で全て発見することは難しいわ」
「セイルは、僕が今言ったこと、全部こなしていたのに?」
「そ、それは……」
「本業じゃない治癒師にできたんだ。本業のスカウトにできない道理はないよね」
「……」
反論できず、ルルカは押し黙ってしまう。
すると、思わぬところから反撃が飛ぶ。
チェルシーだ。
「ってかさー、ティトもダメくない?」
「なっ……ぼ、僕のなにがダメだっていうんだ!?」
「ヘイト管理、ぜんぜんできてなかったじゃん。クライブはともかく、あたしのところまで魔物が襲ってきたんだけど? そうなる前に敵を止めるのが、タンクのティトの役割じゃん」
「ま、魔物の数が多すぎる! あれじゃあ、いくらなんでもヘイトは取り切れない!」
「前に同じようなことになった時、セイルが代わりに全部ヘイトとっていたけど、あれは?」
「うぐ……」
今度はティトが押し黙る。
「……そう言うチェルシーも反省点があるだろう?」
「へ?」
「ティトを魔法に巻き込みかけた。後衛としては、あってはならないことだ」
「それは、まあ……ごめん。でも、いつもあのタイミングで放っていたし。セイルなら、問題なく動いていたし。ってか……そもそもの原因はクライブじゃない?」
「なっ!? 俺に責任転嫁をしようというのか!?」
「だって、そうじゃん。指揮がめちゃくちゃで、敵の動きにまったく対応できてなかったじゃん。やることなすこと後手後手で、どんどん不利になるような命令ばかりされて……だから、あんなに苦戦したんじゃん」
「そ、そのようなことはない! 俺の指揮は問題なかった。指揮通りに迅速に動くことができないお前達に問題がある!」
「いや、無茶言わないでよ。秒で魔法を発動させろとか、そんな無理難題だし」
「私も……スカウトなのに、最前線で戦えとか言われたし。斥候と全体のフォローが私のメインなのに」
「僕も、全体の攻撃をカバーしろ、って言われたね。いや、どう考えても無茶だよね? だって僕は一人しかいないんだから、敵の全部をカバーするなんて、できるわけないよ」
「セイルはできていただろう!」
怒鳴り……
そして、自身の失言に気づいて、口を閉ざす。
結局のところ……
パーティーメンバーの全員がセイルに頼っていた。
セイルありきの戦いをしていた。
「……セイルがいたら、全部、今日の問題、解決していたんじゃないか?」
ティトが小さく言う。
しかし、肝心のセイルはすでにいない。
自分達が追放したのだ。
「「「……」」」
一同が暗い表情に。
もしかしたら自分達は、とんでもないミスを犯したのでは?
「……よし、現状は理解した」
クライブは話をまとめるように言う。
「ひとまず、各々に問題があることが発覚した……俺も含めて、だ」
「どうするの?」
「それは……」
チェルシーの問いかけに、クライブは押し黙る。
「あのさ……やっぱり、私達にセイルは必要だと思うんだ」
チェルシーが真面目な顔で言う。
今なら耳を傾けてくれるかもしれないと、希望を込めて言う。
「みんなはセイルはダメダメって言ってたけど、私は、そんなことはないと思う。セイルって、治癒師なのに本当に色々なことをしてて、だからこそ、私達はうまく戦うことができていたんだよ。だから、私は追放には反対だったの」
「……なら、どうしろと?」
「セイルに戻ってきてもらおう?」
「……」
「みんなで一緒に謝ろうよ。それで、また一からがんばろう? セイルがいないと、私達は……」
「それだけはない」
そう断言するクライブは、憎しみすら抱いているようだった。
「あのセイルにできていたことだ、俺達にできないはずがない」
「で、でも……!」
「今不調なのは、一人抜けたことで、各々の戦闘の感覚がズレているせいだ。パーティーの連携の調整に専念しつつ、今の状態に慣れること。そうすれば、また、元通りに戦うことができるはずだ」
「……本当にそう思うの?」
「もちろんだ。チェルシーが、どうしても不安だというのなら、追加のパーティーメンバーも考えよう。ただし、それはセイルじゃない」
「どうして、そこまで……ううん、なんでもないよ」
説得を諦めた様子で、チェルシーは俯いてしまう。
「今後の方針は、このようなところだな。ティトとルルカはどう思う?」
「僕も、それでいいよ」
「私も」
「なら、反省会はこれで終わりだ。明日に備えて、そろそろ寝るぞ」
そう、クライブは話をまとめて、自分のテントに戻る。
ティトとルルカもテントに戻る。
「……」
一人残ったチェルシーは、空を見上げて、
「……やっぱり、セイルがいないと寂しいよ。ううん、寂しいだけじゃなくて、パーティーがちゃんと機能していないよ。私、どうしたらいいのかな……?」
とある戦場で、クライブの大きな声が響いた。
「えっ、ちょ!? まってまって、あたし、今詠唱中で……って、今ので魔力が散っちゃったじゃん!」
「ティト、チェルシーの援護を!」
「無茶言わないでくれ! 見ての通り、僕は今、三匹を相手にしているんだ!」
「ああもうっ! なら、私がやるしかないじゃない。スカウトなのに!」
ルルカは文句を言いつつ、両手に持つ短剣で、チェルシーに迫る魔物の首を切り裂いた。
「チェルシー、早くしろ!」
「う、うん!」
その間にチェルシーは再び詠唱をして、ティトに群がる魔物を蹴散らそうとするが……
「フレアストーム!」
「うわっ!?」
炎の嵐が吹き荒れて、魔物が炭と化す。
ただ、ティトも巻き込まれそうになっていた。
際どいタイミングで回避したものの、危うく魔物と同じ運命を辿るところだ。
「おいっ、なにをしているんだよ!? まだ僕がいただろう!?」
「だって、今のはクライブが……」
「そもそも、もっと早く詠唱してくれればよかったんだ!」
「そ、そう言われても、ティトが焦らせるようなことを言うから……」
「言い争いをしている場合じゃない、次が来るぞ! 集中しろ!」
クライブの強い声に、二人は渋々言い争いを止めた。
それぞれ戦闘に集中する。
そして……
――――――――――
「くそっ、なんでこんなことに!」
魔物の住処となっていた洞窟を制圧して、野営地に戻り……
クライブは地面を強く殴りつけた。
「いつもと同じような任務なのに、どうして、こうもうまくいかない!?」
「ねえ、クライブ。みんな、そこそこ怪我をしているよ。治療をしてくれないかな?」
「……俺の魔力は無限にあるわけじゃないぞ」
「でも、回復魔法が使えるのはクライブだけじゃないか」
「ちっ……仕方ないな。エリア・フルヒール!」
ルルカ達は淡い光に包まれた。
時間を逆に戻したかのように、それぞれが負っていた傷が消えていく。
「ほら、これでいいだろ?」
「えっと……え、これで終わりかい?」
「なんだ、ティト。ちゃんと怪我は治したのに、不満なのか?」
「いや、しかしね……だるさとか使っちゃった魔力とか、そのままなんだけど」
「は? そんなもの、回復魔法で治せるわけがないだろう。常識でものを言え」
「いや、今までは治せていただろう? セイルの時は、体力も魔力も、全部回復してくれていた。セイルならできたのに」
「……っ……」
セイルと聞いて、クライブは顔を大きく歪めた。
ただ、それは一瞬で、すぐに平静を装う。
「……怪我が治ったのなら、それでいいだろう。魔物は討伐した。今日はもう、休むだけだ」
「まあ、そうだけどさ……」
「その前に、反省会をしない?」
チェルシーが、そう提案した。
「今日は、けっこう危ない戦いだったと思うんだよねー。なんで、こんなことになったのか? 油断はなかったか? きちんと原因を考えたおいた方がいいと思うんだけど」
「……原因ならハッキリしているだろう?」
ティトがルルカを睨みつけた。
「キミのせいだよ、ルルカ」
「えっ、ちょ……なんで私のせいになるわけ!?」
「当然だろう? 会敵するまで魔物に気づかない。罠もいくらか見逃していた。このせいで戦闘前に被害が出ていた……全部ルルカのせいだよね?」
「待って。それ、全部私のせいにされるのは心外よ。まず、あの洞窟は複雑な作りになっていて、視界が効かないの。気配で探知しようにも、小動物もたくさん混じっていたから、魔物だけを探知することは無理なのよ。罠も同様の理由で全て発見することは難しいわ」
「セイルは、僕が今言ったこと、全部こなしていたのに?」
「そ、それは……」
「本業じゃない治癒師にできたんだ。本業のスカウトにできない道理はないよね」
「……」
反論できず、ルルカは押し黙ってしまう。
すると、思わぬところから反撃が飛ぶ。
チェルシーだ。
「ってかさー、ティトもダメくない?」
「なっ……ぼ、僕のなにがダメだっていうんだ!?」
「ヘイト管理、ぜんぜんできてなかったじゃん。クライブはともかく、あたしのところまで魔物が襲ってきたんだけど? そうなる前に敵を止めるのが、タンクのティトの役割じゃん」
「ま、魔物の数が多すぎる! あれじゃあ、いくらなんでもヘイトは取り切れない!」
「前に同じようなことになった時、セイルが代わりに全部ヘイトとっていたけど、あれは?」
「うぐ……」
今度はティトが押し黙る。
「……そう言うチェルシーも反省点があるだろう?」
「へ?」
「ティトを魔法に巻き込みかけた。後衛としては、あってはならないことだ」
「それは、まあ……ごめん。でも、いつもあのタイミングで放っていたし。セイルなら、問題なく動いていたし。ってか……そもそもの原因はクライブじゃない?」
「なっ!? 俺に責任転嫁をしようというのか!?」
「だって、そうじゃん。指揮がめちゃくちゃで、敵の動きにまったく対応できてなかったじゃん。やることなすこと後手後手で、どんどん不利になるような命令ばかりされて……だから、あんなに苦戦したんじゃん」
「そ、そのようなことはない! 俺の指揮は問題なかった。指揮通りに迅速に動くことができないお前達に問題がある!」
「いや、無茶言わないでよ。秒で魔法を発動させろとか、そんな無理難題だし」
「私も……スカウトなのに、最前線で戦えとか言われたし。斥候と全体のフォローが私のメインなのに」
「僕も、全体の攻撃をカバーしろ、って言われたね。いや、どう考えても無茶だよね? だって僕は一人しかいないんだから、敵の全部をカバーするなんて、できるわけないよ」
「セイルはできていただろう!」
怒鳴り……
そして、自身の失言に気づいて、口を閉ざす。
結局のところ……
パーティーメンバーの全員がセイルに頼っていた。
セイルありきの戦いをしていた。
「……セイルがいたら、全部、今日の問題、解決していたんじゃないか?」
ティトが小さく言う。
しかし、肝心のセイルはすでにいない。
自分達が追放したのだ。
「「「……」」」
一同が暗い表情に。
もしかしたら自分達は、とんでもないミスを犯したのでは?
「……よし、現状は理解した」
クライブは話をまとめるように言う。
「ひとまず、各々に問題があることが発覚した……俺も含めて、だ」
「どうするの?」
「それは……」
チェルシーの問いかけに、クライブは押し黙る。
「あのさ……やっぱり、私達にセイルは必要だと思うんだ」
チェルシーが真面目な顔で言う。
今なら耳を傾けてくれるかもしれないと、希望を込めて言う。
「みんなはセイルはダメダメって言ってたけど、私は、そんなことはないと思う。セイルって、治癒師なのに本当に色々なことをしてて、だからこそ、私達はうまく戦うことができていたんだよ。だから、私は追放には反対だったの」
「……なら、どうしろと?」
「セイルに戻ってきてもらおう?」
「……」
「みんなで一緒に謝ろうよ。それで、また一からがんばろう? セイルがいないと、私達は……」
「それだけはない」
そう断言するクライブは、憎しみすら抱いているようだった。
「あのセイルにできていたことだ、俺達にできないはずがない」
「で、でも……!」
「今不調なのは、一人抜けたことで、各々の戦闘の感覚がズレているせいだ。パーティーの連携の調整に専念しつつ、今の状態に慣れること。そうすれば、また、元通りに戦うことができるはずだ」
「……本当にそう思うの?」
「もちろんだ。チェルシーが、どうしても不安だというのなら、追加のパーティーメンバーも考えよう。ただし、それはセイルじゃない」
「どうして、そこまで……ううん、なんでもないよ」
説得を諦めた様子で、チェルシーは俯いてしまう。
「今後の方針は、このようなところだな。ティトとルルカはどう思う?」
「僕も、それでいいよ」
「私も」
「なら、反省会はこれで終わりだ。明日に備えて、そろそろ寝るぞ」
そう、クライブは話をまとめて、自分のテントに戻る。
ティトとルルカもテントに戻る。
「……」
一人残ったチェルシーは、空を見上げて、
「……やっぱり、セイルがいないと寂しいよ。ううん、寂しいだけじゃなくて、パーティーがちゃんと機能していないよ。私、どうしたらいいのかな……?」