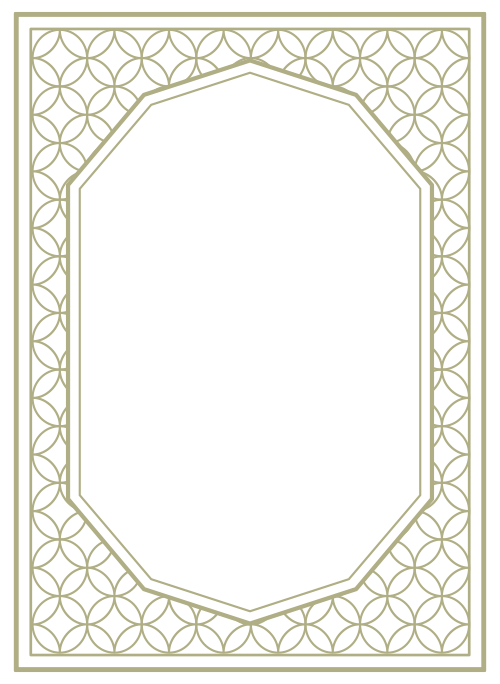「昔はまだ、希望が残っていた。だが、今はもう……」
――――――――――――
「おいっ、ぼさっとすんな! 襲撃だ!!!」
ダンジョンの奥……闇の中で魔物の目が光り、殺意が迸る。
俺は強い声で警告を促した。
「なっ……待て! ここはセーフゾーンだろう? どうして魔物が出てくる!」
防御の要であり、タンクを務めるティトが驚きの顔を見せた。
野営の準備を止めて、急いで装備を身に着けていく。
「ここは……やられた! 偽のセーフゾーン、罠よ!」
斥候。
及び、バフやデバフでパーティーの支援を担当するスカウトのルルカが舌打ちをした。
それから、こちらを睨みつけてくる。
「セイル! あなた、これくらいの罠も見抜けないの!? セーフゾーンの罠はそれほど難しいものじゃなくて、でも、とても重要性は高いから、絶対に騙されないようにって、あれほど口を酸っぱくして……」
「は? 俺はヒーラーだぞ。罠の類は、スカウトのルルカの担当だろうが。自分のミスを俺に押しつけようとするんじゃねえ。ぼさっとしてたのはてめえだろ」
「待って! 今は、言い争いをしている場合じゃないでしょ!?」
火力担当の、アタッカーである魔法使いのチェルシーが間に入ってくれた。
確かに。
彼女の言う通り、言い争いをしている場合じゃないか。
「ルルカが休憩をする間、セイルが斥候を務めるはずだったが……それについては、後で話し合えばいい。今は、魔物の撃退を優先する!」
このパーティーのリーダーであり、要。
勇者であるクライブが、そう強く言い放つ。
そして、最後……
治癒師である俺、セイルに問いかけてきた。
「セイル、魔物の種類と数は!?」
「種類は……ウルフ系だな。ランクはそこそこ。数は、めんどくせえほど……まあ、数にすると、三十前後といったところだ」
「わかった。なら、半分を足止めしろ。残り半分はティトが……」
「おいこら。前々から何度も言っているが、俺は治癒師だぞ。タンクの仕事なんて本来は……」
「そこそこのランクのウルフなら、セイルでも足止めくらいはできるだろう。なにも倒せと言っているわけじゃない、時間を稼げばいい」
「くそっ、うぜえな……まあ、ウルフなんて片手で殴れば十分か。誘い出すだけじゃなくて、ぶち殺してやるよ。やってやろうじゃねえか!」
いつもの無茶ぶりだ。
舌打ちしたい衝動を堪えつつ、俺は、拳を構えた。
――――――――――
無事、ウルフの襲撃をしのいだ。
その後、本物のセーフゾーンを見つけて、休憩の準備をして……
それから、反省会が開かれる。
「では、改めて先の件について話し合おうか。問題は誰にある?」
クライブの言葉に、チェルシーを除いた三人がこちらを見る。
「どう考えても、セイルの責任ね。セーフゾーンの罠を見抜くことができない。それに、魔物の接近に気づくのも遅い」
「だから待てや、コラ。何度も言うが、俺は治癒師だぞ? 人の話聞いてんのか? 耳に穴でも空いてんのか? 治癒師の俺が、ルルカのようなスカウトの仕事ができるわけねえだろ」
「あんた、相変わらずその口の悪さ……まあ、今はいいわ。とにかく。あなたも勇者パーティーなのだから、それくらいしてもらわないと困るのよ」
ルルカは怒りをにじませつつ言う。
「そもそも私は、ずっと活動できるわけじゃないわ。人間なんだもの、休憩が必要よ。その間、代わりを務めるべく、セイルに色々教えてきたじゃない」
「……あの適当極まりない、子供でもできるような講義のことかよ?」
「あなたねえ……!」
「足止めできないことも問題だと思うね」
ティトが呆れた様子で口を挟んできた。
「セイルは治癒師だ、タンクじゃない。それは理解しているけど、ウルフ系の魔物の足止めもできないなんて、あまりにもお粗末な話じゃないかな?」
「眼科行ってこい。ちゃんと足止めしてただろうが? 俺一人で、十匹は担当していたぞ。ってか、全部、ぶっ倒してた。あと、襲撃のタイミングや箇所を教えていただろうが」
「言葉で注意するだけなんて、誰にでもできるよね? それに、足止めしていたのは、クライブが指示した半分以下。やっぱり、お粗末な話じゃないか」
「あのな……」
呆れて声も出ない。
二十匹を一人で担当しろとか、死ねと言っているのと同意義だ。
十匹くらいならなんとかなる。
二十匹でも、戦うだけならなんとかなる。
ただ、全てのヘイトを管理するのは不可能だ。
どうしても取りこぼしが出てしまう。
「いいか、よく聞け。あれは……」
「言い訳をするな」
クライブにぴしゃりと遮られた。
「確かに、セイルは治癒師だ。だが、治癒だけに専念されても困るんだよ。俺達は、勇者パーティーなんだからな」
「だからそれは……」
「現に、ティトもルルカも、アタッカーを兼任している。チェルシーは支援だ。己の職だけではなくて、他所も担当しなければ、この先、やっていけない。それなのに、セイルは言い訳をするばかりで、なにもしていないな」
「……」
愕然とした。
なにもしていない、と言うか。
冒険に出る時は、当たり前のように先頭を歩かされて。
敵の探知。足止め。
及び、攻撃を担当するアタッカー。
ミスが発生した場合は、そのサポート。
合間を見て、指示を飛ばして……
そして、本業である治癒を行う。
それだけしているのに、なにもしていない、と見られているのか。
「クライブは……」
「なんだ?」
「……いや、なんでもない」
彼の目を見てわかった。
本気の言葉だ。
「ね、ねえ! ちょっと言い過ぎじゃない?」
気まずい空気が漂う中、魔法使いのチェルシーが必死な様子で言う。
「セイルって、けっこうがんばっていると思うよ? みんなと同じような役割をこなしつつ、それでいて、治癒師として、しっかりがんばってくれているよ。セイルがいなかったら、もっと酷いことになっていたと思う。それなのに、一方的に責めるようなことは……」
チェルシーの言葉が嬉しい。
クライブ達と違い、彼女は、俺のことをきちんと見てくれているようだ。
「チェルシー、セイルを甘やかすな」
「で、でも……」
「甘やかしてばかりだと、セイルのためにならない。きちんと自分で考えて、成長してもらわないと困る」
「……」
チェルシーは、まだなにか言いたい様子ではあったものの、クライブは聞く耳を持たない。
なにを言っても無駄と悟ったらしく、口を閉じてしまった。
「セイル、もう少しがんばってくれよ」
「もう少し……ってのは?」
「わかるだろ? 今のまま、お荷物でいられたら困るんだよ。こんなことでは、ろくに仕事を任せることができない」
「まったく……やれやれだね。セイルに比べれば、そこらの無能の方がまだ役に立つんじゃないかな? だって、無能は無能なりにがんばろうとするからね。セイルからは、そのがんばりがまったく感じられないよ」
「厳しいことを言うけど、私も同感ね。もっと真面目にやってちょうだい?」
「……おいおい、マジかよ」
三人の言葉が堪える。
パーティーを組んで、それなりの時間を一緒に過ごしてきた。
死線も乗り越えてきた。
それなのに……
彼らは、そういう認識だったのか?
俺が適当にやっていると思っているのか?
真面目にやっていないと。
手を抜いていると。
そう考えているのか?
そう悟った瞬間、なにもかも馬鹿らしくなった。
「……はは」
乾いた笑いがこぼれる。
それは誰にも聞かれることはなくて、俺の耳だけに響いて……
そして、ゆっくりと消えていった。
――――――――――――
「おいっ、ぼさっとすんな! 襲撃だ!!!」
ダンジョンの奥……闇の中で魔物の目が光り、殺意が迸る。
俺は強い声で警告を促した。
「なっ……待て! ここはセーフゾーンだろう? どうして魔物が出てくる!」
防御の要であり、タンクを務めるティトが驚きの顔を見せた。
野営の準備を止めて、急いで装備を身に着けていく。
「ここは……やられた! 偽のセーフゾーン、罠よ!」
斥候。
及び、バフやデバフでパーティーの支援を担当するスカウトのルルカが舌打ちをした。
それから、こちらを睨みつけてくる。
「セイル! あなた、これくらいの罠も見抜けないの!? セーフゾーンの罠はそれほど難しいものじゃなくて、でも、とても重要性は高いから、絶対に騙されないようにって、あれほど口を酸っぱくして……」
「は? 俺はヒーラーだぞ。罠の類は、スカウトのルルカの担当だろうが。自分のミスを俺に押しつけようとするんじゃねえ。ぼさっとしてたのはてめえだろ」
「待って! 今は、言い争いをしている場合じゃないでしょ!?」
火力担当の、アタッカーである魔法使いのチェルシーが間に入ってくれた。
確かに。
彼女の言う通り、言い争いをしている場合じゃないか。
「ルルカが休憩をする間、セイルが斥候を務めるはずだったが……それについては、後で話し合えばいい。今は、魔物の撃退を優先する!」
このパーティーのリーダーであり、要。
勇者であるクライブが、そう強く言い放つ。
そして、最後……
治癒師である俺、セイルに問いかけてきた。
「セイル、魔物の種類と数は!?」
「種類は……ウルフ系だな。ランクはそこそこ。数は、めんどくせえほど……まあ、数にすると、三十前後といったところだ」
「わかった。なら、半分を足止めしろ。残り半分はティトが……」
「おいこら。前々から何度も言っているが、俺は治癒師だぞ。タンクの仕事なんて本来は……」
「そこそこのランクのウルフなら、セイルでも足止めくらいはできるだろう。なにも倒せと言っているわけじゃない、時間を稼げばいい」
「くそっ、うぜえな……まあ、ウルフなんて片手で殴れば十分か。誘い出すだけじゃなくて、ぶち殺してやるよ。やってやろうじゃねえか!」
いつもの無茶ぶりだ。
舌打ちしたい衝動を堪えつつ、俺は、拳を構えた。
――――――――――
無事、ウルフの襲撃をしのいだ。
その後、本物のセーフゾーンを見つけて、休憩の準備をして……
それから、反省会が開かれる。
「では、改めて先の件について話し合おうか。問題は誰にある?」
クライブの言葉に、チェルシーを除いた三人がこちらを見る。
「どう考えても、セイルの責任ね。セーフゾーンの罠を見抜くことができない。それに、魔物の接近に気づくのも遅い」
「だから待てや、コラ。何度も言うが、俺は治癒師だぞ? 人の話聞いてんのか? 耳に穴でも空いてんのか? 治癒師の俺が、ルルカのようなスカウトの仕事ができるわけねえだろ」
「あんた、相変わらずその口の悪さ……まあ、今はいいわ。とにかく。あなたも勇者パーティーなのだから、それくらいしてもらわないと困るのよ」
ルルカは怒りをにじませつつ言う。
「そもそも私は、ずっと活動できるわけじゃないわ。人間なんだもの、休憩が必要よ。その間、代わりを務めるべく、セイルに色々教えてきたじゃない」
「……あの適当極まりない、子供でもできるような講義のことかよ?」
「あなたねえ……!」
「足止めできないことも問題だと思うね」
ティトが呆れた様子で口を挟んできた。
「セイルは治癒師だ、タンクじゃない。それは理解しているけど、ウルフ系の魔物の足止めもできないなんて、あまりにもお粗末な話じゃないかな?」
「眼科行ってこい。ちゃんと足止めしてただろうが? 俺一人で、十匹は担当していたぞ。ってか、全部、ぶっ倒してた。あと、襲撃のタイミングや箇所を教えていただろうが」
「言葉で注意するだけなんて、誰にでもできるよね? それに、足止めしていたのは、クライブが指示した半分以下。やっぱり、お粗末な話じゃないか」
「あのな……」
呆れて声も出ない。
二十匹を一人で担当しろとか、死ねと言っているのと同意義だ。
十匹くらいならなんとかなる。
二十匹でも、戦うだけならなんとかなる。
ただ、全てのヘイトを管理するのは不可能だ。
どうしても取りこぼしが出てしまう。
「いいか、よく聞け。あれは……」
「言い訳をするな」
クライブにぴしゃりと遮られた。
「確かに、セイルは治癒師だ。だが、治癒だけに専念されても困るんだよ。俺達は、勇者パーティーなんだからな」
「だからそれは……」
「現に、ティトもルルカも、アタッカーを兼任している。チェルシーは支援だ。己の職だけではなくて、他所も担当しなければ、この先、やっていけない。それなのに、セイルは言い訳をするばかりで、なにもしていないな」
「……」
愕然とした。
なにもしていない、と言うか。
冒険に出る時は、当たり前のように先頭を歩かされて。
敵の探知。足止め。
及び、攻撃を担当するアタッカー。
ミスが発生した場合は、そのサポート。
合間を見て、指示を飛ばして……
そして、本業である治癒を行う。
それだけしているのに、なにもしていない、と見られているのか。
「クライブは……」
「なんだ?」
「……いや、なんでもない」
彼の目を見てわかった。
本気の言葉だ。
「ね、ねえ! ちょっと言い過ぎじゃない?」
気まずい空気が漂う中、魔法使いのチェルシーが必死な様子で言う。
「セイルって、けっこうがんばっていると思うよ? みんなと同じような役割をこなしつつ、それでいて、治癒師として、しっかりがんばってくれているよ。セイルがいなかったら、もっと酷いことになっていたと思う。それなのに、一方的に責めるようなことは……」
チェルシーの言葉が嬉しい。
クライブ達と違い、彼女は、俺のことをきちんと見てくれているようだ。
「チェルシー、セイルを甘やかすな」
「で、でも……」
「甘やかしてばかりだと、セイルのためにならない。きちんと自分で考えて、成長してもらわないと困る」
「……」
チェルシーは、まだなにか言いたい様子ではあったものの、クライブは聞く耳を持たない。
なにを言っても無駄と悟ったらしく、口を閉じてしまった。
「セイル、もう少しがんばってくれよ」
「もう少し……ってのは?」
「わかるだろ? 今のまま、お荷物でいられたら困るんだよ。こんなことでは、ろくに仕事を任せることができない」
「まったく……やれやれだね。セイルに比べれば、そこらの無能の方がまだ役に立つんじゃないかな? だって、無能は無能なりにがんばろうとするからね。セイルからは、そのがんばりがまったく感じられないよ」
「厳しいことを言うけど、私も同感ね。もっと真面目にやってちょうだい?」
「……おいおい、マジかよ」
三人の言葉が堪える。
パーティーを組んで、それなりの時間を一緒に過ごしてきた。
死線も乗り越えてきた。
それなのに……
彼らは、そういう認識だったのか?
俺が適当にやっていると思っているのか?
真面目にやっていないと。
手を抜いていると。
そう考えているのか?
そう悟った瞬間、なにもかも馬鹿らしくなった。
「……はは」
乾いた笑いがこぼれる。
それは誰にも聞かれることはなくて、俺の耳だけに響いて……
そして、ゆっくりと消えていった。