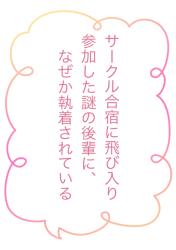土曜日。三連休の初日、しかも秋口の行楽シーズンでもあるせいか、行きの新幹線はかなり混んでいた。
自由席は全て埋まっていて、結局、自由席の通路に立ち乗りしたまま、あと15分もすれば厚海に着く。
「帰りは指定席取りましょうね」
「そうだな」
千冬の実家に泊まらせてもらう、一泊二日の厚海旅行。1時間弱の間、人混みで立ちっぱなしなのは地味に疲れっけど、旅行の高揚感がそれを上書きする。
スマホを開き、厚海の土産や観光地の投稿を眺める。
「行きたいところ、ありますか?」
「プリンは食いてぇ。あと、海鮮丼も美味そう。うわー、ソフトクリームもいいなぁ」
「ふふ。お腹空いてるんですね?」
秋らしいマスタード色のカーディガンを着た千冬が、小さく笑う。
「なら、食べ歩きメインにしましょう。ただ、夕飯は、父と母が張り切って作ると思うので、食べ過ぎないようにしてください」
「ありがてぇけど、なんか悪ぃな。お土産、こんなもんしか買ってきてねぇけど…」
「あ、いいんです!全然気にしないでください。父も母も、料理が好きなんです」
「へぇ?通りで、千冬の料理も美味ぇもんな」
「そ、そうですか?」
「おう、毎日食べても飽きねぇと思う」
「え」
「ん?」
「…ふふ、それなら良かったです」
千冬は、大学入学以来、半年ぶりの帰省らしい。
そのせいか、今日は朝からずっと上機嫌だ。
「そろそろ着きますね」
「そうだな」
車内に降車案内のアナウンスが流れる。
座っている人たちも荷物をまとめ、降りる準備を始めた時だった。
──ガタッ
「うわ!」
「っ、」
ぎゅっ。
停車の直前に車体が揺れ、俺は前に倒れ込む。
転ぶ、と思った時には、千冬に抱き止められていた。
「「………」」
カーディガンの柔らかな質感、そして布越しに感じる、意外としっかりした千冬の胸板。
背中に回された腕の力、千冬の体温、シャンプーの香り…。
ドクン、と心臓が跳ねた。
「……えっと…、わ、悪ぃ」
「…いえ。」
数秒の出来事なのに、時間が止まったかのように感じた。
千冬が優しく俺の肩を持ち、体を起こしてくれる。
「…大丈夫ですか?」
「おう…、さんきゅ」
新幹線が完全に停車し、降車する人の列が進み始める。
千冬も前を向いてしまい、目の前には柔らかそうなピンクの髪。
俺は、何故か、抱き止められた感覚が体から抜けなくて、…身体が熱ぃ。
なんだろ、これ…。
ぼんやり千冬の後ろ姿を見ながら、新幹線を降りる。
すると、千冬が振り向き、栗色の瞳を優しく細めて微笑んだ。
「伊織先輩、楽しみましょうね」
「お、おう…、そうだな」
「ふふ。じゃあ行きましょうか!」
千冬はそう言って、右手をグーに握り、頭の高さに上げる。
「レッツ食べ歩き~!」
「フッ、なんだそれ。…オー!」
千冬と一緒に声を上げて笑う。
そういえば、腹が減ってたんだ。
よく分からないことは、今、考えても仕方ねぇし。
さっき見た美味そうな食い物の写真を次々思い出し、口の端を上げる。
「美味ぇもんいっぱい食うぞー」
「はい!」
俺は千冬に連れられて、厚海のグルメロードへ向かった。
*
「見ろよ千冬!アイスのコーンの上にねぎとろ丼が乗ってんぞ!?」
「……伊織先輩、僕はずっと見てますし、3回も聞きました。はしゃぎすぎです。早く食べてください」
「だって…、は?見ろよ!アイスのコーンの上に」
「しつこい!」
「うぐっ、」
千冬に手を掴まれ、持っていたねぎとろ丼を、口に突っ込まれる。
SNSで話題だった食べ歩きフードで、アイスのコーンに、シャリとネギトロ、そしてネギ、いくらがジェラートのようにトッピングされ、アイスらしく付属のスプーンも刺さっている。
「う、うま~!」
「ふふ、良かったですね」
「千冬は良いのか?」
「さっきプリンもシュークリームもあんぱんも串焼きも食べたじゃないですか!僕はもうお腹いっぱいです」
「そうか…あ、あとであっちの苺ソフトも食べていいか?」
「それ食べながら、もう次の食べ物探してるんですか?」
「朝、時間ギリギリだったから、殆ど食べれてねぇんだよ。腹減ってんの」
「本当に朝、弱いんですね」
「でも遅刻しなかっただろ?」
「……うちに前泊すれば良かったのに」
何かゴニョゴニョいいながら、ジトっとした目で俺を見る千冬。
先程の仕返しも兼ねて、スプーンですくったねぎとろを口に突っ込んでやる。
「…っ!、?!」
「千冬だって、俺が泊まりに行ったとき、机で昼近くまで寝てたじゃねぇか」
「だ、だって、ケホッ、ケホケホ、」
「あ、悪ぃ。大丈夫か?」
口に入れるタイミングが悪かったみてぇだ。
咳き込む千冬の背中を軽く撫でてやる。
「…すみません」
「俺こそな。な、美味くねぇか?もう一口食うか?」
「ふふ、はい、ありがとうございます」
千冬に食わせようと、スプーンにもう一口すくおうとした瞬間。
俺の手に、千冬の手が添えられ、整った顔が近付く。
栗色の瞳が柔らかく俺を見つめ、そのまま齧り付いた。
「あ、」
見上げる視線は、どこか挑発的で、口元は綺麗に弧を描く。
「伊織先輩と一緒に食べるから、美味しいです」
「お、おう…、」
千冬の手が触れていた部分が、じわっと熱を持った。
今持っているのが、本当にアイスだったら、俺の手の熱さで溶けてたかもしれねぇ。
「先輩、苺ソフトも食べるんですよね?」
「あ、ああ…、食べてぇ、な…」
「それなら、」
首を小さく傾け、ピンクの髪を柔らかく揺らす。
「また、一口もらってもいいですか?」
「…っ、」
甘く溶けるようなこっくりした茶色の瞳が、宝物でも見るかのような目で、俺を見る。
その視線に、息が詰まった。
「な、なんか…、腹いっぱいになってきた、かも…」
「そうなんですか?残念です」
綺麗な顔に見つめられて、なんだか妙に気恥ずかしくなったみてぇだ。
腹というか、胸がつっかえるような感覚に、胃の辺りを撫でながら、千冬に答える。
千冬はにこりと微笑む。
「では、そろそろ温泉に行きましょうか」
「温泉っ!」
実は一番楽しみにしていたところだ。
胸が弾んで、一気にテンションが上がる。
「あまり遅いと混みますからね」
「たっのしみだな!」
「ふっ…!え、なんですか、その発音?」
「たっっっ…のしみ?」
「ふふっ、あはは」
腹を抱えて笑い出した千冬に、俺もつられて笑う。
千冬とこうやって、しょうもないことで笑うの、すげぇ楽しいな。
お互いの背中を軽く叩き合いながら、昼下がりの明るい商店街を歩く。
ずっとこうしていたい、なんて思うくらい、心がぽかぽかと温かだった。