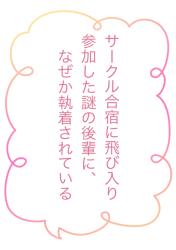千冬と学食でメシを食った日から2日。水曜の今日は、昼過ぎからバイトだ。
店長の趣味でやっているという小さな店だが、駅の近くに立地することもあって、ピークタイムは、テイクアウトとイートインの両方で混み合う。
逆に、昼過ぎの今は、一番落ち着いている時間でもある。
「伊織くん、今日もよろしくね。どう?うちには慣れた?困ってることない?」
「水森さん、お疲れ様です。水森さんも千冬も丁寧に教えてくれるんで、大丈夫です。ありがとうございます」
少し早めに出勤すると、店長の水森(みずもり)さんに話しかけられた。
水森さんは、40代くらいの女性。旦那さんと2人でこの店を経営してる。
面倒見のいい、大らかな感じの人だ。
「千冬くんね。ふふふ。仲良くできてる?」
「はい、仲良いっす。毎週、千冬ん家に泊まる約束もしてるんです」
「えっ…!お泊まり…!?」
口元に両手を当て、優しそうな目をぱちくりと見開く水森さん。
「も、もしかして、とうとう…、その、……成就したのかしら…?」
「ジョウジュ?」
「はぁ~、良かったわねぇ!あのね、実は、半年前からよ?千冬くん、毎日毎日、あの窓際の席でコーヒー飲んで、じっと見つめて…。そのうち、『無給でも良いからここで働かせてください』って言ってきてね?」
「…え、えっと…?」
「そうだ!今度の月曜、祝日よね?二人のお祝いを──」
「水森さん、何の話っすか?祝い?」
「みっ、水森さん!!」
止まらない水森さんの話を遮ったのは、今、出勤してきたばかりの千冬。
この店の制服である白シャツとブラックのエプロンが、千冬の淡いピンク髪とよく似合っている。
そして今日も完璧な顔面だ。
でも、なんか顔が赤ぇ。走ってきたのか?
「あら千冬くん!ねぇ~、良かったわねぇ?やっと叶ったのね?」
「ち、違います!その…っ、…違うん、です……」
必死に何かを訴えつつも、口ごもる千冬。
そして、水森さんも、頬をバラ色に染めながら心底嬉しそうに語っていたのに、徐々に顔色を変えて、俺と千冬を見比べる。
顔に「ヤバッ」って書いてあんぞ。
よく分かんねぇけど、水森さんの反応は面白れぇ。
千冬と水森さんがコソコソと話し始めてしまったから、俺はスマホを開いてカレンダーを確認する。
確かに、月曜に祝日マークが付いている。
スポーツの日ってやつらしい。
あ?なんだ、じゃあ授業ねぇじゃん。
「休みなら、千冬ん家、泊まんなくてもいいな」
「えっ!?で、でも、えっと…」
「用もねぇのに邪魔するほど図々しくねぇよ。折角の三連休だし、お前も色々忙しいだろ?」
水森さんと話し終わった千冬に、そう伝える。
千冬も、曲作ったり歌ったりする活動があるんだろう。
せっかくの休みを、俺が奪うわけにはいかねぇ。
すると、水森さんがわざとらしい咳払いをした。
「あー、千冬くん、確かご実家は、厚海(あつみ)にあるとか言ってなかったかしら?」
「え?は、はぁ。そう、ですけど…」
「へえ?そうなのか」
厚海といえば、ここから新幹線で1時間ほどで行ける温泉地だ。
「折角の連休だし、学生バイトさん同士、親睦を深めるために、プチ旅行でも行くのはどうかしら?千冬くんの地元の案内とかして。土曜のシフトは調整するから!」
「…!」
水森さんはそう言って、千冬に向かって、何か謝るように両手を合わせ、ウインクらしきものをする。
両方の目を瞑ってしまってるから、もしかしたらウインクじゃねぇかもしれねぇけど。
「どうかしら、伊織くん?三連休、何か予定は?」
「え?ああ、特に無いっすね…?」
唐突な提案にちょっとびっくりするも、まあ、言った通り三連休の予定もねぇし。プチ旅行は確かに楽しそうだ。
そういえばマロとカゲヤンが、厚海のプリンが美味しいって話してたな。
食ってみてぇ。
「じゃあ決まりね!スタッフの仲がいいお店は、雰囲気がいいのよ。ぜひ、行ってきてね?」
「はぁ…、そうなんですか?」
「あらやだ!事務仕事が溜まってたわ?片付けてくるわね~」
おほほ、と笑って、逃げるように裏に消えていった水森さんの背を見送る。
「変な水森さんだったな」
「い、伊織先輩!」
「あ?」
「あの、本当に行ってくれますか?…その、僕と、……」
「ああ、千冬が良ければ。俺は暇だし」
そう言うと、千冬は綺麗に口角を上げて微笑む。
「やった…!なら、行きましょう?実家の近くには、おすすめの温泉もあるんです」
「へぇ!いいな」
「伊織先輩さえ良ければ、一緒にウチに泊まれば旅費も抑えられますし、観光地も近いので…!」
「おう。なんか楽しみになってきたわ」
「ふふ。僕もです」
温泉か。肌寒くなってきたし、温泉にゆっくり浸かるのもいいな。
それに千冬の実家っていうのも、興味がある。千冬の家族って、どんな感じなんだろうな…。
「実家に確認して、また連絡しますね」と言われ、その話は一旦区切りになる。
仮にも、バイトの時間だしな。
シンクに溜まったカップや皿を洗い始める。
とは言っても、今は客もいねぇ。
千冬も、俺の隣でカウンター下の在庫確認をする。
「あ、今日もコーヒーの練習、頼むな」
「はい、もちろんです。この時間は、お客さんもあまり来ないですし、ゆっくり練習できそうですね」
「そうか。確かに、静かだな」
「夕方からまた混むと思いますから、それまでにやりましょうか」
目を合わせ微笑む千冬。
2人きりの店内は、BGMの静かなジャズがしっとり流れるのみ。
コーヒーの香りと、穏やかに話す千冬の声がなんだか心地よくて、仕事中なのに、ついリラックスしてしまう。
俺は、緩んだ気持ちで、思ったままを口にした。
「……千冬の声、好きだな」
「っ、は、えッ!?」
──バサーッ
「あっ、」
千冬が手に持っていたテイクアウト用の紙袋の束を落とし、床に紙袋が散乱する。
「大丈夫か?」
「…はい、すみません」
硬い声で返事をする千冬。
丁度洗い物を終えた俺も、千冬の向かいにしゃがんで袋を拾い集める。
千冬は真下を向いていて、表情は分からないが、妙に焦っているように感じる。
さっきまで和やかな空気だったのに…、もしかして俺、千冬の気に障ること言っちゃったか?
「えっと…、変なこと言ったなら、悪ぃ。その、今、千冬の話す声、聴いてたらすごく心地よくてさ。…ずっと聴いてたくなるっていうか…。単純に、それだけだから」
「………、」
「千冬?」
千冬の手が止まる。
俯いたまま黙り込む千冬に、俺も、少し焦る。
どうしたらいいんだ?
「えっと…、すまねぇ」
内心の焦りは隠したまま、一言だけ謝り、紙袋を拾い集める。
これ以上、何か言うのはやめておこう。
すると、拾い上げようとした掴んだ紙袋が、反対側からも引かれる。
千冬が、俺と同じ紙袋を、掴んでいた。
「あ、わり──」
「……声、だけですか…?」
「え?」
微かに震えた声。
そっと顔を上げた千冬は、口元をキュッと結び、真っ直ぐに俺を見つめた。
声、だけか……?
「千冬、どういう…?」
頭の中で千冬の質問の意図を考えていると、千冬は名残惜しそうに紙袋から手を離し、小さくため息をつく。
なんだ?
怒ってんのか…?
そして千冬は、俺から目を逸らしたまま、口元を手で隠し、低く掠れた声で呟いた。
「…不用意に…、好き、とか……言わないでください」
「………え」
──カラン、カラン
「あ、いらっしゃいませ。…先輩、すみませんが、片付けお願いします」
「…おう」
サッと接客モードに切り替えた千冬に、置いていかれる俺。
その場にしゃがみ込んだまま、千冬の今の言葉をゆっくり咀嚼した。
好きとか言うな、って言ったか…?
慣れた手つきでカフェラテを作る千冬の、澄ました横顔を盗み見る。
もういつも通りの雰囲気だし、なんなら「何も気にしてないです」って顔…に、見える。
良かった…、のか?
「ゴミ捨て、行ってくんな」
「はい、お願いしますね」
残りの紙袋を片付け終わると、千冬に声をかけ、ゴミ袋を持って外に出る。
もしかして、声をどうこう言われる以前に、「好き」とか言ったせいで引かれたのか?
確かに、男からそんなこと言われても嬉しくねぇか。
「千冬に嫌われんのはイヤだしな…。気をつけよう」
旅行も楽しみだし、千冬との関係を悪くしたくねぇ。
自分の軽率な言葉を戒めながら、ダストストッカーにゴミ袋を放り込む。
「温泉とプリン、楽しみだな」
週末の約束を思って、俺は軽く鼻歌を歌った。