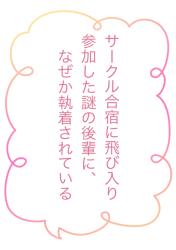翌朝。スマホの着信で呼び起こされる。
枕の周りや下を手探りで探して、スマホを耳に当てた。
「………うるせ…、…はい…、誰?」
「千冬です!伊織先輩、既読つかないと思ったら、まだ寝てたんですか!?」
「…………あ」
「『あ』、じゃないですよ!遅刻しますよ!早く起きてください」
「悪ぃ、ありがとな」
「いーえ。学校で待ってますからね」
危ねぇ。初っ端から遅刻するところだった。
急いで身支度を整えて、バスに乗り込む。
おかげさまで、遅刻は免れそうだ。
後輩オカン、千冬様様だ。
「千冬」
「…あ、伊織先ぱ──」
学校に着くと、教室の入り口前に千冬の姿があった。
イヤホンを耳に嵌め、スマホを見ている千冬に声をかける。
淡いピンクの髪と、濃いチョコレート色の薄手ニットが、柔らかい印象だ。
しかし、千冬も俺に気付いたところで、女子の集団に阻まれてしまう。
「おはよー、千冬」
「千冬、久しぶりー」
「千冬くんも、この授業取ってたんだ?」
「千冬〜、なんでバーベキュー来なかったのー」
……すげぇ。
工学部では見られない、驚異の女子率。
特に千冬の周りが。
羨ましいを通り越して唖然とする。
千冬の顔面の強さと、面倒見のいい性格からして、女子が放っておかないのは当たり前だろう。
実際、バイト先のコーヒーショップでも、千冬目当てらしき女性客を何人も見た。
でもここは……大奥か?
「朝の礼は、後で言えばいいか」
女子に囲まれる千冬に遠くから手だけ振って、さっさと教室に入り、一番隅の机に荷物を置く。
俺と同じ、ぼっちの生徒も数名この辺にいるし、ここに混じって大人しくしていよう。
この授業は、パソコンを使う。
受講人数が多い授業だから、大体2人で一台のパソコンを触ることになる。
2人掛けの机の片方に座り、各机に一台ずつ割り当てられているパソコンの前にテキストを出した。
「先輩!なんで先行っちゃうんですか」
「えっ、」
突然千冬の声がして、当然のように俺の隣に千冬が座った。
「あー、えっと…、千冬は同級生たちと座るかと思って」
「……僕は…、伊織先輩の隣が、いいです」
「そうか?」
テキストを準備しながら、唇を尖らせ、不満そうに言う千冬。
確かに、俺はこの授業を一度受けてるから、授業内容もテスト内容も大体分かってる。
頼ってくれてる、ってことでいいのか…?
「はい、では始めます。──」
この授業を担当する教授が登壇し、室内が静かになる。
俺と千冬も、会話は中断し、教授の声に意識を向ける。
今日はオリエンテーションみたいなもんで、パソコンは使わないらしい。
授業の入り口として、昨今のAI技術の進歩の話だとか、情報倫理を学ぶ大切さだとか、全般的な話が展開されるが…。
だめだ、初歩的な話のせいか、だんだん眠気が襲ってくる……。
*
「………ん…?」
机に突っ伏していた顔を上げ、霞む目で教壇を見ると、誰もいない。
静かだ。
え?
いつの間に授業終わったんだ?
「伊織せんぱい」
「!」
不意打ちに、隣から千冬の甘く優しい声。
内緒話をするかのように小さな声で囁かれ、思わず心臓が跳ねた。
「おはよ?」
「ち、ふゆ…」
千冬は、腕に頭を乗せ、机に突っ伏した姿勢で、顔をこちらに向けている。
微かな動きに合わせ、繊細に乱れる淡いピンクの髪。
幸せそうに細められた目と、優しく緩む口元。
まるでドラマのワンシーンを見てるかのような蕩ける微笑みに、一瞬、言葉を失った。
「…わ、わりぃ、俺……」
「ふふ。おでこ、赤くなってる」
「っ、」
そう言って、人差し指の爪先で、俺の前髪を優しく撫でる。
髪に触れられただけなのに、勝手に息が止まって、顔がみるみる熱くなった。
「あ…、おでこ以外も」
「はっ!?ちょっ、」
指先で、ちょん、と軽く俺の頬に触れる。
俺の反応が面白かったのか、いたずらっぽく微笑みながら、手を戻す。
戻す手は大切に握り込まれ、そのまま唇に当てられる。
栗色の瞳が、はちみつを垂らしたかのように甘く、揺らめいていた。
俺の心臓はまた忙しく鼓動する。
なんだ?
また…、
また、この感じだ。
体が熱くて、心臓が煩い。
「お、おい、悪かったって…、」
「いいえ、大丈夫ですよ」
相変わらず幸せそうに微笑んだまま、千冬はゆっくり体を起こした。
それだけで、心臓に悪い雰囲気が少し薄れた気がして、安堵する。
「…っと、メシ、行こうぜ。時間大丈夫か?」
「僕はあと2時間あります。でも、先輩こそ大丈夫ですか?二葉キャンパスまで戻らないとですよね?」
「あ」
時間は11時。
午後の最初の授業は13時から。
ここから二葉キャンパスまでバスで戻ることを考えると、12時過ぎには切り上げねぇと。
「……学食でもいいか?」
「もちろん。どこでも嬉しいです」
荷物を片付けながら立ち上がると、千冬も席を立つ。
カッコつかねぇな、俺の方が先輩なのに。
来週からは、ちゃんと起きて授業を受けよう。
そう心に誓って、俺は千冬と学食に向かった。