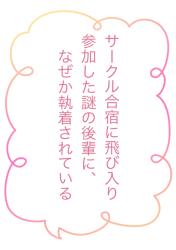一晩中降り続いた雨は、朝にはすっかり止み、外は台風一過の見事な秋晴れ。
瞼の向こうに柔らかい日の光を感じて、俺は目を覚ました。
「……あ、千冬ん家か」
千冬がリビングに用意してくれた来客用の布団から上半身を起こし、今の状況を思い出していく。
昨晩、俺に寝室のベッドを貸そうとしていた千冬に、「流石にそこまでは」と断って、結局ここで寝かせてもらった。
というか、千冬はしつこくベッドを勧めてきて、「そんなに言うなら一緒にベッドで寝よう」と提案したところ、千冬は顔を真っ赤にして硬直し、渋々折れた。
セミダブルだし、2人で寝れねぇことは無いと思ったけど、やっぱり野郎と2人で寝るのは嫌だったみてぇだ。
「まだ寝てんのか?千冬」
スマホの時計は朝の10時。
てっきり千冬の方が早起きかと思っていたから、ちょっと優越感。
千冬だって、言うほど朝は強くねぇんだな。
腹は減ったけど、他人ん家だし、勝手にキッチンを漁るのも気が引ける。
とりあえず顔でも洗おう。
洗面所に向かおうと廊下に出ると、微かな物音が聞こえた。
昨日覗いてしまった、千冬の作業部屋からだ。
「千冬?起きてんのか?」
声をかけながらドアをノックする。
返答はない。
「千冬?」
気になってドアを開けると、部屋の中は夜のように暗い。遮光カーテンで締め切られ、大きなモニターの光だけが部屋を照らしていた。
そして、そのモニターの前で、顔を突っ伏したまま眠るピンクの頭。
「おい、お前こんなとこで寝たのか?」
「………」
「おーきーろ、それかベッドで寝ろ」
「……、ん゛〜……、せん、ぱい…?」
肩を叩いて呼びかけると、緩慢な動作で顔を上げ、殆ど開いてない目で見上げられる。
ピンクの髪は乱れ、パーカーの首元からは綺麗な鎖骨が覗いている。
そのまま「うー」とか「んー」とか唸りながら、俺の腕をぎゅっと抱き寄せる。
……これは、寝ぼけてんな。
「千冬、俺の腕は枕じゃねぇ。放せ、そして起きろ」
「はぁ…。……好き…、」
「は、はぁ?どんな夢見てんだよ?」
抑えきれない愛おしさと、滲む苦しさ。そんな甘く切ない声に、思わずドキリとする。
千冬は、腕に擦り寄りながら、熱い吐息を漏らした。
なんだこれ?
彼女の夢でも見てんのか?
「ちふ…──っ!」
もう一度呼びかけようとしたところで、強く腕を引き寄せられ、前屈みになる。
二の腕に頬擦りされ、吐息の熱さと、シャンプーの匂いを感じる。
くすぐってぇ…。
そのまま千冬が、ゆっくり首を傾げ、淡いピンクの髪がふわりと揺れた。
眠そうな二重瞼の下で、栗色の瞳が甘く細められる。
「早く、俺のものになって…?」
「……っ、」
掠れた甘美な声に、身体がブワッと熱くなり、顔が赤くなるのが自分でもわかる。
心臓は、ドクドクと激しく脈打つ。
…え、なんだこれ。
なんだこれ??
得体の知れない初めての感覚に戸惑っていると、千冬の目がパチリと開いた。
パソコン周りの機材から発されている、静かなコイル鳴りの音だけが、部屋に落ちる。
「………」
「………」
「………え、……い、伊織先輩ッ!?本物!?な、なん、…あっ、!」
──ガタッ、ドスン!
「…痛ぁ〜〜っ…」
数秒の沈黙の後、慌てた様子の千冬は、勝手に驚き、勝手に椅子から滑り落ち、勝手に負傷していった。
「………大丈夫か?」
一人で珍リアクション芸を繰り広げる千冬に、冷静さを取り戻した俺は、改めて手を伸ばす。
素直に手を取り、起き上がった千冬の目には涙が滲んでいた。
「……大、丈夫…です…」
「……なら、いいけどよ」
千冬を引っ張り上げ、手をはなす。
「今10時だけど、お前寝れてねぇの?ベッドで寝てくるか?」
「あ、いえ。もう起きます。…えっと…、伊織先輩、お腹は?」
「減ってる」
「ふふ、ですよね。僕が作っても良いですか?すぐ作りますから」
「いいのか?」
「はい!もちろんです」
「おう。じゃあ頼むわ。ありがとな」
寝癖をつけたままニコリと微笑む千冬に、俺も笑い返す。
激しい鼓動も、燃えるような身体の熱も、いつの間にか引いていた。
でも、千冬に触れていた手は、じんわりと熱を残している気がする。
多分これは、…気のせい…、だよな?