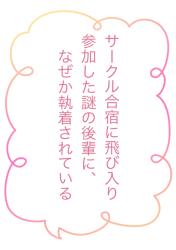「うま!千冬って料理できんだな」
「簡単なものだけですけど」
謙遜する千冬だが、食卓に出されたカルボナーラとコンソメスープは、どちらも文句なしに美味い。
「てっきり千冬は、自炊しねぇタイプなのかと思ってた」
「え、なんでですか?」
「いつもコンビニで弁当買ってたから」
「あー…」
千冬が買う物は、大体弁当か惣菜。その場で温めを頼まれ、レンジ待ちの間に雑談していたのを思い出す。
「……忙しい時は、出来合いのものが…楽なので」
「忙しいって、さっきの部屋のやつか?」
「そう、ですね」
「あれって何なんだ?動画配信?」
千冬のフォークが止まる。
口を引き結び、俺をジッと見つめた。
なんだ?聞いちゃいけねぇことだったのか?
また怒りモードの千冬が出てくるんじゃねぇかとちょっと身構えると、千冬がパスタに視線を戻し、控えめに言った。
「歌、……です」
「歌?」
「…曲を作って、歌って、動画投稿してるんです」
「え…、マジで?『歌い手』ってやつ?」
「はい」
「すげぇな!聴いてみてぇ。YouTubeとか検索したら出てくんのか?」
驚いた。まさか千冬にそんな特技があったとは。
俺が興奮気味に言うと、千冬は頬を赤くして、フォークでパスタを弄りながら答える。
「……『フユ』って名前で、投稿してます」
「へぇ!『フユ』、か」
早速、スマホで検索する。
「フユ」は、ありきたりな名前な気がするけど、検索窓に入力してみると、サジェストに「フユ 歌ってみた」「フユ オリジナル」「フユ ボカロ」「フユ 初春の月」などと出てくる。
「フユ オリジナル」を選び検索する。
1番上に表示された動画は、今年の3月末の動画だ。これが1番人気ってことなんだな?
再生回数は、500……
「500万!?」
「!、びっくりした」
「え、お前、もしかして、すごい奴!?有名人??」
「有名…って程じゃないと思いますけど…、」
「いや500万はすげぇだろ」
「そこまで伸びてるのは、それだけです。他のは、だいたい10万前後ですし…」
「……」
視線を逸らしたままチビチビとスープを飲む千冬を、気持ち遠くに眺める。
10万だって十分すげぇだろ。
ていうか、こいつがどうして、こんなマンションに住んでいるのか、ようやく分かったわ。
「ちょっと、信じらんねぇけど…」
「嘘は言ってません」
「疑ってるわけじゃねぇよ。びっくりしたって言いてぇだけ」
目の前の「有名な歌い手」が作ったカルボナーラを一口、口に運んでから、その動画を再生する。
曲のタイトルは、「初春の月」。
画面に映し出されるのは、オーバーサイズのグレーのパーカーを着て、ギターを持つ手元のみ。
静かなピアノの旋律と、ギターの音が耳に心地よく流れ始めた。
その瞬間、千冬にスマホの電源ボタンを押され、再生が中断される。
「ちょっ、ちょっと待ってください!」
「あ?なんだよ」
「これ聴くんですか…!?今!?」
「だってお前の代表曲だろ?」
「そ、そう…です、けど…っ!」
耳まで赤くして、なんなら若干目は潤んでいる。
全世界に公開しておいて、何を恥ずかしがってんだよ?俺への嫌がらせか?
「とにかく、この曲は、やめましょう」
「はぁ?」
「『歌ってみた』とかにしてください。伊織先輩の知ってる曲もあると思いますから」
「はぁ。まあ…いいけどよ」
アーティストって気難しい生き物だな。
千冬に言われた通り、「フユ 歌ってみた」で検索し直し、適当に選ぶ。
流行に疎い俺でも耳にしたことがある、有名な曲の前奏が流れる。
「なんか……緊張します」
「ネットに公開してるのにか?今更だろ?」
「……伊織先輩に聴かれるのが、緊張するんです」
「ふぅん?」
「お皿片付けるので、食べ終わってたらください」
「おう、さんきゅ」
普段、動画投稿しかしてないなら、リアルな反応を目の当たりにするって、確かに緊張するもんなのかもしれねぇな。
残りの一口を口に入れ、千冬に皿を渡すと、動画から歌声が流れ始めた。
「うわ、上手っ…、ていうか……」
流しに立つ千冬を再び見る。
千冬の歌声は、普段の千冬のイメージとは全く違う、甘く切ない低音ボイス。
心地良い響きなのに、胸の奥を優しく揺さぶられるような、不思議な魅力がある。
思わず聴き入ってしまい、再生が終わると同時に、千冬に話しかけた。
「千冬、すげぇな。これ本当にお前?」
「……ありがとうございます」
「これだけ上手いなら、人気なのも納得だわ」
「上には上がいますから、僕はまだまだですよ」
「そうか?」
「…でも、伊織先輩に褒められるのは、嬉しい、です」
席に戻った千冬が、照れながら微笑む。可愛らしい笑み。
動画の一覧を見ていくと、サムネイルで見る限り、どの動画も顔を映しているものはない。
匿名で活動してるから、あの部屋のことも、秘密にしたかったのか。
「これやりながら、バイトもして、大学も行って…って、大変じゃねぇの?」
「好きでやってることですから、続けられてます」
「へぇ〜、すげぇー。俺なんかバイトしかしてねぇのに、単位一つ落としちまったけどな」
「え?そうなんですか?」
「おう。後期の教養科目。月曜の朝イチだから、つい寝坊しちゃうんだよな……」
「そ、それって、全学部共通の『情報技術概論』ですか?再履するんですか?」
「ああ、それ」
「僕も!僕もそれ、受ける予定です!」
「基本1年生が受ける講義だもんな。知り合いがいてよかった」
後期の授業は10月から。今日は9月末の最終土曜だから、早速、明後日から、この「情報技術概論」の再履修が始まる。
俺の周りの奴らはみんな無事に単位を取得しているから、俺は1人で、1年生に囲まれ講義を受ける。
正直、ちょっと恥ずかしいし、肩身は狭ぇ。
「まあ、問題は、朝起きれるかだけどな。二葉キャンパスから一ノ宮キャンパスまでの再履バスも出てっけど、そもそも月曜の朝イチっていうのが辛ぇんだよな…。寒い時期だし」
俺たちの通う大学は、学部によって2年生以降はキャンパスが分かれる。
工学部の俺は、2年生以降は二葉キャンパスだが、学部共通の教養科目は、一ノ宮キャンパスで講義だ。
つまり、月曜は毎朝、一ノ宮まで行かないといけねぇ。
「伊織先輩、朝弱いんですね」
「寒さにもな。布団から出たくねぇ」
「ふふ、なんか先輩っぽいです」
「それ褒めてねぇよな?」
やたら嬉しそうに笑う千冬を、わざと軽く睨んでやる。
他人事だと思いやがって…。
付けっぱなしにしていたテレビが、夜のニュースに切り替わる。時間は22時。いつの間にか、こんな時間か。
「千冬、明日は何か予定あんのか?」
「いいえ。伊織先輩は大丈夫ですか?」
「俺も特にねぇ」
「あ」
「ん?」
寝るにはまだ少し早ぇから、テレビの前のソファに移動しようと、席を立ったところで、千冬が声を上げた。
どうしたのかと千冬を見ると、千冬は口元を手で隠し、目を逸らす。
「…………」
「…なんだよ?」
「あの…、」
「おう?」
「…月曜は、ここから通ったら、どうですか?」
「………?」
「その、…月曜の、朝だけは……」
月曜の朝はここから通う…?
ここって、千冬のマンションってことか?
「こ、ここからの方が、一ノ宮キャンパス近いですし、」
「…おう?」
「せ、先輩が寝坊しないように、…僕が、起こしてあげられます…し、」
「……おう?」
「伊織先輩の荷物、置いたままにしてもらって良いですし、」
「………」
「あと、朝ごはんも作ります!だから…、」
「………」
「………っ」
赤い頬で、乞い願うような目で俺を見る千冬。
申し出はありがてぇけど……、
「どっちかっていうと、俺が頼む立場だよな?」
「え?」
「あ、いや…、もちろんありがてぇし、千冬が良いなら、そうさせてもらえると助かるけど…」
「!、じゃ、じゃあ…!」
「……いいのか?」
「はい!もちろんです!」
世話焼きな性格も、ここまでくると少し心配になるけど。
千冬がいいっていうなら、俺にとっては断る理由もねぇ。
「ありがとな、千冬。都合悪くなったらいつでも言ってくれよ」
「ふふ、はい、そうしますね」
満足そうに、少し照れながら笑う千冬を見て、俺の頬も緩む。
明日は、毎週の泊まりのために必要な物を買いに行く約束をして、台風の夜は更けていった。