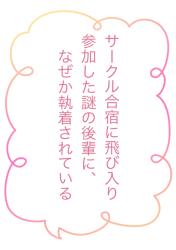公園に着くと、千冬はブランコの近くのベンチに座っていた。
すでに日は落ちていて、辺りは暗く誰もいない。
街灯の明かりの下、淡いピンク色の頭が幻想的に浮かび上がるように見えた。
「あ、伊織先輩!」
千冬は俺に気づくと、弾かれるように立ち上がる。
「千冬、…」
「走って来てくれたんですか?」
息を整えながら千冬に近づくと、千冬も俺に駆け寄る。
眉を下げ、心配そうな表情をしているけど、瞳はキラキラと輝いている。
会えて、嬉しい。
「急がせてしまって、すみません」
「いや、俺が…、早く千冬の顔見てぇなって、思っただけ…」
「…っ、」
最近すっかり運動不足だった俺は、少し走っただけで頭の中が酸欠状態。
余計な心配かけないようにと、ヘラリと笑ってみせると、千冬の瞳が微かに揺れた。
ほんのり頬を染め、長いまつ毛を伏せながら視線を逸らす。
「……そういうとこ、ですよ…」
「え?」
「何でもないです。座っててください。飲み物買ってきます」
千冬が座っていたベンチに誘導されて、一息つく。
10月上旬。日中こそまだ暑い日もあるけど、朝晩は少し肌寒い。
「どうぞ」
「さんきゅ」
自販機で買ったホットコーヒーを渡され、千冬が隣に腰掛ける。
曲を聴いて欲しいという話だったはずなのに、千冬は上着のポケットに手を入れたまま、黙っている。
「千冬?曲、聴くんだろ?」
「………はい」
チラッと俺を見て、躊躇いながらスマホを取り出す。
画面を操作し、しばらくするとギターの音が流れ始めた。
優しい旋律は、次第に明るく爽やかなメロディーに。千冬の優しく透明感のある声が軽やかに響く。
未来への希望を歌った、明るい歌。
「いいじゃん。俺は好き」
「嬉しいです。ありがとうございます」
一通り聴き終わり、率直に思ったことを言う。
すごくいいって心から思ってるのに、こんなチープな感想しか出てこなくて申し訳ねぇなって気持ちになる。
「俺、こんな感想しか言えねぇけど……いいのか?」
「ふふ。伊織先輩は本当にかわいいです」
「…は?」
俺の質問の内容から、回答がズレてねぇか?と隣を見る。
千冬は俺の顔を覗き込むように身を屈め、ピンクの髪をふわりと揺らした。
イタズラっぽい笑顔。
「ちゃんと伝わってます。伊織先輩の、顔、声、身体…、全部から」
鼻先を、ちょん、と突かれる。
頬が少し熱くなって、目を逸らした。
「そう、かよ…」
「はい」
どうやら俺は、結構顔に出るタイプらしい。
自覚無かったけど。
やっと絞り出した言葉に、千冬は優しく微笑んだ。
そしてまた、ポケットに手を戻し、黙って空を見る。
「何見てんだ?」
「……雲、ですかね…?」
「なんで疑問系なんだよ」
ちょっと笑うと、千冬もつられて笑う。
今日の空は分厚い雲に覆われていて、星一つ見えない。
なのに静かに空を見上げている千冬が不思議だった。
当初の要件は済んで、お互い話すこともない。
少しの沈黙の後、千冬が静かに口を開いた。
「…じゃあ、帰りましょうか」
「おう。そうだな」
千冬が立ち上がり、爽やかな笑顔で振り返る。
その声に応えて、俺も立ち上がった。
たわいも無い会話をしながら、公園の出口へ向かう。
小さな公園だから、大した距離はねぇ。
あっという間に出口まで辿り着いた。
「急に呼び出して、すみませんでした」
「構わねぇよ。むしろ、千冬の曲を一番に聴かせてもらえて…なんか光栄?」
「なんで疑問系なんですか」
さっきの俺の言葉と同じツッコミに、二人して笑う。
「じゃあな。気を付けて帰れよ」
「…子供じゃないんですから、大丈夫です。伊織先輩こそ、僕がアパートまで送ります」
「いいよ、すぐ近くだし」
「そう…ですか」
困ったように眉を下げて笑顔を作る千冬に、俺も笑顔を返す。
けど、…なんか、ちょっと寂しい。
なんだか…、呆気ないような、感じ。
「では、また土曜のバイトで」
いつものような可愛らしい笑顔で手を振る千冬に、俺も軽く手を挙げて応える。
物足りない気持ちは抑え込んだまま、背を向け歩き出した千冬を、見送る…、つもり、だったのに。
「……伊織、先輩…?」
「………、ぁ」
手が、勝手に千冬の服の裾を掴んでいた。
「どうかしたんですか?」
「…………」
不思議そうに尋ねる千冬に、なんて答えればいいか、言葉に詰まる。
だって、千冬を呼び止めるほどの用事は何もねぇし。
ただ、…なんか……。
…そうだ。
この前の時、千冬が…言ったんじゃねぇか。
「えっと…、その……」
言い出すのが恥ずかしくて、顔に熱が集まる。
意を決して、千冬を見上げ、小さな声で尋ねた。
「………ハグ…、やって…みねぇの…?」
「っ…、」
街灯の光だけの暗い夜道。
それでも分かるくらい、千冬は耳まで真っ赤になって固まる。
つられて、俺もさらに顔が熱くなった。
「顔を見るだけって…、自分に言い聞かせてたのに…」
「…え?」
何かを呟いた千冬は、俺の手首を優しく掴んだ。
「そんなかわいく、おねだりされて…。断れるわけ、ないじゃないですか…」
「ね、ねだったわけじゃ…!」
静かに瞼を伏せ、千冬の長いまつ毛が頬に影を作った。
儚くも見えるその姿に、思わず口を噤む。
「……いいん、ですか…」
「………うん…」
千冬の手が、俺の手首から滑り降りていって、指先を引っ掛けるように持った。
千冬がそっと距離を詰める。
靴底がコンクリートの上の細かい砂を踏みしめる音と、布切れの音がした。
そして。
──ぎゅっ…。
千冬の腕に包まれ、千冬の首筋に、胸板に、腹筋に…、体が密着していく。
「…、はぁ…。伊織、先輩…っ」
「……っ」
小さな声で名前を呼ばれて、胸がぎゅっとなる。
もう離さないと言わんばかりに、強くなる腕の力。
なのに、身体の苦しさより、胸の中にとめどなく溢れる感情に、息が詰まる。
「……、僕…っ…」
頭の後ろに手を添えられ、顔が、千冬の首筋に押し付けられる。
千冬の体温と匂いで、頭がクラクラする。
千冬の速い鼓動も、直接身体に伝わる。
あぁ、なんか…ヤバい……。
「伊織先輩のこと、好き…過ぎて……、」
言葉を続けない代わりに、腕の力が強くなる。
千冬の気持ちが痛いほど伝わってくるようで、俺の心臓は、もう、いっぱいいっぱいだ。
このままじゃ死んでしまう、と千冬の服の端を控えめに握る。
「…ち、ふゆ……」
なんとか名前を呼ぶと、千冬の体が微かに強張り、不意に拘束が解かれる。
両肩を掴まれ、身体をサッと引き離された。
千冬は口元を腕に寄せて隠し、赤く染まった首筋が俺の目前に晒される。
「ご…、ごめんな、さい……」
急に消えた温もりに、安堵する気持ち以上に、物悲しさを感じて、千冬を見上げる。
千冬は目を見開き、ゴクっと喉を鳴らした。
「あ、煽らないで、ください」
「へ…?」
千冬は、ふぅ…と、ひと呼吸置いてから、肩に置いていた手を放す。
甘い瞳が、切なげに俺を見つめた。
「…これ以上いると、もっと、欲しくなっちゃいます…」
「もっと?」
「…伊織先輩の、唇、とか……」
「く、くちび…っ!?」
千冬の視線が俺の唇を捉え、顔がぶあっと熱くなる。
それって、キス…だよな…!?
え、キ、キス…!?
見るからに動揺しているであろう俺に、千冬は小さく笑った。
瞼を落とし、こっくりした焦茶の瞳で優しく微笑んでみせた。
「今じゃなくて良いんです。…でも、先輩が良ければ…、僕にください」
「っ、」
優しく頬を撫でられる。
妖しく光る瞳は、熱に浮かされたように、ほんのり色香を纏っている。
思わず脚の力が抜けて、すかさず、千冬の腕に支えられた。
「……わ、悪ぃ…」
至近距離にある整った顔は、口元に綺麗な弧を描く。
「大好きです。伊織先輩」
身体中が、かあっと熱くなって、目を逸らす。
ああ、俺…、千冬のこと……。
「……終バス、無くなるぞ。そろそろ帰れよ…」
「はい。そうします」
ふふ、と笑った千冬が、俺から手を放す。
「では、また」
「おう。じゃあな」
ピンクの髪をふわりと揺らし、背を向けた千冬を見送る。
千冬の後ろ姿が見えなくなっても、俺はその場に立ち尽くした。
俺、もう…。
千冬と、ただの友達でいるのは……無理かもしれねぇ……。