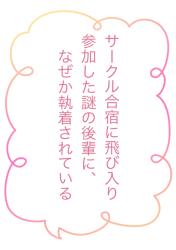「伊織〜、思ったより全然元気そうで良かったよぉ。」
「おう。本当は火曜には、授業出れるくらいには回復してたんだけどな」
「千冬クンから連絡もらった時はびっくりしたわ〜!」
千冬の家から帰った翌々日。2限から5限までというほぼフルコマの長い1日を終え、いつもの3人と二葉キャンパスの食堂で晩メシ。
3人揃った顔を見ると、やっと普段の生活に戻った気がした。
千冬と過ごした数日間が、遠い昔の、夢の中の出来事だったかのように感じる。
「ゴホン、それで伊織。……どうやったんや?」
「え?」
急に神妙な口調で尋ねるカゲヤンに間抜けな声を返す。
どうって何?
他の2人も真剣な顔で俺を見ている。
「千冬氏と、…旅行」
「ああ、厚海な。あ、悪ぃ、土産ないわ」
「そんっっなことはどうでもええねん!!」
「うわっ、びっくりした…」
机を叩くカゲヤンにビビる。
「単刀直入に聞いたるわ。伊織……、千冬クンに、…食われたんか?」
「ちょっ、カゲヤン!」
「いきなりそこまで聞くのぉ!?」
「……?、あ!」
カゲヤンに、マンティスとマロがコソコソ耳打ちする。
最初は何の話かと思ったが、カゲヤンの質問でやっと分かった。
こいつら、俺達が土産のプリンを食ったこと、知ってたのか……。
「……千冬に聞いたのか?」
「図星!?」
「うわぁ、やっぱり…!まぁ二人で温泉旅行だもんねぇ…」
「マジかあああ」
三人共、目を見開き驚いている。
悪かったな、食い意地張ってて。
「俺から誘ったから、千冬は悪くねぇ」
「はぁ?」
「ひょっ」
「うそやろ…。そ、そ、…それで、……どんな感じだったん?……初めてやろ…?」
「おいやめろ、ここ学食だぞ」
「だけど気になるぅ」
プリン如きで何をそんな盛り上がってんだコイツら。
確かに美味かったけど。
「すげぇ、…良かったよ」
「ブッ、」
「うわぁ…」
「…くっ…」
「だって、…すげぇ、甘ぇし…、なんつうか…トロトロにとろけて…」
「や、やっぱやめろォォ!」
「アホ伊織!全年齢向けやねん!この話は!!」
「痛っ!はぁ?なんなんだよお前ら」
意味わかんねぇ。叩くなよ。
プリンを食べた制裁にしてはちょっと過激だ。
そんなに食いたかったのか?
「…悪かったな」
「謝ることはない。…自然の摂理だ」
「摂理?」
「はぁ。結構肉食なんだね、千冬っち」
「でも良かったなあ?めでたく付き合い始めたっちゅうことやろ?」
「は?付き合う?」
「うんうん。千冬っち、頑張ったよねぇ。この鈍感初心男相手にさぁ」
「え、え?ちょっと待てよ。なんの話してんだ?」
しみじみと語る三人にストップをかける。
話の繋がりが全く見えねぇ。
付き合うって…?
「千冬氏と、付き合い始めたんだろ?」
「おめでとおな」
「良かったねぇ、伊織」
「……は、はああ!?付き合ってねぇから!」
「「「…………」」」
顔が火がついたように熱くなる。
驚きすぎて、思ったより大きな声出たわ。
「「「っうええええ!?!?」」」
「うるさっ、」
俺よりコイツらの方がうるさかった。
「なにぃ!?どういうことや!?」
「こ、告白は、されたけど…っ、」
「けど!?けど何!?伊織はそれでいいのぉ!?」
「顔か?顔にやられたのか!?」
「うるっせぇ!とりあえず座れ!」
立ち上がって詰め寄って来た三人を椅子に座らせる。
「千冬に…、告白されて。…でも俺、まだ、返事…してなくて。でも、…手は繋いだ」
「「「………」」」
恥ずかしさを堪えながら白状すると、三人はまた驚いたようなドン引きのような、とにかく変な顔をした。
「カゲヤン、これはじっくり話を聞いた方がいい」
「せやな。次のカラオケ会、土曜の夜でどうや?」
「そうしよ〜」
「承知」
「伊織!お前は問答無用で参加やからな!」
「はぁ?分かったけど…」
それだけ言うと、「根掘り葉掘り聞いてやるからな!」と捨て台詞を吐いて散っていく三人。
…何?俺が悪ぃの?
ぽつんと一人置き去りにされたところで、何気なくスマホを見ると、通知が来ていた。
メッセージだ。
受信は、2時間前。
「…あ、千冬…?」
SNSが苦手な俺に合わせてか、千冬から連絡が来ることは少ない。
そもそもバイトで週2回も顔を合わせるから、そんなに連絡することもねぇしな。
なんて考えながらメッセージを確認する。
千冬《新しい曲ができたので、聴いてみてもらえませんか?》
え、俺に?
絶対、大した感想言えねぇけど…。
頭を悩ませながら返事を考える。
文字しか情報のないやり取りは、本当に苦手だ。
伊織《わかった》
考えた末の返信は、たった四文字。
俺のSNSコミュ力はこれが限界。
スマホを閉じて帰り支度をしようとすると、すぐに返事が来た。
千冬《電話しても良いですか?》
「電話…?」
了承の旨を返信すると、すぐに電話が鳴る。
「千冬?」
「伊織先輩、急にすみません」
「いいけど。曲、聴かせてくれるんだろ?データかリンク送ってくれよ」
「……」
確かイヤホンは、ポケットに入れたはず。
手探りでポケットの中を漁っていると、少し間が空いた後、千冬が静かな声で言う。
「今からお時間ありますか?」
「おう」
「二葉公園に、来てもらえますか?」
「え?」
千冬の言う二葉公園は、ここから歩いて15分くらいのところにある小さな公園だ。
俺のアパートの、すぐ近く。
「そこで、待ってます」
「え!?今いんの?」
「はい」
「…行く。10分くらい待ってろ」
「ふふ、ありがとうございます。いくらでも待てますから、ゆっくり来てくださいね」
電話を切り、机の食器を片付け食堂を出る。
…千冬と、会える。
そう思っただけで、頬が緩む。
自然と、足は速くなっていった。