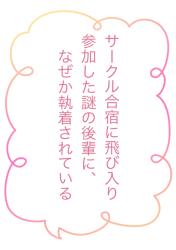俺が帰る旨を伝えると、千冬が駅まで送りたいと言い出し、俺たちは少し早めに家を出ることにした。
「本当に帰るんですか?」
「帰る」
「…ずっとウチにいて良いのに」
「そうはいかねぇだろ」
「………」
唇を突き出し、あからさまにムスッとした表情になった千冬に、思わず吹き出す。
千冬、たまにすげぇガキっぽいよな。
マンションのエントランスを出て、駅に続く道を歩く。
ここから最寄駅までは徒歩で10分ほど。
大学の近くではあるけど、微妙な時間のせいか、人通りは少ない。
「また日曜に泊まりに来るから。よろしくな」
「何時に来ますか?」
「うーん、決めてねぇけど…。千冬が良ければ、昼過ぎ?」
「僕はいつでも大丈夫です。なんなら、土曜のバイトの後からでも、金曜の授業の後からでも……」
「そんなに世話になってらんねぇよ。千冬だって忙しいだろ」
「忙しくありません」
「嘘言うな。曲作る時間も、睡眠時間も、ちゃんととってほしいんだよ。それに、俺だって課題やったり、それなりにやることあるしな」
正直に言えば、俺も、もっと千冬といたい。
でも、千冬に言ったことも本心だ。
千冬のやりてぇこと、応援したい…。
俺は曲作りは手伝えねぇけど、千冬の邪魔にならないことならできるからな。
「……わかりました」
「ん。」
会話は終了して、静かな通りは二人分の足音だけになる。
駅までの道も半分以上まできた。
三日間以上も一緒にいて、千冬との距離は、…かなり、縮まった。
あと数分で千冬といる時間が終わるのが、…寂しい。
そう思った途端、足が止まった。
「千冬……」
「どうしました?忘れ物ですか?」
「………て」
「て?」
俺に合わせて立ち止まり、きょとんとする千冬の目を見つめる。
朝の光を映す栗色の瞳は、甘く柔らかく、俺の平常心を溶かす。
顔が熱い。
心臓がうるさい。
でも、言うんだ。
「えっと……、手、…つなぎ、たい………」
「っ……、」
視線は足元。
胸の前にかかるカバンのショルダーストラップを、ぎゅっと握った。
千冬のつま先が微かに地面を擦り、コンクリートの擦れる音がした。
「………」
千冬の返事がないことを不安に感じて、目だけで千冬を見上げ、そっと様子を伺う。
千冬は口元に手の甲を当て、赤い顔で俺を見ていた。
そして俺から視線を外すと、少し瞼を落とし、ジトっとした目で道の先を見る。
「……今、ですか…?」
「あ、」
千冬の言葉でハッとする。
こんな往来で手を繋ぎたいなんて…、カップルでもねぇのに、恥ずかし過ぎるよな。
俺のアホ…!
「わ、悪ぃ、今の忘れて!」
「え、」
「見送りも、ここまででいいから。じゃあな」
「ちょっ、ちょっと!待ってください!」
「ぅぐッ」
恥ずかしさを隠すように走り去ろうとしたところで、千冬にカバンを掴まれ、よろける。
…久しぶりだな、この感じ。
「先輩、なんで逃げるんですか」
「逃げ…て、ねぇ…けど…」
嘘。逃げようとした。
年上としてのちっさなプライドが、それを認めなかった。
すると、千冬は俺に手のひらを差し出す。
意味がわからず千冬を見上げると、目を細め、うっとりするような甘い微笑みを溢した。
「先輩。僕と、手、繋いでくれませんか?」
「……え…、あっ、」
千冬が優しく俺の指先を取る。
まるで、プリンセスの手にキスする騎士のような仕草で、指先が熱くなる。
「千冬…っ、」
栗色の瞳は、甘く甘く、俺を見つめる。
そのまま手のひらを合わせ、ゆっくり指が交差した。
千冬の体温に、肌の感触に、ドキドキが止まらない。
「伊織先輩の手、小さくてかわいい…」
顔を寄せ、耳元で囁かれる。
きゅっ、と包むように手を握られると、痛いくらい心臓が跳ねて、呼吸が乱れた。
「…、ち、ふゆ…、こんな、人目もあるとこ、で…手なんか……」
「それを気にしてたんですか?」
「え…、いや、千冬が気にしてたんだろ…?」
「僕が?」
千冬は考える素振りを見せ、それから何か思い当たったようで、ぴょこっと眉を上げた。
「もしかして、さっき僕が先輩に尋ねたからですか?」
「……おう」
「あー…、ごめんなさい」
今度は眉をぎゅっと寄せ、顔を顰めながら謝罪する。
それから気まずさを紛らわすように、駅への道を歩き始めた。
そして、少しだけ進んだところで、千冬がちょっと恥ずかしそうに口を開く。
「僕、さっき、…嬉し、すぎて…」
「嬉しい?」
「はい。先輩に、そんなかわいいこと言われるなんて、思ってなかったから…」
目尻まで赤く染めた千冬は、恥ずかしそうに足元を見た。
「連れて、…帰りたくなっちゃったんです」
内緒話でもするかのような、小さな声。
なのに言葉は真っ直ぐで、冗談なんて言ってないことが伝わってくる。
胸の奥がぎゅっと絞られ、体温が一気に上がった。
「今度こそ、手を繋ぐだけじゃ…我慢できないかもって…、思っちゃいました」
「そ、それは…、」
「もっと、先輩に近付きたい、ってことです」
甘く細められた瞳が、横目で俺を捉える。
熱っぽい視線に、また、胸がドクンと鳴る。
千冬は、何も言わずに視線を戻し、足を止めた。
いつの間にか、俺たちは地下鉄駅に続く階段の前まで来ていた。
「伊織先輩、」
名前を呼ばれ、優しく手を引かれる。
千冬が俺の正面に立ち、向かい合わせになる。
「…何、だよ…」
千冬の整った顔が近付き、思わずのけぞる。
長いまつ毛がゆっくり上下して、甘いココアのような瞳に欲が揺れた。
「今度、会ったとき…、抱きしめても…いいですか…?」
「っ、」
心臓が、大きく跳ねる。
千冬は切なさを湛えた表情で、俺を見つめている。
伏せられた瞼から覗く、物憂げな瞳。
頬も耳もうっすら赤く染まり、繋いだ手は請い願うように、きゅっと握られた。
身体の真ん中が、甘く疼いた。
「………、ん…」
俯き、小さく頷きながら、蚊が鳴くような声で応えた。
多分、俺も、耳まで赤い。
握られていた手の力が、ふっと弱まる。
「はぁ…。ありがとう、ございます。…はぁ〜、…ふふ」
「何、笑ってんだよ…」
「嬉しくて、幸せだからです」
言葉の通り、心底嬉しそうな、はにかみ笑顔。
千冬の照れが伝染したのか、千冬と密着している手が、指が、俺の体温をじりじり上げていく。
「…で、電車に乗り遅れる!もう行くからな」
「あ、改札まで送ります」
「いい、」
指をほどき、千冬の手を放す。
離れた後も、手には千冬の手の感覚が残っている。
その感覚を捕まえておきたくて、ぎゅっと手を握りしめた。
顔を上げ、千冬に軽く手を振る。
「じゃあ、な。次は土曜のバイトで」
「…わかりました。気をつけて帰ってくださいね」
「千冬こそ、授業遅れんなよー」
ピンク頭にニッと笑いかけ、振り返らず階段を駆け降りる。
千冬と繋いでいた手を、ポケットの中でもう一度強く握り込んだ。
早く、土曜になって欲しい…。
胸のドキドキが、階段を降りるステップと重なった。