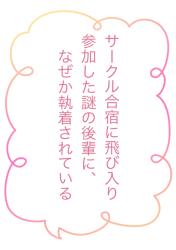「え…、ここ?」
「……ここです」
千冬に連れられて来た場所は、大学生が住むには贅沢なマンション。
俺の住んでいるボロアパートとは全く違う。
「……お前、俺と同じ大学生だよな?」
「はい」
「なんか…ヤベェバイトとかしてる?」
「してませんよっ!」
俺にムッと唇を尖らせてから、エントランスのオートロックを解除する。
千冬、もしかして実家が金持ちなのかもな。
ていうか、こんなとこ住めてんなら、コーヒーショップのバイト、する必要なくねぇか?
「ここの2階です」
「おう」
階数は俺の住んでるアパートと同じか。なんかちょっとホッとする。
いや、それがなんだって話だけどな。
部屋の鍵を開け、玄関に入るとダウンライトが自動点灯。
短い廊下の先にはリビングらしき部屋が見える。千冬は、その手前にある扉を開け、ふかふかのバスタオルを俺に渡した。
「先にシャワー使ってください」
「千冬から使えよ」
「だって先輩、濡れてるじゃないですか」
「お前だって濡れてんだろ」
「僕は…、別に。……でも、先輩が風邪ひいたら、嫌なんです」
静かに輝く瞳が、俺を上目遣いに見る。
確かに。
俺が風邪引いたら、バイトに穴開けることになるもんな。
今は大した戦力じゃねぇだろうけど、たくさんシフト入って、早く一人前になってほしいんだろう。
「わかった。じゃ、お言葉に甘えて。ありがとな」
「はい。こっちです」
「ん」
短く返事をして、脱衣所に案内してもらう。
室内はきちんと整理されていて、清潔感がある。洗面台に千冬の整髪剤なんかが置かれていて生活感はあるが、男の一人暮らしにしては十分に綺麗だ。
……もしかして、彼女か?
彼女が来るから綺麗にしてるっていうなら、納得だ。
千冬ほどの美形なら、彼女の一人や二人、いてもおかしくないだろう。
「お風呂場のものは好きに使ってください」
「おう」
「洗濯物はここに。着替えは置いておきますね」
「ありがとな」
「タオルはこっちにまだあります。必要なら使ってください」
「わかった」
「あと、何か足りないものがあれば、用意するので言ってください」
「いや、もう十分。十分だけど…、」
「?」
「なんか、もてなし感がすげぇな」
ははっ、と笑って言うと、千冬はまた頬を染めて視線を彷徨わせる。
「先輩、だからです…」
「ん?」
「なんでもないです。早く入って来てください」
「おう」
そう言って脱衣所の扉が閉められる。
ほんと、世話焼きなヤツだよなぁ。
*
「千冬、お先。ありがとな」
「いえ。温まりましたか?」
「おう。俺のアパートと違って、風呂場があったけぇな。快適だった」
「なら良かったです。あ、これ。ホットレモネードです。良かったらどうぞ」
ダイニングテーブルに、ガラスのティーカップが置かれる。
はちみつとレモンの甘い香りと、ほわほわ漂う湯気が、すでに気持ちを温める。
「…何から何まで悪ぃな」
「いいえ。先輩のためなら、なんでもしますよ」
「え?」
可愛らしくニコッと微笑んだ千冬に、思わず聞き返す。でも、それに対する返事は無い。
「僕も入って来ますね」
「おう」
「テレビ、好きに見ててください。ゲームもありますから、好きにあそんでいいですよ。あ、スマホの充電したければ、ソファの方にあります。それから、熱い寒いあれば、空調も好きに変えてください。あ、あと、冷蔵庫の中も好きに…」
「あー、もう分かったから」
千冬の背中を押して、風呂場の前まで送り届ける。
「早く入れ。お前こそ風邪引くぞ」
「…すみません」
「じゃ、向こうで待ってるからな」
「あ、待って」
服を掴まれ、引き止められる。
本日2度目だ。
まだなんかあんのかよ?
「あの…、他の部屋には、…入らないでください」
「ん?おう」
「お願い、します」
「そんなデリカシーない人間じゃねぇよ。ほら、早く行ってこい」
「…はい」
やや緊張した面持ちの千冬を置いて、リビングに戻る。
他の部屋には入るなって、そんな汚ぇのか?
意外だな。風呂場やリビングを見る限り、そんな気配はない。
「……あ、彼女か」
ひらめき、合点がいった。
きっと他の部屋には、彼女の私物なんかが置いてあったりするんだろう。
千冬が用意してくれたホットレモネードを一口飲む。
「うまっ」
優しい甘さと、レモンの爽やかさ。雨で冷えた身体が温まるのを感じる。
テレビのリモコンを手に取って、適当なバラエティ番組をつける。
普段は海外ドラマや洋画ばかり見てるから、なかなか新鮮だ。
「トイレ、どこだろ」
レモネードを飲み干し、トイレ欲が高まった俺は、席を立ち、廊下に出る。
千冬はまだシャワー中のようだ。
まあ、トイレなんて、洗面所の近くに決まってる。
ここだろうと当たりをつけて、控えめに扉を開いた。
「………ん?」
俺の予想は見事に外れた。
扉の隙間から見えたのは、デカめのモニターの光と、その周りに置かれたゴツゴツした機材たち。
傍にはギターと、部屋の中なのに更に小さな個室がある。個室の中には、ラジオの公開収録なんかで見るような、アームに取り付けられたコンデンサーマイク。
「なんだこの部屋…」
トイレじゃなかったらすぐ閉めようと思っていたのに、驚きと好奇心から、俺はドアから更に身を乗り出して、部屋の中を見回してしまった。
「なんか…収録スタジオ?──」
「先輩」
ふわっと、シャンプーの香りがして、目の前が誰かの手で遮られる。
真っ暗な視界の中、千冬の声が低く響いた。
「ダメって、言いましたよね?」
「あ、えっと…」
レバーハンドルにかけたままの手に、微かに重なる、熱い指先。
そのままゆっくり扉が引かれ、パタンと閉じた音がする。
視界を覆っていた手が下ろされ、目前には、扉が鼻先につきそうなほどの距離にある。
「千冬、あの…、」
謝罪を言うため、振り返ろうと身体を動かすと、顔の横に手を置かれ、完全に包囲される。
身動きが、とれねぇ。
「はぁ…、」
耳元で、千冬がため息をつく。無意識に、身体が強張った。
「先輩。僕に…、怒られたいの?」
「…っ」
いつもの千冬とは違う、どこか甘美で大人っぽい声。
耳にかかる吐息がくすぐったくて、身体がビクッと反応する。
罪悪感からか、逃げ出せない危機感からか、心臓が、ドキドキと大きく脈打った。
身を縮こまらせていると、千冬の手が下りて、体の横をすり抜けていく。
か、解放された…か?
恐る恐る振り返ると、千冬の綺麗な顔と、至近距離で目が合う。
「……え…っと…、」
伏せ気味の瞼から覗く、甘い瞳。口元は緩く弧を描き、水気を含んだピンクの髪は、毛先に束感を作り、濡れた重みで目の下までかかっている。
なんつーか、……色っぽい。
「ト、トイレと、間違えて…。悪かった。ごめん」
いつもと雰囲気が違いすぎる千冬に緊張して、謝る言葉も尻すぼみになる。
目を合わせるのも、なんか、怖ぇ。
しばらくの沈黙の後、また、ふぅ、と小さな吐息が聞こえた。
「…いいえ、僕こそ、ごめんなさい。ちゃんと伝えておけば良かったですね」
千冬のいつもの声に、落ちていた視線を戻す。
眉を下げ微笑む千冬は、俺の知ってる千冬だ。
良かった。
胸がホッとする。
「でも先輩、」
それから、少し俯いた千冬は、再び顔を上げると、甘い笑顔で俺を見た。
「このことは、秘密にしてほしいです」
「お、おう…」
「僕と、先輩だけの。」
妖しく光る瞳に、反射的に返事をしたけど、正直、部屋の中に何があったのか、よく分かってねぇ。
なんかの収録スタジオみたいだったのは分かった。
「ふふっ。ありがとうございます。…じゃあ、ご飯にしましょうか。伊織先輩、食べられないものってありますか?」
「いや…、」
「あ、その前にトイレですね。トイレはこっちです。僕は、ご飯の支度してきますね」
「おう…」
テキパキと話を進めて、さっさとリビングに戻る千冬。
──僕に…、怒られたいの?
「うおっ、」
千冬の、怒り(?)モードを思い出し、背中がゾクゾクっとする。
「怒ると怖いタイプなんだな、千冬。怒らせねぇように、気をつけよ」
誰もいない廊下でそう呟いた。