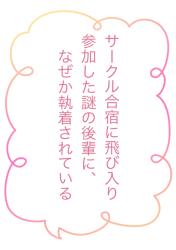部屋に戻って、料理を温め直して千冬の前に出す。
「伊織先輩の作ってくれたご飯が食べられるなんて……感無量です…」
「そんな大したもんじゃねぇから」
「最後の晩餐でもいいくらいです」
「お前やっぱ睡眠足りてねぇな」
二人で少し笑って、手を合わせる。
おにぎりを開けて、味噌汁と目玉焼きと一緒に頂く。
「歌の作業は、進んだのか?」
「はい。昨日録音が終わったので、後はMIX…っていう、録音と他の音を調整する作業をして、週末には投稿できそうです」
「ふぅん?」
音楽のことはよく分からねぇけど、本当に一人で一曲作り上げてんだな。
すげぇなぁ。
「千冬なら、音楽一本でもやっていけそうだよな。どっかの事務所とかから声かかんねぇの?」
「ふふ、ありがとうございます。…連絡をもらうことも…無いわけではないですが…、僕はもっと普通の仕事に就きたいので」
「普通の仕事?」
「はい。法学部ですからね。公務員とか、資格とって行政書士とか…」
「堅っ。マジで言ってんの?」
「マジですよ。音楽の世界は厳しいですから、二人分の生活費を安定して稼げるとは限りませんし」
微笑んでサラッと言い切る割に、千冬の目には諦めきれない何かがあるようにも見える。
本当は、もっと音楽やりてぇんじゃねぇのかな…。
…あ?
今、「二人」って言ったか?
聞き間違いか?
「伊織先輩は目玉焼きに醤油派なんですね?」
「え?あ、ああ」
「ふふ、覚えておきます。あ、お茶のおかわり、飲みますか?」
「飲む。さんきゅ…わ!」
──カタンッ
「あ、わりぃ、タオル…」
「大丈夫ですか?待っててください」
残りのお茶を飲み干そうとして、コップを倒し服を濡らしてしまった。
慌てて近くにあったティッシュで机を拭いていると、千冬がタオルを持って来てくれる。
「服、拭きますね」
「いや、自分でできるから…」
「いいえ、僕にやらせてください」
おとぎ話の王子様のように優しく微笑むと、俺の手を取り、袖口にタオルを当てる。
「これなら直ぐ乾きそうですね。寒くないですか?」
「おう…」
返事をしながら、目の前で揺れる、ゆるくパーマがかかったピンクの髪に気を取られる。
まだセットもされてなくて、全体的にふわふわしてるし、頭のてっぺんと、耳元にも寝癖も見つけた。
…なんか…、気持ち…良さそう。
千冬の髪にそっと触れる。
耳元の寝癖を戻すように梳くと、指先がかすかに耳を掠める。
千冬が小さく反応したけど、そのまま撫で続ける。
だって、この感触は見た目通り…
「…きもちいい…」
「……っ、」
ふわふわで柔らかくて、綿菓子でも撫でているような気分だ。癖になりそう。
手はそのまま綿菓子を撫でたまま、思い出したように時計を見る。
時間は8時。
朝メシも大方片付いている。
2限は10時半からだけど、ここからなら10時に出ても間に合うな。
これなら、千冬を1時間くらいなら寝させてやれるだろう。
よし。
「なぁ、千冬」
「は、い……」
俯いたまま、何故か緊張したように硬い声の千冬。
なんだ?
静かな室内に、固まったままの千冬。
雰囲気に引っ張られて、俺の声も小さく、掠れた声になる。
「そろそろ……ベッド、行かねぇか?」
「っ!?」
自信なさげな声になってしまったけど、千冬にはちゃんと聞こえた…はず。
勢いよく顔を上げた千冬は、顔を真っ赤にして、目を見開いている。
千冬の手から、タオルが気の抜けた音を立てて落ちた。
「千冬?」
「………」
息を飲み、固まったままの千冬。
石化の魔法にでもかかったかのように、全く反応無し。
まさか、立ったまま寝始めたのか?
「おい、寝るならベッドに行ってからにしろ。寝かしつけてやるって言ったろ?」
「……あ、…ああ、なんだ…そっか…」
魔法が解けたようにパッと意識を戻し、ヘナヘナと座り込む千冬。
膝を抱えるようにして、腕の中に顔を埋める。
「伊織先輩の言う通り…、僕、ちょっと寝た方がいいのかもしれません…」
「おう?じゃあ、行こうぜ」
「……、一人で、大丈夫なので…」
「そうか?じゃあ1時間したら起こしてやるな」
「はい…。すみません」
相当疲れてるみてぇだな。
千冬の背中を軽く叩いてやると、ゆっくり立ち上がり、リビングを出ていく。
「さて、片付けるか」
袖が濡れた服は、やっぱ気持ち悪くて脱いだ。
インナーだけで、かなり薄着だけど、部屋はあったけぇし、少しの間だけだし、問題ねぇだろ。
「皿を洗って…、荷物もまとめなぇとな」
体調は十分に回復したし、千冬が大学に行くタイミングで、俺もアパートに帰ろう。
キッチンを片付けて、荷物をまとめる。
大した作業はなくて、30分もかからず終わってしまった。
「千冬がちゃんと寝てるか、見てくるか」
手持ち無沙汰すぎて、部屋を出る。
気分は、修学旅行の時の見回りの先生。
そっと寝室のドアを開けて、中に入る。
ベッドを覗き込むと、顔の横に手を置き、すやすやと眠る千冬が見えた。
「……寝顔、ちょっと幼ぇよな…」
長いまつ毛に、白い肌。少し赤くなった頬と、薄く開いた唇。
悪いとは思いながらも、綺麗すぎる寝顔に、思わず近付いて観察してしまう。
「……」
やがて視線は、千冬の手に。
……少しだけなら、触ってみても、いい…か…?
悪いことをしているような気分で、脈はドキドキと速くなる。
手を繋いだ時のことを思い出しながら、そっと、千冬の手に触れた。
指先、指の付け根、手のひら…。
ゆっくり重ねて、指を絡める。
千冬の声、瞳、匂い…。
あの時の記憶が次々蘇って、心臓は痛いほどドキドキしてくる。
でも、それ以上に、やっぱり……。
自分の気持ちを確かめるように、おそるおそる手を握ろうとした瞬間。
──グイッ、
「うわっ!?」
思い切り手を引かれた。
千冬に倒れ込んだと思ったら、そのままベッドの上に転がされる。
あっという間に、俺の視界は、天井と千冬だけになった。
「ち、ちふ……」
「…伊織先輩」
寝起きで、低く掠れた声。
手はぎゅっと繋がれたまま、頭の上に押し付けられた。
もう片方の手も、手首をベッドに押し付けられ、身動きできない。
千冬は重たい瞼の下から、気怠げな視線で俺を見つめた。
「どういう…つもりですか…?」
「え、……えっと…」
抑揚のない声でそれだけを言う千冬。
頬は少し赤いけど、目が据わっていて、なんだか怖い。
ここで、「寝顔を観察して手を握ろうとした」なんて、言ったらガチで怒られそうだ。
どうしよう、か…。
俺が目を泳がせていると、千冬が「え」と小さく声を漏らした。
「、…なんですか?その格好」
「格好?……あっ、」
今度は羞恥で顔が熱くなる。
今の俺の格好は、首元ゆるゆるで、薄い生地の、半袖インナー姿。
うわぁ…。これは、確実に怒られる。
せっかく千冬のおかげで風邪が治ったのに、こんな格好で、また風邪をひきたいのか?アホなのか?と思われるに決まってる。
そんなの恥ずかしい。
怒られる前に、謝っておこう…。
「……ごめっ…、ちふ、ゆ…」
恥ずかしさのせいで、目にうっすら涙が溜まる。顔の熱も全然引かねぇ。
千冬はそんな俺を見て目を見開くと、ゴクリと唾を飲み込んだ。
そして、見てはいけないものを、それでも止められずに見るように、遠慮がちに視線を落としていく。
俺の体の上を、ゆっくり千冬の視線が這う。
首、鎖骨、胸元、二の腕…。
「ち、ふ…ゅ……」
ちょっと、泣きそうになる。
恥ずかしいし、千冬は黙ったままで、既に怒ってそうだ…。
俺は情けなくも、許しを請うような目で千冬を見上げる。
「ご、めん、…って……」
すると、千冬は苦しげに息を漏らし、赤くなった顔を逸らした。
「……っ、……、生殺し、ですから……」
俺の手をぎゅっ、と強く握る手は、何かに堪えるように、少し震えてる。
「千冬、怒って…る…?」
恐る恐る尋ねると、千冬の喉仏が上下した。
俺の目の前に晒されている首筋は、赤く染まっていて、妙に色っぽい。
「ごめ、俺…、」
「怒って、ない、です…」
もう一度謝ろうと口を開くと、千冬が手の力を緩め、俺を見た。
優しい眼差しに、ホッとする。
強く握られていたせいで、指の間がじんじんと熱を持った。
「伊織先輩…。僕、本当に、先輩のことが、好きなんです…」
「お、おう……」
急に何だ?
改めて言われると、小っ恥ずかしい。
頬がほんのり熱くなる。
「だから…、好きな人に、そんなことされると……、…かなり、堪えます」
「へ…?、」
そんなこと…?
いまいちピンときてない俺を他所に、千冬は深く息をついて項垂れた。
千冬の表情を伺おうと首を傾けると、ピンクの髪の間から、千冬と目が合う。
瞼を伏せ、細められた暗い瞳は、どこか官能的でドキリとする。
「僕、男ですよ?」
「え…、おう…?…あ、ちょ、」
間髪入れず千冬が覆い被さり、耳元に口を寄せた。
「次は、襲います」
低い囁き声に、一瞬で全身が粟立つ。
手の拘束がするりと解放され、千冬がベッドから降りる。
ピンクの髪をふわんと揺らした千冬は、俺を振り返り、爽やかな笑顔を向けた。
「大好きです、伊織先輩」
「…っ、」
かああっと顔が熱くなる。
ゆっくり起き上がるも、なんだか頭はぼうっとする。
廊下から、先に部屋を出た千冬の声が響く。
「そろそろ、支度しますね。伊織先輩も、早く服を着てください」
「…あ、ああ…」
ぼうっと扉の方を見ていると、千冬がひょこっと顔を出した。
「あと、そんな格好するのも、僕の前だけにしてくださいね」
意地悪そうに微笑み、すぐに去ってしまう。
「……、」
心臓が、まだドキドキしている。
俺は熱くなった顔を手で仰ぎ、火照りが治ってから、やっと部屋を出た。