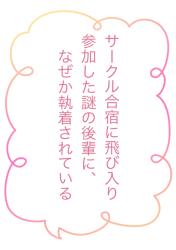「あれ…?」
目が覚めると、ベッドの中にいた。
千冬が戻るまで…、と思ってソファで横になるつもりだったのに、いつの間に?
スマホで時間を確認する。
時間は朝の6時。
俺がこんな時間に、アラームも無しに起きれるなんて珍しい。
「千冬はもう起きてっかな」
ベッドを出て、廊下に出る。家の中は静まり返っていて、リビングの扉を開けてみるが、千冬はいねぇ。
廊下に戻って、作業部屋の扉をノックする。
「千冬?またここで寝てるのか?」
返事はねぇけど、そっと扉を開けて覗く。
「やっぱり…」
日の光を嫌うような薄暗い部屋。
唯一の明かりはモニターの青白い光のみ。その前で突っ伏して眠るピンク髪には、モニタの光に照らされ不思議なグラデーションがかかっている。
眠っている顔は少しあどけないけど、やはり整っていて、本当に俺と同じ次元に生きているのかと疑うくらい、夢幻的な光景だ。
「千冬、ベッドで寝ろ。…千冬」
肩を叩くも、全く起きる気配はない。
「あんまり寝なくても平気って、ほんとか?」
俺はため息を一つ吐いて、側にあったカーディガンをかけてやる。たっぷりした生地のデカめのカーディガンだから、寒くはねぇだろ。
リビングに戻って、キッチンを拝借する。
千冬に世話になってばかりだから、今朝は俺が作ろう。
と言っても、俺は千冬みたいな料理スキルはねぇけど…。
目玉焼きと、味噌汁。
冷蔵庫の中の、目についたものを適当に火にかける。
「あと米…、あ?」
炊飯器の中にも、米びつの中にも米がねぇ。
というか、主食っぽいものが何もねぇ。
少し悩んだ末に、スマホで近くのコンビニを検索する。
「おにぎりでも買ってくるか…」
徒歩で5分ちょっとくらい。
この家のロックは暗証番号式。番号を知らない俺は、千冬が起きなければその辺を散歩でもして時間を潰すしかねぇけど…、千冬は授業あるだろうし、多分戻る頃には起きてんだろ。
千冬のスマホに出かける旨のメッセージを入れて、念の為、作業部屋のドアを開けて千冬に声をかける。
「千冬、買い物行ってくるな。戻ったら連絡するから、鍵開けてくれねぇか?」
「………」
「……ま、いっか」
上着とスマホだけ持って家を出る。
昨日は一日中家にいたし、ほぼ寝てたし、少し運動するのも悪くねぇな。
コンビニで、おにぎりを何個かと、目が合ってしまった肉まんを2つ。
「千冬、今日の授業は何限からなんだろ…」
誰に言うわけでもない独り言と共に店を出た瞬間、横から何かが思い切りぶつかり、そのまま身体を抱きしめられた。
「ぅぐッ!?」
「伊織先輩っ…!!」
「っ、ち、千冬…?」
「先輩、先輩…!どこ行っちゃったかと思った…」
「く、くるし…」
ぎゅうう、と腕の拘束が強くなる。
ここまで走って来たのか、千冬の心臓がバクバクいっている音も聞こえるし、上下する肩と荒い呼吸も身体で感じる。
しかも、声は今にも泣き出しそうな声で、震えている。
「僕が、告白なんかしたから…、我慢できなくて、手なんか握ったから…!…僕のこと、嫌になって出てったのかもって…、」
「千冬…」
ぐすぐす言っている千冬の身体を優しく叩いて、「とりあえず放せ」と伝えると、千冬は慌てて俺を解放した。
ピンクの髪は寝癖がついたままだし、服だって部屋着にダボついたカーディガン。足元も、くるぶしが見えていて寒そうだ。
「落ち着け、千冬」
「…っ、はい、…」
「俺、コンビニ行くって、連絡入れたぞ?」
「…え?…そう、でしたか……ごめんなさい…」
スマホも持たずに家を出てきたらしい千冬に、苦笑する。
慌てすぎだろ。
「俺こそごめんな。一緒に戻ろうぜ」
「…はい」
怒られた子供のように俺の横をトボトボ歩く千冬に、小さく笑う。
「お前やっぱ睡眠足りてねぇんじゃねぇの?ちゃんと休めよ」
「…ごめんなさい」
「怒ってねぇよ。今日授業、何限から?」
「伊織先輩が家にいるのに、学校なんて行きません」
「俺を口実にサボるな。バイトだってあんだろ?」
「…今日は2限だけです」
「じゃあ、朝メシ食ったら少しでもベッドで寝とけ」
「大丈夫です、僕…」
「ダメだ」
千冬の腕に触れ、顔を下から覗き込む。
「千冬のこと、…心配してんだよ」
「っ…」
「あと…、」
無防備な千冬の手に、そっと指先だけ触れた。
心臓が、ドキドキ言ってる。
「告白も、手も、……嫌じゃねぇから…」
「…え……、」
小声で呟くと、赤くなって立ち止まった千冬を取り残し、先へ進む。
「俺が寝かしつけてるから、ちゃんと寝ろよ!」
「へ……は、…?」
「あ、肉まん食うか?」
「…あ、えっと…、い、いただきます…」
「おう」
小走りで追いついた千冬の手に、温かい肉まんを乗せる。
「家着いたら、朝メシできてるからな」
「え!そうなんですか?」
「大したもんじゃねぇけど」
「ふふ、嬉しいです。ありがとうございます」
照れたように笑う千冬に、俺も笑って返す。
肉まんは、いつもよりずっと美味しく感じた。
腹が減ってるからか、それとも、千冬と一緒に食ってるからか…。
千冬といられる時間は、あと3時間。
なんか、全然足りねぇな…。
もっと、一緒にいてぇ…な。