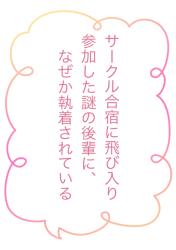ダイニングに座り、向かいの席には千冬。
机の上には、千冬お手製料理。夕飯は、鶏の照り焼きだ。
醤油ベースの甘辛いタレがマジで美味い。俺は毎日これでもいい。
「やっぱり美味ぇ…。天才か?」
「ふふ、ありがとうございます。ネットのレシピ通りに作っただけですよ」
「お前さ、顔も良くて性格も良くて料理も上手ぇ。しかも音楽もできる…」
「え!?な、なんですか急に」
「モテねぇわけがねぇよな」
「褒めてくれてるんですか…?」
「まぁな。僻みとも言う」
「ええ?」
なんつうか、千冬は器用なんだと思う。
…ほんとに俺と同じ男子大学生か?
わざと胡散臭い笑顔を返すと、千冬はクスクス笑った。
「はぁ…、でも僕が惚れられたいのは、世界中で伊織先輩だけですけどね」
「え…」
「そんなに言ってもらえるなら、期待して、いいんでしょうか?」
顔を上げると、千冬が、不敵な笑みを浮かべながら首を傾げた。ピンクの髪がふわっと流れる。
俺は、口の中の物をよく噛まないまま飲み込んだ。
「そ、そういえば、俺の相手ばっかしてて、動画の方は全然時間取れてねぇだろ?いいのか?」
「ふふ。心配してくれて、ありがとうございます。夜に作業してますから大丈夫ですよ」
「それ、寝れてんのか?」
「僕はそんなに寝なくても平気なんです。それに、投稿も、曲ができた時に上げてるだけですし」
いつの間にか俺の皿の中は、ほぼない。
また作って欲しいってリクエストしとこう。
「てかさ、千冬は顔出して動画投稿すれば、爆発的に人気出んじゃねぇの?その顔面パワーで」
「………」
「ん?なんか変なこと言ったか?」
「…あの、伊織先輩って、もしかして僕の顔、好きなんですか?」
「は?」
「さっきからすごく褒めてくれるので」
「いや、誰が見ても美形だって言うだ…ろ」
俺が話してる途中にも関わらず、千冬が俺に手を伸ばす。
俺の顎下に手を添え、軽く持ち上げると、千冬の栗色の瞳とバチっと視線が合った。
「俺の顔、見て?」
「…な、何だよ…?」
何をする気か知らねぇけど、受けて立ってやる。
そんな気持ちで、険しい顔で千冬を見つめ返す。
すると千冬は、こっくりした焦茶の瞳を細め、柔らかく微笑んだ。
俺の変な対抗意識さえ溶かすような、優しい声。
「…大好き」
「〜っ、」
「顔、赤いですよ?」
「うるせ…」
目が泳ぐ。
そんなストレートに言われて、動揺しねぇ方がおかしいだろ…。
「目、逸らさないで。俺の顔、見て」
「……っ、」
「ふふ、先輩、かわいい」
「……もう、いいだろ」
千冬の手をやんわりどけて、顔ごと逸らす。
千冬の表情はどんどん生き生きしてきて、それに比例して、俺の顔は火照って、鼓動も高鳴った。
…俺、千冬の顔が好きなのか…?
「いいこと知りました」
「うるせぇ」
なんか負けた気がして、話題を逸らす。
千冬に断り冷蔵庫を開けると、俺が厚海で買った、カゲヤン達の土産のプリンが綺麗に並んでいる。
「カゲヤン達のお土産のプリン食うぞ」
「え!食べちゃっていいんですか?」
「いい。もう期限近ぇし。アイツらもプリンくらいでごちゃごちゃ言わねぇし」
「そういうものですか…?」
「うるせ!お前のせいだからな」
「ええ〜?」
そう言って千冬の前にプレーンとかぼちゃ味のプリンを置き、蓋を開ける。
「ほら、俺が食わせてやる。食え、ガキンチョ」
「え…」
「……えっと、…あ、…あーん………」
「………」
スプーンにひとすくいして、千冬の口元に近付ける。母親が小さい子供にやるみたいに。
仕返しのつもりで仕掛けたけど、……ものすごく恥ずかしい。
情けねぇことに、顔は赤くなるし、声も弱々しくなる。
千冬の反応がないのが、余計、羞恥心を煽られ、上目遣いになりながら様子を伺った。
「食べねぇの…?」
「…っ、…わいい……」
「え?」
「かわ、いい…っ!もう…、やめてください…!我慢してるって、言ったじゃないですか…!」
手で顔を隠し、顔を逸らす千冬。
指の間から覗く頬は赤くなっている。
……仕返し、成功…なのか?
千冬に差し出していた一口を、自分で食べる。
千冬に勝ったらしい喜びと、甘いプリンが口の中で蕩ける食感に、頬が緩む。
「フッ、あまり年上をからかうなよ?」
「……」
とりあえず勝利宣言。
赤い顔のまま、ジトっとした目で俺を見る千冬を他所に、俺は自分の分のプリンを食べ始めた。
うまぁ。
*
プリンを食べ終えた後は、千冬は風呂。
俺は皿洗いを終わらせて、ソファでスマホを見ていた。
YouTubeで、「フユ」と検索する。
表示された動画一覧の中から、千冬のオリジナル曲を選んで再生していく。
「……優しい、声…」
ギターの音色と、千冬の声に聴き入る。
千冬の動画は、特に喋ることもなく、演奏して、歌うのみ。
それでも10万前後は再生されているし、コメントも寄せられている。
固定ファンが、ちゃんと付いてんだろうな…。
興味が湧いて、動画についたコメントも眺めてみると、千冬を恋慕うようなコメントも散見される。
ラブソングの時なんかは、特に多い。
なんか、ちょっと、つまんねぇ感じがする。
「…千冬にとっては、大事なファン…だもんな…」
モヤモヤした気持ちを割り切るように呟き、コメント欄を閉じる。
千冬の甘く響く優しい声に、胸の内側を撫でられる。
「…指、きれい……」
画面に映るのはギターを弾く手元のみ。
弦を抑える細長い指と、手の甲には時折血管の凹凸が浮かぶ。
千冬の、手……。
手を繋いだ時の感触を思い出して、鳩尾のあたりがきゅんとする。
…もう一度、手をつなぎたい…。
体温がじりじり上がって、頭の中はぽわんとしてくる。
自分の手を無意識に口元に当てた、その時。
背後から伸びてきた手に、スマホを取り上げられた。
「千冬、出てたの…か、っ…」
振り返ると、風呂から上がったばかりの千冬が、至近距離にいた。
背もたれに肘をつき、頭を乗せて俺の顔を覗く。
「本物はこっちですよ。……妬けちゃうな」
水分を含んだピンクの髪と、ほんのり赤く染まる湿った肌。甘い目元と、いじわるそうに微笑む唇。
掠れた声が、俺の背中をゾクゾクさせる。
「……ごめ、ん…」
硬直したまま口走る。
なんで謝っているのか、自分でも分からねぇ。
「歌が聴きたいなら、僕に言ってください」
千冬は、愛おしそうに俺を見つめながら、取り上げたスマホを俺の手に戻す。
「いつでも、先輩のためだけに歌いますから」
清潔な石鹸の香りの中に混ざる、危なげな色気を感じて、俺の心拍数が勝手に上がっていく。
顔、熱ぃ……。
「ありがと…な。……髪、早く乾かしてこいよ」
「はい。そうしますね」
立ち上がった千冬は、いつものような可愛らしく微笑みだけを残して、背を向ける。
「ふぅ……」
千冬の背中を見送って、俺はため息をついた。
ソファにドサリと倒れこむ。
今日1日が、濃過ぎた。
千冬に告白されて、混乱して泣いて。
それから、手を、繋いだ。
「なんか…熱ぃ……」
熱を持つ頭を休めようと、目を瞑っても、思い出すのは千冬のことばかり。
甘い微笑み、優しい声、手の温度……。
心臓がトクトク鳴る。
そんなつもりはなかったはずなのに。
千冬の言葉が、行動が、俺に千冬を意識させていく。
「……好き、なのか?…俺……」
熱くなる顔を腕で隠し、自問自答する。
…好き、なの、かも……。
また深いため息をついて、思考の海に沈む。
結局俺は、そのまま眠りに落ちていった。