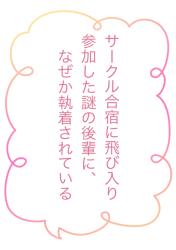味がよく分からなくなった、たまご粥を食べ切った後、俺はシャワーに向かった。
全身を洗い、熱いお湯を浴びると、身体はスッキリする。
でも、頭の中は、まだ熱を持ったままだった。
「…千冬が、俺を……好き…、」
呟いては、顔が熱くなる。
千冬の、溢れんばかりの告白を疑うつもりはねぇ。
でも…、正直、まだ信じられねぇ。
「うぅー、……ウワーッ!!」
シャワーの温度をぐっと下げ、謎の叫びと共に冷水を被る。
顔も身体も熱が冷めて、気分がシャキッとした。
そうだ、何をモジモジしてんだよ?
付き合う云々は、すぐ答えを出さなくていいわけだし、す、好きだっていうのも、嫌われてるより絶対いいじゃねぇか!
「はぁ…。よし!」
タオルで髪をバサバサ拭きながら、意気揚々と風呂場を出ると、同時に、脱衣所の扉が勢いよく開けられた。
「大丈夫ですか!?伊織先輩!」
「わっ、千冬?」
「無事……、」
血相を変えて脱衣所に飛び込んできた千冬。
ヘラっと笑いかけた瞬間、冷たい水滴が、髪から背中に滴り落ちた。
「ひゃぁっ…!?…冷てっ」
「っ…!?」
身体はビクンと跳ねるし、びっくりして変な声出たわ。
冷水なんて浴びるもんじゃねぇな。
「悪ぃ、シャワー浴びながら叫んだりして、うるさかったな?……千冬?」
「……」
千冬は、手の甲で口元を押さえ、その場で固まっている。
そして、何かを堪えるように瞼を伏せ、回れ右。
「無事なら…、良いです…」
そう言って静かに脱衣所を出ていった。
え、俺、また怒らせた…?
体を拭いて着替え、濡れた髪のまま廊下に出ると、シーツを抱えた千冬がいた。
「あ、千冬」
「先輩、まだ髪が濡れてるじゃないですか」
「おう?」
「また風邪ひきますよ。来てください」
千冬に脱衣所に戻される。
シーツを洗濯機に放り込むと、洗面台の前の椅子に俺を座らせた。
「熱かったら言ってくださいね」
鏡越しに柔らかく微笑むと、ドライヤーの電源を入れる。
温かい風を送る低い音と、千冬の長い指が、優しく髪に触れる感覚。
…気持ち、いいな…。
「熱くないですか?」
「おう。気持ちいい」
「ふふ、良かった」
目を瞑って、千冬に髪を撫でられる心地良さに身を委ねる。
頭のてっぺんから、前髪、サイド、後頭部…と、順に千冬の指が髪を梳く。
美容院でやってもらうより、もっと丁寧で、ずっと優しい。
なんか、すごく大切に扱われてる、って、感じが……する。
そっと目を開くと、綺麗な微笑みで愛おしげに俺の髪先を見つめる千冬が、鏡に映る。
心臓がドキリと脈打った。
「…、」
「はい。終わりましたよ。……どうかしましたか?」
「…なんでも、ねぇ」
ドライヤーを片付ける千冬を、鏡越しに盗み見る。
伏せられた長いまつ毛に、スッと通った鼻筋。横顔も絵になるほど綺麗だ。
そして、ドライヤーのコードを束ねる指先にも、目が奪われる。
あの手が、あんなに優しく、俺に触れてた…、のか…。
…なんか、恥ずっ……。
鏡の中の俺は分かりやすく赤くなっていて、更に恥ずかしさが込み上げて、俯く。
「先輩?体調、悪くなっちゃいましたか?」
「あ?……違ぇ。大丈夫」
「そうですか。何かあったら言ってくださいね」
「おう」
立ち上がり、千冬と一緒にリビングへ戻る。
珍しくテレビがついていて、芸能人が観光地を巡るバラエティが流れていた。
「お、厚海じゃん」
「ほんとだ。美術館ですね」
テレビ前のソファに腰掛けると、千冬に何か飲むかと聞かれる。
またホットレモネードをリクエストした俺は、そのままテレビをぼんやり見ていた。
「どうぞ」
「あ、さんきゅ」
ふわふわした笑顔で、ローテーブルにホットレモネードを置いてくれる。
厚海で買った、焦茶のマグカップ。
千冬も手に同じものを持って、俺の横に腰掛けた。
「この後、買い物に行ってきますけど、夕飯はどんなもの食べたいですか?」
「肉食いてぇ」
「ふふ、分かりました。すっかり元気ですね?安心しました」
マグカップに口をつける千冬を、無意識に見る。
ふんわりした淡いピンクの髪、綺麗な二重の甘い目元、つややかで白い肌。
ギターを弾き、たまご粥を作り、俺の髪に触れた、細く長い指…。
千冬が俺を好きだと言ったことが、急に現実の出来事だったか、自信がなくなる。
俺は、思ったままの疑問を口にした。
「…千冬って、いつから俺が好きなんだ?」
「ッ…!?ケホッ、ケホケホ」
「おい、大丈夫かよ?」
「大、丈夫、です…、はぁ…」
「なんか、悪ぃ」
「いえ、変なとこに入っただけですから」
咳き込んで赤くなった顔で、俺を見る。
数秒迷った様子を見せてから、ぽつりと、呟いた。
「……初めて会った…、高校生の時からです」
「…え?高校生!?」
意外な発言に驚きが隠せない。
そもそも、俺が千冬と知り合ったのは、せいぜい数ヶ月前のはずだ。
「覚えてませんか?…あのコンビニで、お茶を買った受験生に、頭痛薬とスポーツドリンクを渡したこと」
「…あ~、あったな。……え…、マジで?」
「マジです」
「…………」
照れくさそうに視線を逸らす千冬。
忘れてたわけじゃねぇ。
2月の雪の日。いつも通りコンビニでレジを打ってると、マフラーを鼻下までぐるぐるに巻いた、明らかに体調が悪そうな高校生がいた。
余計なお世話と思いつつも、声をかけ、たまたま持っていた頭痛薬を渡したことがある。
「全っ然、気付かなかったわ。何で言わねぇんだよ?」
「だって…。気持ち悪くないですか?優しくしてもらって、好きになったからまた会いにきました、なんて……」
「いや、言い方」
思わず笑ってしまう。
「あの時、すごくしんどくて、頼るとこもなくて…。そんな時に伊織先輩に助けてもらって、…その時の、笑顔も……、すごくかわいくて…」
「は?かわいい?」
「はい。…一目惚れ、しちゃいました」
「…ひとめ、…っ、」
「それから、伊織先輩と仲良くなるために、先輩のコンビニ通って、覚えてもらうために、髪色もこの色に変えて…」
「確かにピンク髪の客は千冬しかいなかったからな、すぐ覚えた。でも、そこまでするか…?」
「しますよ」
マグカップを机に置いた千冬が、体を俺の方に向け、端正な顔を近づける。
「なんでもします。伊織先輩と、付き合えるなら」
「付き合っ……ちょ…、…近っ…」
「やっとここまできたんです。…もう、絶対に放しません」
「えっ、ちふ、ゆ…」
俺の腿の横に手をつき、距離をじりじり縮めてくる。
鼻先が触れそうなほど顔が近付いて、俺はソファの隅まで後退する。
それでも千冬は微妙な近さを保ったまま、俺を追い詰める。
「先輩。僕が近づくのは、怖いですか?」
「それは…、怖くは、ねぇ…っ、けど…」
低く囁く声に、心臓がドクンと跳ねる。
レモネードのはちみつと、千冬の匂い。
薄い瞼と長いまつ毛が、チョコレートのような焦茶の瞳を、半分ほど隠している。
千冬の視線は甘くて、熱くて、俺の心臓はドキドキと高鳴る。
そして、千冬が、熱っぽい声で囁いた。
「なら…手は…?」
「手…?、っ!」
ソファの座面に置いたままの手に、千冬の指先が、ちょん、と触れる。
熱い指。
目の前の千冬は、俺の視線を外させないように、じっと見つめている。
光のない目に、吸い込まれそう。
一瞬でも逸らしたら、唇がぶつかりそうな距離にも、心臓がバクバクする。
「俺は、先輩と手、繋ぎたい……いい?」
「え、あ…っ」
ゆっくり俺の指先を持ち上げて、千冬の指が、人差し指、中指、薬指の腹を、根本から先へなぞる。
「…ずっと、こうやって触りたかった…」
「うぁ、くすぐってぇ…から…っ」
指の間に千冬の長い指が侵入する。
指の側面を千冬のきめ細やかな肌が滑っていく感覚に、背中の辺りがソワソワする。
──きゅっ
俺の掌を覆うように優しく握り込むと、千冬の瞳はさらに甘く細められる。
「嬉しい…。大好きです、伊織先輩」
「…っ、」
ただ手を握られているだけなのに、俺の鼓動は耳に響くほど大きく鳴った。
千冬は何度か握り直すようにして、より深く指の間に入り込んでくる。
その度に、俺は呼吸が狂うほど、心拍が上がる。
「先輩。嫌ではないですか?」
「えぇ…?」
「僕たち、友達以上…っぽいこと、してますよ?」
やわやわと手を握る力に強弱がつく。
恥ずかしいのに、拒否できない。
むしろ…。
「…い、嫌では、ねぇ、…」
「うん、」
顔から火が出そうなくらい熱い。
俺の心臓は、今、手にあるんじゃないかってくらい、手からドキドキが身体に伝わる。
「…でも…なんか…熱ぃ、…し、」
「うん、」
「……心臓、痛ぇ、し……」
「……」
千冬の熱い視線に、声が震える。
目だけで千冬を見上げながら、素直な気持ちを答える。
「けど…、…もう少し、…このまま……いたい…かも……」
千冬がゴクっと喉を鳴らした。
ため息と共に千冬が項垂れて、俺の視界はピンク一色になる。
「…あー…、ヤバい」
「え…?」
「手だけで…こんなに危ないとは、…思ってませんでした……」
「危ない?」
再び顔を上げた千冬は、口をギュッと結んで俺を見つめてから、ゆっくり身体を離した。
手を握る力は弱めて、緩く指先を絡めたまま優しく微笑む。
「手、繋げましたね」
「あ……、おう…」
「恋人つなぎです」
「恋…人、」
ふふっと、かわいらしく笑って、繋がれていた手を、静かに放す。
「あ…」
放された手が、寒い。
さっきまであった温もりが恋しい。
「さて。買い物、行ってきますね」
「…え、っと…、」
淡白に言って、立ち上がった千冬を縋るように見上げてしまう。
そんな俺を見た千冬は、息を詰まらせ、一度顔を逸らした。
「はぁ…」
そして、隣に跪いて、優しい声で語る。
「僕は、伊織先輩に嫌われたくないから…、痩せ我慢、してます」
「おう…?」
「だから、あんまり僕を煽らないでください」
「え?」
千冬の目に、欲が揺れる。
「他の人にそんな顔、みせないでくださいね」
「……わか、った…?」
いや、分かんねぇ。
どんな顔だ?
俺、どんなアホ面してたんだ??
「あ、買い物、俺も行くか?っていうか、俺が…」
「いいんです。先輩は病み上がりだし、僕は……一人で頭を冷やしたいので」
「え?千冬も熱っぽいのか!?」
まさか、うつしたかと心配して、尋ねる声が大きくなる。
千冬は小さく笑った。
「そうです。重症です」
ふふ、と上機嫌に微笑み、立ち去る千冬。
…元気そう、だな。
大丈夫か。